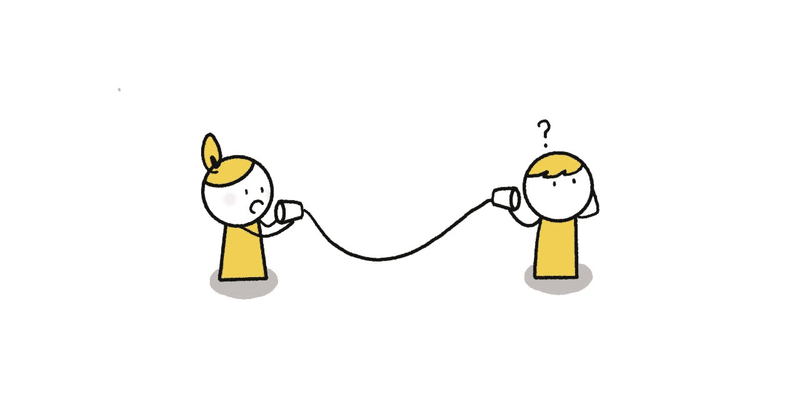
#570:奥村隆著『他者といる技法 コミュニケーションの社会学』
奥村隆著『他者といる技法 コミュニケーションの社会学』(ちくま学芸文庫, 2024年)を読んだ。1998年に日本評論社から刊行された単行本を文庫化したものとのこと。新刊書店の店頭で見かけて、タイトルが気になって購入して読んでみた。
本書を一貫しているのは、私たちが「他者」と安定した関わりを持つことの難しさだと思う。だからこそ、私たちは「他者といる」ために、子どもの頃からさまざまなわざを身につけ、それを自分なりになんとかやりくりして、他者との関係を自分が安心していられる範囲におさめようと、日々苦労している。著者はそうした私たちが身につけてきた/いるそうしたわざを「技法」と名づけて呼ぶことで、そこに光を当てようとしている。そこには、喜びもあれば、痛みも悲しみもあることから目を逸らさないように努めているところに、本書の特色があると言えるだろうか。
他者と関わることは難しい。近づきすぎると、相手に飲み込まれ、相手から傷つけられ、相手から支配されるかもしれない。逆に、相手を飲み込み、相手を傷つけ、相手を支配してしまうかもしれない。遠ざかりすぎると、孤独であるし、疎遠な人々に囲まれていることは、安心からは程遠い。こうした関係の難しさについて、著者は「理解の過少・理解の過剰」と題した最後の章で、「理解」をキーワードに考えを進めようと試みている。
「理解の過少」として、著者は、他者を理解できないこと、他者から理解されないことを取り上げる。そして、「理解の過剰」として、実際には不可能なことだがと断りつつ、他者が私を完全に理解する事態と私が完全に他者を理解する事態を、仮想的に、取り上げる。それぞれが抱える問題、その事態の渦中にある当事者たちの感じる苦しみを論じたうえで、著者は、「「理解」とは別の「他者」といる技法」という問いを立てる。著者が本書で到達した地点を、長くなるが、引用で示そう。
私たちがよく知っているのは、「わかりあう」から「いっしょにいられる」という状態だ。だから、「わかりあえない」とき、「いっしょにいる」ために「もっとわかりあおう」とする。・・・中略・・・しかし、この技法しかもたないとき、「わかりあえない」と私たちは「いっしょにいられなく」なってしまう。おそらくもうひとつの技法があるのだ。・・・中略・・・「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法、「わかりあえない」ままでひとつの「社会」を 作っていく技法。私は、「他者」といること、「社会」を形成することの少なくともある領域において、このような技法を探すことが必要だと思う。(p.290;強調は原著者。ただし原文では傍点による)
一見したところ、格別新しい考えでも、目を見張るような考えでもないように思われるかもしれない。しかし、著者が示している考えは、なんの変哲もないように見えて、実は相当重要なものであると私は思う。
例えば、心理臨床の仕事の世界において、他者=クライエントをよりよく理解できるようになりたいと願う臨床家は少なくないだろう。ただそこで重要なのは、著者が少し異なる文脈で違ったやり方で述べているように、「よりよく理解する」ことは、必ずしも「より多く理解する」ことや「より“真実”に近く理解する」ことではないということだ。
「よりよく理解する」=「より多く理解する」=「より“真実”に近く理解する」ことと感じ・考えている人は、勉強を重ねて、専門家が使う概念からクライエントを理解することがそれであり、そのように理解することで初めて専門家としてクライエントといることができるように感じられて安心を覚えるかもしれない。しかし、それは、いつしかクライエントを理解することから遠く離れて、知識と理論というメガネをかけてクライエントを「理解しているつもり」になっているだけかもしれない。それを“専門家らしいあり方”と考えることは、場合によっては、クライエントに対するある種の“暴力”に転化する危険性さえあると、私は思う。
著者の考えに同意しつつ、私が考えるのは、例えばクライエントを「よりよく理解する」とは、少なくともその重要な一部は、“ある大事なところで、クライエントについて、自分にはわからないところがある”ということをわかるということではないかということだ。“良い専門家であるためにはクライエントについてできるだけ多く理解しなければならない”と考える臨床家は、クライエントとの間に、わからないということを抱えておくことがひどく難しいだろう。
臨床家に限った話ではないが、私たちは、未知のもの・未知の状態に長く向き合い、長く留まること苦手なのだ。しかし、「他者といる技法」が未知を減らす方向へのみ進むとき、著者が本書で述べているように、それは同化と排除の圧力を呼び込む“暴力”に転化しかねない。だから、著者の考えに付け加えれば、「「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法」(前出)が必要なばかりか、「わかりあえない」からこそ「いっしょにいる」ことができる技法もまた、私たちは探し求めねばならないだろう。
このように考えてみると、私が心理臨床の仕事を通じて学んできたことの一つは、まさに後者の技法=わざを、それぞれのクライエントとともに手探りで探り当てようと努める道のりが、その本質の一部であるということであったようにも思われる。「わからない」「わかりあえない」という言葉を、拒絶の身振りとしてではなく、互いへの敬意として、互いの関係を大切にしたいという身振りとして、心に抱くことができるようになること。それはおそらくひどく困難ではあるが、時間をかけて取り組む価値のある仕事ではないか、本書を読んで、そう考えてみたくなる自分に気づいた。
