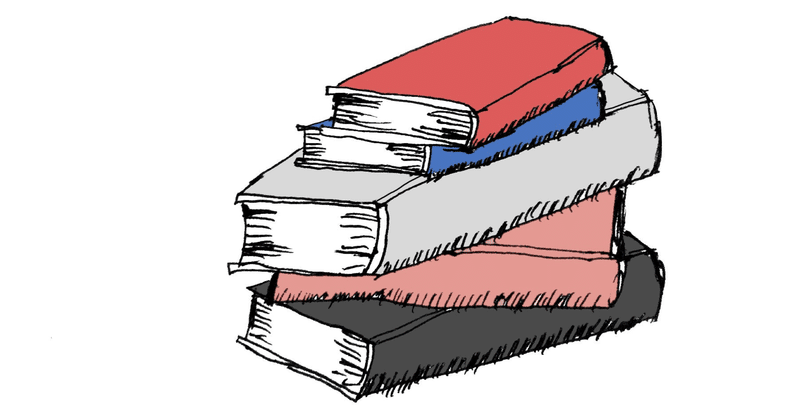
#546:岩波書店編集部編『翻訳家の仕事』
岩波書店編集部編『翻訳家の仕事』(岩波新書, 2006年)を読んだ。「まえがき」によれば、「本書は二〇〇三年五月から〇六年五月までの計三七回にわたって雑誌『図書』に連載された「だから翻訳はおもしろい」に一つの区切りをつけ、まとめたもの」(p.ⅰ)とのこと。錚々たる執筆陣による、翻訳家が語る翻訳(の喜びと苦労)をめぐるエッセイ集である。
どのエッセイも興味深く、面白く読んだが、とりわけ、後半の「3 テクストの呼び声-原作との対話」と「4 生ける言葉-翻訳と創造の狭間で」に収められた諸エッセイでは、それぞれの翻訳家が自らの経験を通じて翻訳という営みの本質に肉薄する思索を垣間見ることができて、とても刺激を受けた。中でも、複数の執筆者が、翻訳の作業を、原著者の、あるいはフィクションであれば登場人物の、<声>を聞き取り、それに日本語としての言葉を与えることとしてることとして表現していることは、私にはとても興味深く思われた。原著者の文章から聞こえてくる<声>に耳を澄ます翻訳家の仕事と、クライエントの<声>に耳を澄ます心理臨床家の仕事には、その本質において、共通する部分があるように私には思われた。例えば、越川芳明氏の次のような一節。
米国詩人ジェイムズ・メリル(1926-95)は翻訳という行為を、通常考えられているより ずっと広義に捉えているようだ。メリルによると、僕たちは皆、日常生活でも「翻訳」をし ているらしい。僕たちは生きながらいろいろと不可解な出来事に遭遇し、知らない言葉をい ろいろ聞き、それがどういう意味なのかを考える。僕たちは、しばしば意味が理解できずに 逡巡する。たまに、わかった!と思ったら、恥ずかしい「誤訳」であったりする。 だから、 どうしていいかわからなくなる。わからないけど解釈しながら迷子になり、迷子になりなが ら、それでも道をさがす。いずれにしても、この世界を完全に理解し尽くす事は不可能だ。 つまり、最終的な「正訳」にはたどり着けない。(p.138)
本書中、独立したエッセイとして最も感銘を受けたのは、伊藤比呂美氏の「ビリー・ジョーと同い年でした」。題材は確かに翻訳だが、それ以上に、母と娘の交流のあり方と、娘さんがもがきながら成長するプロセスが、さらりとした筆致で描かれていることに、深い感銘を受けた。それはおそらく、私の仕事が心理臨床の領域にあることと無関係ではない。
翻訳書を読む人、あるいは翻訳の作業をする人であれば、きっといずれかの執筆者のエッセイに「へぇー」と感心したり、我が意を得たりと得心する部分があったりするだろう。翻訳を愛する(あるいは翻訳に苦しむ)人にとっては、本書はその楽しみ(あるいは苦しみ?)を深める(あるいは癒す?)、贅沢な贈り物だと思う。私はとても楽しませてもらった。
