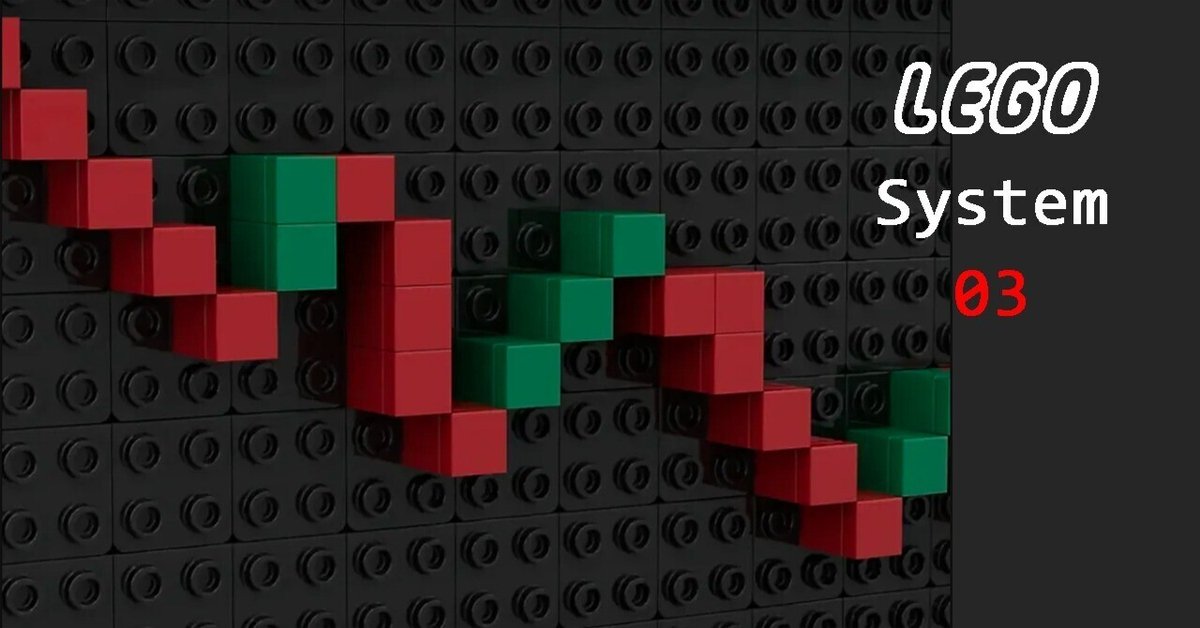
LEGO System 03
練行チャートで使うテクニカル指標の組み合わせについて考えてみよう。チャート上にはトレンド系インジケーターを。サブ窓にはオシレーター系インジケーターを。やはりこれが定番だろう。
トレンド系インジケーターとして
移動平均線
VWAP
ボリンジャーバンド
スパンモデル
一目均衡表
ドンチャンチャネル、などなど。
オシレーター系としては
ストキャスティック
RSI
RCI
TDI
CCI
QQE
RMI、などなど。
さらに、モメンタムを計測するのに
AOやMACDなどを合わせて監視するのがよかろう。
練行チャートに慣れるために、そして、検証のためのアイデアとして、いくつか具体例を紹介する。
Trading Viewはデフォルトで期間14のATRで練行サイズを設定する。これは甚だ具合が悪い。「ATR」を「Traditional」に変更して数値を入力する。

FXのクロス円の場合は、0.01が1 pip
FXのクロス円以外の通貨では、0.0001が1 pip
ゴールド、仮想通貨、株価指数などで単位がドルの場合は、1は$1、0.1は¢10
先物・株で日本円の場合は、1は1円
とっかかりの目安として、ATRの25%~50%あたりから試してみるといいだろう。日足なら日足のATR、1分足なら1分足のATRということだ。
ちなみに、練行足を表示するチャートは、中長期スイングなら日足を、デイトレやスキャルピングなら1分足を使う。
その1
期間9と50のSMAまたはEMA
期間14のDMI(ADXは非表示)
期間10または14のRSI(またはTDI)
期間10 ±2σのボリンジャーバンド
表示を5ずらす(Offset=5)
50 MAより上はロング、下はショート
9 MAを練行足がクロスしたらエントリー
ないしは、9 MAをクロスしたあとBBもクロスするのを待ってエントリー
DMIとRSIをエントリーのフィルターに使う
練行足が再び9 MA(ないしはBB)に戻ったら手仕舞い
一方向にトレンドが発生している間は、BBに沿ってトレール

その2
5、10、50のSMAまたはEMA
ストキャス 5-3-3
50で買いか売りかの目線を決める
5と10およびストキャスのDC(デッドクロス)とGC(ゴールデンクロス)でエントリー

その3
期間10 Offset 5のDonchian Channel
チャネルをブレイクしたらブレイクした方向にエントリー
チャネルに戻ってきたら手仕舞い
SLは反対側のチャネルに置いて、チャネルが移動するたびにSLも移動する

その4
XAUUSD 日足 練行サイズ=$5
期間200のSMAまたはEMA
BB 期間10 ±1σ Offset 5
200 MAの上ではロングのみ
下ではショートのみ
ボリンジャーバンドを上抜けたらロング
下抜けたらショート

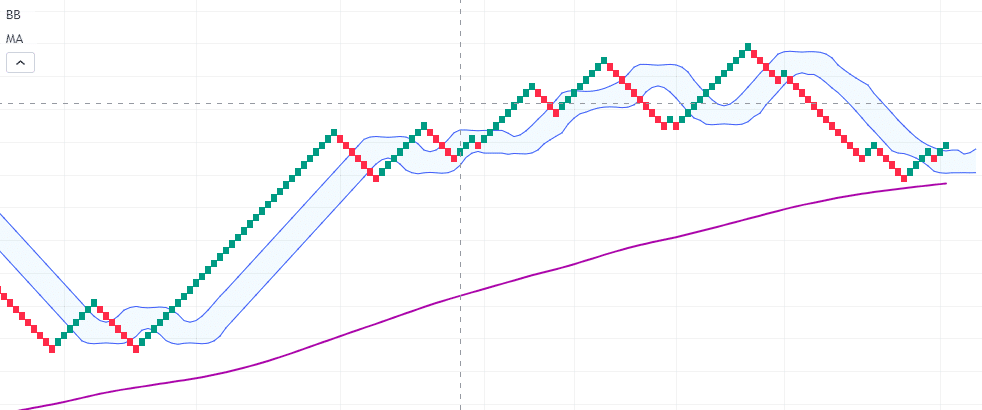
その5
S&P500 日足 レゴサイズ=$10
期間7のSMAまたはEMA
BB 期間21 ±2σ
Laguerre RSI(設定は下図)
LaRSIが底辺から上昇
MA 7 ブレイクでロング
LaRSIが天井から下降
MA 7 ブレイクでショート

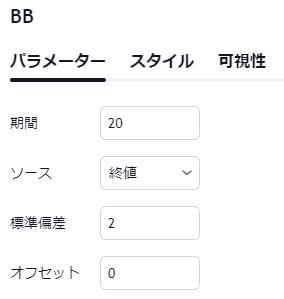

その6
Nifty 50 練行サイズ=35 日足チャート
期間7のSMAまたはEMA
BB 期間5 ±1σ オフセット2
ストキャスティック 12-3-3

その7
GBPUSD 5分足 練行サイズ=0.002(20 pips)
2つ以上売りのレゴ(赤)が続いたあとに、買いのレゴ(緑)が出現したら、次の始値でロング
2つ以上買いのレゴ(緑)が続いたあとに、売りのレゴ(赤)が出現したら、次の始値でショート
TP : SLは1 : 1
その8
期間5のDEMA
期間10のDEMA
期間21のDEMA
期間34のDEMA
AO
TDI
ロング
21 DEMAが34 DEMAより上
5 DEMAと10 DEMAがGC(ゴールデンクロス)
AOがグリーン、またはゼロラインをクロス
TDIのPrice LineとSignal LineがGC
ショート
21 DEMAが34 DEMAより下
5 DEMAと10 DEMAがDC(デッドクロス)
AOがレッド、またはゼロラインをクロス
TDIのPrice LineとSignal LineがDC
エントリー後は21 DEMAに沿ってトレール
練行足が21 DEMAをクロスして確定したら手仕舞い

DEMAでなく通常のEMAのクロスを使う手法もある。
EMAの期間は「2」と「5」
2本のEMAのGCとTDIのPrice LineとSignal LineのGCでロング
2本のEMAのDCとTDIのPrice LineとSignal LineのDCでショート
なお、以下のインジケーターはDEMAおよびEMAのクロスをアラートしてくれる
その9
期間6のEMA
TheLark Relative Momentum Index(RMI)
設定は、4-5-70-30-6
練行サイズを10 pips、チャートを5分足または15分足にする
練行足が6 EMAを上にクロスして確定、RMIが30から上昇で、ロング
練行足が6 EMAを下にクロスして確定、RMIが70から下降で、ショート

その10
John F. Ehlersが開発したインジケーターを練行チャートで使用
Ehlers MESA Adaptive Moving Average [LazyBear]
Ehlers Stochastic CG Oscillator [LazyBear]

その11
Bill WilliamsのBalance Line Tradingを活用する
Purple Lineの上は買いのみ、下は売りのみ
ワニの顎(青ライン)に向かって逆色が2個以上できる(プルバック)
逆色が元の色に戻ったら次の練行足の始値でエントリー
これを機械的に繰り返す

次回はいよいよ落ち穂オリジナルのLEGO Systemを公開する。それまでに、練行チャートに馴染んでおいていただきたい。かなりクセが強いし、勝手知ったるローソク足とはその挙動が全く異なるので、ひたすらチャートを見て体感するしかない。Trading Viewのバーのリプレイが練行足に非対応なのは大いに遺憾だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
