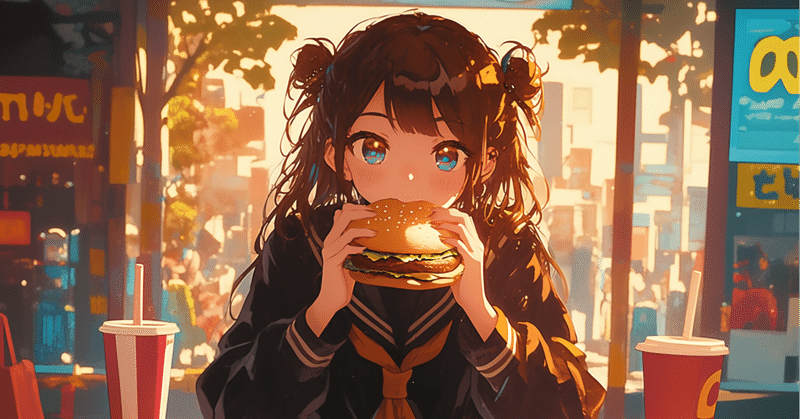
画像生成AIは飽きる、飽きられる、だからこそプロの仕事はこうなる。
「画像生成AI Stable Diffusion スタートガイド」(#SD黄色本)という書籍を出版して3ヶ月経ちます。色んな人に手に取ってもらって、重版もかかって、おかげさまでAmazonでは書評がめちゃいいのです。
「画像生成AIは飽きる」と言われた
Facebookでポジティブな感想として
「画像生成AIは飽きる」という感想をいただきました。
とある経験あるイラストレーターさんから。
まあそらそうなんだよね、という気持ちもあります。
僕と同い年ぐらいのイラストレーターさんなら当たり前だと思う。
彼女いわく
『おもいどおりにならん』がないメディアは飽きるのも早い。
「飽きる」のメカニズム
ゲームも「とつぜん飽きる」ってありますよね。
このセリフ、20代の中盤ぐらいから聴くようになりました。
熱心にゲームばっかりやってた人がとつぜん飽きるんです。
『おもいどおりにならん』がないメディアは飽きるのも早い。
ゲームが上手な人ほど、飽きるのは早い/速いはず。
たとえば将棋のようなゲームがあったとして、
ルールが分かった段階である程度は楽しめるでしょう。
問題はその後で、勝ち負けを探求したり、勝ち筋や定石を理解した段階で飽きてしまう人がたくさんいらっしゃいますよね。
子どものように感情を振り回されながら勝ち負け(アゴン)でプレイしたい人もいれば、飽きずに完全攻略を目指していく人もいます(プロ)。
感情に振り回されないプロ、
感情の変化を楽しむプレイヤー。
僕は、AI将棋を相手に自分の実力を試すことは楽しいと思えるし、
定石に過度に寄せずにスタイルを探求したり、自らの集中力を体感しながら遊ぶことができる。他のゲームとかだとクラロワとかはいまだに遊べます。
画像生成AIもドーパミンどばどば出ている状態から、
とつぜん飽きる人は出てくると思います。
ゲームと同じで、ルールの理解→制御下に置く→そこから?が難しいですね
美の探求から芸の探求へ
本当の意味でのクリエイティブな人間は、それで発信をはじめます。
(ネットゲームの場合は対人戦がそれにあたる)
自らの美の探求って、手を動かしているうちはなかなか究極、終わりがないですが、道具の使い方の問題なのであれば、他者に見せてみるしかない。
他人に見せるところが重たいひとは、多分その前に飽きる。
そして、いまは社会が地獄の業火のような環境なので、他人に見せることはとてもリスクが有る。
そんなわけで画像生成AIだって発信しようと思うと
「思い通りにならん!」はいくらでも味わえますが、
これを飛び越えていける存在はどれぐらいいるだろうか
「AI画像は飽きられる」か
広告を作ってみるとよくわかる
「AI画像は飽きられる」かどうか。
認知に訴える広告を作るには、作り手・選ぶ側に認知のモデルが必要で、それを何も考えずに出稿したら、認知されないのは当然で。どんなに描き込もうが、時間をかけたような絵に見えようが逆効果。
omostとかFooocusのような再起的な画像評価や人間の美的感覚といった認知モデルを組み込んだツールならともかく、ワンショットで運に頼る手法の中にも人間が関与してこその歩留率というところもある。
Stable Diffusionの公式API、1,800枚の画像を生成して比較検証してみた(動画あり)
実際のAI広告の世界はもっと具体的なテクニックだらけなのでこのブログでは割愛するけど、仕事としては言いたいことも言えないこともたくさんあるんだけど、それでも広告業の皆さんが人間の作業に集中できるツールやノウハウはいろいろ公開しています。
#10分で学べるAI Google Slidesでバリエーション広告を大量生成
若い人には無理に勧めなくていい
ところで画像生成AIについて私自身は「若い人には強くおすすめしなくていい」とも考えています。
⭐️それを知るためにも本は買ってみて欲しい。
五体満足で若くて健康で成長し盛りなあなたは、もっと手を動かして努力する機会を与えられているし、少なくとも僕が19歳のときはそうやって描き続けて、撮り続けて、暗室で焼き続けて来ました。そうしないと磨かれない。
わざわざ世界中の絵という絵の知識を知ったかぶりする必要はない、上手く見せる必要がない。だって若くて成長盛りなんだから。
世の中が便利になると
子供を育てるのは難しくなる
「世の中が便利になると 子供を育てるのは難しくなる」って話はいつもしていますが、
子供の頃にこんな便利なツールがあったら、美しい絵を書いて人の心を動かす、ってことを真面目に考えなくなる人も多くなりませんかね。もちろん僕の子供時代はアナログの写真や広告を使ってコラージュという手法に出会いましたし、大学時代もコラージュ作品はたくさん作りました。手法が駄目だとか良いとかそういう話ではなく、「鉛筆で描きたい」と思って鉛筆で描いている人に「デジタルはいいぞ、タブレットを使え」って言ってる大人は何がしたくて言ってるんだろ。仲間が増えて欲しい?自分の手法を肯定して欲しい?僕だったら息子に「鉛筆の削り方を変えてみ」とか「6Bはいいぞ」とか「専門の先生についてみたら」とかいってしまいそう。そんなこんなしているうちに、鉛筆絵もデジ絵も息子のほうがスキルは上になっています。写真はまだ教えられることはあるな。AI画像については当然ですが、それもちょっと教えたらSD黄色本の内容は完全にマスターしているので、追い抜こうと思ったらスキル的にはいつでも追い抜けるのでは…と思います。若くて元気な人達が、写真や画像、CGやメタバースの博士が書いた本を片手に一生懸命やりはじめたら、誰もついていけない、それが現在の世界の画像生成AIの現状です。
だから僕は、飽きない。
僕自身が楽しむ力と、学ぶ力がバランスしているし、きちんと教科書も作った。
誰にとって幸せな道具か
いろいろやってきた経験ですが、
お年寄りとか、描き続けられなかった人々にこそ、意味や価値があると感じている。障害者向けのアートには可能性があります。価値しかない。
ずいぶん前から活動していますし、挑戦もあるし、僕は飽きない。
障害者のアシストツールとしては自在に使える「思い通りに描ける道具」であって欲しいので、まだまだやることは多いと思います。
ところで、すがやみつる先生は賢い
ちゃんと新刊を用意してから炎上を仕込みつつ、世間のあれやこれやを確認してから、出版物にする。
地獄の業火に手を突っ込んで火中の栗を拾う。
プロの仕事だ。世間との対話スキルが常人ではない。
新刊案内に対する多数のご意見・ご感想をありがとうございました。表紙絵に対するご意見が多かったのですが、この絵は「すがやみつるが描いたもの」とは述べていません。本のカバー袖で生成AIを使って作成したことを明記しています(自作絵をDALL-E3にアップロードし、「ファインチューニング」するよ… pic.twitter.com/M2jGEihn24
— すがやみつる (@msugaya) June 24, 2024
新刊案内に対する多数のご意見・ご感想をありがとうございました。表紙絵に対するご意見が多かったのですが、この絵は「すがやみつるが描いたもの」とは述べていません。本のカバー袖で生成AIを使って作成したことを明記しています(自作絵をDALL-E3にアップロードし、「ファインチューニング」するよう依頼。試行錯誤を数十回繰返し、その中で使えそうなものを手描きで修正/添付画像参照)。 著作権の入門書ですので、このあたりのことは配慮しているつもりです。 自分の絵を使わないのは、読者の範囲を狭めてしまうと考えたからです。この表紙絵に対する反応を見ても、著者の名前や経歴など知らない人が圧倒的多数だと思われますので。 著作権についての本を書いて感じたのは、「イラスト」の立場の弱さです。絵柄や画風がイラストの命であるのなら、これらが権利を持てる工夫をしていく必要もあるのかもしれません。 時間がないので、取り急ぎ。
DALL-E3をファインチューニング?うーん、どういうことだろう?
omostを使ってるってことかな?DALL-E3にスタイル学習の機能はないと思うけど、何度も何度も言うこと訊かせるとだんだん画風にあってくる現象は確かにある。
後半の
自分の絵を使わないのは、読者の範囲を狭めてしまうと考えたからです。この表紙絵に対する反応を見ても、著者の名前や経歴など知らない人が圧倒的多数だと思われますので。
ここも興味深いね。ものは言い方という感じもするし、結局、わいのわいの言ってる人も、誰が言うか、誰が何を書いたかというコンテキストによって炎上させているだけで。
マーケティングとして賢い。オーガニックにこの書籍を買う人は本当に専門家しか居ない、しかもその専門家も知財検定を受けるようなレベルだったら知財検定テキストを読んでいるはず(来月試験です)。
まだAmazonには並んでいなかった
マンガ家と学ぶ著作権実務入門
すがやみつる 著
澤田将史 法律監修
マンガ家と学ぶ著作権実務入門
2024 年 7 月 17 日 刊行予定
ISBN978-4-88367-398-8
四六判 約230頁
定価 1,980 円 (本体 1,800 円+税 10%)
内容紹介
マンガ・イラスト・ゲーム・小説等に関連する著作権について,著者自身の実務面での体験をふまえ丁寧に解説したクリエイター必携の一書。近時,話題の尽きない生成系AIにも言及している。マンガやキャラクターの活用を考えている企業や自治体担当者にも有用。
【追記】書影にある女性イラストは画像生成系AI 「ChatGPT-4o」「DALL-E3」に、すがやが描いたサンプル画像をアップロードし、「ブラッシュアップ」を依頼したもの。マンガスタイルの画風の排除など十数回の修正を経て決定したものをPhotoshopで加筆修正
目次
第一章 知的財産権とは?
第二章 著作権と著作者人格権
第三章 著作者人格権にまつわる事件
第四章 パロディと二次創作
第五章 制限される著作権
第六章 原作つきマンガの著作権は誰のもの?
第七章 キャラクターと著作権
第八章 建築と美術の著作権
第九章 写真の著作権
第十章 必ずバレるトレパク
第十一章 ゲームの著作権
第十二章 生成系AIと著作権
https://www.amazon.co.jp/dp/4883673987
刊行記念トークイベント開催決定!!
2024年8月25日(日)14:00~15:30
@ジュンク堂書店池袋本店9Fイベントスペース+オンライン配信
*詳細は7月10日頃に「丸善ジュンク堂書店オンラインイベント」サイトで発表されます。
まあ面白そうな本なので期待。
そんなわけで今日は
「画像生成AIは飽きる」っていう問いが、私を成長させました。
こちらのイベントもよろしくお願いします!
【生成AIの社会と倫理】今週水曜日です
障害者当事者からのご意見もけっこういただいたので紹介しておきたい
画像生成AIは飽きる、飽きられる、だからこそプロの仕事はこうなる。|しらいはかせ(Hacker作家) @o_ob #note https://t.co/CuVl8pUaCW だってツールだもんね(^^)…
— 藤本恭子(はるうさぎ)/双極性2型障害と共生中 (@haruusagi_kyo) June 25, 2024
「道具の使い方の問題ならば、他者に見せてみるしかない」という一文が、最も印象に残りました。
— 大石 勾 (@magari_ohishi) June 25, 2024
自分が絵を描く場面を、動画で発信してみようかと考えています。
画像生成AIは飽きる、飽きられる、だからこそプロの仕事はこうなる。|しらいはかせ(Hacker作家) @o_ob #note https://t.co/TzBBTSjBcH
初めてトレンドに乗った
【最新】今日の注目記事はこちら!
— note (@note_PR) June 26, 2024
👇ここからお読みいただけます。https://t.co/BuYuhRFVoD@Ukikusayukinnko @105_twi @yhiroak @nobu_ykhm @o_ob pic.twitter.com/Zpol2wbXFl
有料のマガジンです。ちょっとえっちな内容があるかもしれない
会社のnoteもあわせて年間700本ブログを書いています
X(Twitter)@o_ob です
偶然ビール飲んでたら書籍を紹介できたイラストレーターのバーバラ・アスカさんへの返信を自然体でブログにして、Gemini AI Studioでタイトルを壁打ちしただだけの作なんだが過去イチでバズった…
— Dr.(Shirai)Hakase しらいはかせ (@o_ob) June 26, 2024
画像生成AIは飽きる、飽きられる、だからこそプロの仕事はこうなる。 https://t.co/gnqqvsYvnY
補足:冒頭のイラストレーターさんより
いちおう申し上げますが、私は「AI創作は飽きる」と言いました。「画像生成AIは飽きる」とは言っておりません。
私は画像AIは初心者ですが、音楽生成AIはそこそこやっておりますので、先のような発言になりました。
画像生成AIに限定されますと、また話が違ってくるかもしれません。
そうなんですね
私の勘違いってことなのですが、オーガニックに傷ついて、
そこで気づきを得てしまっていた私。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
