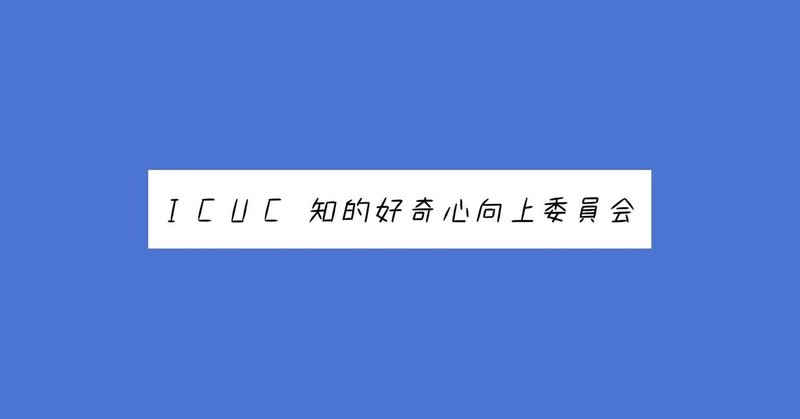
ICUC-106_2022.4.23【何かがわかること:世界と自分の接続】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
角田陽一郎106「何かがわかること:世界と自分の接続」ICUC知的好奇心向上委員会
なんとなくこの2年あまりの鬱屈とした感情が、今週明けた気がします。
そんな極めて個人的な、でもなんかとても世界と接続できたようなお話です。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
明けるきっかけになりそうな想い
おはようございまーす。角田陽一郎でございます。知的好奇心向上委員会でございます。106回目かな?もう土曜日も終わって間も無く日曜日になる感じですが。この時間にね、生配信するのって意外に初めてかな?と思うんだけど。今日、やってみようかなーなんて思ってやっております。だからそんなに見る人いないかも知れないけど、ま、アーカイブですからね。って言うことでやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。
えーと、…あ。彩さん。むしろ彩さんこの時間だとすぐ入ってくるな(笑) どうもこんばんわ。よろしくお願いしまーす。えっとですね、何でね、今日、今やろうかなーと思ったかと言うと。タイトル何にしたっけな?「何かが分かった」みたいなタイトルにしたんですけど。なんかね、ちょっと何か分かったことがあるなーなんて思って。うん。だから今日、今、話したいなーと思ったんですね。だから逆に言うと分かったばっかなので、そんなにちゃんと言語化されてないんですよ。本当はもうちょっと (咳) 言語化するとね、(咳) すいません、咳しちゃった。うん、言語化するとね、いいんだろうなーなんて思うんですけど、言語化されてないんだけど分かったっていうこの感覚のうちに喋っちゃった方がいいんじゃないかなーなんて思って喋ってみようかなーなんて思っております。
でね、そのことを喋ることでじゃないんですけど、何かね、今週ちょっとボクの中で一段落した感じするんですよね。うん、なんか、それこそさっきキャプションって言うか解説か…YouTubeの解説に書いたのはもう本当ここ2年ぐらい──2020年の今頃ってちょうどコロナですもんね、うん──なんか父の病気とかね、あと色々コロナで篭ってたじゃないですか、ちょうど2年前とか。だから何かあの頃から感じていた鬱々とした感じみたいなものが…明けたまで言うと語弊があるかな?明けた…明けるきっかけになりそうな思いが出てきたみたいな、そんなような感じなんですよね。ちゃんと言語化できるか分からないんですけどまあ話してみようと思います。
ボクが思ってることは書いてある
うーんとね、どこから話そうかなーという意味ではですね。まあ最近本読んでて。ちょっと哲学チックな本、メルロ=ポンティとかね。あとは千葉雅也さんの「現代思想入門」みたいな本当かを読んでて。メルロ=ポンティだと「眼と精神」の話って前にしたと思うんですけど──とか読んでて、何かね、ボクが思ってることを書いてるんですよ。書いてあるんですよ。(笑)うん。で、千葉雅也さんの「現代思想入門」とか読んで、デリダとかね、それこそフーコーとかね、なんかそういう人のを読んでて、その人が現代思想とは何なんだ?みたいなことが千葉さんがすごい分かりやすく書いてるから、うん、なかなか読んでて…。
でも書いてあることを読んでですね、これボクが今思ってることじゃん!って思ったりしたわけですよ。で、それって…だから、何て言うんだろう?例えば学問をやるときに学問って自分が思ったことを書くわけじゃなくて、先人達がどのようにそれを論文で書いていたかをちゃんと引用しなさいみたいな話ってあるじゃないですか。まあ、あるわけですよね。それって引用文を面倒臭いなーって思いながらも、一方でそういう自分にユニークな考え方が無い人は、無い人だからそういう過去の論文を引用して論文をまとめてるということにボクに中ではちょっとした抵抗みたいなものがあったんですよね。うん。だって自分が思ったってことが──。
でもね、ボクがじゃあ思ってることがあるじゃないですか。で、思ってることがあるんだけど、そういう哲学の本とかを読んでると「あれ?これボクが思ってることと一緒じゃん。」って思った時に、なんかこの過去の哲学者が論考みたいなものを先行研究を参照しなければいけないみたなことじゃなくて、ボクが今思ってるこの想いみたいなものはまさにその先人達の想いがどこかで読んだのかどこかで見たのかということ以上に社会の中でそういう思想みたいなものが流れていて。で、ボクが世間というかこの世界にいる時に、──例えばじゃあAの方がいいな、Bの方がいいな、って思った時に、ボクはAだなって思うというか。右かな?左かな?ってときにボクは右だなとか。上かな?下かな?っていうとボクは下の方だなって取捨選択するみたいなものが1個ずつ世界で生きてるってあるじゃないですか。社会で生きてると。で、それをそういう風に選ぶ、そっちの方を選ぶみたいなのって、ボクの趣向である意味オリジナルなのかな?と思ってたんだけど、そういうね、例えばフーコーが言ってることとかを見たら「ああー!」とか、ドゥールーズが言ってることはこうなんだとか、デリダが言ってることはこうなんだとか。…「あれ?」みたいな。「同じじゃん?!」って思った時に、むしろそこから過去を参照して、先行研究をあたれじゃなくて、もう自分が頭の中でこういう思いになってるみたいなものっていうのはそういう考え方の積み重ねみたいなものがボクの中に堆積してきて、堆積してきて、堆積してきて、今ボクがいるんだなーって思ったわけです。
世界の堆積
いや、だから何なんだ?!って話なんですけど。だから例えばそうするとなんかこうボクが言いたいことを先行研究を探るじゃなくて、ああボクの考えってのはこの人のこの考え方と、この人のこの考え方がミックスされてるものなんだなと言うか。ボクという実態というか、実態というかボク自身か分かんないけど、なんか所詮その程度なんだよなーなんて思ったし。ああ、だから…何て言うんだろう?学問って先行研究すべきだって意見もなんかすごく腑に落ちたというか。自分という頭の中がどうなってるかってことは過去の成分で出来てて。その成分がデリダ○%、フーコー○%とか、別にパーセンテージで出るかどうか分かんないけど、そういうようなものなんだ、それを記述しろよ、それがつまり論文なんだって言われてるだなってことにやっと気づいたのかも知れないですね。
うん。何かこうそれは不思議ですよね。ボクは今 moving movies っていう週刊プレイボーイで連載してて。それはWEBでも見られるから見たい方、読んで頂けると分かるんですけどね。ゲストで出てくる俳優さんとかタレントさんとか映画監督さんの好きな映画を聞きながら、その人の人生がムービングしたきっかけ、その映画を観て俳優になったとか、その映画を観て映画監督になったみたいなきっかけを教えて頂くんですね。で、最後にそのパネルを描いてもらうんだけど、今の自分の頭の中にその映画が○%占めてますか?みたいな円グラフ、脳内メーカーみたいなものだね、を描いてもらうんですよ。ってことはやってんじゃん!!って、ボクね。既にね。だから映画ではその人の人生を構築している映画みたなものを探るみたいな連載やってるくせに、自分という人間の考え方っていうのはそういう要素で出来てるっていうことに今更ながら気づいたっていうか。だからボクが50年生きてきて、50年以上生きてきて、ガンダム観たりとかね、うる星やつらを観たりとかね、ヤマトを観たりとかね、ムーンライダーズを聴いたりとかね、映画を観たりとか、小説を読んだりとかっていうものがたぶんそういう思想とかが絡められたもの…みたいなもの、それは別に意識か無意識かは置いといて、捉えたものをずーっとずーっと1970年から2022年まで生きてきて、その堆積なんだなボクはっていうことに…なんかね、ちょっとした安心感みたいなものを持ったのかな。なんかボクはオリジナルじゃなきゃいけないみたいなことをも思ってたのかも知れないし、そんな風に…うーん、だからボクという存在は何なんだろう?みたいなこととかを思った時に、なんか実は自分というのって入れ物でしかないんじゃないかって。それはどちらかと言うと悪い意味というより良い意味で。その入れ物の中に何か積み重なって…お重のようにね、お重の中をパッと開けると幕内なのか…何か、うん、そういう様なもので自分というのは出来てるんだなってことに気づいた時に、何か自分と自分以外の世界、体内、体外的なもののコンフリクトと言うか、そういう軋轢と言うか、そういうものに何か悩んでる必要ないんじゃないかなってちょっと思たっていうことなんですよね。
ね。ちゃんと言語化出来てます?出来てないでしょう?で、これ、ちゃんと文章にするとちゃんとした本になるなーなんて思ったりもするんですけどね、うん。なんかね、そんな考えがパッと出てきて。そうすると何かボクはそれこそ博士論文書こうと思ってるんですけど、「あ、何か書けるな!」って思うというか。で、何かいま本がね、発注が来てるんですけど、まだなかなか書けないからここで描いてる…絵ばっか最近描いてるんですけど。何かでも…うん、何か書けるなーって気がしてきたっていう様な意味では、なんかちょとホッとしたみたいなことがあるかなーみたいな。
あともう1つはね、何かこうそれって結果的に対外的な軋轢というか距離感みたいなものを感じると同時に、何か対外的なものに甘えてる自分みたいなものってのをずーっとボクは考えてたんだけど。対人間──ん〜、だから”かまってちゃん”かも知れないしね。だから”かまってちゃん”である自分というのもあるかも知れないし。じゃあこのYouTubeでも、コトブキツカサさんとやってる寿司特でもね、もっと見てくれよ!みたいな、世間にどう評価されるのか?みたいなこととかね、それって評価してくれよって言ってるっていう意味で他者への甘えみたいな。他者への愛情の要求みたいなね、ことじゃないですか。
それって何かこう…世界と自分を分け過ぎてたからそう思ってるんだなーと思った時に、自分の中に堆積されたものって結局世界から受信したもので堆積が詰まったものが自分だとすると、あれ?そこでエラーを起こすというか齟齬があるっていう事ってなんかちょっと…ちゃうんじゃないかなって思ってきた、あるいは思えた。というのが本当に今日、昨日、一昨日ぐらいの自分の変化なんですよね。うん、なんかそれってね、うん…なんかちょっとスッキリしたんですよね。
今週の月火水木曜日
でね、今週。それこそね、最初の月曜日、18日は桜美林大学で今ボクは映像ビジネス論っていう講義を、非常勤講師でこの4月からやっていて。一発目の授業だったりとかしてね。で、火曜日には美術展を観にいったりとかしたんですけどね。で、その後「考具」の加藤昌治くん、ボクの同級生、高校のね…と、あんちょこライブ配信やって。で、水曜日には大阪行って、大阪の国際ファッション専門職大学でメディア概論っていうものの講義をやってるんですけど、そこで抗議してね。で、ちょっと人と会う約束してたんだけどそれがすっぽかされたりしたんですけど。前だったら何ですっぽかされてんだよ!ってちょっとイラッと来たりすんのかなーと思いながらもそんなにイラッともせず…みたいな。で、今ここに描いてある、描いてる絵は油絵なんですけど、油絵ってなかなか乾かないから、油絵は基本ここのアトリエで描いてるんですけど。アクリルの方はね、すぐ乾くんで、せっかくだからアクリルセット持って行ってみようと思って持って行って。で、大阪で一泊してるときに何か絵を描いてたりしてね。なんかすごい…旅先で絵を描いてるのか?!みたいな、よく分かんないけど。まあそんなことをやってたりして。そうすると何かが見えてくるっていうかね。まあ…見えて来たんですね。で、そんな中で今さっき話した様なことを思ったりして。
で、木曜日、急いで帰って来て、ミュージシャンの曽我部恵一さんのね、まさに集英社のmoving movies の取材があったんで、帰って来てすぐ曽我部さんと話して。で、曽我部さんはボクは音楽が大好きなんですけど、曽我部さんの音楽も好きだけど、うちの番組に出てくれたり。2回くらい出てくれたりしてて。で、ボクが好きなムーンライダーズの鈴木慶一さんさんのね、プロデュースを曽我部さんがやったりしてるから、なんか久しぶりに会ってお話しして面白かったし。
その後、今度また新しくやろうと思ってる動画コンテンツがあるんですけど、なかなかね、本当は2月ぐらいから始めようと思ったんだけど、なかなかキャスティングとかがうまく行かなかったりしてたりとか。あとスタッフ繰りとかね。そういうのが上手く行かなかったみたいなのもその後カフエ マメヒコで…もうすぐ閉店するカフエ マメヒコで会議とかしてたらね、何かそれも上手くまとまって。
で、そしてその時に木曜日だから寿司特、コトブキツカサさんと寿司特という、コトブキツカサスペシャルという動画をライブ配信してね。で、今回ね、「リップサービス」ってテーマにしたんですよ。リップサービスって意味よく分かんないじゃないですか。意味分かんないんだけど、つまりボクの中ではそれ見ていただいた方は…まさに寿司特を見ていただきたいんですけど、吉野家の問題ありますよね?あのおっさんが言ってることはたぶん100%悪いことなので、まあそれはいいじゃないですか。いいっていうか良くないんだけど、良くないってことで世間が罰してるわけだから、まあいいんじゃないかなと思うんですけど。たぶんあの方がそういうことを言っちゃうのって大きなリップサービスですよね?リップサービスであんな酷いことを言っちゃうと罰が加わるというのはいいんだけど、実はもっと影響力がある人が…、政治家とかね、こんなこと言ってるみたいなリップサービスだったりとか、じゃあ芸人さんがちょっと最初に笑わせる時にちょっと過剰なことを言うのもまあリップサービス…いい意味でもね、リップサービスだなと思った時に、世間はリップサービスに溢れてるなと。それってネットで記事書いた時にバズる様なキャッチフレーズを入れようみたいなのはよくあるけど、なんかそれがうん…その映画がヒットしてるか分からない、大ヒット映画上映中ってCMするよねーとか。そういうのも全部リップサービスだよなーなんて思った時に、悪いことを言って罰せられるリップサービスだったらむしろ健全で、罰せられないうちにどんどんリップサービスで思想が固まって行くのってすごい嫌だなーみたいな話を思った時に「リップサービス」ってタイトルにしたわけです。
で、つまりそれってバズる様なタイトル──、うーん、それでバズってないからまたあれなんですけど、バズる様なタイトルを付けなきゃいけないみたいな呪縛みたいなものはもう止めて、「リップサービス」意味分からなんなと。だから来週のコトブキツカサさんとの寿司特ではね、いっそのことショートケーキってタイトルで「ショートケーキで何話すんだろう?」みたいなことの方がむしろ面白いんじゃないかなってちょっと思ったりしてね。だからそれって世間に甘える必要…世間にこの動画をたくさん見てねって甘える必要が、甘えるというかおもねる必要がないかなっていう。おもねる必要がないと言うとちょっと勝ち気な感じがするけど、もっと甘える必要ないなって言い方だともっと、こう、自分と世界っていうもののスタンスが変わったっていうさっきの話の、ボクの中では延長線上なのかも知れないですね。うん、まあそんなことをやってね。
随想集 <9>
で、それでその後、いま随想集って、「角田陽一郎 随想集」ってのをAmazonのKindleで出してて。今8まで出てて、 <9> の編集作業をね、やったわけですよ、スタッフとかと。で、やってて、写真決めたりして。で、随想集ね、一応 <9> で完結なんですね。つまりあれってメルマガで書いて来た文章みたいなものを再編集したりしてやってるんで、もうずっと…だから2017年ぐらいからずーっと溜まってた文章を随想集1、随想集2とやってきて。で、随想集…来週とかにアップされると思うんですけど随想集 <9> は編集は見えたわけですね。で、それって <9> の最後の文章は本当に先日満月だったんで、まさに1週間前に書いたエンターテイメントの復活、「エンタメの復活」っていうタイトルでこのICUCで喋りましたけど。あれってあの時のメルマガDIVERSEでも「エンタメの復活 Easter of Entertainment」ってタイトルで文章にしてるんですけど。まさにその文章が角田陽一郎 随想集 <9> の最後の章になるわけです。
…な時に。そのまさにさっき2年ぐらいの自分の思いがちょっと一息ついた、一段落したなみたいなことを言ったんですけど。それってむしろボクがフリーになって、2017年からフリーでバラエティプロデューサーとしてフリーランスで生きてるんですけど。そのまとめみたいなものが、ネガなのかポジなのかみたいな意味で言うとエンタメの復活っていうので終わるってなんかすごいポジティブに終わったなーって。終わるんだなーって思った時に、今言った月、火、水、木と来て…うん、なんかね、うん、なんか、一段落したと言うか、一息ついたって感じがすごくしたんですね。で、その随想集でまとめたことでこの6年間くらいのボクのフリーになってからの思いみたいなもの、まさに随想した気持ちみたいなものとかが何かこうちゃんと整理されて文章として出版されるという運びになって。うん、何か、何かこう見えた。その中ではね、多分に…少しの良いことと、多分にウジウジしていることと、悲しいこととか、怒りとか、そういうようなものがたくさん詰まってるんですね。だけどその詰まってるものってさっきのボクという人間ってのは世界から色んなものを受信したもので出来た重箱なんだっていう話をした時に、その重箱の中身がね、数の子なのか、昆布なのか、黒豆なのか分かんないけど、お節だとしてね、何かそういうものって苦味だったり、怒りだったり、悲しみだったり、愛情だったり、憎しみだったりみたいなこと…みたいなものっていうのが、何かこう綺麗にまとまったんだなーって思ってね。ああ、何か、終わったんだなっていうような感じがちょっとしたんですよね。その終わったんだなっていうのは終わったっていう諦め的な終わりとかではなくて、なんかすごい清々しくて。うん!これでいいのだ!じゃないけどね。これでいいのだって思たと言うかね。うん、だからこう……何かね、スッキリしたんですよね、すごく。
で、そんな中で先ほど冒頭で述べた自分の想い。今コメント頂いてますね。「先行研究を探るんじゃなくて、先行研究に出会う時に出会う。出会うためにボクはボクの積み重ねを続けているのかな。」ってコメントいただきましたけど、そうかも知れないですね。だからそれってもしかしたら随想集というものが結局 <9> 巻まで行って、来週とかに発売されるってことで、自分の中の文章の積み重ねが出来たし。もしかしたらこのICUCってのもね、こうやってずーっと2年ぐらい喋って来て…、うん、ちょっと一息ついたのかな。
今週の金曜日
で、それで金曜日、昨日。昨日もね、色々──そっか、最初にね、あれだ、リモート会議を朝からやってたんだな。で、やって。その後リモート会議2つくらいやって。で、この海の街からそのまま東京に行って。夜にはね、東京画廊で山本豊津さんとライブ配信を「豊津徳(ホズトーク)」ってのをやってね。そこで韓国のアーティストの方の展覧会を見て。その豊津さんの話が面白かったんですけどね。そんなことをしたりとか。で、午前中以降ミーティングやって、午後イチのミーティングまで時間があるからじゃあ油絵描いちゃおうかなーなんて思ってコレ描いたんですね、コレ。で、何か最初にこっちの方を描いたんですけど、そしたらちょっと絵の具が余ってるからと思って今度はこっちの方を描いたりとかして。まあ見せる様な大したものじゃないんですけど。で、何かこう、何かスッキリしたと言うかね、うん。何か対外的なものにすごい執着すると言うか依存するみたいなことは嫌だなってことをししない方がいいやってことを思ってて。常々そんなことを言ってるんだけど。対外的なものに執着しちゃダメだとか、依存しちゃダメだって言ってる段階ですでに対外と対内を分けてますよね。で、そんな分ける必要がないっていうことに気づいた…の、かなぁ。ボクがこの世界に生きていて、ボクが普通に生きるということでただそれでいいのだな、と。で、その時にそれを一緒にやる人もいるし、一緒にやらない人もいるし。で、それをやって何かを作って、それが受けるもあり受けないもありっていうこと。で、その時に自分がこう思うとか、いやこれは違うと思うとかっていうことは積み重なって行くっていう…こと?うん。
──何かあれですね。大学で、2つの大学で教えてて。教えてるというか…ね、若い、19歳とかから21、22歳くらいの方達がね、一生懸命聞いてくれて。ボクが話すとリアクションしてくれたりして。で、ボクはすごい喋ってると思いいますけどね。すっごい、すっごい、こーだ、あーだ、喋ってて。過剰なぐらい。でもそうするとやっぱり反応してくれるみたいなことってむしろそのリアクションでボクが気づくことがあるなーって思うと、──例えば普段何か世界に悲しいことがあったとか嫌なやつがいてみたいなこととか、あああの人はボクの気持ちが分かってくれないんだなとか、みたいな話って、一方で一生懸命授業を聞いてくれる学生さんがいるみたいなことと、悲喜交々って言うか、何でもありじゃないですかって思った時に、何でもあるから面白いんだよなっていう。常日頃ね、バラエティプロデューサーのバラエティってのは色々って言ってるけども、まさにそういう事なんだなってことに…思ったんだなぁ。
世界の決まりの決められ方
今コメントいただきましたね、彩さん。「随想集を最初に出そうと思った理由はなんだったか覚えてますか?そこから <9> のエンタメの復活の満月感という完は、かなり予想外でしたか?」…ああ。随想集を最初に出そうを思った理由はですね。やっぱり自分の今まで書いてきた文章が結構あるから、それをちゃんと形にしたいなーって思ったのと、あれは今Kindleでしか読めないけど、あれちゃんとペーパーバックで印刷できるようにしようかなーと思ってて。やっぱりボクは紙の書物ってのが好きだから、自分の想いというのを随想集という形で出すっていうのをやってみたかったんですね。何かそれがやってみたかったみたいなことだったんだけど、結果自分の思想の40代後半から50になっての思想の変遷みたいなものになってるから面白いなーと思いますね。
で、「そこからの <9> のエンタメの復活の満月感という完はかなり予想外でしたか?」って言うか、<9> のタイトル、いつもタイトルは決まってますよね。 <1> は「激しく健気なころの夏をとりもどせ」とかね。<7> は「コロナな世界」とか…<6>6か!「コロナな世界」とか。<8> は「8月の全ての悲しみにさよならを」とか、いつもその随想集を象徴する文章を書いてたりタイトルにしてるんですけど。 <9> もね、色々考えて。結局タイトルはですね、「世界の決まりの決められ方」っていうタイトルにしたんですよ。それは「世界の決まりの決められ方」っていうタイトルはボクが今やってるnoteの中に基本は自分のオピニオンを書いてる文章が多いんだけど、そこだけはフィクションを書いてて。
で、実はそのフィクションで書いてる部分とかも全部随想集に入れて1章になってるんですけど。その1章のタイトルが「世界の決まりの決められ方」なので、随想集の <9> は「世界の決まりの決められ方」ってタイトルにして写真とかも選んでね、表紙にしたわけですよ。
で、そうなった時に、それって世界の決まりの決められ方っていうのってボクは何か書き続けたいなーって思いがあって。で、その世界の決まりの決められ方っていうのは本当にどうやって決まったのかっていうフィクションじゃなくて、ノンフィクションみたいな意味があるけど。でも世界の決まりなんていつの間にか決まってて、そんなの記述できないじゃん!でもそういう風に決まって行ったんだなって事を作品として、フィクションとして描くと何かボクのフィクションってそういうものになったらいいなーなんて思いがあって。で、書いたりしてて。で、それが随想集の中に入って。で、随想集が「世界の決まりの決められ方」ってタイトルになった時に、「あ!初めて随想集になったんだな!」それまではもうちょっとオピニオンを言ってるって意味で言うと、角田論考集みたいな感じもちょっとあるよなーなんて思った時に、やっと去年のね、8月に『AP』って本を出して。小説を書いて。それはフィクションですけど。ああ、そのフィクションとリアルな世界の接続みたいなことがやっと出来たんだなーって思ったりしたわけです。なんかそういう様な思いみたいなものって、さっきの世界と自分の接続みたいな意味で言うと、現代思想のあらゆる要素ってボクの脳内に入ってるんだなっていう。もしかしたら現代思想だけじゃなくてその前のハイデッガーとかね、フッサールとかね、さらにその前のデカルトとかね、さらにその前のソクラテスとかプラトンとかね、アリストテレスみたいなものまで含めて全部入ってるんだなーっていうのが…。すると、何かやっと接続感が出来た、その接続してる世界とコンフリクトしなくていいじゃんみたいな。する必要もないし、そもそもしないんじゃないかって思える様になって来たみたいな。そんなことが分かったっていうお話でございました。
はい。夜分遅くにありがとうございました。ではまた来週よろしくお願いします。知的好奇心向上委員会ICUC、バラエティプロデューサー角田陽一郎でございました。
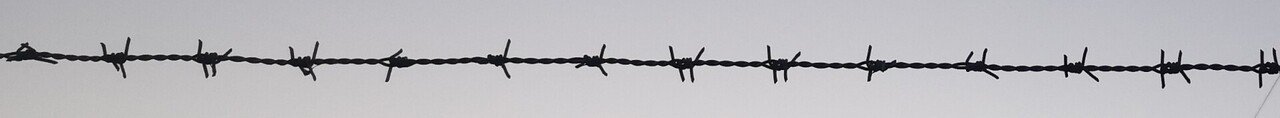
文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
長い歴史の文脈の上に2022年4月23日の角田陽一郎がいる。千年後の3022年という文脈の上に乗っている誰かには2022年の角田陽一郎がいる…かも知れない。その人が出会い積み重ねた思想や知識の中にバラエティプロデューサーがあれば。
考えを捏ねくり回すという言い方がある。捏ねてるだけで問題解決には動かないというイメージが強いけど、角田さんの場合は捏ねくり回しながら問題解決になりそうな方面へも、全く関係ない方面へも出掛けていき、あっちで胡麻をくっ付け、こっちで豆をくっ付け、思いつきで砂糖を足し…としてるうちに、”オリジナル美味い餅”が出来たみたいなことがよくある(様に思う)。そもそも問題解決という表現が間違っている気もする。問題が有って無い様だというモヤモヤを捏ねくり回していてるから延々と餅を製造できると言うか。
この時間に生配信ってあった様な気がするけどツイキャスだったかも知れない。見る人いないかもと言った矢先に入っちゃって…テヘ。今回は豊津徳聴きながらの作業中だったからすぐに通知で分かったけど、どうもYouTubeの通知が安定しないのが気に入らない。日曜なんかずっと気にしてるのに通知が来なかったり、運悪くデバイスから離れてたり。mireva channel だけ通知音変えたいくらいなのにな。
言語化されてないうちに喋った方がいい。夢もそう。どこかにすぐアーカイブしないとすぐに忘れて見つからなくなる。買い控えた本屋の本みたいに。
鬱々とした気分が明けるきっかけになる想いの出現。大きな波の中で上下する小さな波。ICUCが始まってからずっと鬱々してきた→明けたと繰り返していると思う。その1つ1つの鬱だ明けたの話は、よく観察すれば大きな波か小さな波か分かるんだろうけど、ほとんどが小さい波の話で、今回は大きな波の方だったのかな。
ボクが思っていたことが書いてある。セネカだっけ?「現代人は時間がない」と言った…1000年も前から人は忙しくて時間が足りないと思っていた。ボクが今思ってることを、時代も環境も状況も違う誰かが思ってた。”結局”とか、”つまり”とか、”本質的に”とか、そうやって芯の部分(真な部分?)は時がたっても、場が変わっても、状況が違っても、通じるものなんだろう。
角田さん仰いましたよね?この世に全く新しいものなんかもう無いと。1%の新しいものを発見するのはごく一部の天才だと。さらに豊津さんは仰いましたよね?アートの文脈にしっかり乗っている上で、その文脈を覆すような作品が歴史に残るアートだと。
私は多くのものを知ってしまったら、それを糧にオリジナルなんて作れないんじゃないかと思ってたけど、角田さんは「だから残りの99%の僕たちはA×Bで、BはボクのBで、ボクの視点で作るんだ」と仰った。それってつまり今晩の話と同じじゃないかと。世界の文脈の上にいるには先行研究が要るし、それは自身の文脈を知る質問として豊津さんが仰った「自分が富士を美しいと思うのはなぜか?」だ。私の原風景から私の思考の歴史と文脈を浮かび上がらせる。
文字寝かしも、初めて話を聞いた時から感想はコロコロと出るけど、メモする間も無く角田さんの話は進み、「分かった!!」と思ったことも忘れ。文字起こししながらも途中途中画面を変えてはメモしておかないと起こし終わる頃には忘れ。角田さんが紹介してた「英語独習方」にも書いてあった「リスニングは自分のスピードに出来ないから最初のうちはじっくり考えられるリーディングの方が効率が良い」を思い出す。
こうして書いてるうちにも思いが2つ以上出て、瞬間的に選んだ方だけが残り、選ばれなかった思いは忘れる。どこに分岐があったかももう分からない。でももしかしたらそんな状態でも思い出せないだけで記憶には残ってたりして、ある時ふと想いが転がり出てきたりしてるのかも知れない。積読の中に今読みたい本を見つけるような。
こいつ嫌い!と感じる人は、なりたくても成れない自分を見ている、つまり羨ましくて仕方がない状態なのだとか。それってボク達は1%じゃないにも言えるのかも知れない。羨ましさを認めた上で”だからボクはボクというオリジナルじゃきゃいけない”ということだったのかなと。オリジナルとは世界から一線引いた対内とも言えるから。対外と対内のはずだけど、もしかしたら体外と体内の話だったのかも知れない。
文字寝かしの前に挟んでる画像はかなり前に撮影したもので、noteには先々の分まで下書きとして作ってあり、撮影するとすぐに細長く切って入れて行くんだけど。有刺鉄線が今回に当たったのはなんだか面白い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
