
論文執筆について思うこと ④・・ガイドさんに従ってみては?③・・バイアスの評価基準から考える
論文の執筆の際には「ガイドラインに従ってみては?」という主旨で、研究デザインに応じていろいろと発表のガイドラインがありますよということを概要として、そして栄養疫学に特化した内容として以前、紹介しました。
論文執筆について思うこと ②・・ガイドさんに従ってみては?①
論文執筆について思うこと ③・・ガイドさんに従ってみては?②・・栄養疫学研究向け
さて、論文を執筆する際のガイドがあると同時に、論文を評価する際のガイドもあります。今回のNoteはそうしたガイドの紹介です。
論文・研究の評価のガイド
そして主旨としてはその内容に従って(応じるように)論文の内容や構成を考えるのもよかろうという主旨です。そうしたガイドラインも複数あるのですが、代表的な二例として次の介入研究のためのもの(RoB2)、観察研究のためのもの(ROBINS-I assessment tool)が挙げられます。
What's the status & expectations of the implementation of Risk of Bias 2 in Cochrane intervention reviews? Read the statement from the Cochrane Editorial Board with recommendations for Cochrane Review Groups: https://t.co/YcPpkUCsZb #RoB2 pic.twitter.com/v1YGXH9IuI
— Cochrane Methods (@cochranemthds) November 19, 2020
A guide to using ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions https://t.co/Tpp9wxG1gI
— The BMJ (@bmj_latest) October 12, 2016
RoB2はRisk of bias (of randomized controlled trials)の略、ROBINS-IはRisk of bias in non-randomized studies of interventionsの略です。これらの論文は、エビデンスを評価する研究者、つまり系統的レビューを行う研究者に向けて書かれています。
「いや、私はレビューを書く予定はないのですが・・」と思われるかもしれません。しかし、このNoteで伝えたいのは、たとえば「あなたの論文は、ROBINS-Iの評価基準、あるいはそれに近い基準によって評価されますよ。」ということです。
別の言い方、しかし私が重要と考える言い方をすると「ROBINS-Iのような評価の仕方に慣れた査読者があなたの論文を裁きますよ。」「その評価に必要な情報が不足している論文は、判断し難いので読み辛い、質として低いと判断せざるを得なくなりますので気をつけて。」という意です。
良い論文とは研究の良し悪しを評価し易いもの(たぶん)
私たちが行う主にヒトを対象にした研究では、問題点がつきもので完璧なものなどありません。そして一つの仮説に対して、複数の研究から得られたエビデンスを紡いで医療のガイドラインや政策に応用したりするものです。このことから研究者は報告された論文を網羅的に検証し、エビデンスをまとめるプロセスを採ります(i.e. 系統的レビュー)。
私たちが目指す論文とは、科学的に価値がありできるだけ問題点の少ない研究をまとめたものです。しかし完璧には至らず何らかの問題が潜在してしまうことを鑑みると、質の良さを伝えるのみならず問題点があるならばその評価を容易にすることも良い論文の満たすべき条件となります。ですので、系統的レビューを行う研究者が研究論文を評価する際にどういったポイントに着目するのか理解しその要点を押さえれば、より良い論文を書くことができるかも。
その要点をまとめたものが上記のRoB2、ROBINS-Iなどに記載されています。ご存知でなかった方は、「あぁ、こういう内容を押さえて論文を書かないといけないんだな」と参考にして頂ければ嬉しいです。
査読者はエビデンスの質を評価してその論文の良し悪しを判断する
基本的に論文を査読するのはその論文に紹介されたトピックのエビデンスを評価するプロフェッショナルです。そんな査読者は、査読をする際にエビデンスを厳しく評価することを目的で読みます。彼らの頭の中には論文を評価するスタンダードが刷り込まれています。そのスタンダードの平均的な事柄が要約されたものが上記のRoB2やROBINS-Iなどに記載されているというわけです。実際にその策定には学術誌のエディター、介入研究や非介入研究のバイアスに詳しい専門家が集って議論を重ねるなどした経緯があります(Stern et al., BMJ, 2016)。
もちろん査読者によって評価基準は異なります(そのばらつきから残念ながら査読者の当たり外れがあるのは事実かと)。とはいえ一般的に押さえるべき内容として、やはり上記のような評価のためのガイドを把握しておくのがよいでしょう。
今回の主旨は以上です。このNoteが査読者の気にするであろう事柄を記載する、記載の目的などを整理する一助となれば幸いです。読んでくださってありがとうございました。
以下は長いのでおまけとしました。観察研究で評価する内容、およびバイアスのリスクを考える事柄のうち、交絡因子の評価方法について触れたものです。ご関心があればぜひご覧ください。
おまけ:観察研究の評価①・・仮説を明確に
ランダム化比較を行わない研究の評価についてROBINS-Iにまとめられた内容を抜粋して紹介します(Stern et al., BMJ, 2016)。ROBINS-Iのホームページはこちら。専門家によるコンセンサスを経て、研究評価を行うパイロット研究から、仮説を明確にしたのちにその仮説に対して七項目のバイアスを評価すべきとして紹介されています。
仮説の設定を明確にするというのは、たとえば薬Aの効果を検証といっても、複数の状況が考えられます。たとえば、
・Aを摂ってもらうよう処方した効果
・Aを摂り始めて追跡した効果
・Aを摂り続けてきた状況から追跡した効果
・Aを摂り始めてその状況を維持した効果
・Aを摂り始めて、Bを摂るのを止めた効果(Co-intervention・・複数項目の介入)
と何パターンか考えることができます。こうした検証したい内容を明確にし、それに基づいて考えるべきバイアスの可能性、そして導かれたエビデンスの質を評価しましょうというのが期待される流れです。
おまけ:観察研究の評価②・・バイアスの源
次の事柄(”ドメイン”)がバイアスを生む原因になり得る事柄として選ばれています。
1. 交絡因子
2. 研究参加者の選定
3. 曝露因子の誤分類
4. 追跡時の曝露因子の変化(定義からのズレ)
5. 追跡時の欠損情報
6. アウトカムの誤分類
7. 報告する内容の選択
これらのそれぞれについて解説と評価すべきとされる内容が論文の補足資料(Appendix)、およびROBINS-Iの解説文書に記載されています。そして各ドメインのバイアスのリスクについてLow , moderate, serious, criticalのいずれか、あるいはno informationか判断することが求められています(意訳:低リスク、少しのリスク、重篤なリスク、致命的なリスク、情報が不十分)。
本筋に戻ると、論文の査読とはこうした事柄について厳しい目で判断することです。ですので、こうした事柄の判断がきちっと可能になっている論文の執筆を心がけるとよいのではないでしょうか。交絡因子についてであれば、その因子の測定方法、妥当性、解析方法などが挙げられます。研究参加者について参加条件、その条件の妥当性に関する感度分析の生むが挙げられます。
私個人の査読者としては、こうした事柄について明確な論文が良い論文だと考えています。文意を損なわない英文法の誤りなどよりも大切なことと思っています。逆に上記の事柄について書かれていない、あるいは不明瞭であった場合、議論が論文の主張に偏っている場合となると、何らかのバイアスが見過ごされている可能性を疑うことになります。そういった負の印象を極力下げられるよう論文執筆にて心がけねるとよいことかと考えています。
おまけ:観察研究の評価③・・交絡因子の評価
バイアスの源として複数考えられるのですが、ここではROBINS-Iでの一例として、交絡因子に関する評価の例を紹介します。
まず求められるのは交絡因子としてどのようなものが考えられるのか指定することです。私の専門領域でよく考えられる交絡因子の例として「社会経済的な因子(Socioeconomic status)」「果物の習慣的な摂取」を図(青色)にしました。

この図の構成は「系統的レビューをする際に考えなさい」という指南になります。論文の査読を考えると「このトピックであれば、○○、××という交絡因子が考えられるだろう」という前提をもって査読者は査読をすることになります。そして、論文を執筆する側は、「査読者は○○、××といった交絡因子による効果はきっと想定しているだろう」と考えるとよいでしょう。・・という話になります。
考慮すべき交絡因子について整頓した際、それに基づいて各研究の交絡因子それぞれによるバイアスのリスクを判断します(緑色の図)。そしてその一つの研究における総合的な交絡効果のバイアスを判断します(オレンジ色の図)。


こうした建設的な評価を経て交絡因子によるバイアスを判断します。論文を書く際のことを考えると、交絡因子の重要性、測定の確かさ、時間依存性、調整した方法(サンプリング、解析など)についてきちっと書くことが大切になると考えることができますね。
同様に他のドメインについても評価を行って、それらの評価に基づいて研究のエビデンスの質を総合的に判断するというプロセスを経ます。それぞれのドメインで要求される情報が異なるので、その点を理解して論文を書くというのが筋となるでしょう。研究論文の懸念材料を明確にする努力は、きっと良い論文への執筆へとつながるのではと考えています。繰り返しになりますが、お役に立てばと思っています。
おしまい。
画像はWallpaperSafari.com & https://wallpaperaccess.com/ より
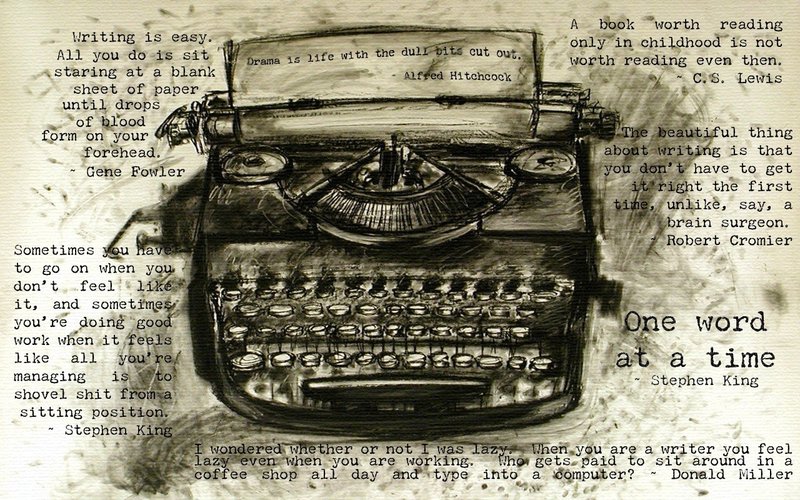
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
