
現役経営コンサルタントが厳選した、実務で役立つ上に面白いビジネス書8選
記事の概要:おすすめのビジネス書紹介します!
こんにちは。NUKです。
この記事では、経営コンサルタントの僕が、独学で経営を学ぶために読み漁った本の中から、特にためになり紹介せずにはいられなかったビジネス書達を紹介していきます。
僕は新卒で国家公務員になったのですが、公務員として働いているうちに、もっとビジネス寄りの立場で仕事がしたいと思い、経営コンサルへ転職しました。
転職を思い立った時、元の職がビジネスと程遠いこともあって「今の自分ではコンサルには転職できない、転職できても入ってから通用しない。」と思い、マーケティング・経営戦略・組織マネジメント・財務会計・イノベーション論等、各分野のビジネス書を読み漁って独学で経営の知識を身に着けました。
その努力の結果、無事今の職に転職でき、コンサルなってから2年以上楽しく働くことができ、社内の賞等もいただくことができました。
そんな僕が、読んでよかった、今も役に立っている、と思う厳選の本を8冊紹介します。
紹介する本の選定基準
今回紹介する本は、以下の基準で選定することで、普段読書が苦手、という人にも読んでもらえるように意識しつつ、読書の楽しさ、本から学べることの奥深さを知ってもらえるように、選んでいます。
今回紹介する本に興味を持って読んでいただけたらそれだけでもうれしいですが、それによって読書の楽しみに気づき、「別の本も読んでみよう!」と思ってくれる人が増えたら、なおうれしいです。
◎その分野の専門知識がなくても理解できる内容である
本を読んでいて最低につまらないのは「用語がわからないせいで読んでもわからない」という状況です。そうならないよう、今回紹介する本は、いずれも専門用語が少ない(あったとしてもその本の中で説明がされている)本を選んでいます。
◎読み物として面白い
どんなに有意義なことが書かれていたとしても、教科書みたいに淡々と描かれている本は読む気が起きないですよね。そういう本は、読むとしても、何か知りたいことがあるときに辞書的につまみ読みする方が適しています。
今回は、そういった教科書的な本は可能な限り除き、語り口が軽妙で、最初から通して読んでもストレスなく読みやすい本を選んでいます。
◎その分野の一級の本である
読みやすさを重視して選んでいますが、だからと言って、内容が浅いわけではありません。今回紹介する本は、いずれも各分野における超一流の本であり、出版されてから時間が経っても、長く名著として読まれ続けているものばかりです。
◎自己啓発本、コンサル本は除く
今回、いわゆる「自己啓発本」は候補から除きました。自己啓発本は、いい本ももちろんありますし、僕もたまに読みます。ただ、自己啓発本は基本的に「やる気を出すためのもの」であって「知識をつけるためのもの」ではないと思っているので、今回はいったん対象から外しました。
また、ロジカルシンキング等のいわゆる「コンサル本」は除きました。これは、今回はコンサルタント向けというより広くビジネス・経営について興味がある人に向けて書いている、というのが理由の1つ目です。また、僕はコンサルタントであるにも関わらず、ロジカルシンキングという手法にそこまで有効性を感じていないというのが理由の二つ目です。(なぜ有効性を感じていないのかは後でお話しています。)
それでは、前置きが長くなりましたが、厳選の本の紹介に入っていきます!
本の名前のところをクリックするとアマゾンのページにとべるので、気になった本はぜひチェックしてみてください!
1.はじめの一歩を踏み出そう

この本は、パイづくりが得意なためパイの専門店を開いたもののうまく経営できず、事務作業に追われパイづくりも楽しめなくなってしまったサラを主人公として、「パイをうまく焼けても、パイ専門店の企業に失敗するのはなぜなのか」、より一般化すると「なぜ得意なことで起業したはずなのに、事業がうまくいかないのか」を物語調で非常にわかりやすく示してくれている本です。
例えば、プログラミングが得意なので、独立してフリーランスのプログラマーとして働こうとしている方とかにはとても参考になると思います。
ネタバレしてしまうと、事業を経営する上で重要なことは「仕組化」だというのがこの本の要点なのですが、具体的にどのような仕組みを作ればよいのか?といったことは、ぜひ読んでご確認ください。
フリーランスの方以外も、「事業を経営する」ということの難しさ、奥深さに興味がある方にはお勧めです。
250ページくらいですし1ページ当たりの文字数もそこまで多くない本なので、ぜひ。
2.良い戦略、悪い戦略

会社の会議で、こんな場面に出くわしたことはないでしょうか
えらい人「わが社の今期の目標は売上15%成長です。」
社員「それは、具体的にどうやって達成するのでしょうか?」
えらい人「今市場は非常に好況であり、わが社の強みを活かせば必ずや~(意訳:どうやってやるのかはわからないけど、頑張ればきっと大丈夫。無理そうならもっと頑張ればなんとかなる!ネバーギブアップ!)」
社員「はあ…。(聞いても無駄だということが)わかりました。」
又は、こんな場面に出くわしたことは?
えらい人「今月は商品Aを発売する。立ち上がりは大事だ。しっかり売ってきてほしい。」
営業「わかりました。商品Aに力入れていきます。」
えらい人「また、うちの主力商品である商品Bも引き続き売らなくてはならないし、商品Cも、X社が競合商品を出してくるので負けないように売らなくてはならない。商品Dは、売れ行きが良くないが、多額の研究費をかけて開発しているので、それを回収するためにもっと顧客にプッシュが必要だ。おっと、商品EやFももちろん忘れちゃだめだぞ。」
営業「(全部じゃん…)」
このようなケースは、多くの企業・部・チームで生じていますが、こういった「とりあえず数値目標掲げてとにかく頑張る」、「全部頑張る」という方針を「悪い戦略」としてバッサバッサと切り捨てて、何がダメなのか、どうしたら成果を残す「良い戦略」を立てることがことができるのか、ということを書いたのがこの本です。
まずは、どのような戦略が「悪い戦略」なのかについて書いた「第3章 悪い戦略の4つの特徴」だけでも読んでみてください。第3章なら30ページ、最初から読んでも80ページくらいで第3章まで読み終わります。
そこで興味を持ってもらえたら、なぜ悪い戦略を多くの企業・部・チームが立ててしまうのかについて書かれた第4章を読んでみてください。
ここまで楽しく読んでくれた方なら、「じゃあどうすればいい戦略が作れるのだろうか。」と気になり始めているはず。そうなったらぜひ、良い戦略に必要な要素について書かれた第5章以降を読んでみてください。
この本で書かれてている戦略の考え方は、事業戦略を考えるだけでなく、やりたいことがたくさんあるのに時間が明らかに足らないとき何に時間を配分するか、自分のキャリアをどの方向に伸ばしていくか等を考える上でも役に立つ、非常に応用の聞く思考方法を与えてくれます。
3.影響力の武器 -なぜ、人は動かされるのか-
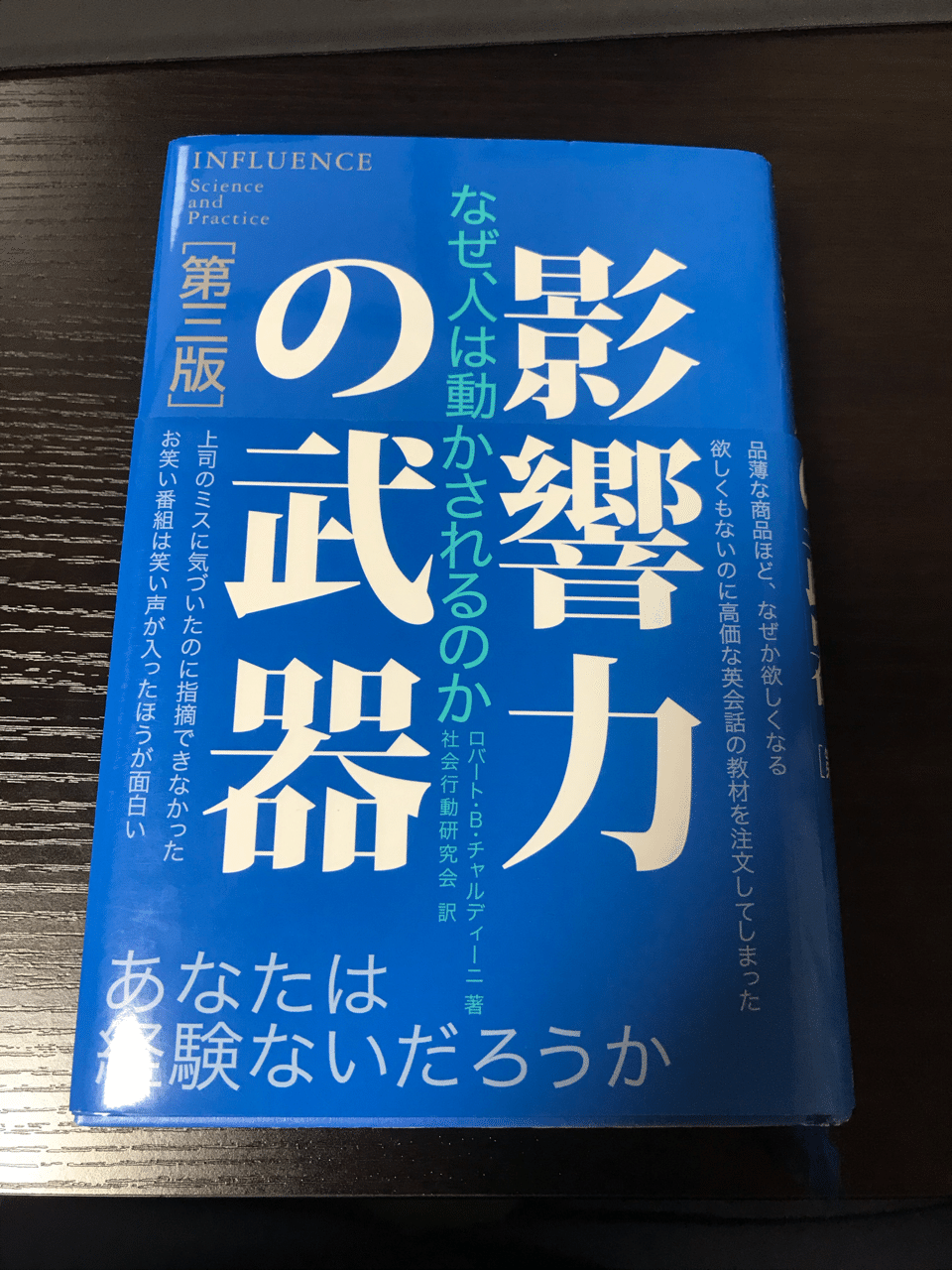
この本は、メンタリストのDaigoさんもおすすめしている本で、本記事執筆時点において、amazonのレビュー数408件、平均4.5点という、ビジネス書としては類を見ないレビュー数と平均点をたたき出しています。
そんなすごい本がどんな本なのか、簡単にご説明しますね。
自社の商品を買ってほしい営業マン、寄附を求める募金者、自分への投票を求める政治家などなど、「他人を自分の都合のいいように動かしたい」と思っている人は私たちの周りにたくさんいます。
この本は、そういう人達から私たちが身を守るために、他人を自分の都合のいいように動かそうとする人たちが使っている心理的テクニックを紹介し、その防衛方法をまとめてくれている本です。(そして、皮肉なことに、マーケターや営業マンもまた、人を動かすためのテクニックをこの本で学んでいます。)
そのテクニックは、人が無意識に持っている以下の6つの要素を利用します。
①返報性:恩を感じると、自分も何か返さなければならないと感じる。
②コミットメントと一貫性:過去の行動と一貫した行動を取りたい。
③社会的証明:みんなが良いといっているものは良い。
④好意:好きな人の頼み事は断れない。
⑤権威:偉い人の言っていることは正しい。
⑥希少性:珍しいものは良いものだ。
「②コミットメントと一貫性」がちょっとわかりづらいので補足すると、例えば、「あなたは良い人ですか?」と聞かれ「はい」と答えた後に何かお願い事をされた人は、良い人であると答えたこととその後の行動の一貫性を無意識に取ろうとして、いきなりお願いごとをされた人と比べて協力する確率が大きく上がる。というようなことです。
これらはいずれも無意識に働くため、私たちの行動を大きく左右しているにも関わらず、そのことに私たちはほとんど気付かずにいます。
おそらく、これを読んでくださっている方々の多くは、「そういう心理的要素があることは否定しないけど、言ってもそこまで大した影響はないでしょ。基本的には人は合理的な判断ができるはずで、それができないのは心理が原因ではなく、意思が弱いか頭が悪いからだ。」と考えるのではないでしょうか。
しかし、この本の豊富な事例は、これらの心理的な要素を利用することの威力がどれほど大きいか、ありありと示してくれます。
大して欲しくないものを買うだけでなく、わけのわからない宗教にハマったり、平気で人に電気ショックを流すようにもなるのです。
心理的な弱点をつかれると人ってこんなにチョロいのかよ、と衝撃を受けることでしょう。
大げさでなく、この本を読んで私は「人間」というものの見方が少し変わりました。純粋な読み物としての面白さでは今回紹介する本の中でもトップクラスですので、ぜひ読んでみてください。
※ちなみに、この本の紹介冒頭で、Daigoさんのおすすめであること、Amazonのレビューが高いことを紹介しましたが、どうでした?「ならこの本面白いんだろうな。読んでみたい。」と思っていただけました?
そうなのであれば、早速あなたはDaigoさんの「権威」と、多数のAmazonレビューの「社会的証明」の影響を受けています。注意してくださいね笑
4.財務3表一体理解法

社会人が「とりあえず取っとけ」とおすすめされる資格ランキング(おそらく)1位に、簿記2級があります。
簿記2級が業界問わず人気がある理由は、財務3表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)を見て企業の経営状況を把握するスキルは、どの業界でも重要だからです。
しかし、簿記2級は基本的に財務3表を「作る」試験です。帳簿の数字をひたすら足しあげたり、数字を帳簿から帳簿に転記したりする作業ゲーです。
財務3表を「読める」ようになることが目的であれば、簿記2級をとることは、無駄にはならないものの、最も効率的な方法とは思えません。
では、効率的に財務3表を「読む」能力を上げるためにはどうしたらよいのか?
この本、「財務3表一体理解法」を読みましょう。
この本は、財務3表が何を示しているのか、に加え、財務3表がそれぞれどのように関係しているのか、モノを買う、仕入れる、減価償却費を計上する場合等に、財務3表にどのように表れるのかを、図を豊富に使いながらわかりやすく説明してくれます。
「損益計算書とか貸借対照表とか、勉強しなきゃとは思ってるけど難しそうだな…。」と思っている人は、この本を読めば財務3表への苦手意識がだいぶ和らぐのではないかと思います。
また、簿記2級にチャレンジしようと思ったものの最初の方の細かい仕分けで挫折した人にとっても、財務3表をマクロな視点で理解することで、仕分けの意味をより深く理解することができ、勉強を進める助けになると思います。
類書もいくつかありますが、私が知る限りこの本が一番よくまとまっていると思います。
ちなみに、この本には「財務3表一体分析法」、「財務3表実践活用法」という続編があります。より踏み込んだ(とはいってもその分野においては基本的な内容ですが。)分析方法を知りたい、という方はそちらものぞいてみてください。
※「一体理解法を買うつもりが間違えて一体分析法買っちゃった!」とならないように注意!
5.稲盛和夫の実学 -経営と会計

この本は、京セラの創業者であり、JALの立て直しでも有名な稲盛和夫さんの書かれた本です。経営における会計の重要性を説き、京セラではどのように経営に会計を取り入れていたのかを示した会計分野の名著です。
同じ会計の本でも、一個前の「財務3表一体理解法」は財務会計の本でしたが、この本は管理会計の本になります。「財務会計と管理会計って何が違うの?」という方もいると思うので、簡単に違いを説明しますね。
◎財務会計
貸借対照表等を用いて、経営状況を外部の株主や金融機関等に示すための会計。外に向けて示すためのものなので、企業会計原則という一定の決まりに従って会計を記録しなければならない。
◎管理会計
経営状況を会社自身が把握するための会計。中の人のためのものなので、どのように記録するかは自社で決めていい。
という違いがあります。
「なんでわざわざ分ける必要があるの?財務会計のルールで記録したものを自社の管理にも使えば、わざわざ2つの方法で会計を記録しなくてもよくて効率的じゃない?」と思われるかもしれません。
しかし、財務会計の記録方法だと、自社の経営状況分析や意思決定には使いにくい面があるんです。具体的にどんな場合?ということが知りたいという人は、ぜひこの本を読んでみてください。
文庫サイズで200ページ足らずと、今回紹介する本の中でも最も薄く、読みやすいので、試しに読んでみてはいかがでしょうか。
6.ファスト&スロー

この本は、行動経済学の研究でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏によって書かれた本です。
従来の経済学が「人間は合理的に行動する」ということを前提にしてきたのに対し、行動経済学は、「人間はそんなに合理的じゃない」ということを前提とし、どのような条件で非合理的な行動をとるのかを研究する比較的新しい学問分野です。
この本では、人間には直観的に素早く判断を下す「システム1」と、合理的にじっくり考えて判断する「システム2」があり、殆どの場合システム1を使って判断しているということを示した上で、行動経済学に関する数々の理論を説明してくれています。
理論と言っても、学術論文のような堅苦しさはありません。「次の問題について考えてみて欲しい。」等と読者への問いかけが豊富にあり、それらの問いについて答えを考えながら楽しく読み進められます。
例えば、以下のような問いかけがあります。皆さんも考えてみてください。
問題1 あなたは現在の富に上乗せして1000ドルもらったうえで、次のどちらかを選ぶように言われました。どちらを選びますか?
A.50%の確率で1000ドルもらえる。
又は
B.確実に500ドルもらえる。
問題2 あなたは現在の富に上乗せして2000ドルもらったうえで、次のどちらかを選ぶように言われました。どちらを選びますか?
A.50%の確率で1000ドル失う。
又は
B.確実に500ドル失う。
この2つの問題は、実質的に同じことを言っています。最初にもらった金額(問題1なら1000ドル、問題2なら2000ドル)も合わせれば、どちらの問題も
A 50%の確率で2000ドルもらえ、残りの50%の確率で1000ドルもらえる。
又は
B 確実に1500ドルもらえる。
となるからです。
なので、合理的なシステム2で考えると、どちらも期待値は同じなので、ギャンブラーな人はどちらの問題でもAを、堅実な人はどちらの問題でもBを選択するはずです。
しかし、おそらく、ほとんどの人は問題1ではBを選び、問題2ではAを選んだのではないでしょうか。つまり、問題1では堅実な選択肢をとったのに、問題2ではギャンブルに出たのです。これは、あなただけでなく、たいていの人は同じように答えます。
なぜこんなことが起こるのか?
まず、問題1についていえば、人はリスクを回避する傾向があるため、50%でもらえない可能性を回避し、確実に500ドルもらうことを選びます。
加えて、人は一度得たものを失うのは、得られたかもしれないものを得られないよりもずっと辛く感じるという性質があります。そのため、問題2では「500ドルだろうが1000ドルだろうが、一度得たお金を失うなんて絶対嫌だ!」となり、確実に損をするBの選択肢ではなく、50%の確率で損をしなくて済むAの選択肢を選ぶのです。
このように、この本の中では、「次の2つの選択肢から1つ選んでください。」→「こちらを選んだのはないでしょうか?」という流れが多く出てきます。そしてこれが気持ち悪いくらい当たります。
これらの知識は、単なる楽しい心理テストではなく、ビジネスにも役立てることができます。
直感的なシステム1の傾向を知り、いつシステム1がバグを起こすのかを理解しておくことで、必要な時にシステム2を意識的に引っ張り出して合理的に判断を下すことができるようになります。
要は「冷静に考えればあんな選択肢とらなかったのに、なんであんなことしちゃったんだろう。」ということが減ります。
事業は難しい選択の連続です。その決断の精度を上げていく事は、必ずあなたの役に立つはずです。
今回紹介する本の中では、上下巻に分かれており分厚い方ですが、章が細かく分かれていてつまみ読もしやすいですし、持ち歩きやすい文庫版も出てるので、上巻だけでも覗いてみてください。
7.クリエイティブ・マインドセット

この本は、ここ数年ビジネス界隈で非常によく聞くようになった「デザイン思考」についての本で、デザイン思考の第一人者であるデイヴィット・ケリーとトム・ケリーの兄弟によって書かれています。
デザイン思考って何?という方もいると思うので説明します。
「デザイナーのための考え方なのかな?」とか「ものの見た目を綺麗にするための考え方なのかな?」と思うかもしれませんが、それは誤解です。デザイン思考は、幅広い問題解決に使える考え方です。
具体的には、何らかの課題解決のために、以下のような手順を踏むアプローチです。
①ユーザーが何で困っているのか、よく観察する。
②困りごとを解決する方法を自由に考えてみる。
③ユーザーの困りごとを解決するための製品やサービスをとりあえず作ってみる。
④ユーザーから感想を聞いて、改善を繰り返す。
※正確に定義しようと思うともっと難しい説明になるのですが、ざっくりと理解する程度であれば、上記程度の理解で問題ないと思います。
これだけ聞くと、「デザイン思考とかカッコいい名前ついてるけど、やってること普通じゃない?」と思う方もいるかもしれませんので、デザイン思考の何がすごいのか、ということを、同じく問題解決のための考え方である「ロジカルシンキング」と対比して説明します。
デザイン思考がロジカルシンキングと比べて優れている点は、大きく分けて二つあります。
まず1つめに、デザイン思考はロジカルシンキングよりも早く判断ができる、という点で優れています。
ロジカルシンキングは、MECE(漏れなくダブりなく)を重視する考え方なので、どういう問題解決方法があるのかを行動に移す前によく検討し、それぞれの選択肢のどれが最適なのか吟味したうえで行動に移ります。そのためロジカルシンキングは、行動に移るまでに時間がかかります。
近年では、非常に環境の移り変わりが早く、時間をかけて検討をしているうちにすでに検討開始時と状況が変わってしまっていたり、せっかく問題解決のための新製品を開発したのに他社に先を越されてしまったりするのです。そうなれば、せっかく時間をかけて検討したものがすべて無駄になります。
一方で、デザイン思考は、検討が生煮えでも、多少クオリティが低くても、とりあえずスピーディーに製品やサービスを作ってみて、使ってもらう中で改善をしていくスタイルなので、移り変わりの激しい昨今の環境にマッチしているのです。
2つ目に、デザイン思考は、それまでにない発想を生み、イノベーションにつなげやすい、というメリットがあります。これこそが、デザイン思考が注目されている最も大きな要因です。
ロジカルシンキングは、どういう問題解決の方法があるのかの選択肢がわかっているときに、どれが最適な選択肢かを考える上では非常に有効なツールです。一方で、「そもそもどういう問題解決の方法があるのか?」ということはロジカルシンキングではわかりません。それまで世の中になかった新しいものを生み出すには、ロジックだけでは限界があり、どうしても「ひらめき」や「感性」の力が必要なのです。
一方でデザイン思考は、左脳(ロジック)だけでなく右脳(創造力や感性)も使いながらアイディアを深彫りしていくため、それまでになかった新しい発想や、新しい製品を生むことも可能です。
一部の天才にのみ可能だと思われていたイノベーションを、普通の人にも再現可能なプロセスとして体系化したこと。それがデザイン思考の最も大きな貢献です。
「最近アイディアに行き詰ってるなー」とか「何かこれまでのものとはちょっと違う新しいものを作ってみたいな」と考えている方はもちろん、「自分は創造力とかないし、アイディア出すとか苦手だな…」、「色々計画は練るんだけど、結局行動に移せないんだよな…」という方にも、ぜひ一読してみていただきたい本です。
8.マイケル・ポーターの競争戦略

利益率の高い会社と低い会社は、何が違うのでしょうか?
利益は、基本的に事業の目的であるはずです(中には「好きでやってるから利益はそんないらん」という人もいると思いますが。)。にも関わらず、日本の名だたる大企業の中にも、超薄利の事業を営んでいる会社がたくさんあります。
私は趣味で株式投資もするのですが、投資先を物色するためにいくつか日本の大企業の決算を見た時は「利益率低っ!ほぼボランティアじゃん!」と衝撃を受けたのを覚えています(どこの企業だったかはもう忘れてしまいましたが…。)
逆に、利益率のいい会社は、業界では有名だったりしても、当時の僕はよく知らないような会社だったんですよね。
そこで冒頭の問い、「利益率の高い会社と低い会社は、何が違うのか?」に興味を持ち調べたところ、その肝は「競争戦略」にある、ということがわかりました。
競争戦略と聞くと、「競争相手を倒すための戦略」だと思われるかもしれませんが、どちらかと言えば競争戦略は「競争をせずに済むための戦略」です。競争をすれば、最終的には価格競争になり、自社も競合もともに利益がなくなってしまいます。なので、他社と差別化をしたうえで、いかにその差別化された状況を維持する「防波堤」を作れるかが競争戦略の要点です。
これだけだとまだわかりにくいと思うので、例を出して説明します。
例えば、あなたがせっけんを作って売ろうとしたとします。せっけんは割と入手しやすい材料で作ることができますし、売るのもメルカリ等を使えば簡単にできるので、参入しやすい事業ということになります。こうなると競争は激化し、利益率は低くなってしまいます。
今後は例えを変えて、あなたは新しいスマートフォン作って売ろうとしたとします。しかし、仮に頑張ってとても処理速度が速くデザインがかっこいいスマートフォンを作れたとしても、全く売れないでしょう。なぜなら、iPhoneのブランドには叶わないというのもありますが、何より重要なのは、iPhoneにはたくさんのアプリがあるのに、あなたが作ったスマートフォンにはない、ということです。アプリも碌になく、電話ができてネットが見れるだけのスマートフォンをわざわざ選ぶ人はいません。しかも、iPhoneのアプリはアップルが作っているわけではなく、無数のアプリ開発事業者が作っています。そのため、あなたがiPhoneのようにアプリを充実させようと思っても、自社のスマホ用のアプリを開発してくれる数千数万の事業者を見つけるか、自社で全部開発するかしなければなりませんが、そんなことはとても不可能です。つまり、「iPhone用アプリを開発してくれるアプリ開発者がたくさんいる」という状況が、アップルにとっての「防波堤」になっているということです。
Yahoo Financeによれば、アップルの利益率は、2019年の決算ベースで21%となっています。日本の企業の利益率の平均が5%程度といわれているので、アップルの利益率は非常に高いといえます。この高い利益率を支えているのが先ほどの「防波堤」なのです。
ここで重要なことは、「技術が高い」、「いいものが作れる」というのは、差別化要因にはなっても、防波堤にはならない、ということです。高い技術は、いつかは真似されてしまいますが、防波堤を築くには、真似されない「仕組み」が必要なんです。
この「仕組み」をどのように作るのか。それを示しているのがこの本、「マイケル・ポーターの競争戦略」です。
マイケル・ポーター博士は、ハーバードビジネススクールの教授であり、競争戦略論の原点にして頂点です。
そしてこの本は、マイケル・ポーター博士の著作「競争の戦略」と「競争優位の戦略」を1冊にまとめたものです。「競争の戦略」と「競争優位の戦略」は、コンサルやMBAでは必ずと言っていいほど必読図書にあげられる超重要書籍なのですが、2冊合わせて1000ページを軽く超え、字も細かいため、これら2冊を読破するのはなかなか大変です。
それを、2012年に発売されたこの本は、読みやすい字のサイズで、たった300ページ程度にまとめてくれています。しかも、マイケル・ポーター博士自身も作成にかかわっているため、オリジナルの良さや深みを失うことなく、エッセンスを抽出することに成功しています。控えめに言って神です。Amazonのレビュー数も、Daigoさんの推薦があるわけでもないのに80件あります。影響力の武器と違って経営学に興味ある人しか手に取らないであろう本なので、80件というのはかなり多い数です。平均点も4.4点と高水準です。(ちなみに私の感覚として、Amazonのレビュー数が30件以上あって平均点が4.4点あったら、その本の品質はかなり信頼できると思います。食べログでいう3.5点くらいの信頼感があります。)
今回紹介した本のなかでは、分野的にとっつきにくく感じるかもしれませんが、とても重要な示唆が得られる本なので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
というわけで、8冊の本を紹介させていただきました。
どれも本当に面白く、ためになる本です。大きな書店に行けば8冊ともだいたい置いてあるので、パラパラとみるだけでもしていただけたら嬉しいです。
最後に、ここまで読んでいただけた方にお願い・ご連絡です。
・この記事やこの記事で紹介した本を読んだ感想・ご意見、ぜひコメント欄にお願いします!今後の記事作成の参考にさせていただきます!
・この記事で紹介した本の他にも、「こんなこと知りたいんだけどいい本ない?」、「〇〇って本が気になってるんだけど読めてなくて、もし内容知ってたら簡単に教えてくれない?」等あったら、気軽にコメント欄に書いてください!同じく今後の記事作成の参考にさせていただきます!
・この記事が役に立った、面白かった、という人は、ぜひフォローお願いします!Twitterもやっているのでよかったらそちらもお願いします!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
