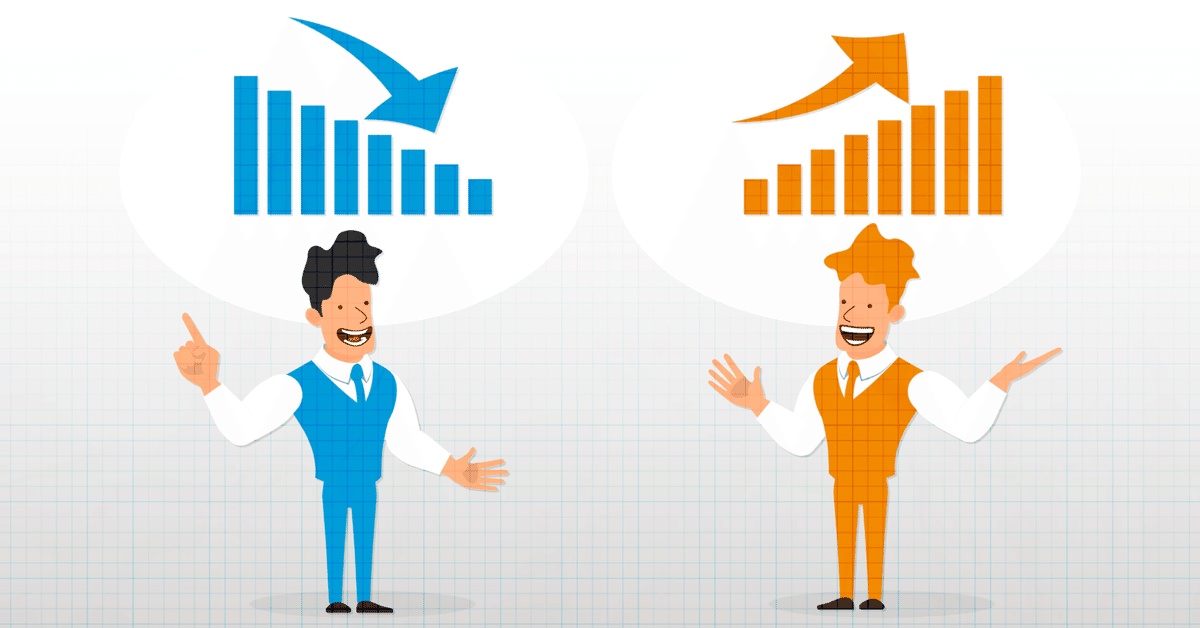
為替レートってどうやって決まるの?②
こんにちは。りろんかぶおです。
私は31歳でFIREを達成し、noteでは「サラリーマンでも若くしてFIREするための具体的な方法を発信」しています。
私がFIREしようと思った理由や、経緯については以下でまとめています。
また、「最速でFIREしたい方限定!若くして最速でFIREするためのノウハウを大公開!完全攻略ロードマップのテンプレ付き!」もあわせてご覧ください。
では、ここから本題です。
前回に続き、今回も為替レート決定にまつわる理論の話です。
前回ご説明の通り、為替レート決定の理論には大きく以下三つがあります。
購買力平価説
フローアプローチ
アセットアプローチ
前回は購買力平価説を解説しました。
今回はフローアプローチです。
フローアプローチとは
まず”フロー”って何でしょうか?
フローとは”流れ”です。
ある一定期間に流れる量を表します。
フローの対義語はストックです。
これはある時点の残高ですね。
例えば、年収はフローです。
そして、貯金がストックです。
ドル円に関して日本から見た場合のフローアプローチを考えてみましょう。
ここでいうフローアプローチとは、ある一定期間におけるドルに対する需要と供給の量によって為替レートが決まると考える理論です。
ドルに対する需要と供給とは何でしょう?
ドル買い(円売り)が需要で、ドル売り(円買い)が供給ですね
この需要と供給が発生する要因は大きく以下三つに分類されます。
経常収支
民間金融収支
日本政府の外貨準備の変化額(米国は為替介入しない前提)
ひとつひとつ見ていきましょう。
経常収支
これは、「海外への輸出額と、海外からの利子・配当収入」から「海外からの輸入額と、海外への利子・配当支払い」を引き算したものです。
基本的には”ドル円レート”、”米国GDP”、”日本GDP”で大方決まる数字です。
例えば輸出などが多くて経常収支が黒字の場合、日本人はその分のドルを持つことになります。
そしてそのドルを円に戻す必要があります。
つまり、ドルを売って円を買うという売買が発生します。
為替市場にはドルが供給されますね。
つまり、経常収支がプラスの時はドル供給圧力が、
経常収支がマイナスの時はドル需要圧力がかかる
と覚えておきましょう。
民間金融収支
これは、「日本の民間企業による海外への投資」から「海外から日本への投資」を引き算したものです。
フローアプローチの理論が確立されたころには、この金融収支は海外と日本の金利差のみで決まると考えました。
つまり海外の金利の方が高ければ、みんな高金利を求めて海外に投資するので民間金融収支はプラス、
海外金利の方が低ければ、逆に民間金融収支はマイナス、といった感じです。
本来であれば、海外に投資するかどうかは将来の為替レートの予想変化率も考慮されますが、フローアプローチの理論が確立されたころにはこれが考慮されていませんでした。
日本企業が海外に投資する際には、持っている円をまずドルにかえる必要があります。
つまり、円を売ってドルを買うという売買が発生します。
為替市場ではドルに対する需要になります。
つまり、民間金融収支がプラスの時はドル需要圧力が、
民間金融収支がマイナスの時はドル供給圧力がかかる
と覚えておきましょう。
日本政府の外貨準備の変化額
これは、その名の通り日本が持つ外貨準備の変化額です。
国家というのは、時には自ら為替介入をしたり、為替介入をするための準備資金としてある程度の外貨を持っています。
日本政府も現在1.3兆ドルの米ドルを持っています。
外貨準備が増えたらプラス、減ったらマイナスであらわされます。
日本政府が外貨準備を増やすということは、手持ちの円をドルに換える必要があります。
つまり円を売ってドルを買うという売買が発生します。
為替市場ではドルに対する需要になります。
つまり、外貨準備の変化額がプラスの時はドル需要圧力が、
外貨準備の変化額がマイナスの時はドル供給圧力がかかる
と覚えておきましょう。
フローアプローチで成り立つ計算式
ここまで見てきた通り、為替市場における売買の元となる要因は、”経常収支”、”民間金融収支”、”日本政府の外貨準備の変化額”の三つがあることがわかりました。
そしてドルの供給圧力となるのが経常収支、ドルの需要圧力となるのが民間金融収支と外貨準備の変化額です。
為替市場では需要と供給が一致するように為替レートが変動しますので、以下の等式が成り立ちます。
経常収支 = 民間金融収支 + 日本政府の外貨準備の変化額
※経常収支は”為替レート”、”米国GDP”、”日本GDP”によって変動し、
民間金融収支は”日米金利差”によって変動すると考えることが前提とされています。
例①
仮に日本政府が外貨準備を増やすとします。
すると、上記の等式の右辺がプラスになりますね。
するとその分の経常収支のプラスを生み出すように為替レートは円安ドル高になります。
例②
仮に日本が利上げを行って、日米金利差が縮小した場合、民間金融収支はマイナスになります。
なぜなら、金利差が縮小した分、海外投資の魅力が下がって、日本企業が海外に投資していた資金を円に戻すからです。
すると、上記の等式の右辺がマイナスになりますね。
するとその分の経常収支のマイナスを生み出すように為替レートは円高ドル安になります。
例③
もう一つ例を挙げてみましょう。
仮に、米国のGDPが増えて日本のGDPが不変の場合、日本から米国への輸出が増えるので経常収支はプラスにふれます。
ところが、日米金利差が不変で、政府の外貨準備も不変だとすると、上記の等式の右辺はゼロのままです。
よって、左辺で生まれた経常収支のプラス分を打ち消すように為替レートが円高ドル安に振れます。
今の状況はどう説明される?
フローアプローチで現在の円安(2022年5月27日時点で127円/ドル)を説明してみましょう。
もう一度、等式を再掲します。
経常収支 = 民間金融収支 + 日本政府の外貨準備の変化額
※経常収支は”為替レート”、”米国GDP”、”日本GDP”によって変動し、
民間金融収支は”日米金利差”によって変動すると考えることが前提とされています。
今の状況というのは、米国において急速に利上げされている一方で、日本はゼロ金利政策継続中です。
つまり、日米金利差が拡大しているのです。
これによって高金利を求めた海外投資が拡大するので、民間金融収支はプラスになります。
日本、米国共に為替介入はしていないので外貨準備の変化額はゼロです。
すると上記の等式において右辺がプラスになりますね。
そうなると、その分の経常収支のプラスを生み出すべく為替レートが円安ドル高にふれる必要があります。
証明終わりです。
結局、今は日米金利差拡大を織り込むための円安ドル高なんですね。
但し、フローアプローチで重要なのは、一定期間の”フロー”をベースに考えているところです。
一旦、日米金利差拡大が為替レートに織り込まれたら、一旦リセットされます。
今後、米国で予想されていたよりも利上げするということになれば、更に円安ドル高になるでしょう。
利上げはするものの予想よりも利上げしないということになれば円高ドル安になるでしょう。
STOP
いかがだったでしょうか?
理論の考え方はしっくりきますよね。
一方で、フローアプローチの考え方は、実際の為替レートの短期的な変動を説明できていないと厳しい批判にさらされてきました。
それには様々な要因があります。
そこで注目されてきたのがアセットアプローチです。
次回はフローアプローチについて解説します!
「最速でFIREしたい方限定!若くして最速でFIREするためのノウハウを大公開!完全攻略ロードマップのテンプレ付き!」については以下でまとめていますので是非こちらもご覧ください。
以上
りろんかぶお
Twitter:https://twitter.com/nrhr5342
ブログ:http://buffettbu.jp/
もしこの記事がためになったなと思えた方はサポート頂けると喜びます(^^) 今後もっと皆さんにとって有益な記事を書くための活動費として使わせて頂きます!
