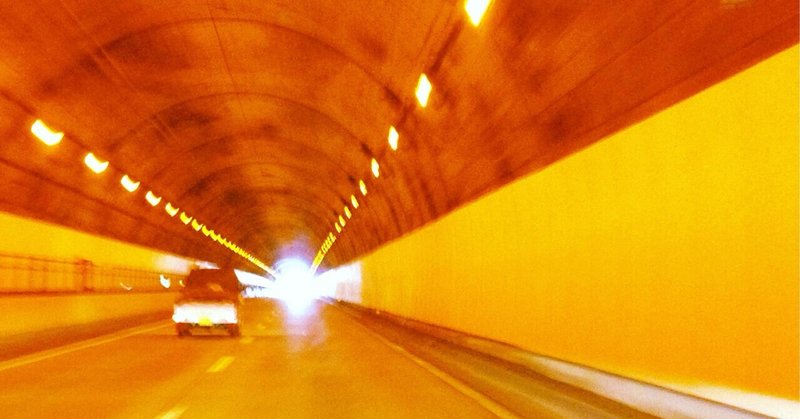
問題を持ち続けながら生きる
支援観
当事者でありながら支援者の役割を遂行するにあたって、僕はテレビ画面越しに相手をみる感覚が必要不可欠であると思っている。
同じ苦しみなんてない
この世界には似たような苦しみはあっても同じ苦しみなんてない。たとえ同じ病気を抱えていても、その生きづらさは十人十色なのだ。
当事者が支援者になるとそのことを忘れがちになる。自分の経験が相手にも当てはまると考えてしまったり、相手の話に対して「わかる」なんて安易な言葉を使ってしまいかねない。
相手が生きづらい思いをしていること自体を「わかる」ことができても、その内容が「わかる」なんて──そんなことはありえない。
だからこそ、僕は面接の場において、相手との間にテレビ画面を用意する。それは僕の頭の中のイメージではあるものの、相手の物語を客観的に「観る」ためには必要なのだと思う。
問題を持ち続けながら生きる
症状を無くすことは、檸檬さんの成長ではなく、症状と向き合いながら上昇スパイラルに身を置くことができるのが、檸檬さんの成長と思います。疲れたら休むことを恐れないで下さい。「問題を持ち続けながら生きる」そのことを支え合うのがソーシャルワークと思います。
ひとりよがりに「問題を持ち続けながら生きる」ことはしないで下さいね。
これは恩師から頂戴した手紙の一部抜粋である。「檸檬さん」の部分は原文が本名なので改変したものの、内容自体はそのままだ。
これを読むと、当事者性は捨てなくてもいいという恩師からのメッセージを感じる。当事者から脱却して支援者にならなければならないと空回りしていた僕に、恩師が贈ってくれた言葉だ。
問題を持ち続けながら生きる僕が、その当事者性を顕在化させず、それでいて捨て去ることもせず、相談者から語られる物語に耳を傾ける。
このことの意味を僕はまだ理解できていないものの、いつか自分の言葉で定義できればよいと思っている。それが恩師から僕に与えられた宿題であって、エールでもあるのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
