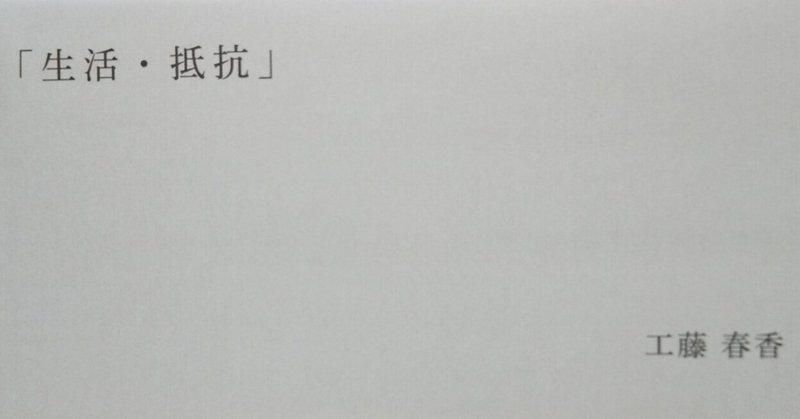
工藤春香さん「生活・抵抗」(神保町PARA,2023年4月30日~5月7日)
移転したPARAにお伺いするのははじめてで、階段を使って2階まであがると左手に扉があり、開けてすぐの受付で入場料を払う目の端には、先客がふたり、手前と奥のモニターの前にそれぞれ座っているのが確認できた。
撮影不可の説明が終わる頃には、奥の壁際のモニターが空いたようなので、先にそちらへと向かう前にも、室内にはなんとも言えない強い匂いがしていて、しばらく後になってわかったものの、その出所は、展示室内に持ち込まれたニンニクと唐辛子(たしか、前者は29片で、後者は11本)のようだった。
そして、奥に向かうと言っても、部屋の中央にはブルーシートが敷かれていて、その時は踏んでよいのかわからなかったので反時計回りに迂回して進むと、長方形の部屋の短辺から長辺へ移る曲がり角の辺りにはツナ缶?が置いてあって、蓋は空いており、ラベルが逆向きになっている。近くの壁面には、缶を集めて飯ごうをつくったり、草を煮て食べたりしたことが書かれていて、この後、室内をそのままぐるりと巡っていくと、様々な体験談が5つくらい壁に点々と記されており、これらは、相模湖ダムの歴史を記録する会による、『相模湖[ダム]の歴史 : 強制連行の証言記録』や『「地域からの平和集会 相模湖・ダムの証人 于さんらと語ろう」記録』から引用されたものらしい。
そのままブルーシートと壁に挟まれ細い通路のようになった長辺を進むと、半ばあたりに目的のモニターがあって、モニターはタイルカーペットのピンク50枚くらい、黒6枚くらいが角をずらすように積み重ねられていて、さらにまな板のような木の板が載せられたその上に鎮座していた。そこに映し出されていたのは《1944年にいた中国人労働者の作ったマントウのレシピで中国人留学生とマントウを作るあいだ話す》というタイトルの通り、工藤さんと、お二方の留学生がマントウを話しながら作るというもので、コツを知らないともろもろ崩れてまとまらない黄土色の生地を、留学生の方が手際よくこねているあいだ、話は文化大革命や、広州、杭州、光州…と、中国と韓国には“コウシュウ”が多いことなどにわたっていた。蒸しあがったマントウは、本来ならばもっとトウモロコシ粉が多いので黄色いらしいけれど、色味もかたちもお菓子のひよ子のようで、あまりなじみがなかったので検索してみたマントウの画像、白くてふわふわとした、そう言えばチャーシューとかが挟まったハンバーガーみたいなものをどこかで見たことがあったのを思い出したものの、どのみち違っており、口の中の水分がぜんぶ持っていかれてまずいそう。モニターの前には丸イスが4脚ほど置かれていて、そこに掛けて映像を見ていたけれど、そのすぐ右横、出っ張った壁には先ほど同様、おからと古くて臭くなったトウモロコシ粉の蒸しパンはまずかったし、そもそも量が少なかったという証言が記されており、モニター向こうの壁には《喝茶》の習字が貼られ、その言葉はたしか映像に出てきていた。
モニター奥の隅にはダンボールの箱が置かれていて、その手前には青くて毛足の短い毛布が、うずくまった人のようにも三日月型のクロワッサンのようにも見えるかたちで床に放り出されている。箱に向かう途中、《喝茶》の左隣あたりにはこれまた証言が書かれていて、“折檻があった。上官の命令は天皇の命令だった”とある。
たしか箱には、“遺骨すら見つからなかった”、みたいな証言が書かれていて、箱の後ろに置かれたスマホからは声が流れており、名前を読み上げている。
その名前は、先ほどの毛布の左隣のあたりに、四隅の上ふたつを天井の鉄筋へ、下ふたつの隅は石へそれぞれ結びつけられ、あたかも磔にされたような透明なシート《相模湖ダム殉職者名簿》に、縦6名×横14列分印字されたもの、それを縦におひとりずつ読み上げていることが少し眺めているとわかって、そこには中国の方、韓国の方そして日本人の御名前が刻まれていた。
そして、その《名簿》の斜め後ろ、窓に面した壁には細長いダンボール箱が立て掛けられ、“点呼で足りなかったひとりがホッパー(生コンクリートや土砂を仮受けする漏斗状の装置だそう)から出てきた、あっちこっちで死んでいる”、という話が刻まれ、そのことと、《名簿》に整然と並んだ殉職者の方おひとりおひとりの御名前が結びついて、“ひとり”、“あっちこっちで”という、ついやってしまいがちな数に落とし込んだ指し方との対比、容易にそちらへと傾斜してしまう“合理的”な考え方は、いただいたハンドアウトに記載されている、「一千KW発電能力あたり、一人死ぬのが当時の見方」というダム工事技術者の見解や、京浜工業地帯に近いからという理由で、勝瀬集落を沈めて相模湖を造ったこと…と、思いのほか近しいのかも知れない。
その左隣の隅はそこだけ奥まっていて、黄色い壁面に、土のう袋?で作られたタンクトップと短パンがあって腰のゴムはビニール紐で代用されている。
その壁にも証言が書かれていたけれど、日差しのせいか読みづらくて、それでも、しばらくすると弱まって、“布団1枚…セメントを入れる紙の袋を布団にも衣装にもしました。冬はたくさん着ました”と読めた。
そして、部屋の短辺からもう一辺の長辺へ、今度は入り口へと帰る方向に進むと、いよいよブルーシートがこちらの壁際まで届いていて、その上を歩かなければならなくなったけれど、すでに他のお客さんが上を平気で歩いているのを見ていたので、少しのためらいで踏み入ることができて、そのブルーシートの縁のあたりには、先ほどの服の素材でもある土のう袋が転がっており、土砂と石、何かを固定するためと思しき金具がこぼれている。
ブルーシートには、ところどころに黄色いシミ?のような、跡のようなものがついていたり、ここから見ると左奥、床に落ちたツナ缶から少し離れたあたりには赤い盛塩みたいなものがあって、後で入り口の、最初スルーした映像を見た後に改めてそれを見ると、キムチ用の粉唐辛子らしいことが分かってくる。ちょうど中央には、砕いた貝殻のような白い砂が丸く敷かれていて、上から映像が投影されており、それが《1947年7月相模湖天皇行幸を湖の中から見る》だった。
タイトル通り、昭和天皇・香淳皇后両陛下が1947年7月に完成した相模湖へ戦後初の行幸啓をされた時の写真が映し出されているものの、その写真の上には水が張ってあったようで、波紋が行ったり来たりしている。そして、タイトルや「私は湖底からの景色を想像したかった」というハンドアウトの言葉を踏まえると、写真の上に水が張ってあるというより、私たち鑑賞者が水の中から見ていて、しかも“水面”を見下ろしていると思っていた姿勢は、むしろその面に足をつけて“仰ぎ見ている”かたちに思われてきて、“相模湖”を境に天地が逆転してしまったような心地が、「戦後初の人造湖」への「戦後初の行幸啓」という輝かしいニュース、そして大抵、“そちら側”に立っていると思ってしまうその反対側に、移転や労働という犠牲を強いられた方々がたしかにいらしたことを感じさせて、四角いブルーシートに丸く敷かれた砂は、砕いた貝殻のようにはじめは見えたけれど、“遺骨すら見つからなかった”という壁面の証言がにわかに思い出されて、湖底に取り残されている(のかもしれない)骨が旗を成し、スクリーンとして映像を支え、そしてその上に私たちも乗っていることが、なにか避けがたいもののように感じられる。
映像を見る鑑賞者の真後ろのあたりには、《相模湖と旧日蓮村勝瀬地区》というドローイングが掛けられていて、映像の投影された砂の方へ向かう際にも横目には見えていたものの、改めて眺めてみると、丁寧に彩色がなされ、あまり下書きが見えていた印象のない、たとえば山並みのような水面より上の部分に対して、相模湖の中には、ところどころ長いストロークの線描が横切っていて(撮影禁止だったため確認できず、自信はあまりないけれど)、その対比も、綺麗に整えられた地上と、人も生活ももろとも沈めた湖底を、そしてそれ以上に、それを忘れる前にそもそも知らず享受している私のような者と、伝え残そうとされている方との断絶のようでもある。
そして、「合流点」(五味家,2021年)で拝見した、佐々木健さんの《相模川》を思い出しつつも、佐々木さんの絵が、絵を見るわたしたちと向こうのやまゆり園との、その水平方向の遠さがまっすぐ奥へと伸びる川として描かれていたのに対して、工藤さんの作品にはそれこそ垂直方向の隔たり、水の深さがあって、お二方のアプローチが当たり前のように違うことが、あることについて語らなけらばならない時に、それが根本的な時ほど無難な、他の人とずれないように“正解”を当てに行くようなことをしてしまいがちなところ、「作家さんだから(特別)」と言うのは容易いけれど、自らの視点、考え方のベクトルを恐れず表明できることを、ただ見ているだけでなく学び取りたい。
ブルーシートの上を、壁を右手に進んでいくと出入口のところまで戻ってくるけれど、その手前には繭玉が自らの糸によって吊り下がっており、そして最初に見なかった、入り口付近のモニターの後ろには《名誉の行幸啓》があり、ブルーシートを隔てて《名簿》と相対していて、機械音声によって絶え間なく読み上げられその文章はここまで見る間もずっと聞こえていた。
モニターは踏み台のごとく二段になったその二段目に置かれていて、手前にはニンニクと唐辛子が置かれており、ここで、今までずっと感じていた不思議な匂い、はじめは建物の匂いか何か気になっていたものの、途中からは忘れていたその出所がわかった。一段目にはこれまで同様証言が書かれていて、自由労務者という、相模ダム工事以前から在日されていた労働者の方たちのことについてだった。
モニターには、《キムチができるまで話す》が流れていて、《マントウ》が中国からの留学生の方と料理しながら話すものだったように、こちらでは在日コリアンの方(FUNIさんというラッパーの方で、MOTアニュアル2022で拝見した高川和也さんの映像や、飯山由貴さんの《In-Mates》でお見かけしていた)と話しながらキムチを作っていて、水に漬けたニンニクの皮を一片一片剥き、白菜の間に丁寧にキムチペーストを塗っていく中で様々なことが語られていたけれど、印象的だったのは、たしか同級生の半分くらいは通名を名乗っていたみたいな話だった。本名と通名ということは、別にはじめて知ったわけではないはずなのに、その時まで耳から入ってきては抜けてきたこととはじめてぶつかったようで、ここで、モニターの向こうにブルーシートの湖面越しに見える《名簿》の日本人名を、疑いもなく日本人だと思っていたこと、実際日本人かどうかに関係なく、ましてやひとりひとりの方が亡くなったことの軽重はなんら変わらないけれど、それでも可能性として少しも浮かばなかったことを突きつけられた気がする。
そして、たくさんのキムチを作るその過程では、ニンニクの皮、その他にもたくさんの切れ端やらなんやらが出て、当然ながら台所、そしてまな板の上は“汚く”なっていく。そのことは、マントウを作る手が生地でべとべとになることや、展示室のトイレの床にまかれ、先客によって踏みつぶされた大豆の粉が、よく見ると展示室の方までうっすら続いていること、ブルーシートの上に砂や土や粉唐辛子が“こぼされ”、そもそもシート自体に使用感があること…へとつながるようで、生活や労働をする上で出てくる“汚さ”や乱雑さを見えないところへと追いやってしまうのではなく、むしろそれを、どんな立場にも共通することとして提示しているようで、私が嗅ぎなれなかった故に不思議に思った匂いが、故郷の、家庭の香りに思える人もいるはずで、さらには、MOTアニュアル2022における工藤さんの展示、背中合わせになった《1917年から2022年までの主に旧優生保護法を中心とした障害に関する政策・制度・法律等をまとめた年表》と《1878年から2022年までの障害当事者運動に関してまとめた年表》の下から覗く靴の履きこなれた感じ(展示として元々置かれたものをあれば、来場者が今まさに履いているものもあった)や、相模原障害者施設殺傷事件の被害者の方の部屋を模したインスタレーションの生活感とも通じて、そうした生活の生々しさは、ひとりひとりの体臭、たしかに生きている証であって、決して数に還元できないこと、当たり前だけれど何度も思い出さないと忘れてしまうことを思い出させてくれる場だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
