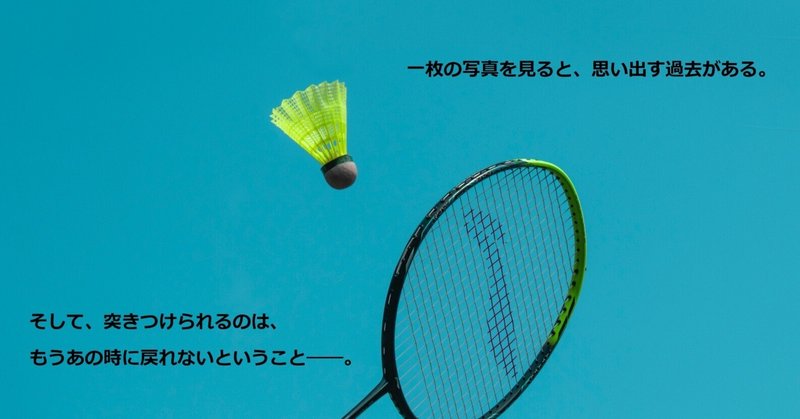
[短編小説]いつかふたり
***
一枚の写真を見ると、否が応でも思い出される過去がある。
それは想い出と呼ぶには甘くもなく、胸中に痛みと切なさを過らせるほど苦々しいもので、もう一年ほど前だというのに刻銘に記憶を辿ることが出来る。
あの日の私は、バドミントンクラブに所属していて、物心ついた時から知っている美月と一緒にダブルスを組んでいた。美月と涼花の名前から一文字ずつ取って、『涼月ペア』とよく称されて、世間の一部からも認識されるくらいには少しだけ名が知れ渡っていた。他を圧倒する実力から、周りには中学生ナンバーワンになるのも夢ではないと期待されることもあった。私達も優勝することを望んでいた。
実際、美月とペアを組めば全国一の称号を手にすることだって出来ると、あの時の私は確信していた。栄冠を取るための努力を惜しんだつもりは、私も美月も一切なかったからだ。
しかし、結果は私が望むものとは異なっていた。
地区予選決勝を迎えたあの日――、涼月ペアは負けた。
あれだけ努力して練習を重ね、周りからも期待されていたというのに、結果はこのざまだ。しかも、私達を降した相手ペアも全国大会初戦で敗退をしたので、余計に私達の立つ瀬はなくなった。
私のスマホの中にある写真は、この負け試合の日に撮ったものだ。
写真の中の私と美月は、正反対だった。いつも不愛想な表情をしている私は口角を上げているのに対して、いつもニコニコとしている美月は口をへの字に曲げていた。「写真なんだから、笑って笑って」と言う周りの声に、私は純粋に従ったけれど、この時の美月は一向に笑おうとしなかったのだ。「これも想い出か」とシャッターを切られたけど、美月には珍しい表情だったから、濃く印象に刻まれている。
それから、私は居心地の悪さを憶えるようになって、美月だけではなくバドミントンからも距離を置くようになった。
同じ中学校だった美月とは、中学を卒業すると、互いに違う高校に進学するようになった。美月からは「高校に行って互いに実力をつけようね」と言われたけれど、私はから返事だけをして帰宅部を選んだ。
今まで出来なかった分、高校に入ってから仲良くなった友達と遊ぶようになった。
そういうことが重なったから、私と美月が疎遠になることは必然だった。
バドミントンの強豪校に入学した美月は、朝夕問わず練習に身を注いでいると風の噂で聞いたけれど、私にはどうでもいいことだった。
あの決勝戦まではいつも一緒にいて、お互いのことは何でも分かるような阿吽の呼吸みたいな関係性だったのに、離れてしまえば分からなくなってしまうものなのか――。そう少しだけ胸の奥が疼いたけれど、今の私は自分の生活を送ることで精一杯だった。
スマホからも私の記憶からも消してしまえば、こんな煩わしい思いをしなくてもいいのに、何故か消すことは叶わなかった。
見なければいいと分かっていても、時間がある時に気付けば写真を開いてしまっている。
「ねぇ、スズ。今度の夏祭り、どうする?」
「え?」
突然名指しで声を掛けられて、反射的にアプリを閉ざして顔を上げた。現実に戻る。今は、ファミレスの四人席なのにも関わらず無理やり六人でぎゅうぎゅうに詰めながら、ドリンクバーで何時間も話し込んでいるところだった。
会話が途切れ、互いにスマホでSNSなどを確認するような空白の時間が生まれていたから、つい私は何も考えずに写真を眺めてしまっていたようだ。
訊ねて来たユッコは、頬杖をつきながら苦笑を漏らす。
「話、聞いてなかったっしょ?」
「いやいや、聞いてたって。夏祭りのことでしょ? イツメンで行くに決まってるじゃん」
「スズカならそう言うと思った。でもさ、マミは花火の時は元中の男子と合流するんだってさ」
「えー、裏切りものなんですけど」
「友達なら喜んでよぉ」
いじられながらも、マミは嬉しそうだった。
「祭りの時になんか奢ってくれたら、素直に見送ってあげよう」
「もーめっちゃ奢る」
「あー、彼氏いいなぁ」
「まだ彼氏とかそんなんじゃないけどね」
「またまたぁ。私達も、誰か男子でも呼ぼうか」
こういう恋愛沙汰の話になると、置いていかれているような気分に少しだけなる。でも、空気を壊したくないから、私は相槌を打ったり笑ったりする。
そして、少し途切れた会話を繋ぎ止めるように、
「で、夏祭りっていつだっけ?」
私はぼんやりと手帳を開きながら、何となく皆に問いかけていた。
「さっき行くって言ったのに」
「適当っ」
呆れ混じりに皆が笑い、私も笑う。
「来月後半の土日だよ。大丈夫?」
「あ、その日ね。うん、平気平気。今のところは何の予定もなしだよ」
「んじゃ、土日のどっちかで行こ。近くなったら、また決めればいいっしょ」
言われたばかりの土日に蛍光ペンで丸をつける。日付の近くに、花火の絵も書いておいた。
この日以外にも、プールの予定や買い物に行く予定が入っている。今から今年の夏休みは忙しくなりそうな予感がしていた。何も考えずに友達と遊ぶだけの夏休みなんて、初めてに近いから楽しみだった。
カラフルに予定が埋められていくことに期待を抱く一方で、一年前と中身が全く異なる事実が、何故か私の胸を少しだけ締め付けた。
***
激しい練習と縁を切った日々は、瞬く間に過ぎて行く。プールや買い物、時には目的もない遠出なんかりもして、充実した日々を過ごすことが出来た。今までの長期休みといえば、体育館の熱気を我慢しながら練習に励むことが常だったのに、あまりにも違っていた。
恐らく中学三年間の休みで笑った分は、この半分ほどしか過ぎていない夏休みだけでも優に超えてしまった。
それくらい楽しい日々を過ごすことが出来た。
そして、今日は以前から皆で計画を立てていた夏祭り当日だ。
本気でバドミントンに挑戦するようになってから今まで浴衣なんて着て来なかったから、本当に久し振りだった。いざ浴衣を着てみると、なんだかドラマの中のヒロインになったような気がして、心が弾んだ。いつもの十倍は可愛くなったように思える。
家を出てからずっと弾むような足取りで、お祭りの会場となる場所まで向かった。
お祭りの会場に到着すると、すでに皆集まっていた。集合時間まで残り1分ほどだったのに、意外と皆真面目なのだ。
全員集まったところで、ユッコは「よし」と手を合わせると、
「揃ったから行こ行こ」
「まずどうする? たこ焼き? 焼きそば? お好み焼き?」
「炭水化物ばっかじゃん」
「そんな食べたら太るよー」
「えー、やだー」
「スズの浴衣、すごく似合うね」
「ありがと。マミもめっちゃ可愛い。気合十分だね」
「えへへー」
それぞれが話したいように話しながら、夏祭りの会場を回っていく。
たこ焼き、射的、わたあめ、焼きそば、ラムネ、チョコバナナ、ヨーヨー釣り、金魚すくい。目に入って誰かの興味が惹かれたものは、ひとまず出店の前まで行くことにした。冷静に考えれば絶対にいらないでしょ、っていう出店まで訪れた。祭り独特の空気に、皆で馬鹿みたいに笑った。
何も気にせずに食べ飲み笑う夏祭りは、今までにないくらい楽しかった。堪能しすぎて財布のひもが心配になるくらいだったけれど、それでも良かった。
そして、そろそろ夏祭りのメインである花火の打ち上げが近付いた頃。
「じゃあ、私はそろそろ別行動するね」
「マミいいなー」
「報告忘れんなよ」
幸せそうな表情を見せながら別れるマミを、なんだかんだ言いながらも私達は笑顔で見送っていく。
「んじゃ、私達も移動しますか」
ユッコの後に続くように移動を始めた。
ここからでも花火を見ることは出来るけれど、どうせ見るならよく見える場所で見たい。五人全員の総意だった。
「混み過ぎじゃない?」
「ね。花火まで間に合うかなぁ」
「こんなんじゃ、食べ歩きすら出来ないよ」
「あんなに食べたのに、まだ食べる気なの?」
考えることは皆同じなのだろう、開けた視界である河川敷までの道のりは、歩くことも困難なほど混みあっていた。
せっかくオシャレに着込んだ浴衣だけど、周りの誰もが可愛らしい浴衣を着ているから、霞んで見えてしまう。マミみたいに特定の人がいるのなら話は別だろうけれど、この人ごみの中、誰が私のことを認識してくれるだろうか。
バドミントンに打ち込んでいた時には味わったことのない感傷に、ふっと息を吐いた。私の吐く息は、雑踏の中にすぐ埋もれてしまって、なかったことになる。
夜空に大きく輝く花火を見れば、少しは気分も晴れるのだろうか。
「――ぇ」
ふと私は視界にある人物の姿を捉えてしまった。
祭りの風物詩でもある花火を見るために多くの人が移動している中、その人物は半袖短パンという動きやすさを重視した服装にスポーツバッグを背負っていて、美味しそうにイカ焼きを頬張っていた。
「……美月」
その人物の名前が、つい私の唇から漏れた。
間違えるはずがなかった。美月の姿は、過去の記憶と変わらない。
それに今の美月は、祭りというこの場所において目立つから分かる。いかにも練習帰りに寄りましたみたいな格好をしているのは、美月ただ一人だ。
「ミッキーは本当マイペースだよね。待ち合わせに遅れるし、イカ焼きなんて食べてるし、花火は見ようとしないしだし」
「だって、練習もあったし、タンパク質も取らないとなんだもん。あ、でもね、お祭りに誘ってくれたのはすごっく嬉しいよ。ナルと遊べるのずっと楽しみにしてて、インターハイを迎えるまでのモチベだったし」
「だから憎めないんよなぁ。結果はどうだったん?」
「一回は勝ったけど、やっぱ強いね。そんな甘くない。でも、来年は優勝するよ」
聞きたくないし、聞くつもりもないのに、この雑踏の中で私の耳は、美月とその友達の会話を正確に聞き取ってしまった。
そして、その短い会話のやり取りでも、美月がまだ真剣にバドミントンに向き合っていることが裏付けされてしまった。しかも、インターハイに出場できるくらいの強い選手になって、だ。
バドミントンから距離を置くようになって、美月の動向を調べようとも思っていなかったけど、強豪校に行った美月は、中学の時とは比べ物にならないくらいに実力を身に着けている。それこそ、今耳にした言葉――かつて涼月ペアとして描いていた『優勝』という夢を、一人でも実現できるくらいに。
「……対して」
一心に努力する美月に対して、私は何をやっているのだろう。高校に入学してから、いや、写真を撮ったあの地区予選決勝の日からの私の行動を思い返す。
周りから勝手に期待されて、その期待に応えられなくて勝手に塞ぎ込んで、バドミントンからも距離をおいて勝手に美月のことも裏切った。
その後の私は、普通の女子高生を謳歌しようと高校生活を過ごしている。
幸いなことに友達にも恵まれているし、私が想像した高校生活を送れていると表現しても過言ではないだろう。
――だからこそ。
だからこそ、身に残っていることは何もなかった。楽しかった、という想い出は確かに胸の内に残っているけど、ふんわりとしている。前までは目に見える形で残っていたのに。
以前は、涼月ペアとして周りから立てられたり、試合で相手に勝利したりすることで、私にしか出来ないことをしている感覚はあった。
けれど、今の私は特別なことは何もしていない。むしろ、周りに解け込むように周りと同じことをしているだけだ。
私の個性は、埋もれてしまっている。
自分という存在に、いきなり虚しさを感じた。浴衣を着て舞い上がっていた私に、驕り昂るなと言ってやりたい。
ここに『涼花』はいない。だって、周りと同じになって、溶けている。同じような服装をして、同じ場所に向かって、同じ道を進むだけ。私らしさなんて、どこにもない。
もう美月と私の道が交わることは――。
「ちょいちょーい! どこまで行くの、スズー!」
背後から声が聞こえて、ふっと我に返る。振り向けば、少しだけ離れた場所にユッコ達がいる。
どうやら花火を見る場所を陣取ったのに、何も考えずに前の浴衣を追っていたことで離れてしまったようだ。
「スズー! こっちだよー!」
「あ……、っと、ごめんごめん! すぐ行く!」
両手を口元に沿えながら叫ぶと、意を決して逆流し始めた。人とぶつかる度に謝罪の言葉を口にしながら、人並の合間を縫って何とかユッコ達に合流することが出来た。
そして。
「わぁっ!」
皆と合流した途端、夜空に花火が広がった。
この場にいる誰もが、空に視線を注いでいる。
客観的に見たら綺麗だと思った。
ドンッドンッという轟音を伴いながら夜空に散る花火を、暫くの間、私達は息を呑んで見つめていた。
皆、何を考えているのだろう。きっと楽しい想いに浸れているのだろう。だけど。だけど、私は。
「花火、めっちゃ綺麗なんだけど!」
「ね、超やばい!」
「……うん」
私には花火を楽しめる余裕なんてなかった。
周りの温度感についていくことが出来ず、曖昧な相槌を打つことで空気を壊さないように必死だった。
***
人生において、何が正解になるかは分からない。
まだ十五年そこらしか生きていない女子高生が、何を分かった気になっているのかと言われると思うけれど、そう感じたのだから仕方ない。
その時は正しいと思って選択した行動が、後の人生になって悪手となって自分を傷つける。
あの夏祭りの日に美月を一目見てから、そんな感覚が拭えずにいた。
言葉を交わすこともなく、私が一方的に一目見ただけだというのに、美月は全く変わっていないことを察した。
涼月ペアとして、同じ時間に同じ相手に敗北を味わったはずなのに、どうして美月は変わらずに挑戦し続けることが出来ているのだろう。
当時の私は、バドミントンから距離を置くことが正解だと確信していた。身の程を知って、私にはこれ以上がないと確信してしまったからだ。
けれど、その選択が正しかったのかは、今更になって疑問として降り注ぐ。
同じ景色を見ていたはずなのに、私と美月の道は明確に分かたれてしまった。
――一身に進んで夢を掴もうとしている美月。
――敗れたショックから抜け出せずに逃げた私。
正しかったのは、どっちなんだろう。
疑問が頭を過るたび、私は写真に目を向けた。そして、都度、私は答えを突きつけられる。
この写真を見れば、一目瞭然だ。
本気で打ち込んでいるなら、負けた直後のタイミングで笑顔を浮かべることなんて出来ない。美月のように、悔しそうに歯噛みをするはずだ。ましてや、無名の相手に夢が阻まれてしまったとなれば尚更に。
けれど、写真の中の私は、ここまでかと納得するように取り繕った表情を見せている。
この差が、私と美月の命運を分かたせたてしまったのだ。
たった一度の敗北と期待を裏切った罪悪感から、私は最後まで続けることに耐えられなくなってしまったが、美月は一心に突き進んでいく。むしろ、敗北すらも糧にして、より一層練習に励んでいる。
結果、美月はインターハイというステージに進み、優勝という目的を現実のものにまで近付けた。
もしも美月のように諦めることをしなければ、こんな想いを抱かずに済んだのだろうか。今も変わらずに涼月ペアで、全国一を目指すことだって出来たかもしれない。
もう戻れない過去を思って時々胸を痛めることは以前からもあったけれど、ここ最近は頻度が多くなって来た。
原因は、分かっている。
しかし、私がこんな葛藤を抱いていることは、誰にも相談出来なかった。両親にも友達にも話すことなく、一人で頭を悩ませていた。
そんな虚しさに蓋をしようと、私は今まで以上に友達と過ごすようになった。
普通の高校生がするようなことを、ギュッと凝縮して、とにかく遊んだ。
時間が過ぎるのは早い。徒に過ぎる時が、私の心を癒してくれる。
そう思っていたはずなのに、正体の分からない何かが私の胸を掴んで離さなかった。
遊んでいる瞬間は、確かに忘れられる。だけど、一人になった時、ふと襲い掛かる。特に、夜に一人でベッドに潜っていると、症状が顕著に現れて、胸が締め付けられた。
ありふれた人間になって、私はこのまま埋もれていくしかないのだろうか。美月のように――いや、美月と一緒に、特出した人間になることはもう出来ない。
夜の天井に、花火が散っていく。そんな幻想が、何度も脳裏に過った。
夏祭りに花火を見た時、多くの人が花火のもたらす美しさに心を奪われていたが、私は儚さの方に焦点を当てた。
花火が輝くのは刹那だけ。その後は、夜の闇に溶けて、誰からも意識を向けられない。次に打ちあがる綺麗な花火を、周りは期待している。
切なかった。
私みたいだと思うと、余計に胸が締め付けられた。今の私は新天地で友達を作って無理に明るく振る舞っているけれど、本当の私はドが付くほど真面目で悲観的で暗い。
これ以上苦しい想いをしたくなくて、力強く目を瞑った。消えない。布団にかぶさって、上瞼と下瞼がくっついて二度と開けられないと思うくらい、更に強く瞑る。それでも、浮かんでは消えない。
散り行く花火は、私の心に刻まれてしまっている。
これから私は一人になる度、消え行く自分を突きつけられなければいけない。
嫌だった。
いつか消えることを願って、でも消えなくて。
なかったことにしたいと願うのに、ふとした時に写真を眺めて。
蓋をしたいのに、いつも開いてばかりで。
何がしたいのか、自分でも分からなかった。
そんな時だった。
全国大会の決勝まで進んだと、美月から直接連絡が届いたのは――。
***
全国大会決勝の会場を後にする人達の表情は、いい映画を見終わった後のように満ち足りた表情だった。
あの壮絶な試合を見たら、確かに納得出来るものだ。
決勝という舞台で、私達と同い年の相手に対して、美月は互角の試合を展開させた。
互いの陣地を何度も往復するラリーが繰り広げられるとドッと会場は湧き上がり、両者どちらかが点を決めれば、ラリーの時の興奮を優に超えるほど盛り上がる。
会場中にいる人全員が、手に汗を握るような一進一退の攻防に、夏の暑さだけでは言葉に出来ない熱気に当てられた。傍から見ることで、試合の会場がこんなにも熱に包まれていることを初めて知った。
まさに見ごたえのある試合だった。
しかし、勝敗というプレッシャーを浴びていないからこそ客観的な表情を浮かべることが出来るのであって、舞台裏では悔し気に涙を流す選手がいる。
私はそんな選手の涙を近い位置で眺めながら、自分自身に場違いさを感じていた。
「……なんでこんなところに呼んだのよ」
美月から届いたメッセージに対して、小さく愚痴を漏らす。
――話したいことがあるから、終わったら少し待ってて。
私からしたら話したいことは特になかったけれど、メッセージが届いたのなら会わないわけにはいかない。美月からその後に送られたメッセージに従って、選手口の方で時間を潰すことにしていた。
だけど、後悔に変わるのは早かった。
選手口ということだけあって、当然ながら殆どの人がスポーツ着を着ている。その中で、一人私服でいる私はかなり浮いた存在に思えた。私がここにいるのは相応しくないと暗に言われているようで、一刻も早く帰りたかった。
ただでさえ私の心の中では、花火が散り続けているのに。
地区予選決勝で敗北して以来初めて試合を観戦したことで、傍から眺めているだけのはずなのに、当時を鮮明に思い出してしまった。記憶だけじゃなくて感覚までも甦らせてしまい、写真を眺めるだけよりも強く濃くハッキリと、私の心を刺激する。
何で私は客観的に眺めているのだろう。成長した美月を見て、変わらない自分の姿に胸を焦がしていた。
そんな劣情に胸がかき乱される中、
「涼花、久し振り!」
この場で唯一気兼ねなく笑顔でいられる資格を持つ人物――美月がやって来た。べたりとした前髪に、首元にはタオルをぶら下げていた。まさに先ほどまで体を酷使していた証拠だ。隣には美月ママもいて、私に対して会釈をしてくれたから、私も頭を下げた。美月ママが持っていた物を見たくなかった心理も、少しは働いたかもしれない。
「中学校卒業してから、一回も会ってなかったよね」
私の手を取って嬉々とする美月の話し方は、まるで久し振りの再会なんてなくて、今までずっと一緒にいるかのように自然で記憶通りのものだった。
「……」
ちょうど一年前の夏祭りの日、私は美月のことを目にしたけど、そのことは言えなかった。
視線をどこに注いでいいのか分からなくて、私は自分の足元ばかりを見つめながら、マメでごつごつとした美月の手に握られるままだった。
何でだろう。美月を前にすると、『涼花』という自分ではいられない。
「涼花なら絶対頑張ってると思ったからさ。私が納得できるまで会いたくなかったんだ」
私が変わっていない、と美月は思い込んでいる。あの地区予選敗退から、何年経っていると思っているのだろう。二年もあれば、人は変わる。
あまりに言葉を発さない私に、美月は一瞬だけ小首を傾げたけれど、
「ねぇねぇ、お母さん、写真撮ってよ」
私から手を離して、美月ママに自分のスマホと首にかけていたタオルを手渡した。タオルに隠れていた金メダルが、キラリと光る。「ね、涼花。せっかくだし、撮ろ撮ろ」と、美月に促されるまま、私は美月の隣に立つ。
美月ママの「二人とも、笑ってねー」という声と同時、スマホのシャッターは切られた。美月は「ありがとう」と言って、美月ママからスマホを受け取ると、早速今撮ったばかりの写真に目を向けた。
美月と近くない人であれば見逃してしまうくらいの僅かな時間、スマホを見つめる美月の顔は強張った。どうしたのだろう、と疑問を言葉にすることなく、
「逆だね」
「……え?」
いきなりの美月の言葉を、私は理解することが出来なかった。美月はスマホの画面を私に向けた。
美月のスマホに写っているのは、今しがた撮ったばかりの私達の写真。
「前は私が顔をしかめていたけど、今は涼花が顔をしかめてる」
写真の中には、金メダルを掲げて満面の笑みを浮かべている美月とその隣に悔しそうに唇を噛み締めている私がいた。美月の言う通り、二年前の予選敗退の時に撮った写真とは正反対な構図になっている。
私の表情はどこか見覚えがあったけれど、すぐにその正体に思い至った。バドミントンから足を背け、ただの観客に過ぎないはずなのに、私は優勝を逃した選手たちと同じ表情だった。
無難に写るようにポーズをしていたはずなのに、こんな表情になっているとは思いもしなかった。
「あの時の私は負けたことが悔しくて、笑うことも出来なかった。でも、今はね。優勝したから笑える。笑いたくて、ひたすら一心に努力し続けて来た」
「それは美月に才能があったから……」
元々才能があることに加えて努力さえも惜しまなくなってしまえば、美月であればインターハイ優勝という夢も実現することが出来るだろう。
卑屈っぽく聞こえるかもしれないけど、事実だから仕方がない。私は私に期待していない。自分の実力を正確に把握し、分を弁えている。
汚れを知らず歩きにくいオシャレな靴をジッと見つめていると、「ねぇ」と言う美月の声が頭上から落ちた。
「今日私が勝った相手って知ってる?」
「中学の時に全国大会で優勝した人……でしょ」
美月が戦う相手の名前が『千輪』だと見た時、ピンと来た。地区予選で敗退してしまってからも、一応その年の全国大会の結末だけは追っていたからだ。優勝したペアは日輪ペアとして当時から有名で、中学の一時期は『東の涼月ペア、西の日輪ペア』と言われていたこともあった。
「そう。そしてね、あの地区予選決勝で私達に勝ったペアが初戦で負けた相手でもあるんだ」
私達に勝った相手が早々に負けたということだけは噂で聞いていたけれど、その相手が日輪ペアだとは今初めて知った。
少しだけ余談ではあるが、中学の全国一に輝いたペアのもう一人である『日鞠』は、準決勝の時に美月に負けた。けれど、ダブルス戦では、今年の優勝ペアはこの二人だった。
つまり、私と組んで涼月ペアになんかならなければ、美月は中学校の時から優勝を手にすることが出来たかもしれないのだ。
しかし、美月は言葉を続けていく。
「だから、私に才能があるわけじゃない。あの地区予選決勝の時は、たまたま相手の方に運があっただけ。来年こそ、涼花もインターハイ決勝に出れるよ」
「私にはそんな実力なんてない……」
私と美月の腕が拮抗していた時もあった。同じ実力を持ったプレイヤー同士でなければ、ペアを組んでも長続きはしない。
けれど、それはもう二年前の話で、バドミントンから足を洗った今の私と青春を全てバドミントンに捧げている美月とでは、雲泥の差が生まれている。
あまりにも突飛めいたことを、あたかも当然のことのようにどうして言えるのだろう。
「だって、練習試合の時、涼花に一度勝ったことないもん」
中学時代を思い出した。確かに美月と練習試合をした時は、僅差ながらも、いつも私が勝っていた。ただし、それは過去の話だ。
たったそれだけのことで、美月は確信めいたように断言しているというのか。
呆れてものが言えなくなるとは、まさにこのことだ。
「……冗談でしょ?」
「冗談なんか言わないよ」
嘲笑混じりの小さな呟きを、美月は真剣な顔つきで首をすぐに振った。
「私は今も涼花のことを凄いプレイヤーだと思っている。だからね、涼花に勝たないと、全国一になった気がしないんだ」
涼月ペアと周りから称されながら敗北してしまった時、あまりの自分の高慢さに私は私を見限るようになった。
期待に応えられず、自分でも自身を信じられなくなった私に嫌気が差して、バドミントンの道から離れた。もう誰も期待してくれる人なんていないと思って、本当の私を見つめてくれる人なんていないと思い込んでいたのに。
なのに今も美月は変わらずに私に期待を注いでくれている。
そんな想いを敏感にハッキリと感じ取ってしまった。
「今からでも出来るのかな……」
意識していなかったのに、しがみつくような言葉が自分の口からするりと飛び出して来た。無自覚に人の心を動かす何かが、昔から美月には備わっている。
美月が立った栄光の場所。私も立ってみたかった、場所。確かに憧れはないと言ったら嘘になる。表彰台に立つ美月を見て、羨ましく思った自分もいる。
けれど、現実を考えると時間が足りない。来年の今頃、美月と勝負をしているイメージを描くことなんて、私には出来ない。
臆病になってしまった私の心に、
「涼花なら出来るよ」
花火のように明るい光が、差し込む。
「だって、私よりもひたむきに努力する練習の鬼だったじゃん」
「……鬼って」
涼月ペアと称される前から、幼馴染である美月と一緒に過ごして来た。
そうだ。インターハイ優勝という肩書きに呑まれてしまいそうだけど、美月は時々独特な言葉を用いて、人を笑わせていた。
だけど、この真剣な場面で言うことかなぁ。
いつまでも変わらない美月らしい言葉のチョイスに、涙が出るくらい笑った後、私は一息吐き、
「一年でインターハイ決勝まで行けるって、本気で思ってる?」
「うん、本気」
「……そっか」
反論する余地もないほどハッキリと断言されてしまえば、納得せざるを得ない。
ここで約束を交わしたとて、美月のようにインターハイの舞台まで昇り詰められるかは分からない。
上手く行かないことが多く、挫折することも多いだろう。
「美月」
「なに、涼花?」
「またこの時期になったら、写真撮ろう」
それでも、私は約束を交わす。
次に美月と写真を撮る時は、悔いなく写れるようになるまで挑戦してみせる。
「その時は、どっちが笑顔になっても怨みっこなしだよ」
「うん!」
今日一番の笑顔を浮かべながら、美月は大きく頷いた。
一年後の私が、どのような想いで今日の写真を眺めているのか、そしてどんな表情で写真に写っているのか、少しだけ楽しみだった。
<――終わり>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
