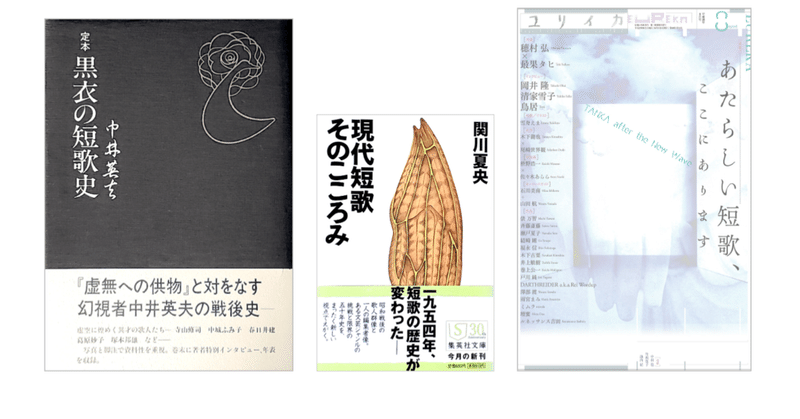
関川 夏央『現代短歌 そのこころみ』/中井 英夫『定本 黒衣の短歌史』
☆mediopos2633 2022.1.31
一九五三年
斎藤茂吉・釈迢空という
日本短歌界を牽引していた二大巨星が亡くなる
翌年の一九五四年
当時短歌雑誌の編集者だった中井英夫の
新人発掘のための新たな企画をきっかけに
現代短歌の「こころみ」がはじまることになる
その「こころみ」のなかから
中城ふみ子や寺山修司も見出されている
後に『虚無への供物』という
戦後推理小説の代表作とされている作品をはじめ
さまざまな幻想小説で知られている
中井英夫という編集者の存在がなかったら
寺山修司という巨星も現れなかったかもしれない
中井英夫は二十六歳から三十七歳の頃
(昭和二十四年一月から昭和三十五年六月)
当時の短歌の三つの雑誌
日本短歌社の「短歌研究」と「日本短歌」
そして角川書店の「短歌」の編集長をつとめていたが
それ以降は短歌の世界を離れることになる
当時の詩壇・俳壇はその中井英夫の「こころみ」に対して
それらはほんらいの短歌ではないということで
常に鋭い批判的な立場を崩さなかったようだ
中井英夫の「こころみ」と歩みをともにした存在は
塚本邦雄や岡井隆であり葛原妙子であったが
そうした存在がなければ今これほどに豊かな歌の世界が
短歌の歴史に刻まれることはなかったように思われる
ちなみに当時たとえば塚本邦雄の存在を評価していたのは
吉本隆明・吉岡実・辻井喬・高橋睦郎・大岡信といった方々で
そういう意味では時代のなかで
確かな眼を持ちえていたひとたちの視点を
当時の詩壇・俳壇は持ちえていなかったといえそうだ
このことは同時代のアカデミズムを見わたしてみても
同様なことがいえるかもしれない
その基準が過去の型にはまったルーティーンでしかないからだ
ちなみに編集者中井英夫が短歌界にのこした偉業のことは
最近ようやく知ることができたが
みずからの不明に恥じ入るばかりである
そのきっかけになったのが
まさに塚本邦雄であり
数年前になってようやく
その存在の巨大さに驚愕して以来
遅まきながらようやく短歌の世界に
遊ぶことができるようになった
(じぶんで短歌をつくるわけではないけれど)
とはいえその後の現在進行中の現代短歌の多くに対しては
塚本邦雄に対するほどの驚きを持ちえてはいないけれど
ちなみに現代の短歌の世界は
従来のような短歌総合雑誌と結社による活動の場
商業出版をも含む幅広い読者による短歌の場
そしてネットにおけるコミュニケーションの場だという
(すでに「新聞短歌」の世界は次第に縮小しているようだ)
たしかにネット上では
夥しいほどの短歌や俳句の世界が
見わたすことのできないほどに広がっている
以下の引用での荻原裕幸氏も
「それらを俯瞰する方法」が見つけられないそうだ
塚本邦雄は「短歌における「現代」」(1967)で
こう述べているが
「短歌は、今日無用の文学である。
否無用という否定や拒絶すら感じさせぬ、無関心の文学であろう」
「しかもなお、現代短歌は、今日まぎれもなく存在する。
日本の現代詩歌から、短歌を差引いて語ることは許されない。」
日本の詩歌は短歌の現在がどうであろうと
短歌への射程を失うことはできない
そのためにも万葉集以降古今集・新古今集から現代短歌まで
さまざまに紡がれてきた「歌」への感受をなくすことは
日本語の可能性を閉ざすことにもなるだろう
■関川 夏央『現代短歌 そのこころみ』
(集英社文庫 集英社 2008/1)
■中井 英夫『定本 黒衣の短歌史』
(ワイズ出版 1992/12)
■荻原裕幸「インターネットと短歌」
(ユリイカ 2016年8月号 特集=あたらしい短歌、ここにあります」所収)
(関川 夏央『現代短歌 そのこころみ』より)
「この本は、現代短歌の果敢な「こころみ」を記述しようとする「こころみ」である。短歌には門外漢だが日本語表現について日頃考えをいたしている者の、一種の短歌論の「こころみ」でもある。
ここではおもに「戦後」といわれた時代、その五十年間の短歌と歌人についてしるした。その起点は、斎藤茂吉、釈迢空の二巨人が没した一九五三年である。翌年、短歌雑誌編集者中井英夫は編集上の積極的な「こころみ」を開始し、このとき現代短歌は躍動しはじめたのだと私は考えた。
中井英夫はすでに一九六〇年代なかばには短歌を離れていたから、その一九九三年の死はなにごとかの契機とはならなかったが、期せずその前後頃からあらたな動きが目立つようになった。
それは、「結社」ではなく、「座」を中心とした若い歌人たちや歌を好む一般人たちの、抒情とユーモアに富んだ向日的作品群の出現である。彼らは中城ふみ子や寺山修司による「一九五四年の衝撃」を知らず、しかし先行歌人たちの「こころみ」を間接的にまた無意識的に伝達されているのである。そのあたりを歴史記述のいちおうの終着点とした。」
「短歌誌編集者時代の中井英夫は、中城ふみ子、寺山修司を世に出し、塚本邦雄、葛原妙子を強く推した。また春日井建、浜田到、村木道彦を「発見」した(・・・)。」
「五三年に斎藤茂吉が死に、八三年に寺山修司が死んだ。寺山はすでに十五年以上前に短歌を事実上やめてはいたが、ふたりの死の間に横たわる三十年の歳月のうちに現代短歌が成立したことはたしかだ。現代短歌をになう歌人たちの多くが、「前衛短歌」以降八〇年代初頭までにその表現を開始したのである。
一千九百九十三年十二月十日、中井英夫は七十一歳で死んだ。肝硬変であった。奇しくも『虚無への供物』の冒頭の場面と同じ日付、おなじ曜日であった。」
(中井 英夫『定本 黒衣の短歌史』より)
「私は昭和二十四年一月から昭和三十五年六月までの足かけ十二年間、日本短歌社の「短歌研究」と「日本短歌」、角川書店の「短歌」三誌の編集長をつとめた。年齢にして二十六歳から三十七歳までである。これらの雑誌はいわゆる歌壇の総合雑誌−−−−商業誌であって、「アララギ」などの歌人が主宰する結社雑誌とは違うものだが、その間の私は歌舞伎の黒衣ながら、つとめて表へ出まいとし、本名で短歌評論を書いたり歌集の月旦をしたりということはなるべく謹んできたものの、なのぶんにも長い年月なので、その間、匿名あるいは記者として書き綴った文章は相当の量にのぼる。整理してみるとその折々の雑文とはいえ、おのずから戦後短歌の側面を語って、〝黒衣の弁〟をなしているので、潮出版社のおすすめに従い、中から現代にも通じる問題を含んでいると思われるものを選んで一冊にまとめることにした。
(荻原裕幸「インターネットと短歌」より)
「短歌の世界には、ジャンルのパブリックなメディアとして、短歌総合誌と呼ばれる雑誌が存在している。短歌研究社の『短歌研究』、KADOKAWAの『短歌』、本阿弥書店の『歌壇』等がある。ビギナー向けにシフトした紙面もしばしば見られるけれど、短歌的なステータスの最上位にあるメディアだとみなされている。肝心の多くは結社と呼ばれる団体に所属し、定期刊行の機関誌である結社誌に、作品や短歌評論を発表するといったスタイルで活動を続けてきた。結社内部の賞、その他、活動が認められると、第一歌集の出版や前述の短歌総合誌の主催する新人賞への応募を勧められる。短歌総合誌は、各結社の動向をうかがいながら、結社間のバランスをとるようなかたちで誌面を構成していた。誌面への露出は、ある種のステータスであり、その都度小さな活気を生んでいた。」
「しかし、こうした短歌の世界のありようは、一九八〇年代に大きく揺らぐことになった。端緒になったのは、林あまりの第一歌集『MARS★ANGEL』(一九八六年、沖積社)が、爆発的に売れたという話題が広がったことだったと記憶している。(・・・)出版部数は一般に一〇〇〇部以下で、過去に例がなかっただけではなく、それが、結社と短歌総合誌とが構成する場の他にも短歌に影響を与える場が存在し得るという事実を露呈したからだろう。俵万智の第一歌集『サラダ記念日』(一九八七年、河出書房新社)が、ダブルミリオンセラーとなり、商業的な出版物としての歌集が断続的に刊行されるようになる中、短歌は一九九〇年代を迎える。」
「一九九〇年代の半ば、私も、世の趨勢に従うように、ワープロから切り替え、パソコンのユーザーとなり、メールやパソコン通信を利用しはじめた。誰にどう伝えたのがきっかけだったかは忘れたけれど、程なくして、短歌の仲間から声がかかり、比較的若い世代の歌人のメーリングリストによるコミュニケーションの場に参加することになった。」
「歌集にも商業的な出版の可能性がある、と認識されはじめた状況に加えて、ネットが普及しはじめる。世紀を跨いで、短歌をめぐる状況は変化し続けた。現在、単純に言って、三つの焦点となる場がある。一つは、従来からの、短歌総合雑誌と結社が構成する、短歌史とのつながりにおいて短歌を考える場。さらに、一つは、商業出版を視野に入れて、短歌を書かない、短歌の外の読者をも意識して短歌を考える場、そして、もう一つは、前二者とかかわりながらも、ネットにおけるコミュニケーションに短歌の快さを求める場である。」
「二〇一〇年代になり、スマホの普及とも相俟って、短歌とネットの親密さは、さらに加速度的に進んでいるようだ。ただ、それらを俯瞰する方法が、私にはうまく見つけられない。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
