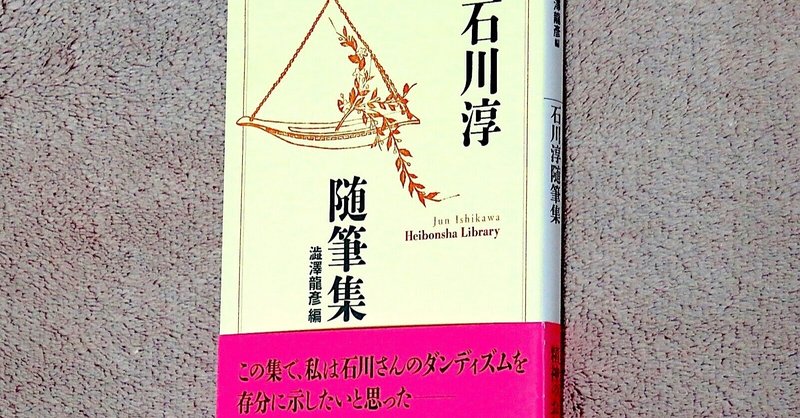
澁澤龍彦編『石川淳随筆集』
☆mediopos-2289 2021.2.21
ダンディズムといえば
ぼくのなかではすぐに石川淳の名が浮かぶ
ダンディズムとは
美意識であり精神の絶えざる運動である
とはいえここ数十年にわたって
石川淳を読まずにきていたのだけれど
ある意味で石川淳はダンディズムの象徴だから
それを仰ぐだけで満足していたところがあった
ようやく澁澤達彦編の随筆集(一九八二年刊行)が
昨年文庫化されたのもあって
小説なども含め久しぶりに読み直している
澁澤達彦もまた石川淳のダンディズムに畏敬をもっていた
もっとも石川淳はダンディズムという言葉を使ってはいない
石川淳という「文士」の存在そのものがダンディズムなのだ
かつては石川淳のカッコよさに憧れていただけなのだが
この年になってあらためて
石川淳のダンディズムのなんたるかを
ようやくわずかながら理解できてき気がしている
随筆集の内容から二つほど
「面貌について」と「敗荷落日」の
最初のあたりを少し引いてみることにした
面貌というのは美醜のことではなく
美意識ゆえに現れるその存在の姿のことだろう
「美意識であり精神の絶えざる運動である」
ダンディズムは人格という見えぬ姿であらわれる
永井荷風にかつてあったそれが
晩年になって失われた姿を慟哭しているのが
「敗荷落日」という随筆である
畏敬をもっていた荷風の死にあたって
その晩年の「落日」を語る言葉は
なぜあの永井荷風が・・・というように
荷風からダンディズムが失われたことを
激しく慟哭しているのだといえる
現代を見渡すと
ダンディズムはすでに失われて久しい
いまや世の中はフェミニズムである
フェミニズムにはダンディズムはみられないようだ
ダンディズムは性別もジェンダーも問わない
美意識であり精神の絶えざる運動であるにもかかわらず
現代では避けて通ることのできないフェミニズムに
ダンディズムを感じることができないのは残念だ
おそらくフェミニズムにダンディズムが加わったとき
真の意味での人間復興になるはずなのだが・・・・・・
■澁澤龍彦編『石川淳随筆集』(平凡社ライブラリー 2020.8)
※本著作は一九八二年彌生書房から刊行された『現代の随想16 石川淳集』を改題したもの
(澁澤龍彦「解説」より)
「この集で、私は石川淳さんのダンディズムを存分に示したいと思った。ダンディズム、つまり精神のおしゃれであり、当世ふうにいえばカッコよさである。べつだん若い読者層をねらったわけではないけれども、私は石川淳さんのカッコよさにもっぱらスポットをあてるような編集をしてみたいと思ったのである。はたして成功したかどうか。
もっとも、石川さんご自身は、ダンディズムという言葉をほとんど使ったことがないのではないかと思う。おしゃれとか、粋ごのみとかいったヴォキャブラリを石川さんはよき使う。虚栄心などという言葉をぬけぬけとお使いになることさえある。まあ、言葉の詮議はどうでもよく、私はただ、このダンディズムなりおしゃれなりが、精神の価値をあらわすものだということをここで一言注意しておけば足りるのだ。
石川さんの専売特許というべき、あの今ではあまりにも有名になてしまった「精神の運動」という言葉を引き合いに出すならば、このダンディズムなりおしゃれなりも、明らかに「精神の運動」の一様態と考えてよいであろう。
「たとえば『夷斎筆談』にふくまれる「面貌について」という秀抜なエッセーなどは、その意味から、この集の冒頭を飾るにいかにもふさわしい、石川さんのダンディズム宣言のようなものだと考えて差し支えないのではないか。面貌に直結するところにまで生活の美学を完成させた、西欧のエピキュリアンに似ていなくもない明清の詩人のことから、小説が取り扱うべき人間エネルギーの運動の子よまで話が展開するが、この話をひっぱってゆく主導観念は、ただ一つなのである。すなわち、おしゃれの理想と散文の理想とが一直線につながっているのである。」
「「敗荷落日」は、読みたびに私を同じ感動に誘い込む畏るべき文章である。いままでに何度読んだかわからない。この文章について、かつて「竹林の七賢のひとりが母の喪に痛飲泥酔したという故事を思い出した」と書いたのは桑原武夫であるが、たしかにその通りで、死者に鞭打つ苛烈な口ぶりの裏に堰きとめられた万斛の涙を、私たちはそこに見ないわけにはいかないのである。ちなみに、石川さんはすでに荷風の享年よりも長く生き、しかも一向に衰えを見せぬ、みずみずしい筆力をいまに示している。」
(石川淳「面貌について」より)
「黄山谷のいうことに、士大夫三日書を読まなければ理義胸中にまじわらず、面貌にくむべく、ことばに味が無いとある。いつの世からのならわしかわからないが、中華の君子はよく面貌のことを気にする。明の袁中郎に至っては、酒席の作法を立てて、つらつきのわるいやつ、ことばづかいのいけぞんざいなやつは寄せ付けないと記している。ほとんど軍令である。またこのひとは山水花竹の鑑賞法を定めて、花の顔をもって人間の顔を規定するように、自然の享受には式目あり監戒あるべきことをいっている。ほとんど刑書である。按ずるに、面貌に直結するところにまで生活の美学を完成させたのはこの袁氏あたりだろう。本を読むことは美容術の秘薬であり、これは塗りぐすりではなく、ときには山水をもって、ときには酒をもって内服するものとされた。詩酒微遂という。この美学者たちが詩をつくったことはいうまでもない。山水詩酒という自然と生活との交流現象に筋金を入れたように、美意識がつらぬいていて、それがすなわち幸福の観念に通った。」
「今日では、士大夫すでにほろびて、その美容術はみごとにすたれた。天下は小人のものと定まったらしい。本なんぞは三年読まなくてもすむ。山水花竹は骨董同様ひとが任意に火をつけて燃すものとなった。自然もまたはかなきものであって、詩はそれに対して抵抗感覚をうしなったのか、挽歌すら出ししぶっている。」
(石川淳「敗荷落日」より)
「一箇の老人が死んだ。通念上の詩人らしくもなく、小説家らしくもなく、一般に芸術家らしいと錯覚されるようなすべての雰囲気を絶ちきったところに、老人はただひとり、身辺に書きちらしの反故もとどめず、そういっても貯金通帳をこの世の一大事とにぎりしめて、深夜の古畳の上に血を吐いて死んでいたという。このことはとくに奇とするにたりない。小金をためこんだ陋巷の乞食坊主の野たれじにならば、江戸の随想なんぞにもその例を見るだろう。しかし、これがただの乞食坊主ではなくて、かくれもない詩文の家として、名あり財あり、はなはだ芸術的らしい錯覚の雲につつまれて来たところの、明治のこのかたの荷風散人の最期とすれば、その文学上の意味はどういうことになるか。
おもえば、葛飾土産までの荷風散人であった。戦後はただこの一篇、さすがに風雅なお亡びず、黄興もっともよろこぶべし。しかし、それ以降は・・・・・・何といおう、どうもいけない。荷風の生活の実状については、わたしはうわさばなしのほかにはなにも知らないが、その書くものはときに目にふれる。いや、そのまれに書くところの文章はわたしの目をそむけさせた。小説と称する愚劣な断片、座談速記なんどにあらわれる無味な饒舌、すべて読むに堪えぬもの、聞くに値しないものであった。わずかに日記の文があって、いささか見るべしとしても、年ふれば所詮これまた強弩の末のみ、書くものがダメ。文章の家にとって、うごきのとれぬキメ手である。どうしてこうなのか。荷風さんほどのひとが、いかに老いたとはいえ、まだ八十歳にも手のとどかぬうちに、どうすればこうまで力おとろえたのか。私は年少のむかし好んで荷風文学を読んだおぼえがあるので、その晩年の衰退をののしるにしのびない。すくなくとも、詩人の死の直後にそのキズをとがめることはわたしの趣味ではにあ。それにも係らず、わたしの口ぶりはおのずから苛烈のほうにかたむく。というのは、晩年の荷風に於て、わたしの目を打つものは、肉体の衰弱ではなくて、精神の脱落だからである。老荷風は曠野の哲治のように脈絡の無いことばを発したのではなかった。言行に脈絡があることはある。ただ、そのことがじつに小市民の痴愚であった。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
