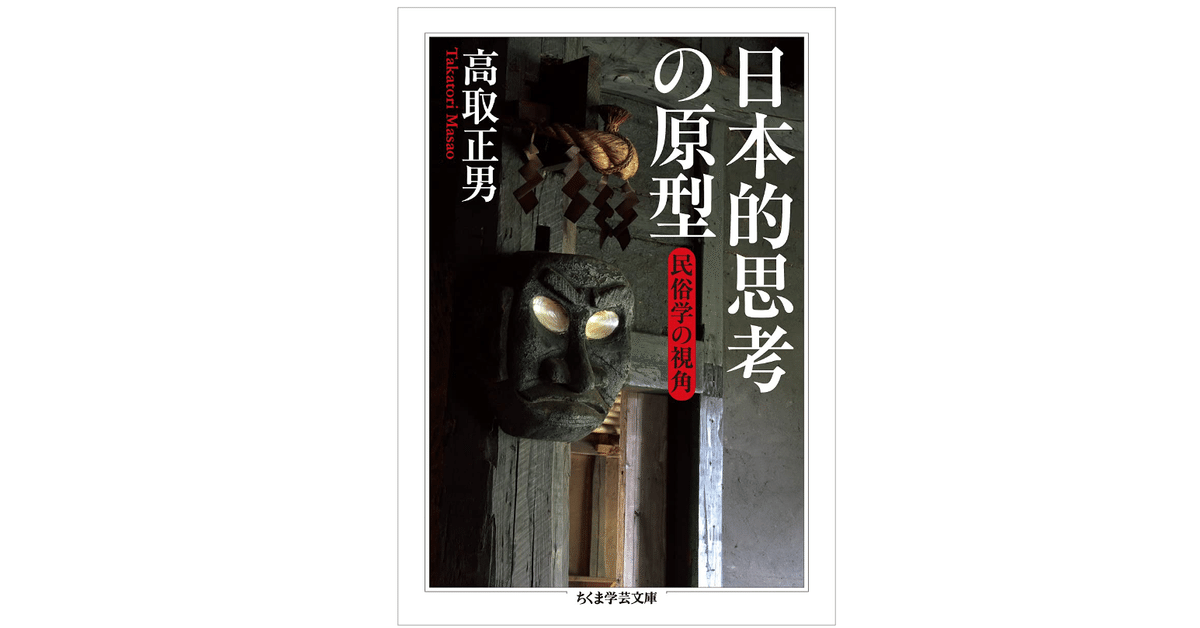
高取正男 『日本的思考の原型 ――民俗学の視角』
☆mediopos-2440 2021.7.22
本書は最初に
「ワタシの茶わん」の話ではじまる
家族にはそれぞれ
「ワタシの茶わん」があって
それをほかの人が使うと
違和感を覚えるという話である
ふつう考えると
個人意識の強い近代人ほど
自分の食器という意識が強そうだが
ヨーロッパやアメリカではもともと
個人の食器を用意する習慣はなかったそうだ
それに対して
いわゆる近代的意識以前の日本人が
「ワタシの茶わん」という意識を強くもっている
著者の高取正男によれば
私たち日本人の意識下には
「モノ」と一体になった「ワタシ」があり
その「モノ」は「茶わん」のようなものであり
また所属する家族や組織や地域のようなものでもある
そのために「ワタシの茶わん」という意識が強く働く
そんな「ワタシ」の上に
明治以降の西洋文化の受容に際して
近代的な個人意識が接ぎ木され
その二重構造が
近代以降の「ホンネ」と「タテマエ」を
生むことになっているという
高取正男はその「ワタシ」を
「エゴの本性」と名づけ
「日本的思考」の「原型」だとしているのだが
本書の議論から少し外れて論じるならば
「モノ」と一体になった「ワタシ」は
述語的なありようを生きる自我であり
近代西洋的な個人意識としての「私」は
主語的なありようを生きる自我であるともいえる
高取は「ワタシ」を
「エゴの本性」と呼んでいるのだが
それよりもそれを
個人意識が生まれてきた出自としての
集合的意識(無意識)と表現したほうがいいかもしれない
その「ワタシ」は多くの場合
「影」のような無意識になってしまい
それを意識的にとらえることはむずかしいのだが
むしろそれを意識化していくことで
新たな可能性をみていくこともできる
近代は集合的な形をとりがちな述語に
包摂されることのない
主語としての自我を
主体的な自我としてきた
それは主語的であるがゆえに
むしろ「影」を強固にし
そのことで魂にとってだけではなく
自然認識においても
環境問題をはじめ
さまざまな問題を生むことになった
その「影」を自覚することが
必要になってきているのである
「影」は「ワタシ」でもあるのだが
それを自覚することが求められている
自覚が伴わない場合
ただの集合意識(無意識)のなかで
主体的な自由をなくしてしまうことになるからである
主語的なものは述語的なものに
自覚的なかたちで包摂されることで
新たな自我への
錬金術的統合と変容を得る可能性を得る
ある意味でそれは
禅でよくつかわれる
「花は紅 柳は緑」という
悟りのプロセスの展開にも似ている
はじめモノと一体化していたワタシから
モノとワタシが分かれ
そのうえでモノとワタシが
統合され変容するという錬金術
■高取正男
『日本的思考の原型 ――民俗学の視角』
(ちくま学芸文庫 2021/7)
「日本人にとって、食器は所持者の象徴としてあつかわれてきた。それは個人の私権を擁護するさまざまな制度など、およそ近代社会の創出した理性の産物とちがい、それ以前の、より根元的な世界に所属している。おなじ類のものをヨーロッパ世界の伝統的な生活習俗のなかに求めるなら、家や部屋の鍵などがそれに当たるだろう。すでにのべたように、日本人は有効のしるしとして、同盟のあかしとして酒席で盃を共にしてきた。日本座敷の日本料理の席でなされる盃の執拗な献酬は、その残留形式である。これに似た西洋の週刊は、鍵の贈呈だろう。名誉市民の称号を贈ったしるしに、その市の紋章入りの金・銀製の飾り鍵を手渡し、それを有効のしるしとする風習などは、いまでは日本でもまねられている。」
「世の中には、言わなくてもわかる人でなければ、言ってもわからないということがある。縁なき衆生には度しがたいという言葉もあるが、回心の体験をはじめとする信仰の内面のことなど、こうした問題の中核部に所在している。必然的に、日常生活内部での人の禁忌意識のありようなどといったことなども、この問題の末席に位置しているといってよいだろう。伝統の潔癖感にもとづく私たちの拒絶反応は、おなじ日本人として民族の生活文化をともにになっておれば、説明なしに相互に了解しあえる。そして、個人の私権、プライバシーといった世界中どこにでも通用する普遍的概念も、衛生的という近代科学のもたらした概念とおなじように、現実には民族ごとに濃厚に個性をもつ伝統的な禁忌意識や潔癖感に支えられ、両者はたがいに秩序をもって固く結ばれている。
明治以降の知識人の多くは、私たちの内面にほんねとたてまえというかたちで所在する如上の重層構造を、しばしば単純にとりあつかう誤りを犯してきた。西洋近代の文物をうのみにし、その表面の合理的にみえるたてまえの部分に合致しないものを、つめたく批判するのでなければ、逆に伝統の感情に発する拒絶反応に身をまかすという両極端を、不用意に往復するだけに終わることが多かった。いま大切なのはここで立ち止まり、日常の生活内部を掘り下げて、氷山の下にかくれている部分をさぐりあてたあと、もういちど水面に浮上する作業にとりかかることである。それは、私たちの日常の生活文化の、構造的認識とよばれるものである。
その場合、私たちにとっていちばん気になるのは、すでにのべたように、近代市民社会の根幹をなしている個人の自覚、ないしは個人意識のよってたつ根拠についてである。というのは、明治以来、西洋近代に開花した文物すべてを手本とみなし、法律制度をはじめ、社会文化すべての分野にわたって、そのたてまえを移植する努力がつづけられてきた、だが、それを植える土壌まで輸入することはできない。そのためには接ぎ木の台木をさがすようにして、私たち日本人の個人意識の根底になるようなもの、近代個人主義の土台となるエゴの正体を、ひろく伝統的な民俗のなかにたずねる必要がある。最初に「個人のシンボル」という題で、個人の食器をめぐる伝来の禁忌意識から考察をはじめたのも以上の理由にもとづいている。しかも、こうした禁忌意識に発する人々の前論理的な拒絶反応が、個人を主体に、個人をめぐってあらわれるだけでなく、先にみたようい方言をひとしくするような地域社会をも単位とし、個人の場合と同じようにしてあらわれることにも注意する必要がある。」
(阿満利麿「解説 「現在学」としての「民俗学」」より)
「「ワタシの茶碗」を家族といえでも使用すると、なぜ違和感を覚えるのか。まして他人が使えば、なにか後味の悪い感情が生まれるのはなぜなのか。あるいは、葬儀の出棺の際に、故人の使用していた茶碗を割る慣わしがある。どうしてそのようなことをするのか。
高取は、こうした例から「モノ」と一体になった「ワタシ」が、私たちの通常の意識下にあると考え、それを「エゴの本性」と名づけ、「日本的思考」の「原型」だとする。つまり、近代以前の日本人には、なんらかのモノ、あるいは所属する家族や組織、地域に一体化させて自分を認識する傾向が強かった。それは、明らかに近代の個人意識とは異質である。」
「では、私たちの自我が、このような「ワタシ」を内にふくんでいる理由はどこにあるのか。それは、明治以降の西洋文化の受容に際して、一種の「接ぎ木」現象が生じたからである。つまり、西洋近代に発する人権、平等、自由という理念は、今までの自我のあり方を台木として受容された、したがって、折にふれて、台木が姿を見せることになる。
そしていうまでもないが、このような自我の二重構造が、私たちのものの考え方に「タテマエ」と「ホンネ」を生む原因ともなっている。」
「「ワタシ」は、近代以前の個人意識なのだが、高取は、しばしば「一寸の虫にも五分の魂」の「五分の魂」、あるいは「意地」とも呼ぶ。それらは、あまりにも感覚的な表現だが、高取はその特徴として二つのことをあげる。
一つは、台木となっている「ワタシ」の外延は思いのほか広い、ということ。(・・・)かつて勤めていた企業も「ワタシ」の範囲にあるのだ。ワタシなりにその理由を考えてみると、近代の自我意識が、個人の独立、自立を前提とするのに対して、「ワタシ」は、自己を取り巻く諸々の関係を優先させて自己を意識するからではないか。
二つは、近代の自我が、家やムラなどと対立することによって形成されてゆくのに対して、「ワタシ」は「所属する共同体に自己を同一化」することによってはじめて存在することができたという点である。」
「高取は、「日常の生活内部を掘り下げて、氷山の下にかくれている部分をさぐりあてたあと、もういちど水面に浮上する作業」つまり、「日常の生活文化の構造的認識」にとりかからなければ、日本人に本当の必要な主体性は形成されない、とのべる。」
「本書で一貫して強調されていることは、日本人の思考が世間の常識が是とする考え方、見方に尽きているのではなく、かならず、もう一つの思考や感覚が、まるでその「影」のように付随しているという点であろう。
しかも、その「影」の部分に気づくことは大変難しい。だから、「正統」(表向き)の思想や感じ方だけで物事を進めると、思わぬ壁にぶつかることが生じる。大切なことは、そのとき、なぜこのような事態にいたったのかを、わが身をふり返って、よくよく「内省」することなのだ。「内省」こそ、「民俗学」を支えるキーワードなのである。
にもかかわらず、明治以降の日本の近代化の道は、このような「影」の部分を切り捨てるばかりで、その役割を評価することがなかった。また、「内省」よりも、外部に向かって自己を主張する生き方が評価されるようになった。その結果、日本人の思考は、単線化、一元化してしまった。それは分かりやすいが、問題を解決し、前に勧める強さからは遠い。
高取は、近代的自我(「私」)と「ワタシ」、「表街道」を支えてきた「裏街道」の役割、「定住」と「漂泊」という暮らしの二重性、「先祖神」と「マレビト」といった「神」の「原形質」の違い、つまり「正統」とその「影」を種々のレベルで対比することによって、私たちの自己の全体像を認識しようと試みている。主体的に生きるとは、このような認識から生まれてくるのである。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
