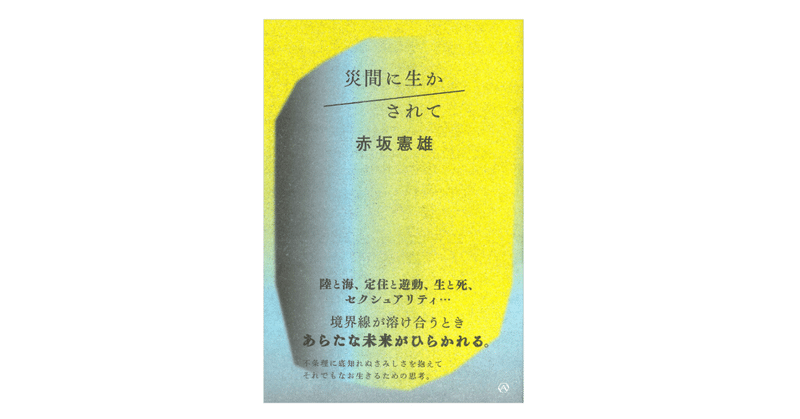
赤坂憲雄『災間に生かされて』
☆mediopos2994 2023.1.28
自由を生きるということは
さまざまな境界を越えてゆくということでもある
物理的な境界
人為的な境界
身体的な境界
心の境界
生と死という境界…
そんな境界を越えて生きようとすれば
矛盾や不条理のまえで立ち竦まざるを得ないときがある
自然による災厄だけではなく
利害や主義のもとでの人為的な災厄が起こり
グローバルという名のもとに
硬直した管理社会へとますます傾斜している現代において
その先にはどんな未来が見えるだろうか
そこで生き抜くためには
どのうようにすればいいのだろう
本書に描かれている「災間を生きる」ための
能舞台のうえでの「夜語り」のなかで
とくに印象に残ったのは
「第五夜 遊動と定住のはざまに、生きよ」だった
そこでは
「わたしたちはなぜ、逃げることを心の深いところで忌避するのか」
という問いかけがある
人類は一万年前の「定住革命」により
「人類の生存戦略は「逃げられる社会」から
「逃げられない社会」へと転換して」いったが
そこで生じた人の心の変容について
あらためて問いなおしてみる必要がある
管理社会というのは「逃げられない社会」である
「定住革命」の極北がそれだといえる
人は社会システムのなかでも
さらにはそこに適応した心的なあり方においても
「逃げる」という選択肢が封印されてしまっている
つまりそこにある「壁」「境界」の「外」が
禁じられてしまうようになっているのである
それを超えることは「病」であり「罪」であると
しかしそんな時代であるからこそ
「あらたな逃げられる社会」が拓かれる必要がある
空間的な意味において「広い世間のいたるところに、
隙間やあわいにアジールの穴を無数に穿つ」ことはもちろん
思考や感情や論理などにおいても
「西洋的なロゴスによるくびきを脱して、
世界を二元論的に分割する思考をやわらかく壊してゆく」
「レンマ的なものへと、舵を切ること」が求められている
さまざまな「災厄」は
ある意味でその可能性への象徴的な合図ともなっているのかもしれない
外へと逃げてはいけない
教えられ決められ指示されたことに従わなければならない
そんなすべてのことから自由へと向かうための合図として…
■赤坂 憲雄『災間に生かされて』(亜紀書房 2023/1)
(「夜語りの前に」より)
「いま、わたしたちは身の丈の言葉を取り戻すためのささやかな戦いを、それぞれの生きてある現場から始めるしかないのかもしれません。」
「災間を生きる。災間に生かされる知恵の構えは、来るべき災厄の訪れを予期しながら、つねに備えを怠らずに、いまを生き延びてゆくことが、自明な前提となるはずです。それに耐えられるような、持続可能でしなやかな社会を構想することが求められています。仁平典宏さんは、災間に時代に求められているのは、弱者を基準として、社会的に多様な「溜め」や「遊び」を用意することだ、と語られていました。しかし、三・一一以後の荒々しい現実は、それとは真逆の方向へと転がってきたようです。自己責任の名のもとに個人にリスクを負わせることを正義と見なすような発想が、加速度的にわたしたちの社会の表層を覆い尽くしてきました。そこでは、つねに社会的な弱者がだれよりも痛みを強いられるのです。」
「東日本大震災が始まって数か月後に、あるランチミーティングの場で講演をしたことがありました。それは経済界のリーダーたちの集まりでした。わたしが一時間ほどの講演を終えると、だれも質問する人はなく、いくらかの沈黙のあとに、一人の方がマイクを握られました。名前を広く知られた有名な企業の、たしか経営者でしたか。かれのスピーチは、わたしの記憶に強く刻まれました。ただし、覚えているのは、「先生のお話には、一度も数字が出てきませんでした。ポエムですね。残念ですが、再エネは地域に雇用を生みません」という言葉だけです。
思えば、わたしの話にはいつだって、数字というものはほんの稀にしか出てきません。とはいえ、指摘さてたこともなく、うかつにも気づいていませんでした。わたしは数字の裏付けなき言葉が、詩(ポエム)とひとくくりに呼ばれて、蔑まれていることを知ったのです。それ以降も、わたしの話には滅多に数字が出てくることはありません。いずれであれ、わたしはそのとき、心から、ならば詩人になりたいと思いました。だれに認められることもないままに、詩人になること。しかも詩を書くことのない詩人になることを願ったのです。」
「数字がしばしば、客観性や学問的な装いやらを凝らしながら、巧妙に人を欺くことも知りました。数字は人を虚勢し、思考停止の状態へと追いこんでいくのですね。数字を掲げて巧みに他者を批判する者が、なんとも恣意的に数字を操作しこねくり回す姿に遭遇して、脱力感に襲われたことが、幾度となくありました。ふくしまの声はいつだって数字に踊らされ、翻弄されてきました。それが原発事故以後の歳月を歪めてきたのではなかったか、と思うのです。」
「これから幕を開けるのは、いわばまぼろしの講演会のようなものです。」
(「第一夜 しなやかにして、したたかに。汝の名は」より)
「さて、生まれてはじめて、能舞台のうえでお話をさせていただきました。
そもそも、話のオチなどありません。とても困っています。いや、途方に暮れています。大言壮語でもするかのように、「しなやかにして、したたかに。汝の名は」という言葉を書きつけていました。汝の名とはなにか。
(…)
汝の名とはなにか。そこにたどり着くために、トラウマだらけの記憶の雑多な穴蔵から、忘れかけているものたちを曳きずりだして、さらに、つたない思索と歩行を重ねてゆくことにします。名づけがたきものたち、怪しいものたち、幽けきものたち、頼りないものたち、小さなものたち……との、はるかな和解と連帯のために。(…)
生きとし生けるもの、すべての命のために、わたしはいったい、なにを捧げることができるのか。
だから、何度でも、汝の名は。」
(「第四夜 民話という、語りと想像力のために」より)
「ふと、わたしは考えるのです。わたしたちはもっと深く絶望し、もっと惨めにひき裂かれながら、途方に暮れたほうがいいのかもしてない、と。」
(「第五夜 遊動と定住のはざまに、生きよ」より)
「たとえば、わたしたちはなぜ、逃げることを心の深いところで忌避するのか、と問いかけてみます。それが身を守るという生存戦略にとっては、きわめて不自然かつ非合理な選択であることは否定できません。命をめぐる危険水域にまで追いつめられ、それをあきらかに認識していながら、人はなぜ、ときに、なおそこに留まるという選択をするのか。隷従と自己犠牲のはざまに、いったいなにが起こっているのか。その選択の背後には、なにか不思議な、たとえば人の心にまつわるメカニズムが隠されているのかもしれません。しかし、意外なほどに、それがそれとして問われる場面はすくない気がするのです。
およそ一万年前に、ユーラシアのいたるところで定住革命が始まった、といわれています。人類は遊動を基調とする生活様式から、ある土地に家を建てムラの掟にしたがって暮らす。人類は遊動を基調とする生活様式から、ある土地に家を建てムラの掟にしたがって暮らす、定住的な生活様式へと移行していったのです。
(…)
いわば、定住を無意識の前提として、それを心の主旋律とする世界観が人々を呪縛しているうような、そうした世界の片隅にわたしたちは生かされているのです。そこでは、逃げる・去る・離れる、といった心的な防衛機制がマイナスの色合いに染めあげられ、断罪され、心の病いの原因と見なされることでしょう。しかし、定住革命以前の遊動をつねとしていた人類は、離合集散をくりかえしながら、やわらかく社会を維持してゆくために、むしろ逃げる・去る・離れるといった行動原理を、プラスの生存戦略として受け入れていたらしいのです。
(…)
一万年前の定住革命によって、人類の生存戦略は「逃げられる社会」から「逃げられない社会」へと転換していきましたが、そのとき、人の心はいかなる変容を強いられたのか。それはまさに、現代においてこそ切実に問われるべきテーマであるのかもしれない、と感じています。」
「遊動生活を営む狩猟採集民の社会では、生態環境から社会・文化にいたるまでのシステム全体が、妬みを回避するように機能している、と説明されることがあります。妬みというのは、相手はもっているけれども、自分はもっていないという亀裂を先鋭化させずにはいない、心のあり方です。遊動の民が織りなす社会は、そうした妬みや恨みといったものを曖昧に散らして、廃棄する社会だったことを確認しておきましょう。そもそも、遊動の民は運搬能力以上の物をもつことが許されません。わずかな基本的な道具のほかは、キャンプ移動のときに棄てられ、いわゆる富の蓄積とは無縁なのです。妬みの起源は定住のはじまりと軌を一にするのかもしれません。」
「遊動と定住という問題を、心という視座から論じることは可能だろうか、と思いを巡らしてきました。それは可能ではないか。という予感めいたものはあります。すでにはじまりの問いとして、わたしたちはなぜ、逃げることにたいしての忌避感をこれほど強くもっているのか、と問いかけておきました。それほどにつらい状況ならば、そこから身を離して、よその世界へと逃避すればいいにもかかわらず、それが容易ではないのはなぜなのか。わたしはそこに、定住革命以後の一万年の時間が、見えない澱のようんび堆積していることを思わずにいられません。」
「広い世間が、たとえば学校や教室という閉じられたムラのような世界の向こう側に、たしかに広がっていることを知っていれば、きっと生き延びることができます。しかし、わたしたちはそれを、きちんと子どもに伝えているでしょうか。いじめという名の「全員一致の暴力」にたいして、有効に対処するのはかぎりなく困難なのです。大人だって、じつのところ、帰属する組織や社会のなかに生起する「全員一致の暴力」の前では、翻弄されるばかりで、有効な対抗手段を持ち合わせてはいないのです。だから、ときには「逃げる」という選択肢だって許されていることを、子どもたちにそれとして伝えるべきだと、わたしは考えています。
(…)
妬みや恨み、あるいは不快なもの、危険なもの、穢れたものにどのように向かい合うのか。それはまさに心理学的な問題でもあります。それは無意識というものをどのようにコントロールするのか、という問いに置き換えることができるかもしれません。無意識と遊動性との関わりを問いかけることは可能でしょうか。わたしたちは感じている心のストレスや病といったものには、どこかで定住革命以後の一万年の歴史のなかで織り上げられてきた見えない定住規範性が影を落としています。
(…)
定住革命がもたらした、逃げられる社会から逃げられない社会への転換は、人の心にいかなる変容を強いてきたのか。逃げる/逃げられないという二元論に根ざした問いがいま、とても大切なテーマになりつつあると感じています。逃げる・去る・離れるといった心理的な防衛機制が、病の原因とされてしまうような社会のあり方を、いくらかでもやわらかくほどき、離合集散を当たり前に認めるような方向へと転換してゆく。そうした促しが始まっているのかもしれません。」
「あらたな逃げられる社会は可能か、という問いが向かうべきなのは、空間的な外部ではありません。いや。つかの間の外部はありえるし、それはそれで必要なのです。広い世間のいたるところに、隙間やあわいにアジールの穴を無数に穿つことは、いつだって求められています。そのうえで、西洋的なロゴスによるくびきを脱して、世界を二元論的に分割する思考をやわらかく壊してゆくことが、戦略的に求められているということです。ロゴス的なものからレンマ的なものへと、舵を切ること、と言い換えることもできるでしょうか。山内得立さんの『ロゴスとレンマ』(岩波書店、一九七四)のかたわらへ。」
【目次】
夜語りの前に
■災間を生きるために
■中世の訪れを予感し、抗いながら
■不安は数量化できない
第一夜……しなやかにして、したたかに。汝の名は
■そのとき、友は巡礼に
■津波の痕を訪ねて
■世界の終わりのような
■幽霊と出会うとき
■生きとし生けるもの、すべての命のために
■山野河海を返してほしい
■いのちの思想を紡ぎなおす
第二夜……東北から、大きなさみしさを抱いて
■被災体験に触れる
■なぜ、わたしが生き残ったのか
■人間の根源的な無責任について
■その理不尽に折り合いをつけるために
■巨大な体積をもったさみしさ
第三夜……渚にて。潟化する世界のほとりで
■潟化する世界に出会った
■海岸線は揺らぎのなかに
■人間という原存在への問い
■無主の海からみんなの海へ
■海のかなたから訪れしもの
第四夜……民話という、語りと想像力のために
■おれは河童を見たことがある
■大きな真っ白い鳥が飛んだ
■奇譚が遠野と会津を結びなおす
■狐に馬鹿にされた、という
■民話的想像力によって、布を織る
第五夜……遊動と定住のはざまに、生きよ
■心の考古学は可能か
■あらたな飢えと村八分の時代に
■われらの内なる山人
■定住革命のはじまりに
■遊動という離合集散のシステム
■住まうことと建てること
■妬みや恨みを抱えこんで
■分裂病親和性と強迫症親和性
■あらたな逃げられる社会は可能か
■あとがき
◎赤坂 憲雄(あかさか・のりお)
1953年、東京生まれ。学習院大学教授。専攻は民俗学・日本文化論。
『岡本太郎の見た日本』でドゥマゴ文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞(評論等部門)受賞。
『異人論序説』『排除の現象学』(ちくま学芸文庫)、『境界の発生』『東北学/忘れられた東北』(講談社学術文庫)、『岡本太郎の見た日本』『象徴天皇という物語』(岩波現代文庫)、『武蔵野をよむ』(岩波新書)、『性食考』『ナウシカ考』(岩波書店)、『民俗知は可能か』(春秋社)など著書多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
