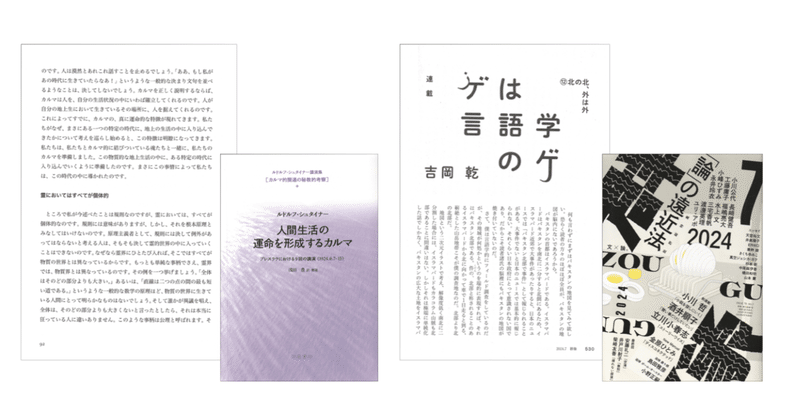
吉岡乾「連載 ゲは言語学のゲ⑫北の北、外は外」(『群像』)/シュタイナー「霊においてはすべてが個体的」(『人間生活の運命を形成するカルマ』)
☆mediopos3505 2024.6.22
右と左
東と西
だれかと向かい合っているとき
「私から見て左(右)」といったように
基準点が明かな場合は
左(右)がどちらなのかを示せるが
国語辞典で
「左」「右」が
どのように説明されるかをみると
たとえば
「左」は「東に向かって北のほう」
「右」は「東に向かって南のほう」
といった説明がなされているものの
たとえば北極点や南極点ではこの説明は成り立たない
北極や南極にいないときでも
体内磁気とでもいったもので
だれもが東西南北の方角がわかるわけではない
「相対的な表現というのは難しい。」
「左の物は右の物の左にあり、
右の物は左の物の右にある」ように
「私」が「ここ」にいて
「私」の「右」がこちらで
「左」がこちらである
というように
「私」といった認識における中心があってはじめて
そこから「相対的な表現」が可能にはなるが
そうでない限り「左」と「右」は示せない
相対的な表現であっても
右か左か東か西かといったことについて
それなりの「規則」を示すことはできるが
それはこの地球上でのこと
(ここから話はすこし飛ぶが・・・)
ルドルフ・シュタイナーによれば
「規則には意味があ」るものの
「霊界にひとたび入れば、そこではすべてが
物質の世界とは異なってい」て
「霊においては、すべてが個体的」だという
「全体はそのどの部分よりも大きい。」
「直線は二つの点の間の最も短い道である。」
といった明らかだとされていることも意味をもたなくなる
「霊の世界の中では、原理というものはあり得」ず
「すべては個体的」であって
「ひとつひとつの事柄を、
それ自体として知らなければ」ならない
その意味でいえば
認識における中心があってはじめて
相対的なものを示すことが可能となるように
霊界においてはあらゆる認識が「個体的」なのである
それはおそらく空間的な認識だけではなく
時間的な認識にも関わってくることで
ひょっとしたら
言語における相対表現の困難さというのも
そうした個体的な霊的認識に由来するところも
多分にありそうだ
この地上世界を説明する言葉や論理が
往々にして矛盾に満ちているのも
「霊」における「個体的」なところを源として
生まれてきているからなのかもしれない
■吉岡乾「連載 ゲは言語学のゲ⑫北の北、外は外」
(『群像』2024年7月号)
■ルドルフ・シュタイナー(浅田豊訳・解説)
『人間生活の運命を形成するカルマ』(涼風書林2024/4)
**(吉岡乾「連載 ゲは言語学のゲ⑫北の北、外は外」より)
*「相対的な表現というのは難しい。
例えば左右。テーブルを挟んで誰かと向かい合って座っていて、テーブルの上の物体の位置を言う際に左右を使おうと思うと、〝私から見て左〟などのように、基準点を明示しないと分かりづらい。〝その、スマホの右の封筒を開けて〟とだけ言われても、スマホの両側に配置されている封筒のどちらを開ければ良いか、判定できない。
言語によってはこういう場面すら、〝スマホの南の封筒〟とか、〝スマホの浜側の封筒〟みたいな、絶対方位や地勢的表現を用いて位置を表すことがあり。寧ろ、そういう言いかたしかできない言語もだ。
パキスタン北部で話されているブルシャスキー語(系統的孤立語)では、〝家の左〟や〝牛の右〟は言えるが、〝封筒の左〟や〝木の右〟は言えない。家や牛には、玄関や頭などを前方の基点としたそれ自体の向きがあるが、封筒や木にはそれ自体の向きがないと理解されるため、そういった物体を基準点として左・右で示すいい方が許されない。話し手と聞き手とがその基準の物体に向かって横並びで居たならば、〝そちらの側〟か〝こちらの側〟かで左側か右側かを区別できる(立ち位置によってどちらがどちらになるかは逆転する)。あるいはもう、別の物体を基準として参照するか直接指さすなど身振りを用いて指定するくらいしか、「封筒の左」や「木の右」の位置を手短に占める術はない。」
*「そういった言葉を辞書などで「定義」するのにも、悩ましい側面がある。例えば、どの辞書でも構わないのだが、手許の『国語辞典』(久松潜一・林大・阪倉篤義監修、1979年、講談社学術文庫)から抜粋してみよう。
ひだり【左】(名)①東に向かって北のほう。←→右。②(さかずきは左手に持つ、また鉱山で左手を鑿手と言うとも)酒を好むこと・人。③急進派。左翼。←→右。(856頁)
みぎ【右】(名)①東に向かって南のほう。←→左。②文書で、前に述べたこと。前条。←→左。「——のとおり」③二つのうち、すぐれたほう。「——に出る者がない」「④保守的であること。右翼。←→左。(984頁)」
*「東に向かって北か南かという定義は、北極点に居たら使えない。北極点からは全ての方向が南であり、北も東も西もないからである。恰度立っている場所が北極点でホッキョクグマに襲われんとしている場面、〝熊から眼を逸らすな。合図とともに俺が懐に飛び込んで囮になるから、お前はその隙に走って逃げるんだ。ここから右手に真っ直ぐ行けばさっきスノーモービルを駐めた場所だからな〟と相棒が懸命に指示出しをしている最中に、〝右ってどっちだろう!? ここ北極点だから東も北もないんだけどなあ!〟などと考えていたら、後はもう大惨事である。南極点でも同様に成立しない。
第一、世の中には東西南北の意識がそんなに強くない人でだってあるだろう。僕は得てして屋外にいれば脳内マップが開けるので東西南北もささっと把握できる質の者だが、僕の妻を見れば東西南北は日常感覚の外に捨て置いているようだ。(・・・)
ではどう定義しよう。特定の文化・地域に縛られない定義を考えると、正に難題である。
人体を正中線で切って心臓が多く含まれているほうだとか言っても、左右を確認するためにその都度、人を掻っ捌かなければならなくてしんど。だけど人体は基本的に、外貌がほぼほぼ左右対称にできているので、外見では決め手に欠く。北半球や南半球でシンクに溜めた水を抜いた際の渦の巻く向きを基準に取っても、赤道直下で困る。ヒラメやカレイの向きで定義されたら、山岳民が泣く。利き手は個人差が出る。(・・・)
左の物は右の物の左にあり、右の物は左の物の右にある。
周縁地域は中央から見れば周縁にあるが、周縁から見ればそこが中央であって中央が周縁になる・・・・・・かと思えば、そうとも言えない。
中央と周縁とは必ずしも相対的な表現ばかりであるわけでなく、地理、経済、政治といった様々な側面が複合的に織りなしている概念になっている。僕の調査しているパキスタンの北縁は南アジア地域の北縁でもあり、地勢的にも平地の拡がる南方とは異なって峻厳な山地で構成された周縁である。だからこそ暮らし易い平野部をマジョリティに占拠され追い遣られた少数民族が暮らし、様々な形容の小さい言語、小さい民族が複雑なモザイクを描いている。北の北の現地に来たとしてもそこは周縁であって、中央は遙か南にあるのだ。」
**(シュタイナー『人間生活の運命を形成するカルマ』〜
「講演4 1924.6.10/霊においてはすべてが個体的」より)
*「霊においては、すべてが個体的なのです。規則には意味がありますが、しかし、それを根本原理とみなしてはいけないのです。原理主義者として、規則には決して例外があってはならないと考える人は、霊的世界の中に入っていくことはできないのです。なぜなら霊界にひとたび入れば、そこではすべてが物質の世界とは異なっているのです。その例を一つ挙げましょう。「全体はそのどの部分よりも大きい。」あるいは、「直線は二つの点の間の最も短い道である。」というような一般的な数学の原理ほど、物質の世界に生きている人間にとって明らかなものはないでしょう。そして誰かが異議を唱え、全体は、そのどの部分よりも大きくないと言ったとしたら、それは本当に狂っている人に違いありません。このような事柄は公理と呼ばれます。それは、それ自体として真理であり、よく言われるように、それを証明することは可能でもなければ、必要でもないのです。このように表現されるのです。「直線は二つの点の間の最も短い道である。」という命題についても同様です。しかしこの二つの命題は霊の世界ではもはらや妥当しないのです。霊の世界では、「全体はそのどの部分よりも常に小さい。」という命題が実に妥当するのです。そしてすでに人間の本性の中において、これが真実であることが確証されることがわかるのです。つまり皆さんが、皆さんの物質的人間の霊的なものを霊的世界で観察してみれば、どれは、皆さんが物質界で存在しているのとほぼ同じ、やや大きいですが、ほぼ同じ大きさを持っています。しかし皆さんが霊界で皆さんの肺や肝臓を観察するならば、それは巨大なのです。しかしながら、それらはより小さなものの部分なのです。そこで私たちは、考え方を変えることを学ばなければいけません。霊の世界では、直線は最も短い道ではまったくありません。そうではなく、最も長い道なのです。なぜなら、霊界において私たちがある一点から次の点に来るとき、その行き方はまったく違うのです。物質世界は杓子定規です。この道は長い、次の道はもっと長い、そしてあの道は最も短い、これが直線です。————霊界はそうではありません。そうではなく、「まっすぐに」来ることには大きな困難がつきまとっています。どんな曲がった道も、直線よりも短いのです。ですから、「直線は二つの点の間の最も短い道である」と言うことは、意味がありません。それは実際には、最も長い道なのですから。
霊界においてはすべてが物質界とは異なっているということに精通しなければいけません。人々は、全体はその部分よりも大きいとか、あるいは直線は二つの点の最も短い道であるというような先入観にとらわれて判断しているので、彼らは誠実に練習していても、霊界に入っていくことがとても難しいのです。公理とじゃそういうものなのです。しかし霊界の中に入り込んでいこうとする場合には、物質界に妥当するそれ以外のすべての真理もまた捨てなければいけません。つまり霊の世界の中では、原理というものはあり得ないのです。すべては個体的です。ひとつひとつの事柄を、それ自体として知らなければいけません。論理的に包括するようなひどいこと、そして一般的な規則を提示するようなこよは、霊の世界にはまったくないことです。そして、人間がグループとして地上生活の発展を遂げていくということは真理であり、全体としては妥当するのですが、この真理についてももちろん同じことが言えます。つまりこの真理は破られるのです。そしてまさにこの真理が破られるときに、この真理の意味が本当にわかってくるのです。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
