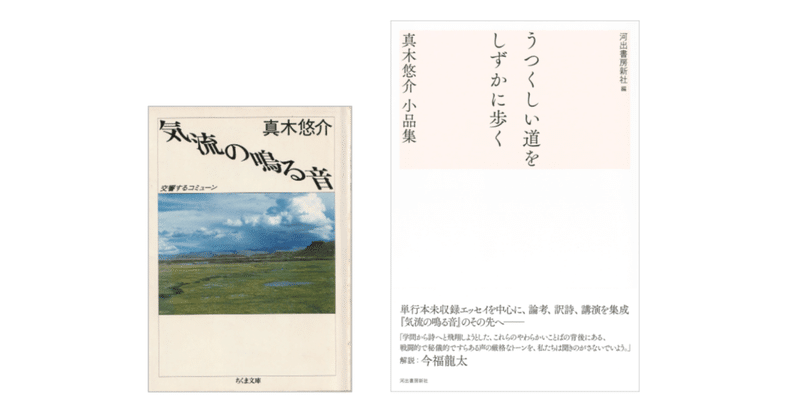
真木悠介『うつくしい道をしずかに歩く/真木悠介 小品集』/『気流の鳴る音―交響するコミューン』
☆mediopos-3062 2023.4.6
昨年亡くなった真木悠介の(見田宗介の名ではない著作)
『気流の鳴る音』は一九七七年に刊行されているが
本書はその後の一九八〇年代に書かれた
単行本未収録作品を中心にした貴重なエッセイ集である
タイトルの「うつくしい道をしずかに歩く」は
『気流の鳴る音』でもとりあげられている
ナヴァホ・インディアンの賛歌(引用で紹介)
真木悠介という名に込められた
「悠々としたものによせる心」にも
通じている賛歌である
引用紹介では
収録されたエッセイから
「悠」の感じられるものをとりあげてみた
「都会————幻影の荒野」では
アメリカ・インディアンの文化において
「かならずいちどは、その社会の外へ出なくてはならない」
というイニシエーションを経て獲得される
秘密の名まえ/守護してくれる動物の霊/秘密の歌
に対応するものを作り出すために
わたしたちは現代における
「真に荒野の名に値する深さをもった荒野」を
持たねばならないことが示唆される
「生きている色」では
色の名はほんらい
「平板な色相環などからくるものではな」く
たとえば「生きている色」と「死んでいる色」のような
「世界の息づかいのようなものから」生まれていることを説く
即物的記号的なありかたから自由になるために
そして「虹の歌」では
「万葉集には虹の歌がない」というところから
「万葉のうたびとたちは、
春が来たことのよろこびを歌うことはあっても、
春の〈美しさ〉をどこかに求めるということはなかった」
かれらは「〈世界から分かたれて〉いなかった」からだという
世界に帰還するためにはどうすればいいのだろう・・・
巻末に付されている今福龍太による解説にあるように
真木悠介は「出会われる出会い」というような
不思議な受動態を使う
その受動態にはさまざまなヴァーションがあり
「「表現」とは「あらわす」ことではなく、「あらわれる」こと」
「自分から「創る」のではなく、
なにものかによって自分は「創られる」」のだというように
「自己内創造の他律性」として表現される
現代人の自我はさまざまな軛(くびき)をもっているが
そこにあるのは
「私が」表現しなければならない(「私が」書く・「私が」論じる)
「私が」創らなければならない(「私が」演じる・「私が」作る)
というように
強迫的な自我病のようなものだといえる
真木悠介の使う受動態は決して受け身なのではない
「うつくしい道をしずかに歩く」
というときにもおそらく
「私が歩いている」というよりは
自律的でありながら
その根底において導かれているという「他律性」である
現代人の歩まねばならない「荒野」でのイニシエーションは
「私が」という自我の軛から
「やわらかく解放」するものでもあるだろう
そうすることで
「老いた日に
しずかに私は歩くだろう
このうつくしい道のゆくまま」
ということもできるのではないか
■『うつくしい道をしずかに歩く/真木悠介 小品集』
(河出書房新社 2023/3)
■真木悠介『気流の鳴る音―交響するコミューン』
(ちくま学芸文庫 筑摩書房 1986/8)
(『うつくしい道をしずかに歩く』〜訳詩「うつくしい道をしずかに歩く」より)
「 今語っているのは神
あなたの足で私は歩く
私はあなたの肢体で歩く
私はあなたのからだを運ぶ
私にかわってあなたが思う
あなたの声が私のために語る
美がまえにある
美がうしろにある
美が上を舞う
美が下を舞う
私はそれにかこまれている
私はそれにひたされている
若い日の私はそれを知る
そして老いた日に
しずかに私は歩くだろう
このうつくしい道のゆくまま
※ナヴァホ・インディアンの賛歌、真木悠介訳(出典=Walk Quietly the Beautiful Trail:Lyrics and Legends of the American Indian.Hallmark Editions,1973/真木悠介『気流の鳴る音』ちくま学芸文庫)
(『うつくしい道をしずかに歩く』〜「比較社会学ノート三 都会————幻影の荒野」より)
「多くのアメリカ・インディアンの文化においては、その社会の一員は、かならずいちどは、その社会の外へ出なくてはならないことになっている———— 人間の網の目の外へ、「自分の頭」の外へ、一生にすくなくとも一度は。彼がこの幻をもとめる孤独な旅からかえってくるとき、秘密の名まえと、守護してくれる動物の霊と、秘密の歌をもっている。それが彼の「パワー」なのだ。文化は他界をおとずれてきたこの男に名誉を与える。」
「だがそれにしてもこの密林は、原初の密林とおなじように深いか?
都会という荒野をおとずれる現代の部族の青年たちは、その幻をもとめる孤独な旅の年月に、おなじように〈守護してくれる動物の霊〉と〈秘密の歌〉とを獲得することができるか?〈パワー〉を充電することができるか?
ぼくたちが作りださねばならないものは、ローラーをかけられた荒野ではなく、むしろ反対に、真に荒野の名に値する深さをもった荒野でないか?」
「初出=『80年代』四号(野草社、一九八〇年七月)」
(『うつくしい道をしずかに歩く』〜「比較社会学ノート四 生きている色」より)
「柳田國男は、日本には色をあらわすことばが以外にもすくないことをのべている。
空色や草色などは色のことばであるというよりも、ものの名を示すことばを色に転用したものにすぎないと考えてみると、結局、色そのものをあらわすことばは、
シロ、クロ、アカ、アオ、キ、ミドリ
この六つしかないように思う。」
「コンクリンという人の報告をレヴィ=ストロースが紹介しているのをみると、フィリピンのハヌノー族は、すてきな分類法をもっている。すなわち色をまず、「生きている色」と「死んでいる色」とにわける。
近代人がみると、はじめかれらは、色をまず、「赤」系統と「ミドリ」系統にわけているようにみえる。ところが、切ったばかりの竹のつややかな栗色は、「ミドリ色」だとハヌノー族はいう。それは色相からいうと、むしろ「赤色」に近いものである。ハヌノー族はじつは、近代人のように色相で色を分けるのではなく、生きている植物の色と乾燥した植物の色、というふうにわけているのだ。だから、切ったばかりの竹の生き生きとした赤色は、「ミドリ」の草木の色に近いと、ハヌノー族は感じとるのだ。
色というものは、世界の息づかいのようなものから、抽象されていないのだ。」
「日本語の色のなまえも、もともとは平板な色相環などからくるものではなかった。
アカとはあかるい色のことであり、クロとはくらい色のことである。シロとは、しるし(印、標)などと同根で、クッキリとさえて目立つことであり、反対にあいまいで目立たぬものをアヲと言ったという。」
「初出=『80年代』五号(野草社、一九八〇年九月)」
(『うつくしい道をしずかに歩く』〜「野帖から五 虹の歌」より)
「万葉集には虹の歌がない。
ただひとつあるが、それは「現れる」ということばをひきだすたんなる序詞としてであって、虹そのものを歌ったのではない。
それから、ぼくの知るかぎり、蝶の歌もないように思う。
雲や雨や月や日の歌はたくさんあるのに、虹はなぜ歌われないのか。
それは万葉の歌人たちが、〈美しさ〉をそれじたいとして歌おうなどとはしなかったからだと思う。
虹や蝶などの〈美しさ〉とは、自然のうちに〈生きること〉のすきまのない充実のようなものからいったんひきはなされて、ながめられ「鑑賞」された自然の〈美しさ〉にほかならない。そしてこのような〈美しさ〉のなりたつためには、自然の中から自分自身をひきはがし疎外した主体の成立がなければならない。
平安貴族が、春はあけぼのというふうに、〈美しさ〉としての自然を鑑賞して「文字」を生みだしたのは、この人工の都の生活がかれらの存在を、自然そのものからいったんはひきはがされた主体として成りたたせていたからだ。
万葉のうたびとたちは、春が来たことのよろこびを歌うことはあっても、春の〈美しさ〉をどこかに求めるということはなかった(最後期の家持をたぶん除いて)。
それはかれらは、ル・クレジオのことばをつかえば〈世界から分かたれて〉いなかったからだ。〈美しさ〉などというものをけっして求めることのないものだけのもつ、美しさあがある。」
「初出=『80年代』一一号(野草社、一九八一年九月)」
(『うつくしい道をしずかに歩く』〜今福龍太「解説 二つの井戸、二つの風」より)
「本書が主として収めるのは、近代知の黄昏に屹立する書物『気流の鳴る音』が書かれたあとの時期、空の見えざる気流を切りさいて飛ぶ真木悠介の羽ばたきの音がもっとも透明で研ぎ澄まされた響きを持つことになる、一九八〇年代の批評的エッセイ群である。息の長い考証による理論書のスタイルを捨て、短く鮮烈で直感的・断片的な逸話と警句がやわらかく読者の心に触れてくる、真木悠介独自のスタイルの結晶をここに見ることができるだろう。
これらの文章で、著者は真木悠介という名に自ら込めようとした「悠々としたものによせる心」を読者に共有しようと呼びかける。」
「本書の記述を敷衍すれば、「わたし」とは幸福の水脈を求めて世界を掘りつづける井戸である。そして「われわれ」とは、それぞれの場所でこのおなじ探求をおこなう無数の井戸である。それらの無数の井戸が、それぞれの探求の情熱と汗に見合う深さと美しさを備えつつ、人類にとっての「普遍的な地下水」に到達するとき、そのときの漣の呼応、その井戸と井戸のおもいがけない邂逅こそ、何ものにも代えがたい希望のコミューンのあかしである。
この思いがけない呼応、この不意の邂逅は、自ら求めた恣意的な出会いというよりは、偶発的な「出会われる出会い」である。真木の使うこの不思議な受動態。「出会われる」とは、あるがままに存在することによって、いわば来訪的に生じる出会いである。この示唆的な受動態は、真木悠介独特の語彙として無数のヴァージョンをもつ。「表現」とは「あらわす」ことではなく、「あらわれる」ことである。この顕現の美しさに拠りさえすれば、表現は生を裏切らなくなる。自分から「創る」のではなく、なにものかによって自分は「創られる」のである。この自己内創造の他律性を信じさえすれば、自我という軛から人間はやわらかく解放される。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
