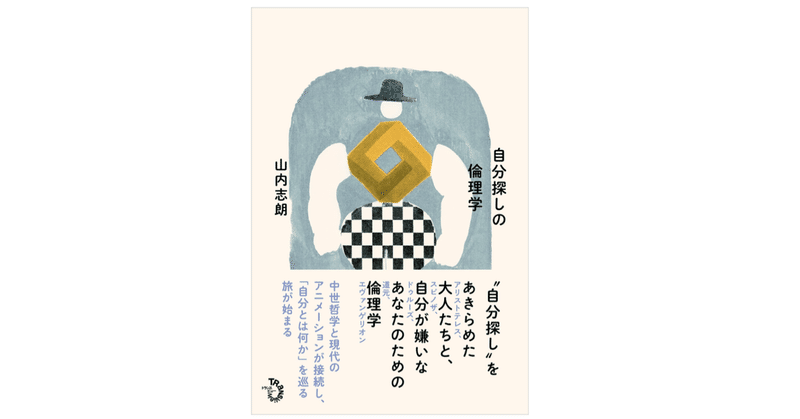
山内志朗 『自分探しの倫理学』
☆mediopos-2441 2021.7.23
「自分探し」をして
「自分はXだ」という「自分」を
見つけることはできない
そこでわかることはせいぜい
「自分探し」をしているということそのものが
いまの自分にほかならないということに
気づくことができるくらいだろう
気づければいいけれど
悪くすればそれに気づくことさえできずに
でっちあげられた「X」に
じぶんを投影してしまうのがオチだ
「人生とは巡礼に似ている」
巡礼は聖地をめざす行為だが
聖地そのものが目的ではない
巡礼することそのものが巡礼なのだ
悟りとは往還だともいわれる
聖なる至高の境地に至るのが目的ではない
日常を生きる場所に戻らなければならない
その往くことと還ることが
メビウスの環のごとくにつながりながら
螺旋を描いてゆくような巡礼である
〈私〉には〈私〉が分からない
だからこそ〈私〉は
〈私〉と〈私〉でない〈私〉を往還し
生と死まやそれに替わる変容を
往還して終わることがない
「自分とはハビトゥスの上で咲く〈花〉なのである。」
ハビトゥスとは山内志朗の言葉を借りれば
「反復してなされることによって、
精神に根付き、それをあまり意識しなくても
実行できるようになった能力」のことである
それは身体化されるほどに
精神の深みから働くようになってはじめて
〈私〉という〈花〉を咲かせることができる
〈私〉は意識・無意識を含め
あらゆる行為そのものである
その行為そのものである〈私〉を
「Xである」とすることはできない
「X」としたとたんに
〈私〉は取り逃がされてしまうことになる
せいぜいが「X」は〈私〉の過去の行為を
言語化したものにすぎない
「道徳」なるものが取り逃がすのも
その〈花〉である
教えられる「道徳」に花は咲かない
ゆえにそこに〈私〉は存在できない
可能なのは
ハビトゥスである〈私〉を
生き続けるということだけなのだ
■山内志朗
『自分探しの倫理学』
(トランスビュー 2021/7)
「自分探しとは、自分ということが概念として与えられて、「なるほどこれが自分なのだ」と思えるような形式で与えられるようなものではない。「自分とは何か」「私とは何か」という問いに対して、「私とはXである」とか「自分はXである」と答えられるようなものとしてあるのではない。就活の面接で「あなたはどのような人ですか」と尋ねる場合も、その人の本質を、その人が何であるかを確認したくて尋ねているわけではない。その人が自分自身をどのように把握しているのかを尋ねているのだ。
サン=テクジュペリの『戦う操縦士』の中に、「自分とは何か? それは敵の死だ。自分とは何か? それは息子の救出だ」という言葉があった。人はその場その場で夢中になっていることに全力を尽くし、その行為そのものと化している。そういう時間をアリストテレスはエネルゲイアと表現していた。目的がその行為そのもののうちに実現している状態である。行為や出来事と自分が一体化しているのである。だから「自分」と「息子の救出」が重なり合うのである。
自分が一体化している出来事・行為とは、それを言葉で表現するのであれば、それはその出来事が終わってから、回顧的に表現されるのであって、過ぎ去ってから言語の中に収まり、「分かる」ものとなる。出来事に夢中になっているとき、何も分かりはしない。」
「人生とは巡礼(peregrinatio)に似ている。巡礼者の風景は中世の光景にも満ち満ちていた。巡礼は単なる物見遊山ではなかった。悔悛の後に求められる償いの一環として巡礼行が必要だったのである。救済されるために必要な行為であり、それは「魂の身代金」であったのだ。罪が許されるために必要な行いであった。
目的とされる聖地は、治癒の奇蹟をもたらすものを考えられていた。また巡礼者や貧民のためには、質素だが無量の宿泊施設である施療院や貧民宿があった。だから、巡礼を構成したのは、改悛者が多くを占めるとはいえ、様々な病人を含んでいた。巡礼の道の路傍には、名もない多くの雑草が花を咲かせている。その一つの花に心惹かれ、そこにその花と共に根を生やすこともあろう。いや、私達一人一人、世界という大きな道から見れば、路傍に咲く雑草の一輪なのだろう。
聖地に辿り着いて目的が実現し、行為が終わるということはない。単なる旅であれば目的地に辿り着いて行為は終了する。巡礼とは聖地に辿り着いて終わるものではない。はじまりの地点、日常生活に戻らなければならない。往還が基本形式であり、しかも往還は一度で終了するものではなく、反復されるべきものとしてある。永遠の往還こそ巡礼の基本形式なのである。それは永劫回帰、無意味な行為の反復として嘆かれるべきものではない。
巡礼の終わりはいつも巡礼のはじまりなのである。自分探しは巡礼に似ている。自分に辿り着いて終わるのではなく、単なる出発点なのである。自分探しは生きている間続くというよりも、死んでも続くのである。終わりと始まりを両方持つものこそ、無限なるものの特徴である。花が終わりと始まりとの両方を備えたものであるならば、それは小さくとも、終わりなき一つの世界なのだ。
自分とはハビトゥスの上で咲く〈花〉なのである。」
「〈私〉には〈私〉が分かりはしない、これが私が哲学においてこだわり続けている論点だ。精神分析が自己意識の根底に無意識を見出したとき、なぜ哲学は、デカルトの「我、思うゆえに我あり」というドグマや、カントの超越論的に統覚やフッサールの間主観的意識といった基本概念を弾劾しなかったのだろうか。自己意識や主体といった概念はちっぽけで、大手を振って歩けるような存在者ではないのではないか、そんな風に思っていた。この〈私〉というのは、たった数十年間この世界の中で、一人前の顔をして、おぼろげな生を送るだけではないのか。お前は有名になりたいのか、裕福になりたいのか。人々の役に立つという、憧れるべきでありながら、圧倒的多数が挫折をせざるを得ない犠牲の道に入り込みたいのか。青年よ、大志を抱けという、倫理的催眠術にかかりたいのか。しかし、概念による〈私〉への登山道を夢みるな、ということが人生道の教えだったとしたらどうなるのか。
自己意識は自分自身への御前立となって、自己を見るための障害になっていないのか。反省モデルは、反省の作用や自己意識が自分の代理(vicarius mei)となって、自己(ego ipse)を隠すことに無頓着である。反省は思考作用の透明性を前提としているが、対象を見ることが、「見る」ということを困難にしていることを考えても分かるように、対象に向かう直行的作用と、作用に向かう作用としての反省的作用は両立しがたい。認識と、認識への認識であるメタ認識は共存できるわけではない。
〈私〉の分からなさということを、反省の非透明性として私は考える。自分のことは自分が一番よく分かっていると思いがちだ。しかし、自分では自分を見えないことがごく普通だ。将来何になりたいか。それはお前の自由だと言われて、自分が何になりたいか即座に答えられる者は、そのままでよい。哲学かた遠い者だろう。分からないと思う者と、分かっているとしても、分かっていないのかもしれないと疑う者が、哲学に近い者たちだ。」
「死は、新たな自分自身に生成変化するために必要なものだった。本当の愛とは、激しい感動をともなうものというよりは、たえず新しい自分を創り出すことを可能にしてくれる、複雑に絡み合った絆としての愛なのだ。生と死とは、親の敵のように憎しみ合う関係にあるのではなく、アッシジのフランチェスコが述べたように、姉妹のようなものとしてあると思う。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
