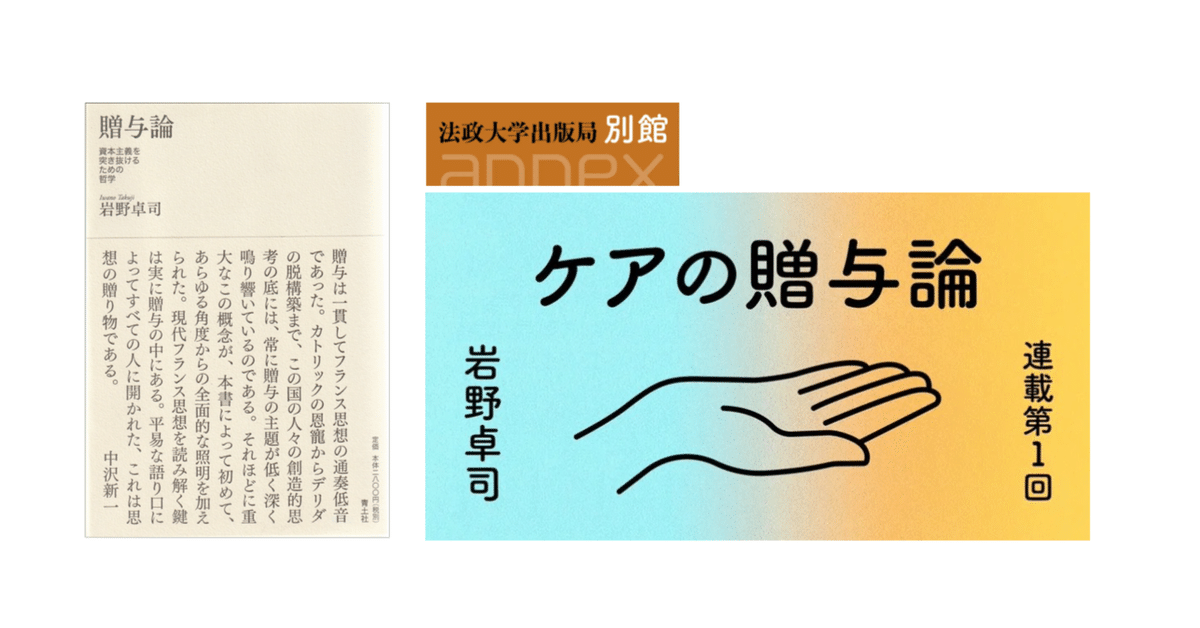
岩野卓司『ケアの贈与論』(法政大学出版局◉別館)/『贈与論/資本主義を突き抜けるための哲学』
☆mediopos3479 2024.5.27
岩野卓司『贈与論』については
主に「補章『借りの哲学』保管計画」を中心に
mediopos-1776(2019.9.26)でとりあげているが
今回は「ケア」の倫理を「贈与」の思想と結びつけ
「来るべき共同体」の可能性についての考察である
『ケアの贈与論』(「法政大学出版局◉別館(note)」)から
現代においては「共同性」を考えるにあたり
その構成員の「多様性」を尊重する必要があるとされるが
そのひとつに「ケア」の問題がある
そして「ケア」の問題を探求する際には
健常者どうしの関係ではなく
障がい者との関係に向き合わざるをえない
そこに「根源的な共同性」があるからである
それが成立するには少なくとも三つの条件が必要だと
岩野卓司は示唆している
ひとつは「他者との非対称な関係」
「他者は決して自己に還元できない。
他者の他者性は尊重されなければならない」
このことは「ケア」においても重要となる
さらには「ケアの倫理」
「自己と他者が同等の価値をもつ存在として扱われ、
力の違いにかかわらず物事が公正になるという理想像」と
「すべての人が他人から応えてもらえ、受け入れられ、
どの人も取り残されたり傷つけられたりしないという理想像」
である
そして「共同体(性)をもたない者たちの共同体(性)」
「介護される者も最初は介護する者と
多くの話題などを共有しているだろう」が
「介護される者が死にゆく者になるにつれて、
ひとつひとつ共有のものを失っていく」
そんな「あらゆるものを剥ぎ取ったときにあらわれる、
他者との関係」に
ケアの本質を垣間見ることができる
以上のことをふまえ
ケアにおける「根源的な共同性」と「贈与」は
どのように関係しているのかについて考えるにあたり
人類学者であり社会主義の活動家でもあった
マルセル・モースの『贈与論』がとりあげられる
モースは資本主義社会の行き過ぎを警戒し
社会保険を贈与交換の理論で根拠づけようとし
さらには「贈与が与える者と受け取る者のあいだに
精神的なつながりをもたらす」必要があると考えた
「他者との非対称な関係、誰も取り残さないという理想、
何も共有しない共同性、どれも等価交換に
還元できない面をもっている」というのである
しかしモースの『贈与論』では
「贈与には必ずお返しの義務がともなわれていた」が
贈与について深く考えていくと
「贈与はその本性をよく考えてみれば
必ずしも贈与交換にとどまってはいない。
特にケアの場合は、もっと根本的な贈与にまで至る」
ケアは単に貸し借りのような
互酬的なものとしてはとらえられないのである
mediopos-1776でとりあげたことをふりかえってみると
「借りの哲学」においては
互酬的な道徳から出ることはできなくなるが
「根源的な共同性」においては
存在そのものが存在を与える「存在の自己贈与」や
「あらゆる受動性に先立つ受動性」としての
根源的な応答に対する主体という視点が必要となる
そもそも私が私であるという自己同一性は
根源において贈与の産物にほかならず
私は「呼びかけ」という贈与によって
他力的に自己を成立させているのである
そこに「根源的な共同性」を
見出すことができるのではないか
■岩野卓司『ケアの贈与論』
連載第1回 イントロダクション(前篇)ケアと共同性
連載第2回 イントロダクション(後篇)ケアにおける贈与と共同性
(2024年4月26日・27日 法政大学出版局◉別館(note))
■岩野卓司『贈与論/資本主義を突き抜けるための哲学』(青土社 2019.9)
**(『ケアの贈与論』連載第1回
「イントロダクション(前篇)ケアと共同性」より)
*「今の時代、共同性を考えるにあたって、多様性を尊重することが必要とされている。そのひとつの試金石として、ケアがある。
全共闘の活動家で、水俣病を告発する闘いにも参加した最首悟は、長い間ダウン症の娘を世話してきたが、次のように述べている。
無神経に「共に生きる」といわれると、重い知恵遅れの子と暮らしている身としてはムシャクシャしてしまうのであるが、しかし同時にその子の存在が、人間の根源的な共同性を想起させることも事実である。そして、社会主義思想も共産主義思想も、その根源的な共同性に思いをいたして、というより、共同性が危うくなる一方の状況の打破をめざして生まれてきたことも、忘れるわけにはいかない 。(最首悟『星子が居る──言葉なく語りかける重複障害の娘との20年』世織書房、1998年、6頁)
これまで僕たちは人間関係のモデルとして健常者どうしの関係を当たり前のように考えてきたが、ケアのテーマを探求する際には、障がい者との関係に向き合わざるをえないのだ。このことが人間の共同性を考えるにあたって、重要なのではないだろうか。ケアの対象となる障がい者・子供・高齢者を考慮にいれることで、「根源的な共同性」に着目することができるだろう。」
*「それでは、この「根源的な共同性」をどう考えたらいいのだろうか。この共同性には少なくとも三つの条件が必要だ、と僕は考える。」
「ひとつは、他者との非対称な関係である。フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナスは『全体性と無限』のなかで、他者との関係は非対称であると主張した。他者は〈私〉と同じものではないのだ。レヴィナスは、他者を自我と同じ型のものであるという見方を批判する。西欧の哲学の伝統は他者を自己と同じものや分身と見なしてきたのだが、これは他者を自己と同一視することで暴力的に支配することにほかならない。しかし、レヴィナスによれば、他者は決して自己に還元できない。他者の他者性は尊重されなければならないのだ 。
この考え方は、ケアにおいても重要ではないだろうか。健常者は障がい者とは非対称な関係にあるのだ。それを同型で考えてしまうと、多くの問題が生じる。健常者は障がい者よりも圧倒的に強いからである。そうであるがゆえに、善意の上で同じように扱っても、そこに意図せざる暴力が生じることになる。
社会における共同体や共同性を構想するとき、多くの場合に健常者どうしの関係を前提にしてしまっている。その結果、最首の語るような「根源的な共同性」を見落としてしまう危険があるのだ。この場合、健常者はレヴィナスが糾弾する西欧の哲学者たちが犯した過ちと同じ前提を共有してしまっているのではないだろうか。」
「この「根源的な共同性」を考えていくために、もうひとつ考慮に入れたいのが、キャロル・ギリガンの「ケアの倫理」である。彼女は『もうひとつの声で』のなかで、二つの理想について述べている。ひとつは、「自己と他者が同等の価値をもつ存在として扱われ、力の違いにかかわらず物事が公正になるという理想像」であり、もう一つは、「すべての人が他人から応えてもらえ、受け入れられ、どの人も取り残されたり傷つけられたりしないという理想像」である。前者は正義の理想である。そこでは、他者は力関係から奴隷にされたり権利を奪われたりするのではなく、身分や力の違いがあっても同等に取り扱われる。これは現代の民主主義の政治などで必須の理想である。それに対して、後者はケアの倫理の理想である。自己と他者が同等であるという論理からこぼれ落ちてしまうものを救う考え方である。能力に差があっても同等に取り扱われれば、そこに困難が生じる可能性がある。各人に応じて対応することで誰も取り残されることはないのだ。ギリガンによれば、正義の考えは男性中心の論理に基づいており、ケアの倫理は女性に特有のものである。
これまでは倫理においても男性中心の正義の思想が支配的であり、女性がケアの倫理によって声をあげるのは難しかった。ケアの倫理は抑圧されるか無視されてきたのだ。しかし障がい者と向き合い、そこに新たに共同性を見ていくためには、ケアの倫理が要求される。ただ、この倫理は女性特有のものとみなすべきではない、と僕は思う。どんな人間も男性性と女性性を持ち合わせているからである。男性も自分のなかのケアの声を抑圧してきたのである。誰もが自分のなかにある複数の声に耳を傾けるべきなのではないだろうか。このケアの倫理を考えることで、「根源的な共同性」が見えてくるのだ。」
「最後のひとつは、フランスの思想家ジョルジュ・バタイユの文句「共同体(性)をもたない者たちの共同体(性)」である。これは友人の思想家モーリス・ブランショがバタイユの草稿から見つけて自著『明かしえぬ共同体』(『明かしえぬ共同体』西谷修訳、ちくま学芸文庫、1997年)のエピグラフに置いた文である。バタイユもブランショも政治、宗教、文学の次元での共同体の根本について考えていたのだが、他者との関係のいちばん深いところには、何も共有しない者どうしの共同性が存在しているということなのだ。これはケアにおける他者との関係にもあてはまる、と僕は思う。そこには共同性の極限が垣間見られるからである。ふだん僕らはあまり意識しないが、同じ言語を話し、なに不自由なく会話を楽しみコミュニケーションをとっている。さらには、同じ話題、同じ思い出、同じ好みなどを共有している。介護される者も最初は介護する者と多くの話題などを共有しているだろう。しかし、介護される者が死にゆく者になるにつれて、ひとつひとつ共有のものを失っていく。言葉も通じなくなると、話題・思い出・好みについて通常のコミュニケーションがとれなくなる。その最たる例は、寝たきりで意識もない重度の障がい者である。何かを共有することでのコミュニケーションはとれないのだ。しかし、そういう者たちが何かに反応し答えたとき、そこにはある種の共同性を認めるべきではないだろうか。そこには、あらゆるものを剥ぎ取ったときにあらわれる、他者との関係が存在する。何も共有しないところであらわれる共同性に、ケアの本質が垣間見えるのではないだろうか。」
**(『ケアの贈与論』連載第2回
「イントロダクション(後篇)ケアにおける贈与と共同性」より)
*「他者との非対称な関係、誰も取り残さないという理想と複数の性の声の解放、何も共有しない共同性。これらはケアにおける「根源的な共同性」の条件だ、というのが前回の結論だった。」
それでは、このケアにおける「根源的な共同性」と贈与はどう関係しているのだろうか。これを問うていくのが、この連載の主題である。今回のイントロダクションではその方向性だけを示しておこう。」
*「前回、最首悟が「社会主義思想も共産主義思想も、その根源的な共同性に思いをいたして、というより、共同性が危うくなる一方の状況の打破をめざして生まれてきた」と書いていたことを思い出してみよう。
社会主義や共産主義の思想が誕生したのは、「根源的な共同性」が脅かされていたからである。最首は「根源的な共同性」が抑圧されてしまう原因が資本主義にあることを看破していたのである。例えば、利潤の追求、競争、弱肉強食を基調とする市場原理が支配的になると、「どの人も取り残されたり傷つけられたりしない」というギリガンの理想は、ほとんど不可能になってしまう。誰かの支えが必要な障がい者や高齢者は「役に立たない」というレッテルを貼られて、社会から切り捨てられてしまう危険があるのだ。」
*「資本主義のこういった行き過ぎを防ぐために、19世紀のヨーロッパ以来、社会保障の制度が整えられてきた。『贈与論』の著者マルセル・モースは学究的な人類学者であるとともに社会主義の活動家でもあった。彼はオセアニアや北米の先住民たちの風習、古代ローマやゲルマンの法などを研究し、そこから贈与にはお返しの義務があるという法則を導き出したが、『贈与論』(『贈与論』森山工訳、岩波文庫)の結論部分では、彼が生きていた20世紀前半の社会を論じ、そこで先住民や古代人たちの贈与の知恵によって利益追求の社会のあり方を変えようと試みたのだ。彼によれば、それまで地方の村などで多く見られた贈与の習慣もしだいに失われていき、人間は「エコノミック・アニマル」になりつつあった。彼は資本主義社会の行き過ぎを警戒していたのである。
そこでモースは、社会保険を贈与交換の理論で根拠づけようとした。労働者は自分の労働の対価として給料をもらっているとふつうは考えられがちだが、そうではない。労働者は自分の労働力だけではなく、自分の生命も雇用者に贈与し委ねているので、雇用者はお返しとして給料のみならず、何かあったときのための保障もしなければならない。疾病や失業の保険、年金などである。そのため、雇用者は他の雇用者や国と連携して社会保険というお返しの義務を果たさなければならないのだ。贈与交換の理論は、現代で新しいかたちで生かされているのである。ここにケアと贈与が結びつくひとつの理由がある。」
*「ケアと贈与が結びつくもうひとつの理由は、贈与が与える者と受け取る者のあいだに精神的なつながりをもたらすということにある。資本主義が前提にしているのは市場における交換であり、ふつうは数値化されたものの等価交換である。そこでは、他者との関係も数値化され、等価であるかどうかが問題になる。心のきずなも利潤につながるかどうか算定されて、その役に立つならば考慮に入れられるが、そうでなければ無視される。(・・・)こういった交換体制の下で、「根源的な共同性」を見つけることはできるだろうか。たしかに、ケアにおいても介護ビジネスは存在しているし、今の僕らの生活が市場原理抜きになる事態を想像するのはむつかしい。しかし、ケアは教育や医療などと同じように、市場での交換に馴染まない面をもっているのではないだろうか。他者との非対称な関係、誰も取り残さないという理想、何も共有しない共同性、どれも等価交換に還元できない面をもっている。」
贈与には、プレゼントなどからもわかるように、人と人をつなげる有縁的な性格がある。(・・・)贈与は物の授受を通して心のきずなをつくることなのだ。
だから、障がい者、子供、高齢者をケアする際に、贈与による交流は必要不可欠なものではないだろうか。この場合の贈与は、物質的なプレゼントには限定されない。献身やサービスまでふくめて広い意味での贈与なのだ。贈与が「人に物を与えること」や「人に自己を与える(委ねる)こと」を通して、サービス、自己犠牲、相互扶助などと結びつくからである。贈与は利潤を求めるための交換とは異なる人間の行為なのだ。」
*「さらに、もっと深い次元ででも贈与について考えていく必要がある。モースの『贈与論』では、贈与には必ずお返しの義務がともなわれていた。何か贈り物をもらったとき、そのままもらいっぱなしで何もしないでいたら、贈り主との関係は切れてしまう。最低でもお礼の言葉ぐらいは必要だ。関係を強めたいのであるならば、こちらからもお返しの贈り物をする。モースが取り上げた「友情」のエピグラフが示すように、片方が贈与しているだけでは社会的な関係は成立しない。社会的な慣習の多くは、贈与に対してお返しを要求する。しかし、贈与はその本性をよく考えてみれば必ずしも贈与交換にとどまってはいない。特にケアの場合は、もっと根本的な贈与にまで至る。例えば、ほとんど無反応になっている障がい者や高齢者に接する場合である。彼らとは話す内容での共有物が見つけられない場合がある。それでも彼らが、こちらの呼びかけに何か身体的に反応してくれたとしよう。そのとき、これはこちらの言葉の贈与に対して相手が応答してくれたことだ、と言えるのではないだろうか。通常のコミュニケーションのできない者との交流、共有するものをもたない者との共同性は、ある種の贈与によって開かれるのではないだろうか。そして、「根源的な共同性」は、ケアにおけるこの贈与と深くかかわっているのではないだろうか。」
**(岩野卓司『贈与論』より)
*「「もの」を交換し社会を営んできた人間。狩猟採集から農耕への移り変わりとともに「貨幣」を生み出し、資本主義というシステムを作り上げた。等価交換から生まれたシステムは、いまや行き詰まりをみせ、新たな段階を模索している。例えば、ボランティア、臓器移植、ベーシック・インカム、自然エネルギー・・・・・・。行為や思想の根底に、交換ではなく見返りを求めない「ただ与える」という贈与の精神が存在していると思われる。贈与の思想は、人間社会に多くの慣習や交易を生み出してきた。一方、アイヌの熊祭りのような神話的思考、チンパンジーの毛づくろいにみられる動物世界の習慣は、人間と動物のあいだ、動物と動物のあいだにも贈与の思想が存在していることを教えてくれる。人間はけっして経済的動物ではない。
人間、動物、自然をふくめた世界を互酬的ではない贈与の視点から捉え直すとき、交換や資本の論理にからめとられた世界から解放されるだろう。「ただ与える」の思想が、これまでにない関係性の未来を提示してくれる。」
*「ハイデッガーは『存在と時間』で、現存在という人間存在の探求から出発して存在の意味を解明していこうとしたが、その後しだいに考え方が変わってきて、存在は人間によってとらえきれないものと考えるようになる。そして、この存在を存在そのものとして考えていき、西欧の思想の歴史を存在の自己展開としてとらえるようになる。このように彼の哲学は、現存在による「自力」の探求から存在による「他力」の探求へと転換していくのである。ハイデッガーの哲学が神秘主義的な色彩を帯びてくると言われるゆでんである。戦後すぐ彼は『ヒューマニズム書簡』という作品を発表しているが、そこでは Es gibt das Sein.という重要なフレーズについて述べている。このドイツ語の文をそのまま訳せば、「存在はある」というふうに訳せる。ドイツ語のEs gibtは、英語のThere isやフランス語のIl y aに相当する表現で、「〜がある」の意味である。どうしてこういう言い回しをするかと言えば、存在と存在者とを区別するためである。存在は存在者ではない。(略)このEs gibtにはgebenという「与える」の意味の動詞が使われている。この語句を文字通りに訳せば、「それは与える」となるが、ドイツ語の慣用では「〜がある」の意味になる。ハイデッガーはこの慣用を尊重しつつも、「それが与える」という文字通りの意味をフレーズに含ませる。そして、Es(それ)もまた「存在」と解釈し、Es gibt das Seinを「それ(存在)が存在を与える」と考える。つまり、存在の自己贈与というわけである。」
*「「存在の贈与」はこういった経験を成り立たせるような贈与、存在を存在せしめるような贈与にほかならない。言い換えると、社会学を含めて経験諸科学が論じるいかなる贈与も、ハイデッガーの視点に立つならば、この根源的な贈与なしには生じえないと言えるだろう。」
*「サルトゥー=ラジュは、レヴィナスの他者の倫理を評価しつつも、彼が主張する「他者に対する責任」と自分の考える「生まれながらの借り」の違いを明確に示している。
彼女によれば、レヴィナスの場合、人は生まれながらにして他者に責任を負っており、生きることはその責任を果たすことなのである。だから、この責任を果たすために、人は他者に対して自己を贈与するのだ。責任は、他者に対して一方的に負っているものであり、責任を果たすことは見返りを期待しない純粋な贈与なのである。
これに対して「生まれながらの借り」の場合は、一方的ではない。子は親に育ててもらった恩を、老後の面倒というかたちで返せば、相互的である。また、この借りを、誰か違った人に何かを贈与することで「返す」場合もある。あるいは、この贈与がめぐりめぐって自分に「返って」くることもある。この対比を通して。サルトゥー=ラジュはレヴィナスの「贈与」よりも自分の「借り」の重要性を強調していく。」
*「人は他者に応答することで何かを肯定的に返しており、そのことは責任に繋がる(略)。この応答は「私」が望もうと望むまいと、意識しようとしまいと、すでに生起している。だから、この根源的な応答に対する主体の関係をレヴィナスは「あらゆる受動性に先立つ受動性」と言っている。そして、この無条件の応答を通してのみ、他者への責任をもった主体が確立されるのだ。」
*「サルトゥー=ラジュの借りの論理が乱暴に見えてくるのは、レヴィナスが丹念に語っている根源的な応答を無視して、自分を他者に捧げる自己贈与のみを強調しているからである。」
*「レヴィナスの応答の考えを継承しながら、この考えを贈与の論理によって練り上げていったのが、ジャン=リュック・マリオンである。(略)彼によれば、自己は知を構成したり行動したりする能動的な存在である以前に、呼びかけ----他者の呼びかけでも神の呼びかけでもいい----を受け取る存在なのだ。(略)マリオンは自己をまず、受け取ることに身を捧げる存在と定義し、さらに踏み込んで、「与えられるものから自己を受け取る」とまで言う。つまり、呼びかけの贈与を受け取ることで、自己の同一性が確立するのである。根源的な贈与なくしては、自己は成立しない。自己同一性は贈与の産物とも言えるだろう。」
*「所有と利潤の追求を目的とする資本主義は、バタイユの主張するような「消費のための消費」を無視してきた。彼が挙げた「賭け」や「供犠」や「贈与」の例を考えてみると、これらも現代社会では資本主義に抵抗するものというよりは、きれいにそこに収まっているという印象のほうが強い。(略)
しかし、もう一度バタイユ的な視点から「賭け」や「供犠」や「贈与」を見つめ直したらどうだろうか。(略)人間の無意識との関係から考えていけば、賭博の欲望には自己の破壊へと誘う危険が願望が見て取れるし、供犠の根本には残酷な暴力性が潜んでいるのがわかる。」
*「相手が返せないくらいの法外な富を消費して、ポトラッチに勝つのが各首長の理想だろう。あるいは損失が莫大すぎて、名誉は得るものの自己破壊のケースもあるだろう。もちろん、理想と現実は違う。現実には贈与交換は行われ続ける。ただここでバタイユが見抜いているのは、ポトラッチのシステムにはそれを破壊する危険が必ず伴われているということである。この贈与交換のシステムには、システム自身を不可能にする可能性が常にインプットされているのだ。そして、システムの破壊が何らかのときに、生じるかもしれない。贈与交換とは不可能と背中合わせのものと言えるだろう。」
○岩野卓司(いわの・たくじ)プロフィール
明治大学教養デザイン研究科・法学部教授。著書:『贈与論』(青土社)、『贈与をめぐる冒険』(ヘウレーカ)、『贈与の哲学』(明治大学出版会)、『ジョルジュ・バタイユ』(水声社)、共訳書:バタイユ『バタイユ書簡集 1917–1962年』(水声社)など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
