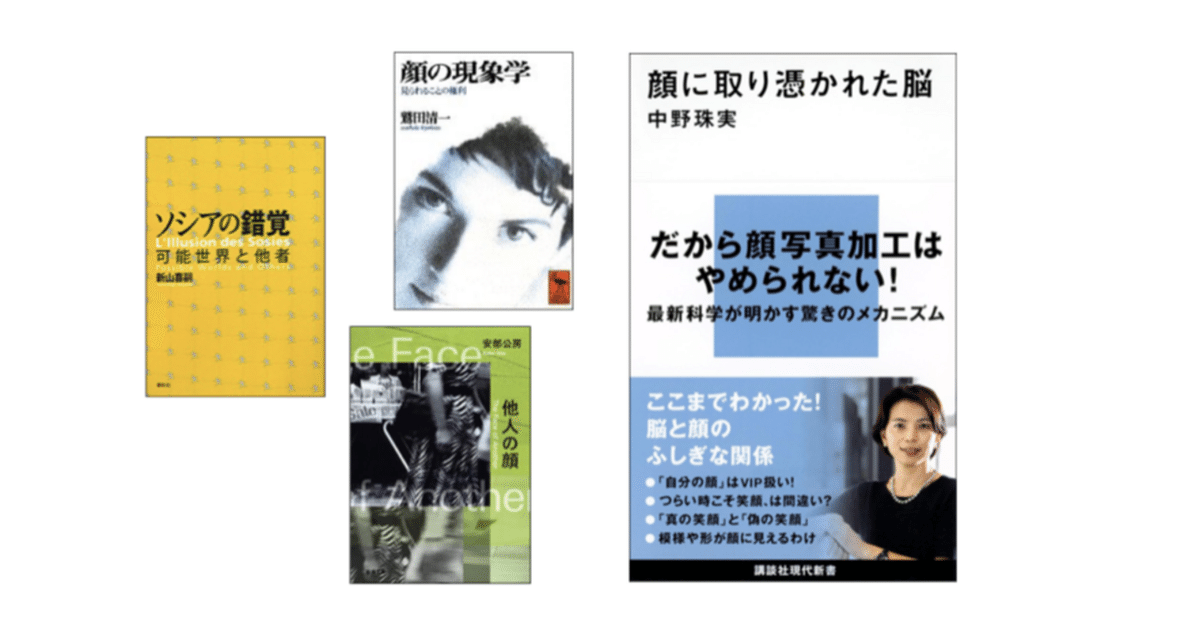
中野珠実『顔に取り憑かれた脳』/鷲田清一『顔の現象学』/安部公房『他人の顔』/新山喜嗣『ソシアの錯覚』
☆mediopos3565(2024.8.23)
「顔」には
わたしがわたしであることを
そしてその人がその人であることを
識別するときのもっとも重要な役割がある
もし鏡にうつるじぶんの顔が
それまでじぶんの顔だと思っていたものと
まったく異なっていたとしたら
わたしはじぶんがじぶんであるという自己認識が
ゆらいでしまうことにもなるだろう
じぶんの知っている人の顔も同様で
その人だと思っている人の顔が
著しく異なってしまっているか
あるいはまったく別人のようになっていたとしたら
その人に対するイメージも変わってこざるをえない
昨今では「顔認証」というテクノロジーも進み
「顔」のかたちがその人がその人であることを
社会的に保証する重要なものともなってきているが
そのようなデジタル時代を迎えているいま
ネット上は加工された顔や
ヴァーチャルにしか存在しない顔なども多く
またメイク技術の進歩もあって
メイクによってまったく別人のような顔がつくられたり
マスク技術によって仮面を被るだけで
まったく別人に変身することも難しくはなくなっている
そんな現状だからこそ
「顔」とは何なのか
「顔」が「その人」であるということは
どんな意味をもっているのか
また「その人」が「その人」であるためには
「顔」だけが重要なのかどうか
そうしたことを考えておく必要があると思われる
中野珠実『顔に取り憑かれた脳』(講談社現代新書)では
「脳科学や心理学、それに人工知能などの情報科学に焦点を当てながら
「顔」と「脳」の密接で精巧な関係を紹介し、
その関係性が「わたし」という自己意識の形成にまで影響を与えること」
について考察がくわえられている
「脳の底面には、顔を見分ける巨大な神経ネットワークがそなわり、
脳の横には相手の心を読み取るために必要な
「動き」に関するネットワーク」があって
「人はこうした脳の活動で他者の顔からさまざまな情報を読み取っている」
子どもの発達においては「鏡像段階」があり
「鏡像が実像ではなく虚像であることを理解し、
鏡や写真にうつる親の姿を認識するようになり」
その「半年後には、鏡に映る自己の姿が
自分であることに気がつくようにな」り
「運動と視覚像の随伴現象に基づき、鏡の象徴化機能を獲得し、
そして、Iとmeを結びつける同一化機能を獲得することで、
社会的な自己意識が形成されるようになる」
しかし「カプグラ症候群」という
顔を認識するネットワークに問題がないにもかかわらず
「外見が瓜二つの別人が自分の家族になりすましている、
という妄想を抱く」という症例がある
これについてはmediopos-164(2015.4.28)で
新山喜嗣『ソシアの錯覚/可能世界と他者』(春秋社)を
紹介したことがあるが
それは「自分のもっとも身近にいる他者が、
ある日突然に顔だちがそっくりのにせものに
入れ替わったと感じる体験をさし」
「顔だちがそっくりであるばかりでなく、
たとえしぐさや性格から始まるあらゆる特徴が
以前と全く変わりがなくとも」
「相手が本物ではない別人であると感じてしま」うというものだ
「顔」についての考察においては
鷲田清一『顔の現象学』が知られているが
そこではある顔を「素顔」としてとらえるとき
私たちは「その背後に、一つの人称的な存在」
「「だれか」(=人格)としての自己同一性と連続性とをもち、
顔の外面性に対しては内面性としてとらえられるべき存在」を
透かし見ているという
また安部公房の小説『他人の顔』は
顔全体に大やけどを負って顔を喪失してしまった男の話だが
「人間という存在のなかで、顔というものが
いかに大きな比重を占めているかを浮き彫りにして」いる
「素顔であれ、仮面であれ、
外面は常に自己の内面と深い関わりを持っており、
しかも、その自己の内面は、外面の影響を受けて容易に変化する、
可塑的で不安定なもの」であって
「いずれの外面も、他者の反応から自己の顔を想像するという点で、
自己と他者の関係性からつくられる想像的共有物」にほかならない
そんななかで「顔」とはなんだろうと考えるとき
私たちが通常依存している視覚やそのほかの感覚が
まったく働かないとき
わたしがわたしであることや
その人がその人であることが
どうやって認識できるのだろうかという問いも生まれる
顔=ペルソナ=人格
そうしたものをかりそめにもつくり
支えているのはいったい何なのだろうか
たとえば死後肉体を失ったとき(死後の生だが)
じぶんをじぶんだと認識し
じぶん以外の存在をそれとして認識するのは
いったい何によってなのだろうか
■中野珠実『顔に取り憑かれた脳』(講談社現代新書 2023/12)
■鷲田清一『顔の現象学 見られることの権利』(講談社学術文庫 1998/11)
■安部公房『他人の顔』(新潮文庫 1968/12)
■新山喜嗣『ソシアの錯覚/可能世界と他者』(春秋社 2011.8)
**(中野珠実『顔に取り憑かれた脳』〜「はじめに」より)
*「現代の私たちの自己意識には、過剰なまでに自分の顔のイメージがつきまといます。鏡の普及に続いて、カメラを手にした人々は、幼少期から老年期までの自分の顔の写真を、分厚い背表紙のアルバムに人生の証として大切に貼り付けました。美しく修整した顔をSNSにアップするようにもなりました。テクノロジーの急速な発展がもたらした「自分の顔」を、私たちは取り憑かれたように追い求め、劣等感に苛まれ、さまざまな行動に駆り立てられます。「自分の顔」に取り憑かれるのは、技術革新が生み出した現代病なのかもしれません。」
*「人間にとって顔というものは、他者を理解するうえでも、そして自己を理解するうえでも、とても重要な意味を持っています。そのため、人間がどのような脳の仕組みで「他者」と「自分」の顔を認識しているのかを知ることは、視覚機能の範疇を超え、感情、社会性、自己意識がいかにして生成されるのかを理解することにつながります。また、鏡の中に自分の姿を発見する過程は、それらの複雑な機能がどのようなプロセスで発達していくのかを知る重要な手がかりを与えてくれます。さらに、ヴァーチャル・リアリティや人工知能などの科学技術が急速に発展している中で、自分の顔の在り方は大きく変わってきています。それらは、私たちの自己意識や他者との関わりにどのような影響を及ぼすのでしょうか。自分の顔を取り巻く問題については、脳科学や心理学、進化や文明の歴史、社会学から工学まで、幅広い観点から理解していく必要があるのです。
このうち、本書では脳科学や心理学、それに人工知能などの情報科学に焦点を当てながら「顔」と「脳」の密接で精巧な関係を紹介し、その関係性が「わたし」という自己意識の形成にまで影響を与えることを見ていこうとも思います。」
**(中野珠実『顔に取り憑かれた脳』〜「第1章 顔を見る脳の仕組み」より)
*「脳の底面には、顔を見分ける巨大な神経ネットワークがそなわり、脳の横には相手の心を読み取るために必要な「動き」に関するネットワークがあります。人はこうした脳の活動で他者の顔からさまざまな情報を読み取っているのです。」
**(中野珠実『顔に取り憑かれた脳』〜「第2章 自分の顔と出会うとき」より)
*「生まれたての赤ちゃんが人の顔を注目して見るのは、上丘ー視床枕を通る皮質下経路のはたらきによるものだろうと推測されている。その情報をもとに顔の情報がたくさん脳に入り、顔を認識するための神経ネットワークが生後数ヶ月の間に急速に発達すると考えられている。」
*「鏡像自己認知の発達の研究からは、鏡の中の像が自分であることを認識できるようになるのは、早くて2歳頃という結論が導き出される。」
*「我々の心を常に悩ます複雑な感情は、「客体である自己」の姿を自己の中に取り込み、それを他者と比較する社会的な自己意識の発達により生まれる。」
*「子どもの発達を振り返ってみると、まず鏡像が実像ではなく虚像であることを理解し、鏡や写真にうつる親の姿を認識するようになります。それから半年後には、鏡に映る自己の姿が自分であることに気がつくようになります。つまり、まず運動と視覚像の随伴現象に基づき、鏡の象徴化機能を獲得し、そして、Iとmeを結びつける同一化機能を獲得することで、社会的な自己意識が形成されるようになるのです。逆に、アルツハイマー型認知症は、象徴化機能が最初に障害されることで、同一化機能にも障害が起き、やがて自己意識が解体していきます。両者は現象としては逆方向に進むのですが、いずれにおいても、象徴化機能の獲得あるいは喪失が起点となっているようです。つまり、鏡像が実存する物体の虚像であることを理解する能力が土台となり、そのうえで、自分の中で捉えている自己の概念と、他者から見えている自分の姿が対応付けられ、その結果、社会的自己意識が培われていくのだと考えられます。」
**(中野珠実『顔に取り憑かれた脳』〜「第3章 自分の顔に夢中になる脳み」より)
*「自分の顔写真を優先的に見つけたり、化粧や自分の顔写真の美加工に夢中になったりするのは、脳のVTA(腹側被蓋野)や側坐核というドーパミン報酬系のはたらきが関わっていると考えられる。」
*「ドーパミンは、報酬に伴う快楽ではなく、期待していた報酬と実際に得られた報酬の間の違い=「報酬の予測誤差」を伝えている物質である。」
*「自己意識には、身体の所有感などの原始的な自己意識や、複雑な感情などの社会的な自己意識、過去から未来まで連なるアイデンティティなどがあり、それぞれに脳のさまざまな場所のはたらきが関わっている。」
*「家族や親友の顔を見て、彼らに想いをはせるとき、私たちは自分に向き合うのと同じような感じで、その内面を捉えようとしているのかもしれません。逆に、恋い焦がれる人の顔は、私たちにとって、何としても手に入れたい外的な対象で、自分の中にすでに内在されたものではないようです。
しかし、そんな家族の顔を見ても、強烈な違和感を訴える症例があります。まったく外見が瓜二つの別人が自分の家族になりすましている、という妄想を抱くのです、これを「カプグラ症候群」と言います。外見上は自分の家族の誰であるかということは認識できるので、顔を認識するネットワークに問題はありません。一方、本来、自分の家族の顔を見ると、自分にとって非常に親しい存在だという感覚が自然と湧き上がるはずですが、その親しみの感情が顔を見ても湧き上がってこないのです。そこで「偽物がなりすまして家族ふりをしているにちがいない」と誤った推測をするのではないかと考えられています。
このカプグラ症候群は、妄想型統合失調症に多く見られますが、他にも、認知症や脳の損傷で起きることがあり、特に、脳の前頭葉に問題が生じたときに起きやすいという可能性が指摘されています。こうした症例は、私たち人間が、顔という外見だけでなく、それに付随して湧き上がるさまざまな感情や想いを含めて、この人は誰なのかを認識しているということを教えてくれているのです。」
**(中野珠実『顔に取り憑かれた脳』〜「第4章 自己と他者をつなぐ顔」より)
*「コミュニケーションには非言語的情報も大きな役割を果たしている。そして、言語情報と非言語情報が食い違うときは、非言語情報の方が強い影響を与える。」
*「ポール・エクマンが行ったフィールド調査により、喜び、悲しみ、怒り、驚き、嫌悪、恐怖という6つの感情を表す表情は、全人類に普遍的であることが示され、現在でもこの考えが広く受け入れられている。」
*「信頼できる顔や、魅力的な顔、瞬きによる間の共有など、顔からはさまざまな情報が発信され、コミュニケーションにおいて重要な役割を担う。まさに「顔」は自分と他者をつなぐハブとなっているのである。」
*「近年の情報技術の目覚ましい進展により、私たちのコミュニケーションの在り方は大きく変化しています。SNSを介して、私たちは前よりもたくさんの他者の情報にさらされ、また自己の情報をさらすようになっています。また、オンラインゲームや仮想空間で他者と交流する時間が急激に増加しています。今後、通信速度はさらに速くなり、より大量の情報をリアルタイムに送れるようになれば、この傾向はより一層進むでしょう。さらに、人工知能の技術の発展に伴い、本物とまったく見分けがつかない偽物の人間の顔をいくらでもつくれるようになりつつあります。そのような時代において、私たち人間にとって、顔はどのような存在になっていくのでしょうか。また、それが自己意識にどのような影響を及ぼすのでしょうか。」
**(中野珠実『顔に取り憑かれた脳』〜「第5章 未来社会における顔」より)
*「アバターの見た目は、そのユーザーの気持ちや行動に影響を与えるという実験結果がある。実験を行った研究者は、この事象を、ギリシャ神話に出てくる変幻自在に姿を変える神、プロテウスにちなんで「プロテウス効果」と名付けた。」
*「「潜在拡散モデル(latent diffusion model)」など、AI技術の進歩によって、本物と皆違う存在しない顔を誰もが簡単につくれてしまう時代に突入した。」
*「外面は常に自己の内面と深い関わりがあり、その内面は、外面の影響を受けて容易に変化する、可塑的で不安対なものである。また、いずれの外面も、他者の反応から自己の顔を想像するという点で、自己と他者の関係性からつくられる想像的共有物である。しかし、それがないと、私たちの自己は不安定になり、他者との関係も上手く機能しなくなる。つまり、「顔」は、私たちが社会で生きていくうえで、必要不可欠な通路なのである。」
*「なぜ、私たちはそこまで素顔にこだわるのでしょうか。
哲学者野鷲田清一は、『顔の現象学』という著作の中で素顔について以下のように考察しています。
——鷲田清一著『顔の現象学』(講談社学術文庫 1998年)、55頁より
われわれがある顔を素顔としてとらえるときには、その背後に、一つの人称的な存在、「だれか」(=人格)としての自己同一性と連続性とをもち、顔の外面性に対しては内面性としてとらえられるべき存在が透かし見られてり、そういうもにとの関係のなかで顔がとらえられているわけである。素顔においてはだから、〈顔〉は〈わたし〉との関係のなかで組織されているのである。
(・・・)素顔というのは、アバターのような仮面とは異なり、その人の内面と同一線上にあるために、相手の内面を深く知るためには、どうしても素顔を通して関わりたくなるのです。また、素顔を知られていない状態においては、自分の内面性を本当には理解してないから、あくまで仮想の関係性だというわけです。
さらに、(・・・)鏡や写真の登場により、他者目線に基づく自分の顔の認識・評価というものが自己意識の中に入り込んできたことにより、素顔は単に内面を透かし見せるものではなく、内面に大きな影響を与えています。そうなると、なおさら〈素顔〉が〈わたし〉を具象化するものとして、重要性を増してくるわけです。
この問題を徹底的に掘り下げたのが、1964年に出版された安部公房の小説『他人の顔』です。この小説の主人公は、化学実験中に液体空気の爆発により顔全体に大やけどを負って顔を喪失してしまいます。包帯で覆われた顔に対する周囲の反応に悩んでいたころ、さらに妻に性交渉を拒否されたことに強いショックを受けるのです。そこで、他人の顔を模った精巧な仮面をつくり、それを被って別人物をよそおって妻を誘惑します。その後、妻と「仮面の男」と「素顔の自分」という三角関係に耐えきれなくなった主人公は、すべてを書き記したノートを妻に見せました。ところが、妻は、仮面の正体が主人公であることを最初からわかっていた、という手紙を残して去ってしまいました。打ちのめされた主人公は、仮面を被り、拳銃を手にして妻を待ち伏せるところで物語は幕が閉じます。
この小説は、人間という存在のなかで、顔というものがいかに大きな比重を占めているかを浮き彫りにしています。」
「自分の存在というのは、他者の反応を通して想像するしか知りえないもので、それを媒介する顔を失うと、自分の存在すら揺らいでしまうということです。つまり、顔の喪失は、社会との関係だけでなく、自己すら消滅させかねないわけです。」
「ある意味、素顔は私たちを一つの自己に縛り付けているとも言えます。仮面を被ること、仮想空間でアバターを使うこと、偽物の顔写真を使うことにより、素顔にとらわれている自己から解放されるのです。」
「しかし、本当に仮面は自己を解放するのでしょうか。鷲田は、『顔の現象学』の中で、ディディ=湯ベルマンの見方を取り上げています。
——鷲田清一著『顔の現象学』(講談社学術文庫 1998年)、117頁より
たしかに仮面はひとの顔を覆い隠しはするが、そのとき仮面は、過去を覆うことによって、その顔が隠しているものをあらわにする。
(・・・)
素顔であれ、仮面であれ、外面は常に自己の内面と深い関わりを持っており、しかも、その自己の内面は、外面の影響を受けて容易に変化する、可塑的で不安定なものなのです。そして、いずれの外面も、他者の反応から自己の顔を想像するという点で、自己と他者の関係性からつくられる想像的共有物なのです。しかし、それないと、私たちの自己は不安定になり、他者との関係も上手く機能しなくなるのです。つまり、本物の顔であれ偽物の顔であれ、「顔」というのは、私たちが社会で生きていくうちで、必要不可欠な通路なのです。」
**(新山喜嗣『ソシアの錯覚/可能世界と他者』より)
*「「ソシアの錯覚」とは、自分のもっとも身近にいる他者が、ある日突然に顔だちがそっくりのにせものに入れ替わったと感じる体験をさします。この入れ替わったという感覚は絶対的であり、顔だちがそっくりであるばかりでなく、たとえしぐさや性格から始まるあらゆる特徴が以前と全く変わりがなくとも、「ソシアの錯覚」ではやはり相手が本物ではない別人であると感じてしまいます。」
*「われわれの周りには同一と非同一の両方に関して宙ぶらりんの個体が、常時いくつもぶら下がっているのである。それは、いかにも奇妙な景色に違いない。われわれは、日々それらの個体の多くに対して「同一」という称号を与え、そして、おそらくもっとも少ない個体に対しては「非同一」の称号を与えながら生活をしている。しかし、これらの称号の授与式にあたっては、授ける方も授かる方も、式の参加者としての正当な資格がないことは言うまでもない。/われわれの眼前にある宙ぶらりんの存在は、ひょっとするとわれわれをソシアの錯覚へといざなうのかもしれない。たしかに、ソシアの錯覚はわれわれ全てに発祥するものではない。しかし、先にも述べたように、患者が発して言葉は、患者が意図した通りのままでわれわれに伝達されてしまう。その時には、ソシアの錯覚の訴えの中に潜む個体、同一性、人物といったものに関わる患者の形而上学的な直観の振動に、われわれの直観もおそらく共振しているのだろう。ソシアの錯覚は、われわれの日常の中に潜む形而上学的な真理を糧として、今日も発症の機械を妖しく窺っているかのようである。あたかも、この宙ぶらりんを恨むかのように。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
