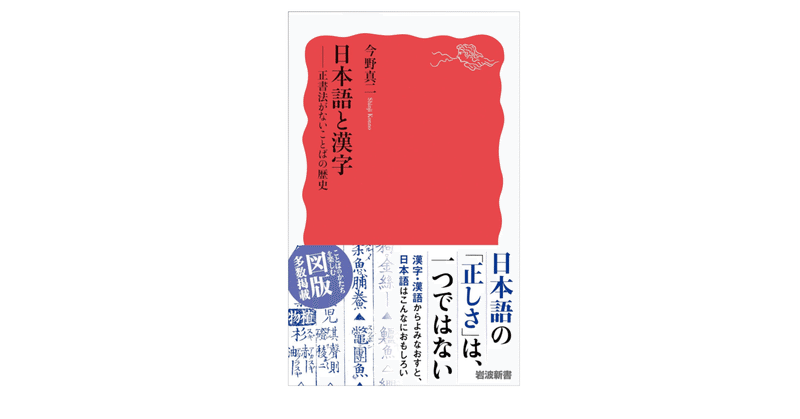
今野真二『日本語と漢字──正書法がないことばの歴史』
☆mediopos3457 2024.5.5
日本語は「正書法(orthography)がないことば」である
「正書法」のあることばとは
正しい書き方=正しい文字化がたった一つだけあることばで
「文字はその音声言語を写した二次的なもの、
というみかたが一般的」な欧米ののことばには
「語をどのように文字化するか、という書記論・表記論」は
基本的に欧米の言語学には存在していない
日本語は「つねに文字化に関しての選択肢がある」
つまり「正書法がないことば」なのである
たとえば「心」にしても「こころ」「ココロ」
あるいは「精神(こゝろ)」というように
文字化するにあたってつねに選択肢がある
漢字も仮名もルビをふることで
そう読ませることもできる
今野真二『日本語と漢字』は
「「正書法がない」という観点から
「日本語の歴史」をみなおしてみよう」というものである
日本語表記における「漢語」は
中国からもたらされた「外来語」ではあるのだが
日本語の語彙体系内に借用されている漢語が多いため
すでに「和語」にかぎりなく近い語
あるいはすでにその一部にさえなっている
日本語を文字化するための文字として
表音文字(音節文字)である
仮名(平仮名・片仮名)が生まれた後も
表意文字である漢字は使い続けられている
「日本語は表意文字と表音文字という、
機能の異なる二つの文字を文字化に使っている」のである
仮名は漢字から生み出されたが
すでに「『古事記』『日本書紀』『万葉集』が成った」時点で
「漢字によって日本語を文字化する」ことができていたようだ
「日本語を文字化する」ということの中心に漢字があり
漢字訓読という「翻訳方法」から
「かきことば」は生まれることになったが
その頃から「漢字は日本語とともにあり、
その頃から漢字とともに日本語の歴史が動き出した」
ということができる
しかし漢文訓読文はあくまでも
中国語寄りの「かきことば」であって
「中国語を離れた日本語の「かきことば」」が獲得されるのは
鎌倉時代に入ってからと考えられているという
とはいえ「はなしことば」と「かきことば」は
かなり隔たっていた
しかし「中国語を離れた日本語の「かきことば」」といっても
日本語そのものの語彙体系のなかでは
多くの漢語が借用されていて
文字化に使っている文字の一つというのではなく
日本語の重要な構成要素とともなっているように
漢語が日本語の形成に切り離しがたく関わっているといえる
「正書法がない」ために
ルビがふられていないと
「ヨム」ことができない(音声化できない)ことも多々あるが
「よむ」(内容を理解する)ことはできたりもするように
(「よめるけどヨメない」)
音声に縛られ文字化の選択肢に乏しいことばにくらべ
ややこしくはあるが
その成立にあたって生まれたややこしさのなかに
そしてそのややこしさから読みれることのなかに
日本語を使う魅力とその可能性もあるようだ
「書記論・表記論」が重要となる「正書法がないことば」
という視点で日本語を見直していくことは
「正書法」に縛られたことばには閉ざされているような
日本語表現の世界をひらくための
重要な契機となり得るかもしれない
■今野真二『日本語と漢字──正書法がないことばの歴史』
(岩波新書 2024/4)
**(「序章 正書法がないことばの歴史」より)
・正書法
*「日本語は仮名が生まれた九世紀末頃以降は漢字と仮名とを使って文字化を行なっている。仮名には平仮名と片仮名とがある。英語「heart」にあたる日本語は「心」「こころ」「ココロ」と少なくとも三つの文字化のしかたがある。「憚(はばか)りなき精神(こゝろ)を溺れしめた」(夏目漱石『三四郎』書版三三五〜三三六頁)のように二字の漢字「精神」によって文字化することもできる。夏目漱石の例は、過去における「事実」であるが、過去の文献にひろくあたれば、他の文字化の例も存在していたことが予想される。
つまり、日本語の文字化に際してはつねに選択肢がある。選択肢があるのだから、文字化のしからが一つではない。だから「正書法」はない、ということになる。「正書法」がないというと、「正書法」のある言語が優れていて、ない言語はだめな言語と思いそうになるが、そういうことではまったくない。「正書法」がある言語は、ラテン文字のような「表音文字」を使っていることが多い。(・・・)
本書のサブタイトルは「正書法がないことばの歴史」である。「正書法がないことば」が日本語で、「正書法がない」という観点から「日本語の歴史」をみなおしてみようというのが本書の目的である。」
・「はなしことば」と「かきことば」
*「その言語を文字化するための文字を獲得した言語には「はなしことば」と「かきことば」とがあるとみることができる。「かきことば」を獲得するためには文字を獲得する必要があるといってもよい。」
「当初は記録にちかい面もあった「かきことば」が使われ続けていくいちに「かきことば」が「ことがら」の記録を離れ、人の「気持ち・感情」をのせ、「表現」を担うようになっていった。そもそもことばを発する、ことばを使うということは「気持ち・感情」を表出したいという人間の歴史を記録したものとみるならば、『万葉集』は民族の「気持ち・感情」をもりこんだ和歌を記録したものといってもよいだろう。「ことがら」と「気持ち・感情」をもりこむ「器」がことば=言語であるとみることができる。
現代は「はなしことば」と「かきことば」との違いが大きくない。したがって、そもそも「はなしことば」と「かきことば」という二つの言語態があることが意識されにくいかもしれない。過去においては、「はなしことば」と「かきことば」はかなり隔たったものであったと思われる。」
・漢語が語彙の半分を占める日本語
*「漢語は中国からもたらされた後であるので、「外来語」といってもよいが、日本語に関して「和語」「漢語」「外来語」という三つの語種を設定する場合の「外来語」は中国以外の外国からもたらされた語である。つまり中国からもたらされた漢語はいわば特別扱いされている。それはなぜかといえば、日本語の語彙体系内に借用されている漢語が多いからということにつきる。」
・非ソシュール的な言語のとらえかた
*「「正書法」がある言語には文字化に際しての選択肢がない。選択肢がないので「表記」について論じる「表記論」もない。つまり、欧米流の言語学は言語を「文字・表記」の面から観察することがほとんどないといってよい。
日本語を文字化するための文字として表音文字(音節文字)である仮名をうみだした後も日本語は表意文字である漢字を使い続けた。日本語は表意文字と表音文字という、機能の異なる二つの文字を文字化に使っている。」
**(「第一章 すべては『万葉集』にあり」より)
・『万葉集』は試行錯誤の場ではない
*「漢字から仮名がうみだされたのは、九世紀末頃と推測されている。それは『万葉集』が成った八世紀から二五〇年ほど後にあたる。(・・・)日本においては短期間に漢字から仮名をうみだした、とみるむきがある。
しかしおそらくそういうことではなく、『古事記』『日本書紀』『万葉集』が成った八世紀の時点では、「漢字によって日本語を文字化する」ということが一つの到達をみていたために、そこから仮名の発生まであまり時間がかからなかったということでないだろうか。仮名のようなものが必要であるという「日本語内部での圧力=内圧」がたかまっていた、といってもよいだろう。漢字によって日本語を文字化することに関しての試行錯誤があったとすれば、それは『万葉集』が成る前の二五〇年間がそうした時期なのであろう。その試行錯誤の跡を窺わせる文献は存在していない。」
「「日本語を文字化する」ということの中心に漢字があった。そして(・・・)漢文訓読が日本語の「かきことば」の発生に深くかかわっていた。そうであるならば、漢字は日本語を文字化するための文字であることを超えて、日本語に深くかかわりをもった存在であったことになる。そう考えると、仮名がうまれたからといって漢字を捨てなかったことは、むしろ当然といってよい。八世紀の時点ですでに漢字は日本語とともにあり、その頃から漢字とともに日本語の歴史が動き出したといえるだろう。」
・『万葉集』の余裕————和歌の文字化を考える
*「亀井孝(一九五七)は、「春楊葛山發雲立座妹念」のように、漢字によって文字化されている日本語を、具体的な日本語にまでもどす操作を「ヨミ・ヨム」、内容を理解することを「よみ・よむ」と表示して、「読み」に二つの相(phase)を設定した。具体的な日本語にもどすことはできない。しかし内容=言いたいことはわかるという場合は、「よめるけどヨメない」ということになる。」
・よめるけどヨメない
*「具体的な日本語がつかめていない=ヨメていないにもかかわらず、なぜ内容=言いたいことが(だいたいにしても)わかるのだろうか。それは漢字が表語文字であるからといってよい。漢字一字は中国語一語と対応している。「楊」であれば〈やなぎ〉、「雲」であれば〈くも〉という語義をもった中国語をあらわしている。
「楊」や「雲」を使って文字化している以上、その背後にある日本語も〈やなぎ〉〈くも〉という語義をもっている可能性がたかい。可能性がたかいというよりはそうでなければおかしい。そう考えると「春楊」であればこの漢字列があらわしている語義は〈春〉+〈楊〉だろう。」
・漢字による翻訳
*「中国語における漢字は表語文字であるから、語すなわち語義を示すことにはたけている文字ということになる。したがって、漢字によって日本語を翻訳できないことはないし、文字化できないことはない。しかしその翻訳や文字化は漢字寄り、すなわち中国語寄りにできあがる。」
・漢字訓読から「かきことば」が生まれた
*「それを示すテキストは見つかっていないけれども、奈良時代には中国語文を訓読することがおそらく行われていただろうと推測されている。そして、平安時代の初期頃から訓点を記入したテキストが少なからずみられるようになる。
寛弘五(一〇〇八)年には、部分的にしても成っていたと推測されている『源氏物語』には『史記』や『白氏文集』などの一節が漢文ではないかたちで引用されている。つまりこの頃には、漢文を訓読し、それを日本語文として「書き下す」ということが行なわれていたと推測できる。訓読さて、日本語文として書き下された中国語文は漢文訓読文ということになる。書き下されているのだから「かきことば」ということになる。こうして漢文訓読という「翻訳方法」から日本語の「かきことば」が生まれてきた。ただし、漢文訓読文は、中国語寄りの「翻訳文」であるので、それを「かきことば」とみることはできるが、きわめて中国語寄りの「かきことば」であることになる。中国語を離れた日本語の「かきことば」の獲得は鎌倉時代に入ってからと考えられている。」
・日本語のバックヤード
*「漢字による日本語の文字化は奈良時代から現代までずっと行われている。大げさにいえば、文字化をするたびに、すりあわせや重なり合いの確認が行なわれ、そのプロセスで中国語と日本語とが結びつきを形成するのだから、結びつきもつねに検討され続け、場合によっては更新(アップデート)され続けているようなものだ。つまり和語Xと中国語Yとの結びつきは固定的、静的なものではなく動的なものであり、かつそれがずっと行なわれていたことになる。」
**(終章 日本語と漢字————歴史をよみなおす」より)
*「本書は日本語と漢字との関係を軸として「正書法がない」ということに着目しながら日本語の歴史をよみなおすことを目的とした。終章では、どのような点をおもに「よみなおした」かということと、よみなおすことの意義の二つについて述べてみたい。」
*「欧米の言語学においては、まず音声言語があって、文字はその音声言語を写した二次的なもの、というみかたが一般的といってよい。語をどのように文字化するか、という書記論・表記論は基本的に欧米の言語学に存在しない。正しい書き方=正しい文字化がたった一つだけある言語は「正書法(orthography)」がある言語で、文字化に関しての選択肢がない。日本語は「正書法がない言語」で、つねに文字化に関しての選択肢がある。
欧米流に考えると。漢字は文字化に使っている文字の一つということになる。そして文字が言語そのものに何らかの影響を与えているとは考えないだろう。しかし、日本語の場合は、多くの漢語を借用して日本語の語彙体系ができあがっている。漢語を借用するということは、その借用した漢語を語彙体系内に位置付けるということで、位置付けるためには、和語とどのように結びつけるか、和語とどのように語義上の「距離」をとるかということをすりあわせる必要がある。すりあわせるためには、漢語の語義をきちんとおさえる必要があり、それは漢字字義を通して行なわれた。そう考えるると、漢字はいわばただの文字ではないことになる。漢字・漢語を軸にして文献や資料をよみなおしてみると、どういう「風景」がみえるか、ということが本書の「よみなおし」のひとつである。」
*「表音文字としての仮名が発生してからも、日本語は表意文字としての漢字を使い続けた。そして、漢字は表意的に使うのがいわば「本筋」ということになる。仮名が発生した当初は、漢語は漢字で、和語は仮名で文字化していたと推測するが、次第に和語も漢字によって文字化するようになっていった。」
*「主観的に述べるな、客観的に述べよ、といわれる。しかし、「語り」はつねに「語り手」が語っているという点において、人間を離れることができない。つまり必ず主観的であることになる。「客観的」はむしろ、語りが主観的であることを意識することというべきではないか。本書においては、言語を使う人間、言語を観察する人間を意識するようにして記述を行った。」
*「「日本語の歴史」を観察することの起点は、一つ一つの文献・資料=テキストを観察するとこにある。一つ一つのテキストの観察においてわかったことを重ね合わせていくことにとって、この時期の語義はこのようにとらえられていただろうということがわかったりする。「わかる」といってもそれは、そのように推測できるということである。それは具体的な観察をもとにして抽象的な推測に至るということでもある。」
*「本書が、「日本語の歴史」を読者のみなさん自身がよみなおし、みなおすきっかけに少しでもなってくれれば、筆者としてこんなに嬉しいことはない。そして、日本語において漢字が、語を写す文字であることをいわば超えて、日本語そのものと深くかかわっているということを知っていただくきっかけになれば嬉しい。」
□今野真二(こんの・しんじ)
1958年神奈川県生まれ。1986年早稲田大学大学院博士課程後期退学。高知大学助教授を経て現在―清泉女子大学教授。専攻―日本語学。
著書―『仮名表記論攷』(清文堂出版,第30回金田一京助博士記念賞受賞),『漢語辞書論攷』(港の人),『日本語の考古学』(岩波新書),『辞書からみた日本語の歴史』(ちくまプリマー新書),『辞書をよむ』(平凡社新書),『北原白秋 言葉の魔術師』(岩波新書),『『日本国語大辞典』をよむ』(三省堂),『言海の研究』(小野春菜との共著,武蔵野書院),『日日是日本語』(岩波書店),『『広辞苑』をよむ』(岩波新書),『日本語の教養100』(河出新書),『うつりゆく日本語をよむ』(岩波新書),『日本とは何か』(みすず書房),『横溝正史の日本語』(春陽堂書店)ほか
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
