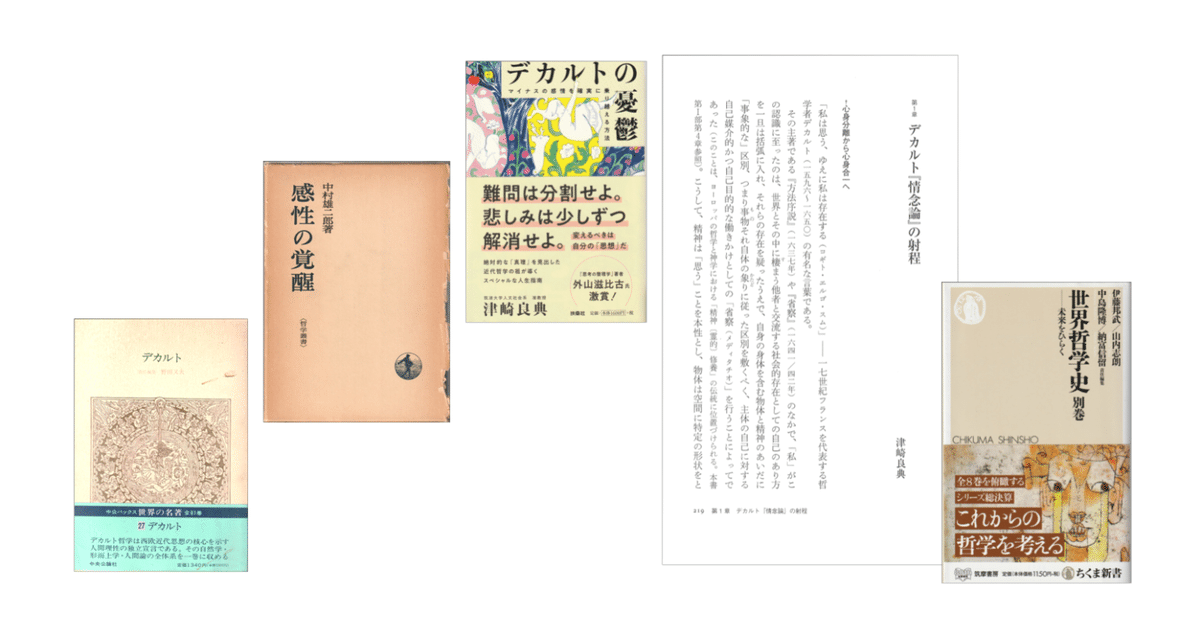
津崎良典「デカルト『情念論』の射程」(『世界哲学史別巻』/『デカルトの憂鬱』/中村雄二郎『感性の覚醒』
☆mediopos3483 2024.5.31
デカルトの生前最後の著作は『情念論』である
『世界哲学史別巻』(ちくま新書)には
津崎良典の「デカルト『情念論』の射程」が収められている
mediopos-1168(2018.1.26)でも紹介している
同著書による『デカルトの憂鬱』のなかでも
『情念論』がとりあげられているが
今回はその『情念論』を中心に・・・
デカルトは一六四三年
オランダのハーグで亡命生活を送っている王女エリザベトと
哲学的文通をはじめたが
「情念」をめぐって議論を交わしたのは
文通をはじめてから二年目の一六四五年春
「王女はデカルトに、空咳と発熱を伴った
欝症状(メランコリー)を訴え、
彼はその原因を「悲しみ」という情念に求めた」が
デカルトはその夏には
「「一切の情念から自由な状態(アパテイア)」を説いた
古代ストア派の哲学者のなかから
セネカの『幸福な生について』を選んで批判的考察を深め」
秋にはエリザベトに
「私はこのところ、その本性をもっと詳しく吟味すべく、
すべての情念の数と順序を考えています」と
『情念論』を書き進めていく
一六四九年にはスウェーデン女王クリスティーナから招かれ
女王のために朝5時からの講義を行うが
朝寝の習慣のあるデカルトは一六五〇年には肺炎で客死
『情念論』が生前最後(一六四九年)の著作となった
デカルトは『方法序説』『省察』などの著作で知られているが
『情念論』について興味をもったきっかけは
中村雄二郎『感性の覚醒』だったことが思い起こされる
中村雄二郎は一九七〇年代後半〜一九八〇年代
「臨床の知」につながる「パトスの知」について
その必要性と重要性について論じていたが
そのなかで『情念論』がとりあげられていた
「情念」は「情動(エモーション)や
「感情(センチメント)」に関わるテーマであるだけに
ロゴス(理性)に偏りがちな哲学のなか
中村雄二郎の視点はそこに欠けているものについて
重要な視点を与えてくれていた
デカルトの視点はいうまでもなく心身二元論で
情念(パッション)は
身体からの心に対する働きかけであり
能動(アクション)にもとづく受動としてとらえられている
(パッションはキリストの「受難」でもある)
それは思考することを本質とする精神と
身体とを実体的に区別することで
精神の主体性と自由が確保できるとする観点であり
その視点から理性あるいは意志による
情念の統御が意図されているのである
その視点のもとにデカルトは情念を
「外的対象によって引き起こされる外的感覚とも、
身体の内的状態によって引き起こされる内的感覚とも区別」し
「魂それ自体の状態」であるとし
「身心の相互作用の現場を
「松果腺」という脳内の部位に定め」ている
そして「松果腺」を「共通感覚の座」としている
『情念論』では情念の分類もなされていて
「すべての情念は、驚き、愛、憎しみ、欲望、喜び、悲しみという
六つの「基本情念」の組みあわせである」とし
それぞれの「情念」についてさまざまに論じられているが
そのなかでも第一の「基本情念」は「驚き」であるとしている
アリストテレスが「哲学」のはじめには
「タウマゼイン」(驚き)があったとしているように
デカルトにとっても「驚き」というのは特別な感情なのだろう
どの「基本感情」を第一のものととらえるかは
その人の魂の傾向性によって異なるだろうが
『情念論』の最後の項(二一二項)に述べられているように
(身心を二元的にとらえる視点は保留が必要だとしても)
「精神は身体と独立に自分だけの喜びを持つことができる。
けれども、精神が身体と共通にもつ喜びのほうは、
まったくもろもろの情念に依存しており、
情念によって最も多く動かされうる人々が、
この世の生において最も多くの楽しさを味わいうる」
ということは年を経るごとに実感されることでもある
「みずから情念を支配せしめ、情念をたくみに処理せしめて、
もって情念の起こす悪を大いに耐えやすくし、さらには、
それらすべての悪から喜びを得ることさえできるようにする」
そのことが重要な課題であることは確かだが
その前提にあるのは
どれほど感情を豊かに育てられるかということだろう
「死んだ思考」ではなく「生きた思考」
しかも「ハートの思考」こそが重要だが
それも豊かな感情という器があってはじめて可能となる
貧しい感情からは豊かな精神も生まれようがない
「善人なほもって往生をとぐ。いはんや悪人をや」
という『歎異抄』で有名な言葉も
そのことから理解することができるだろう
善とされる小さな器のなかで閉じる世界と
悪さえもなし得るほどの器をもって
回心を遂げるときの可能性である
統御することが困難なほどの「情念」を統御し得たとき
魂は豊かに変容を遂げることができる
■津崎良典「デカルト『情念論』の射程」
(『世界哲学史別巻————未来をひらく』ちくま新書 2020/12)
■津崎良典『デカルトの憂鬱』(扶桑社 2018/1)
■中村雄二郎『感性の覚醒』(岩波書店1975/5)
■『デカルト』(中央バックス 世界の名著27 1978/8)
**(津崎良典「デカルト『情念論』の射程」〜「身心分離から身心合一へ」より)
*「「精神を感覚から引き離す」(『省察』)ことを自身の哲学的企図の中心に据えていたデカルトにとって、しかし精神と身体が現実には「実体的に」合一して「全体としての私」(『省察』)をなしていることは、哲学的反省以前の日常的事実であり、両者のあいだに自然に成立している相互作用のメカニズムについて解明する必要は、さほど自覚されていなかった。これを「心身問題」として積極的に取り上げたのは、デカルトと同時代の、そして後代の知識人たちであった。
そのうちの一人に、プファルツ選帝侯フリードリヒ五世の長女エリーザベトがいる。家族から「ギリシア人」と揶揄されるほど勉学に打ち込んだ彼女が、デカルトと高度な哲学的文通を始めてから二年目の一六四五年春のこと、二人は「情念」をめぐって議論を交わす。
情念(パッション)とは、ただの感情ではない。激烈な感情である。人生の様々な出来事を契機に「私」の内部に生じながら、あたかも外部に存在するかのようにして「私」に襲いかかり、意志や理性の統制に服することなく、「私」をして予期しない行動へと駆り立てる。その典型は、愛と嫉妬、怒りと憎しみ、恐れと哀れみである。
(・・・)王女はデカルトに、空咳と発熱を伴った欝症状(メランコリー)を訴え、彼はその原因を「悲しみ」という情念に求めたのだった。」
**(津崎良典「デカルト『情念論』の射程」〜「身心関係という「問い」」より)
*「人が、これら哲学的な問いに直面せざるを得なくなるのは、かの「私」を当たり前のように生きられなくなったときではないか。エリザベートという一個人の事例に認められるように、そしてその彼女に自分の経験を重ねてみれば分かるように、それは具体的には、病を患ったときである。心に不調をきたせば食欲は失せ、熱が上がれば難しいことを考える気にならない。その一方で人は、たとえば悲しみに浸れば、涙が頬を濡らすのが感じられ、結果、自分の身心が特定のしかたで結合・関係していることに気づかされる。
つまり、病気や情念という、いわば非常態的な事象が、日常生活に埋没した、自分の身体ならびに精神の「存在」と両者の「関係」について哲学的反省を促し、さきに挙げたような一連の問いに誘うのである。」
「実際、ヨーロッパに話を限っても、病気と情念は古代よりこのかた、哲学的主題の一角を占めてきた。もちろん、病気が身体に由来し、その影響が身体に限定されるときは、医学や生理学の対象となる。がしかし、身体の変調が魂に影響する場合、あるいは、病気の原因が魂に求められる場合は、古代人がそう呼ぶ「魂の病」を扱う哲学の出番である。
その典型が、エリーザベトも苦しんだ「メランコリー」なのである。」
**(津崎良典「デカルト『情念論』の射程」〜「「パトス」という基礎概念」より)
*「この言葉(パッションpassion)は、ギリシア語のパトス(pathos)、ラテン語のパッシオ(passio)に由来し、キリスト教においてはキリストの「受難」を意味するなど多義的で、医学、詩学、修辞学など適用範囲も広いことが分かる。だが、フーコーが『自己への配慮』で述べているとおり。第一義的にはやはり身心関係についての、しかも哲学的な考察に欠かせない基礎概念をなす。」
「パトスの問題は、古代ギリシア文化圏では、プラトンの後期対話篇『ティマイオス』においておそらく初めて本格的に考察され、プラトンを批判的に継承したアリストテレスが『魂について(デ・アニマ)』や『ニコマコス倫理学』などで論究した。その後、この言葉がラテン語に翻訳されて、古代ローマ文化圏ではストア派の哲学者たちの多大な関心を集め、アウグスティヌスの『神の国』によってキリスト教の伝統に引き継がれ、トマス・アクィナスの『神学大全』において一つの体系化を見る。
そして一六世紀後半から一七世紀にかけて現在のオランダやベルギー、フランスにおける哲学の中心的課題の1つをなした。」
**(津崎良典「デカルト『情念論』の射程」〜「『情念論』の執筆背景とその意図」より)
*「デカルトは、王女を苦しめる「悲しみ」を癒やす手段として、ときに「緑の森、色づいた花、飛ぶ小鳥」に親しんで気晴らしをしつつ、理性をもって毅然とこの情念に立ち向かうよう勧める。それでも彼女は恢復しない。哲学者も事態をただ傍観することはせず、同年の夏には、「一切の情念から自由な状態(アパテイア)」を説いた古代ストア派の哲学者のなかからセネカの『幸福な生について』を選んで批判的考察を深め(・・・)、また秋には彼女に、「私はこのところ、その本性をもっと詳しく吟味すべく、すべての情念の数と順序を考えています」と告知するなどして、スウェーデンはストックホルムで一六五〇年に客死したがゆえに最後の刊本となった『情念論』(一六四九年)を準備してゆく。
デカルトはその序文のなかで、自分はこの論考を、雄弁家としてでも、倫理学者としてでもなく、「自然学者」として、現代風に言い直せば自然科学者として書いたと述べている。」
「デカルトは、たとえばアリストテレスが『弁論術』で行ったように、説得の一手段として聴衆の心のうちに引き起こすべきものとして情念を分析することをしない。あるいは、ストア派がそうしたように、情念は倫理的に中立か、それとも悪かといった問いや、これに関連して、情念に支配される人間の行いに責任はあるかといった問いを手段的に取り上げて論ずることもしない。デカルトによれば、なるほどそれ自体は悪とはみなされない情念は、その誤用と過度を避けさえすればよい(『情念論』第二一一項)。つまり人は真の認識に導かれるかぎり、「情念に最も多く動かされる」ことで「人生において最も多くの心地よさを味わう「(同第二一一項)ことになる。このような見解は、ヨーロッパの情念論の系譜において最も楽観的なものと言え、それほどに彼の行動は倫理学者然としていない。」
**(津崎良典「デカルト『情念論』の射程」〜「自然学者デカルトの眼差し」より)
*「情念とは、一方で、外的対象によって引き起こされる外的感覚とも、身体の内的状態によって引き起こされる内的感覚とも区別された、魂それ自体の状態である。他方で、その発生原因が動物精気の運動に求められることで、魂を原因とする意志とも区別される。情念は、魂の受動であると同時に身体の能動でもあるのだ(同第二九項)。
デカルトは、この身心の相互作用の現場を「松果腺」という脳内の部位に定める(同第三一項)。」
**(津崎良典「デカルト『情念論』の射程」〜「諸情念の分類————「驚き」に注目して」より)
*「デカルトはエリーザベトに約束したように、情念の分類も行っている。すべての情念は、驚き、愛、憎しみ、欲望、喜び、悲しみという六つの「基本情念」の組みあわせである(同第六九項)。この分類では、情念を引き起こす対象は自分にとって有益か有害か、また、問題となる善悪はすでに自分に生じているか否か、という従来の情念論に由来する基準が踏襲されているが、驚き(アドミラシオン)を第一の「基本情念」とすることは、デカルトの創見である。この情念は、或る対象が「希少かつ異常な」ものとして立ち現れ、それが「私たちに適したものか否か」が判明する以前に私たちの注意をそれに向かわせる(同第五三、七〇項)。」
「この創見の射程は思いのほか広い。デカルトは驚きの対象の具体例として、たとえば人間に自由意志が備わっていることを挙げる。自由意志に関する明晰かつ判明な認識は「真理」と言ってよいが、魂はこのような真理の探究において、動物精気の運動にではなく、魂それ自体の働きに起因する「内的情動」(同第一四七項)。をも感ずる。これは定義上、情念とは異なる魂の受動状態で、「純粋に知的な」感情である(同第九一、九二項)。真理を探究する魂は————ここでは精神と言ったほうが適切か————、その発見を渇望し、上首尾に終わったら、そのことから「このうえない満足感」(『方法序説』第二部)を得る。その反対に、間違いや不毛なアプローチは精神を悲しませ、疑いは精神を苛つかせる。」
「哲学史を思い切って鳥瞰するなら、驚きという情念へのデカルトの眼差しは、プラトンの中期対話篇『テアイテトス』やアリストテレスの『形而上学』において「哲学」というものの出発点が「タウマゼイン」すなわち驚愕に求められたことに届いているかのようである(『情念論』七六項)。」
**(津崎良典『デカルトの憂鬱』〜「前書き」より)
*「一六四五年の五月ないし六月のこと、四十九歳のフランス人哲学者デカルトは、自分より二回り以上も若い女性に手紙を書きます。
「私自身にも経験のあることですが、殿下とほとんど同じかそれ以上に危険な病苦が、今しがたお伝えしたやり方で治ったのです。と申しますのも、私の母親は数々の身廊が原因で肺を病み、私を産んでから数日して死にました。私は母親から空咳と青白い顔を受け継ぎ、二十歳すぎになるまでそうでした。そのためか、それ以前に私を診た医者は全員、私は若死にすると宣言したのです」
この手紙を受け取った人物は、それ以上は無理だと諦めていたデカルトよりも、その時点で少しばかり長く生きられた王女エリザベトです。彼女は当時、二十七歳でした。(・・・)
彼女はオランダのハーグで悲惨な亡命生活を送りながら、一六四三年にデカルトと哲学的文通を始めたのでした。
その話題は、哲学、神学、数学など多岐にわたりましたが(・・・)、医学的・心理学的なものです。
それでは何が彼女を苦しめたのでしょうか。
本人が同じ年の六月二十二日にデカルトへ送った手紙のなかで用いているフランス語で言えば「メランコリー」つまり憂鬱症です。」
**(津崎良典『デカルトの憂鬱』〜「01 デカルトはいつも「方法に従う」」より)
**「デカルトが考える方法はどのようなものでしょうか。」
*「ここで繙くべきは、デカルトが四十一歳の時に公刊した『方法序説』(一六三七年)です。題名からして、単刀直入なところに惹きつけられます。それもそのはず、物事に取り組む時は気を抜くな、という哲学者の命令が、方法の四つの規則として第二部のなかで具体的に展開されているからです。」
「「第一の規則は、私が名証的に真であると認めた上でなければ、いかなるものも真として受け容れないことであった。つまり、速断と偏見を注意深く避けることであり、そして、私がそれを疑ういかなる理由も持たないほどに、明晰かつ判明に私の精神に立ち現れるもの以外は、何一つ私の判断には取り入れないことであった。」」
「「第二は、私が検討する難題のそれぞれを、できる限り多くの、しかもそれらを一層うまく解決するために要求されるだけの小さな部分に分けること」」
「「第三は、私の思想を順序に従って導くこと。最も単純で最も認識しやすいものから初めて、少しずつ、言わば段階を登って、最も複雑なものの認識にまで上がっていき、かつ自然のままでは前後の順序を持たぬものにさえも、順序を想定して進むこと」」」
「「何も見落とすことがなかったと確信しうるほどに、一つ残らず枚挙し、全体にわたる通覧とを、あらゆる場合に行うこと」」
*「哲学者が考える方法の規則は以上の四つです。たった四つしかない。とても少ないです。どうしてでしょうか。理由は簡単です。方法の規則はその数が増えればそれだけ一層、全部を同時に守のが難しくなるからです。
(・・・)
デカルトにとって方法は、どのような問題に取り組もうが、つねに従わなければならないものです。その規則は一つとして蔑ろにされてはならない。そうであってこそ、規則の数はできるだけ少ないほうがいい。
(・・・)
まず、方法という「道」に断乎として「従う」のだ、と自分に強く言い聞かせることです。前もって決断するのです。そして、問題や課題が解決するまで、要するに最後まで守り続ける。最初の決断を捨てまいという決意を新たにするのです。
(・・・)
私たちが直面する「難題」は、現実にはどれ一つとして同じではありません。私たちは日々、新たな問題に遭遇する。それなのに、方法の四つの規則を「つねに」守れとは、何が言いたいのでしょうか。
そう、臨機応変に(・・・)いろいろと思考錯誤せよ、ということです。どうすればうまく適用できるのか、そのための工夫を自分なりに凝らす。そして、うまくいかなかったら、どうしてなのかをきちんと反省する。
この思考錯誤のやり方は、人それぞれです。つまり、手引き書は同じ一冊しかない。しかし、直面する問題や課題は千差万別だから、これを乗り越えるための創意工夫もまた多種多様だ、ということです。
ですから、方法の四つの規則に「つねに」従えとは、ある意味で私たちにクリエイティブであれ、オリジナルであれ、と求めるのに等しいのです。そして、そうなるためには、実際に方法を使ってみることから始めるしかない。
「方法は、理論よりも実践に存するのです」
処女作『方法序説』の出版という記念すべき年に、親友メルセンヌに宛てた手紙(一六三七年四月二十日頃)のなかで哲学者が書いているとおりです。私たちなりに言い換えるなら、習うより、慣れろ、となるでしょうか。」
**(中村雄二郎『感性の覚醒』〜「Ⅱ 心と身体の結びつきと共通感覚」より)
*「アリストテレスの「共通感覚」、またそてに先立つ「感覚」についてのとらえ方の特徴は、多種な感覚の対象(所与)を綜合し統一する能力を。感覚の領域の外に求めることをせずに。その統合する力の萌芽を感性そのもののうちにみとめたことである。こうして、感覚されるものの間の識別と比較がこの統合力によってなされることのほかに、理性もこの力の高度化としてとらえられることになるのである。
その上、アリストテレスでは、想像力(構想力)もまた、共通感覚との関係でとらえている。彼によれば、「心像(ファンタスマ)」つまりイメージがわれわれのうちに生ずるのは、感覚作用が終わったのちにも、感覚印象の働きかけが感官をその根底に至るまで、つまり共通感官に達して動かし、そこにとどまることによるものとされる。言いかえれば、一つの特殊感覚の感覚器官あるいは感覚能力の受けとった印象が共通感官にまで働きかけ、その働きかけの結果生じた変化、つまり「共通感覚のパトス」が、はじめの感覚の終わったのちまで残るとき、それが心像なのである。そして、このような心像を生み出すこと、「共通感覚のパトス」を再現することが「想像(ファンタジア)」なのである。」
「原理的な考え方の上でアリストテレスとはおよそ正反対なところの多いデカルトが、まったく目立たないかたちで、この概念を受けつぎ、「松果腺」によってこれを置き換え、独自な新しい理論的な展開を行っている(・・・)。
*「まずデカルトは、精神(心)と身体、思考と感覚との結びつきが「松果腺」をとおして行なわれることを指摘し、松果腺こそが「共通感覚」の座にほかならない、と言っている。すなわち、一つ一つの神経は個々の或る感覚運動に当てられている。(・・・)松果腺はといえば、それらの神経のうちの一つが他のもの以上に特別に松果腺に通じているということはない。(・・・)
松果腺こそ古くから言われてきた共通感官であり、共通感覚の座であるというわけである。」
*「デカルトは、共通感覚の働くところを心、あるいは精神の首座として、また想念、あるいは思考の首座としてとらえただけではなかった。第二にいっそう重要なのは、さらにすすんでかれが共通感覚のいわば高次化したものとして、人間の言語能力と理性の開かれた全体性をとらえていることである。少なくともその方向への大きな示唆を与えていることである。」
「デカルトは共通感覚を理性と直接関係づけてはいない。にもかかわらず、かれが思考と感覚とを結びつけるものとしての「共通感覚」に対して理性を「ボン・サンス」と呼んだことは、おのずと理性を共通感覚の高次化したものとして関係づける————この考え方はアリストテレスにははっきりある————ことになっている。そしてこの「共通感覚」と「理性」との対比は、人間の言葉あるいは言語能力をどのようなものとして考えるかという問題と大きくかかわるのである。」
*「「共通感覚」とは(・・・)まず「そこで身体中に諸感覚————感覚されたもの————が出会い、結びつき、配置をとり、まとまり、おのずと或る秩序が形づくられるもの」と考えられる。あるいはまた、人間のうちにあるそのような働きをモデル化して、これを「共通感覚」と呼ぶことができる。アリストテレスのいうような互いに異なった特殊感覚を見分けたり比較したりするだけでなく、感覚作用そのものをも感知することができるのである。また、特殊感覚の力だけではとらえられない物体の運動、静止、形、大きさ、数などをも知覚することができる。さらに、想像力(構想力)はこれを「共通感覚の受動(パトス)」を再現する働きとしてとらえることができる。他方、「共通感覚」は、デカルトの示すように、思考と感覚、心(精神)と身体とは相互にきびしく区別されたときにおいてさえ、これらのそれぞれを結びつけるものであり、心臓に位置するのではなくて脳の奥まった部分に位置し、身体の全体にかかわるとともに精神(心)の座をなすものである。
このように共通感覚は、それ自身も一種の感覚でありながら、身体的な諸々の特殊感覚を関係づけ、秩序づけつつ、高次の統合へと向かう方向性を持っている。」
**(『デカルト』(中公バックス)〜『情念論』(二一二項)より)
*「人生の善と悪とのすべては、ただ情念のみに依存すること
(・・・)精神は身体と独立に自分だけの喜びを持つことができる。けれども、精神が身体と共通にもつ喜びのほうは、まったくもろもろの情念に依存しており、情念によって最も多く動かされうる人々が、この世の生において最も多くの楽しさを味わいうるのである。もっともそういう人々はまた、もし情念を善く用いる術を知らず、偶然の運に幸いせられない場合のは、この世の生において最も多くの苦さを見いだすかもしれぬ、ということも事実である。けれども、知恵の主要な効用は、それがわれわれをしてみずから情念を支配せしめ、情念をたくみに処理せしめて、もって情念の起こす悪を大いに耐えやすくし、さらには、それらすべての悪から喜びを得ることさえできるようにするということなのである。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
