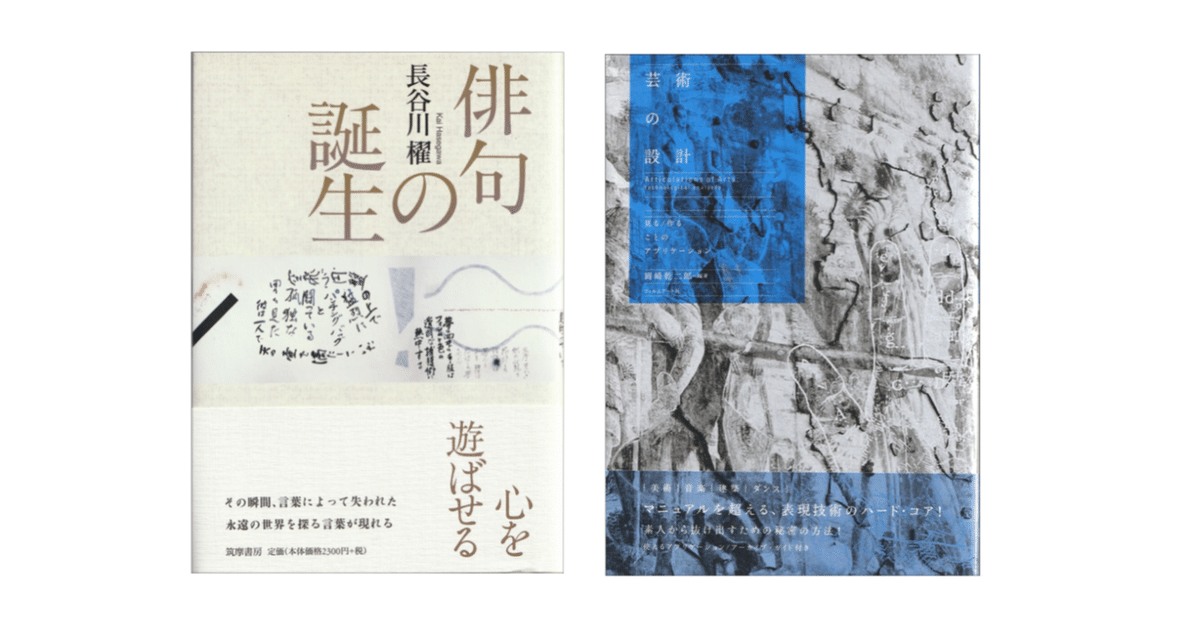
岡﨑乾二郎『芸術の設計 見る/作ることのアプリケーション』/長谷川櫂『俳句の誕生』
☆mediopos3521 2024.7.8
昨日〈mediopos3520(2024.7.7)〉は
俳人「井月」の関係で
正岡子規の「月並調」俳句への批判をとりあげたが
それに関することについてはすでに
〈mediopos-2373(2021.5.16)〉でふれたことがある
(長谷川櫂『俳句の誕生』)
子規の批判は似非古典主義俳句が跋扈している
「大衆化」に対するもので
そのため子規は「写生」を提唱し
さらに虚子は亡くなった子規の後を受け
「客観写生」を唱えることになる
「客観写生」とは
「主観を排し、客観に徹して対症を描け」
ということなのだが
そこには「言葉の想像力を視野に入れない
という重大な欠陥」があった
そのため虚子が主宰していた
雑誌「ホトトギス」の雑詠欄(投句欄)は
「全国から寄せられるガラクタ俳句で埋ま」ることになる
虚子は新たに「花鳥諷詠」を唱えるのだが
そのことで「俳句の対象が花鳥の象徴する
趣味的な四季の風物だけに限定され、花鳥以外の対象、
戦争や災害や時事を詠んではならない
という誤解を与え」てしまうことになる
虚子が没すると
「多数の結社が生まれ、細分化」し
そして「極端な大衆化」が進み現代に至っている
長谷川櫂は「これは俳句の世界だけの問題ではない。
大衆社会全体が直面している現在進行形の問題である」
としているが
「作品」を制作する芸術家なる存在すべてについて
この「極端な大衆化」という問題は等閑にはできない
「極端な大衆化」は「極端な専門化」でもある
「だれにでもできる」&「だれにもわからない」
自称芸術作品と自称芸術家の増殖である
岡﨑乾二郎は『芸術の設計』において
(「極端な大衆化」を主題としてはいないが)
そうした芸術作品の制作に関して重要な示唆を行っている
岡﨑乾二郎は建築・音楽・ダンス(舞踏)・美術の
「設計」に関する示唆を行っているのだが
(いうまでもなく他のジャンルの制作もあてはまる)
「おおよそ技術は技術であるかぎり誰にでも開かれている。
つまり誰にでも習得できるという前提において構築される」が
「実際に制作すること、実行することは異な」り
「誰にでもできるものではなく」「会得しがたいもの」だという
そこで問われるのは
そうした技術習得のためのマニュアル設計では
「かえって技術の習得をむずかしくさせるのも知らずに」
「その本質を理解しなくてもすむような安易な方法が
植え込まれていただけではないのか」ということである
諸ジャンルの芸術作品の制作過程は「共通の論理を持ってい」て
「パソコンの普及によって異なるジャンルの制作が同じく、
キーボードやマウスの操作によってディスクトップ上で
繰り広げられるようになっ」ていて
「情報として考えるかぎり、
共通のメディア(基盤構造)の上に
取り替え可能なコンテンツ(情報)がのる階層構造は
どのメディアも同じ」なのだが
「物質的な生産過程としてみると、
その差は決定的な通約不可能性(複製不可能性)を意味している」
技術を「教えるとは咀嚼すること、
つまり全体としては捉えがたい対象
(身体芸のように本来、無形で連続した出来事をも)を、
伝達でき咀嚼できるような要素にまで、
ばらばらに分解し(つまり解体し)、
その解体された要素を、再びつなぎ合わせて見せること」だが
教わる側にとって難しいのは「解体された要素(タネ)」を
「再び、どう一つの連続した全体として組み立てるか、
つなぎ合わせるか」ということであって
「そこにこそ秘伝がある」
「大衆化」ということは
「誰にででも開かれている」がゆえに
「誰にでもできる」という錯誤から
形ばかりの「作品」なるものが制作され
それを制作する者が「芸術家」を自称するということである
パソコンひとつあれば
そこそこの画像処理やデザイン
作曲や演奏までも自在にできるし
いまやAIによって文書作成も手軽にできる
パソコンがなくても
たとえば作文程度の能力さえあれば
詩歌や小説などを書くことも手軽にできる
しかしそれは「技術を理解すること、
把握すること、習得する」ことだとはいえない
先の繰り返しになるが
これは「大衆社会全体が直面している現在進行形の問題である」
岡﨑乾二郎は「ほんとうに素人になる」ことが
「いままでしたことのなかった技術を会得する最大のコツ」だという
それは「刷り込まれた観念=身体から自由になるということ」
だからである
mediopos3487(2024.6.4)で
「ラーン(learn)」(学ぶ)に対する
「アンラーン(unlearn)」(学んだことを忘れる・離れる)
についてふれたが
「型に縛られる」
つまり与えられたものをそのまま
知識として覚え込むような「洗脳」的なことを
「解除」することによってしか
ほんらいの「技術」としての「制作」はむずかしい
■岡﨑乾二郎『芸術の設計 見る/作ることのアプリケーション』(2007/5)
■長谷川櫂『俳句の誕生』(筑摩書房 2018/3)
**(岡﨑乾二郎『芸術の設計』
〜「まえがき この本の構成について 4 技術を学ぶのはつねに素人である」より)
*「おおよそ技術は技術であるかぎり誰にででも開かれている。つまり誰にでも習得できるという前提において構築されるものだが、「あなたにもできる」と容易な習得をうたうマニュアルの数々が、前提にしている(売れている)のは、一方で、にもかかわらず誰にでもできるものではなく、それが会得しがたいものであるという事実である。
いいかえれば、その技術の素晴らしさ、面白さは理解できるが、それを実際に制作すること、実行することは異なる、しかし、われわれは本当に理解していたのだろうか。その本質を理解しなくてもすむような安易な方法が植え込まれていただけではないのか。素人だったのではなく「誰でもできる」式のマニュアルによってかえって素人にされてしまったのではないか。そのことがかえって技術の習得をむずかしくさせるのも知らずに(ほんとうに素人になるというのは、こうして刷り込まれた観念=身体から自由になるということである、それこそが、いままでしたことのなかった技術を会得する最大のコツなのだが)。
技術を理解すること、把握すること、習得するということはいかなることなのか。本書が最終的に目的にしているのはこの秘伝の解明である。」
**(岡﨑乾二郎『芸術の設計』
〜「芸術の設計 技術の条件としてのノーテーション 0 技術の条件」より)
・技術を持つ
*「人の持つ技術が技術たりえるのは、その特定の仕事、行為の反覆可能性、持続性が保たれるゆえにである。たまたまゴールが決まったのではなく、いつでもゴールできるこよがサッカーのフォワードの技術であるように、つねに同じ結果をもたらすことができる能力こそが技術である。(・・・)しかしそれは可能なのか? 可能なのだと信じられるならばなぜなのか。何によって技術は頼りにできるのか。この本の主題の一つはここにある。」
・技術を学ぶ=思い起こす
*「「技術を持つ」といういい方は、「技術」が人間にとって外在的なものであるということを示している。」
「人は自分のもともと持っていなかった技術を習得し、忘れ、そして再獲得する。それが技術を学ぶ、持つとうことである。」
「ゆえに人は手掛かりをもとめ、それを記し、一種の外的な記憶として保存しようとする。楽譜や図面、ダイヤグラム。あるいはいたずら書きのように見えるメモ、デッサン。覚書。とらえがたく忘れやすい、つねに出来事として生起するだけで不安定な行為を、記号化し記録する、こうした外的な記録を作ることを、広くノーテーション(記譜)と呼んでおこう。」
・「技術」に構造を与える「事物」
*「ノーテーションは技術そのものではない。その手段、つまりそれ自身、道具の一種である。」
「この本で使われるノーテーションという語の意味を突きつめれば、「技術に構造を与えるための外的な参照物」ということにもなるだろう、「技術」とは出来事、行為における同一性の確保であり反覆可能性の確保である。そのつど差異として生成するだけの出来事を構造として把握し、つねに同一の対象として客体(オブジェクト=物体)的に扱いうることである。この構造的同一性はいつでも、外的参照物によって補われている。」
・教えること、伝えることは解体することである
*「教えるとは咀嚼すること、つまり全体としては捉えがたい対象(身体芸のように本来、無形で連続した出来事をも)を、伝達でき咀嚼できるような要素にまで、ばらばらに分解し(つまり解体し)、その解体された要素を、再びつなぎ合わせて見せることである。」
こうして教わることにとって、教わる側は「奇跡的な芸にもタネや仕掛けもあった、秘密がわかった」と、ときには勘違いしてしまう。が、もちろんむずかしいのは、どう解体するか、にあって、その解体された要素(タネ)にあるのではない。そして、それを再び、どう一つの連続した全体として組み立てるか、つなぎ合わせるか。そこにこそ秘伝がある。
こうして伝授されるのは、芸そのものではない。むしろその芸を行なう名人が、その芸をどのように把握しているか、というその構造である。」
「一つの統合された芸から、単語同様にばらばらに解体されてしまった要素は。いまや互いに、外的な事物として相互に参照しあうものになる。教えの基本となるのは比喩————「たとえばこれをあの動きであるとする」であり、そしてそれがすぐに比例————「この動きがあの動きの〜であるなら、この動きは〜となるだろう」へと発展する。伝授の過程で、統合された技芸の連続は、参照関係を作り出す、互いに独立した事物のようなボキャブラリーの集合へとばらされるわけである。」
・認識とは再制作である
*「同じものの確保という意味で技術は、つねに認識に伴われている。伝達の過程で現れるのは、この事実である。そして認識は、そこで認識される対象の再生産、複製という行為を前提(先取り)し、それに裏打ちされている。」
「くり返し。再生産。同一なものを同一なものとするのは構造である。」
「ノーテーションによって記述されるのは、この構造であり、言いかえれば構造を構造として規定するのはノーテーションである。くり返せば、ノーテーションとは一つの外的な参照物、つまりそれ自身が一つの事物である。」
・分節とプログラム
*「変形生成しても、その構造としての同一性は保たれる。ゆえに分節の効用は効率性として現れる。たとえば文章を圧縮する際、主部/述部などのシンタクス(統辞法)、分節を保つことで、情報を効率よく要約することができるように。
これはいうまでもなく、コンピュータのプログラミングを支える基本的な考えであった。(・・・)すべては要素間の関係へ解きほぐされ、順序構造として組み立て直される。いかなる出来事、事物の差異も、こうしてあらかじめ分節され枝分かれた道筋、構造の内でだけ生起するようプログラム(構築=記述)され直す(ゆえにプログラミングとは、ノーテーションの作業のそのまま延長にある)。
**(岡﨑乾二郎『芸術の設計』〜「あとがき」より)
*「建築、音楽、ダンス(舞踏)、美術といった芸術諸ジャンルの表現形式をそれぞれの技術的特性から理解したい、という欲望は、芸術を志す人であれば誰でも描くものだと思う。それぞれの表現形式はそこで扱われる感覚の違い、メディアの違いにもかかわらず、制作の過程において案外、共通の論理を持っているのではないか。こうした直感は、かつてローマの大詩人ホラティウスが「詩は絵のように」(ut pictura poesis)と言った諸ジャンルを結びつかる共感覚というよりも、今日パソコンの普及によって異なるジャンルの制作が同じく、キーボードやマウスの操作によってディスクトップ上で繰り広げられるようになった事態に由来しているといっていいだろう。
古くはローマの大プリニウスの『博物誌』、十八世紀啓蒙主義のドゥニ・ディドロとジャン・ル・ロン・ダランベールの『百科全書』、あるいは一九六八年スチュアート・ブランドたちの『ホール・アース・カタログ』まで、人間の扱う技術全般を網羅するマニュアルを一書としてまとめようとした大それた企画はつねにあったが、現在ではそれは一台のパソコンに種々様々なアプリケーションを搭載することで容易に果たされている。
とりあえず何がしかの技術を学ぶ教科書を探しているなら、まず学びたいジャンルでよく遣われるアプリケーションを入手し、その仕組みを学ぶことである。漫画でも映画でも必ず便利なアプリケーションが見つかる。そのメニューバーの構成を見るだけで、そのジャンルの表現がどのように作られるのか手にとるようにわかる。そしてコンピュータ上で作品を組み立てていく手順はどのジャンルでも驚くほど似ているのである。パソコンを使いだすと一般にコンテンツと考えられているものは、おおよそ取り替え可能な付加的要素であったことに気づく。たとえば同じ生地の上、トッピングだけ手をかえ品をかえメニューを賑やかしているだけの宅配ビザ。しかし一方で素材、見掛けは似底ても、ものの組み立て、制作プロセスが異なる事物の差異をパソコンは表現しきれない。たとえばお好み焼きともんじゃ焼き。パソコンは宅配ビザの違いは表現できても、もんじゃ焼きとお好み焼きの違いはたとえ3Dソフトを使っても表現しきれない。そもそも、もんじゃ焼きはもっとも写真写りの悪い(おいしそうに写せない)食物として有名だった。
こうしたパソコンは事物を組み立てる論理の分裂に気づかせる。情報として考えるかぎり、共通のメディア(基盤構造)の上に取り替え可能なコンテンツ(情報)がのる階層構造はどのメディアも同じだ。しかし物質的な生産過程としてみると、その差は決定的な通約不可能性(複製不可能性)を意味している(油彩画で水墨画は作りだせないように)。もんじゃ焼きとお好み焼きは水墨画と油彩画ほどに異なる。けれど現実の場面では、われわれはワインの味の違いのようにこうした生成プロセスの違いをコンテンツの違いとして的確に認識している。」
*「本書を通読していただければわかるように、結局のところコンピュータは人間の文化が長い時間をかけて形成してきた、さまざまな技術間の通訳可能性そして通約不可能性のそれぞれを再確認するための反面教師としての役割を果たしている。」
*「本書の企画は、近畿大学国際人文科学研究所=四谷アート・ステュディウムに集まる、若い研究者や作家たちと筆者が開いてきた「ノーテーション・リサーチ」を母胎にしている。当初、半ば冗談のように共有していた「諸技芸、全表現ジャンルを統合的にとらえる形式論理を構築する」という野心は、こうして見事に(予測通り)挫折し、最終的に技術は(不可逆的、非対称的な)歴史をいかに形成するか、というテーマに行き着くことになった。われわれの到達した結論はおそらくジョージ・クブラーの『時のかたち』に近い。」
**(長谷川櫂『俳句の誕生』〜「俳句とは何か」より)
*「正岡子規が明治時代に説いた写生という俳句の方法は対象への凝視、精神の集中を要求する。しかし私の乏しい経験からいえば、俳句ができるのは精神を集中させているときではなく、逆に集中に疲れて、ぼーっととするときである。心が自分を離れて果てしない時空をさまよう。そうしたときに心は言葉と出会い、俳句が誕生する。それは俳句が浮かんでくる、はるか彼方からやってくるという感じである。
俳句を作るには子規が説いた集中ではなく、心を遊ばせること、いわば遊心こそが重大なのだ。芭蕉も蕪村も一茶も、また写生を唱えた子規や虚子自身も、さらに楸邨も龍太も心を遊ばせて俳句を作っていたのではなかったか。なぜならそれこそ古代の柿本人麻呂からつづいてきた詩歌の本道だからである。」
「写生が量産する、眼前のものを言葉で写しただけのガラクタ俳句は写生の努力が足りないのではなく、心が遊んでいないということになるだろう。
人間の心は遊んでいるとき、自分を離れ、言葉におおわれたこの世界を離れて、はるか昔に失われた言葉以前の永遠の世界に遊んでいる。人間が言葉を覚えたことによって失われた永遠の世界。その永遠の世界への脱出の企てが詩であるのなら、集中ではなく遊心こそが詩の母胎であることを認めなければならないだろう。
言葉によって失われた永遠の世界を言葉で探ること。そこに重大な矛盾が潜んでいるのは誰にでもわかる。しかし人間はあえてこの矛盾に挑まなければならない。なぜなら世界は言葉で覆われているからである。そして言葉の覆いを剥がして永遠の世界と出会うには人間は言葉という道具を使うしかないのである。
言葉を剥がす言葉、それこそが詩である。その詩の中で俳句はもっとも短い十七拍の定型詩である。しかも十七拍の内部に「切れ」という深淵を抱えこんでいる。俳句は永遠の世界をおおう言葉を最少の言葉で剥がそうとする恐るべき企てなのだ。」
**(長谷川櫂『俳句の誕生』〜「第八章 古典主義俳句の光芒」より)
*「芭蕉から蕪村へと受け継がれた古典主義俳句は蕪村以降、どうなったのか。ただちに消滅したわけではなかった。徐々に進行する俳句の大衆化に気づかず、芭蕉を神格化しながら命脈を保つことになる。明治になって子規が「月並俳句」と呼んで排斥しようとしたのはこの似非古典主義俳句だった。」
**(長谷川櫂『俳句の誕生』〜「第九章 近代大衆俳句を超えて」より)
*「保田與重郎も三島由紀夫も大衆化ではなく西洋化を近代の指標と誤解したために、近代をどう超えるか、大衆化にどう対処するかという問題と出会わなかった。その結果、この問題は手つかずのまま現代に持ち越されてしまった。どの分野でも火急の課題は戦後の高度成長を機に新たな次元に入った大衆化にどう立ち向かうかである。俳句も例外ではない。
大衆化が極限にまで進み、内部から崩壊しつつある現代俳句について考えるために時間を少し溯らなくてはならない。明治時代、正岡子規は「写生」を提唱した。子規の写生は一茶の時代にはじまった近代大衆俳句の方法だったが、言葉の想像力を視野に入れないという重大な欠陥を抱えていた。ところが子規は写生の欠陥が露呈する前に短い生涯を終える。写生の抱える問題に直面することになったのは子規の後継者を名乗った高浜虚子である。
子規の死後、虚子は子規の写生をさらに進めて「客観写生」を唱えた。それは客観写生という言葉のとおり主観を排し、客観に徹して対症を描けということである。虚子の客観写生は、目の前にあるものを言葉で写せば誰でも俳句ができるという子規の写生をさらに先鋭にしてものだった。しかしこれが言葉における想像力の働きを無視するという、写生がもともと孕んでいた欠陥をさらに際立たせることになった。
俳句にかぎらず、そもそも主観を排除して言葉を客観的に用いるということが可能かどうか、そこから考えなければならない。
(・・・)
主観、客観は明治以降、さかんに使われるようになった言葉の一つだが、こうした言葉の常として世界を不要に分断し無用の対立を作り出す厄介な言葉である。主観といえば、それに対立する客観が立ち上がる。逆に客観といえば主観が立ち上がる。しかし主観にも客観にも実体はない。主観や客観が存在するというのは言葉の生み出す幻覚にすぎない。
主観と客観がこうした弊害をもっていることを承知の上で使うなら実害は少ないかもしれない。しかし客観という実体、主観という実体が存在すると思いこんで客観写生に邁進すれば、いいかえると俳句から主観を排除しようとすれば、(果たしてそんなことができるとしての話だが)それは言葉の自殺行為にほかならない。
じっさい虚子が客観写生を唱え始めると、主宰していた雑誌「ホトトギス」の雑詠欄(投句欄)は全国から寄せられるガラクタ俳句で埋まった。ガラクタ俳句とは客観写生に従って主観を排除しようとし、客観に徹して詠もうとした結果、想像力が働かず、対象の形態だけを写したガラクタのような俳句のことである。
驚いた虚子はすぐ新たに「花鳥諷詠」を唱えて客観写生を修正しようとする。花鳥諷詠とは花や鳥に心を遊ばせて俳句を楽しむということであり、芭蕉の「風雅」を虚子風に言い換えたものである。いいかえれば言葉の想像力を虚子流に回復しようとしたのだった、花鳥に心を遊ばせよとは想像力をもっと働かせよ、簡単にいえば、ぼーっとせよ、心を遊ばせよという遊心の勧めにほかならなかった。虚子はここで子規を離れて柿本人麻呂、紀貫之以来の詩歌の本道に帰ろうとしていたのである。
花鳥諷詠は客観写生と根本的に対立する。それは虚子もわかっていたはずである。
(・・・)
虚子が新たに唱えはじめた花鳥諷詠は俳句についての別の誤解を生むことになる。虚子の花鳥諷詠のもとになった芭蕉の風雅は宇宙に起こるすべてを文学の立場から眺めて俳諧(俳句)にするということだった。ところが虚子は風詠にあえて花鳥を冠して花鳥諷詠としたために、俳句の対象が花鳥の象徴する趣味的な四季の風物だけに限定され、花鳥以外の対象、戦争や災害や時事を詠んではならないという誤解を与えてしまった。虚子の花鳥諷詠は俳句を趣味の世界に閉じ込めてしまうことになる。」
*「客観写生、花鳥諷詠のほかにも虚子は漢字四文字の熟語を次々に作りだした。これらの四文字熟語は単に虚子の趣味だったのではなく、じつは膨張しつづける俳句大衆を束ねる近代特有の標語だった。
近代大衆社会は指標となる言葉、つまり標語を必要とする。近代大衆社会の指導者は大衆を束ねて動かさなければならないからである。一方、大衆は自分一人で判断したがらない。大衆は自由を求めているようにみえながら、じつは自由を恐れているからである。
明治時代の富国強兵、文明開化、殖産興業、昭和戦争時代の八紘一宇、鬼畜米英、一億玉砕、戦後の租特倍増、安保反対、列島改造など、どれも大衆を束ね、動かすための標語だった。指導者たちはこれらの標語を、同じく近代とともに誕生した新聞、のちにはラジオ、テレビ、インターネットを通じて大衆に繰り返し呼びかけ、指導者が望む方向へ大衆を導こうとする。大衆は嬉々としてそれに従った。客観写生、花鳥諷詠などの虚子の四文字熟語も俳句大衆に対してこれと同じ働きをした。
俳句大衆の指導者という役割がいかに危険か、戦前戦後の虚子の動向をみればわかる。」
*「虚子の真の批判者となり、同時に虚子の真の後継者となったのは加藤楸邨(一九〇五−九三)、次いで飯田龍太(一九二〇−二〇〇七)の二人である。どちらも秋桜子のように浅はかに虚子を攻撃することはしなかったが、虚子のような俳句大衆の指導者になろうともせず、作家としての俳人に徹した。その行き方自体が虚子に対する無言の批判だったのである。そして二人とも言葉の想像力を自在に遊ばせて俳句を詠んだところが共通している。それは虚子の俳句の詠み方でもあった。」
*「昭和戦争での敗戦が日本と日本人を変えてしまったと誰でも思っているが、じつはそうではない。古い日本と日本人をその内部から破壊し、新しい日本と日本人を出現させたのは敗戦から十年後、昭和三十年代にはじまった高度成長だった。日本と日本人は敗戦という外部の力によって変えられたのではなく、日本人自身が推進した高度成長によってみずから変わったのである。敗戦はその遠因にすぎなかった。
俳句もその例外ではない。高度成長時代に入ると、近代大衆俳句は飽和状態に達し、内部から崩壊がはじまる。俳句の変化の明らかな兆候はこの時代、俳句の選とそれを支える批評が衰退したことである。
近代大衆俳句は江戸時代半ばの一茶の時代にはじまり、それ以来一貫して俳句人口は増えつづけてきた。これが現代までつづく俳句の大衆化現象である。ところが戦後の高度成長時代に入ると、俳句を作るだけでなく誰もが批評めいた発言をするようになり、誰もが選句をするようになった。その結果、どれがよい句でどれがダメな句なのかわからなくなってしまった。
この変化の背景にあったのは半世紀にわたって俳句の世界に君臨してきた虚子の死である。虚子は優れた俳人であったばかりでなく、批評と選句の能力を備えた俳句大衆の指導者だった。その虚子が偶然にも高度経済成長の初期、昭和三十四年(一九五九年)八十五歳で亡くなる。虚子の死によって俳句は大俳人と同時に俳句の批評家であり選者である存在を失ったことになるだろう。
どの句を評価し、どの句を評価しないか、どの句を選び、どの句を棄てるか、俳句の批評と選句は俳句大衆の道標である。それは単にどの俳句が好きか嫌いかというその人の好みの問題ではなく、言葉と詩歌の歴史を俯瞰しながら行われるべきものである。
ところが虚子が没すると、俳句の世界では多数の結社が生まれ、細分化が進んだ。その結果、誰もが批評まがいの発言をし、選句まがいの選句をするようになった。こうなると俳句の批評と選句の信頼性は失墜し、俳句大衆は誰の批評を信じ、誰の選句を信じていいかわからない。
信頼できる批評と選句。高度成長時代、これが衰退する代わりに幅を利かせはじめたのが人気である。俳句と俳人の人気を測る方法はいくつかあって、一つは本の売れ行き、もう一つはマスコミへの露出度、極めつきはアンケート調査である。」
「極端な大衆化がもたらした批評の衰退。これは俳句の世界だけの問題ではない。大衆社会全体が直面している現在進行形の問題である。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
