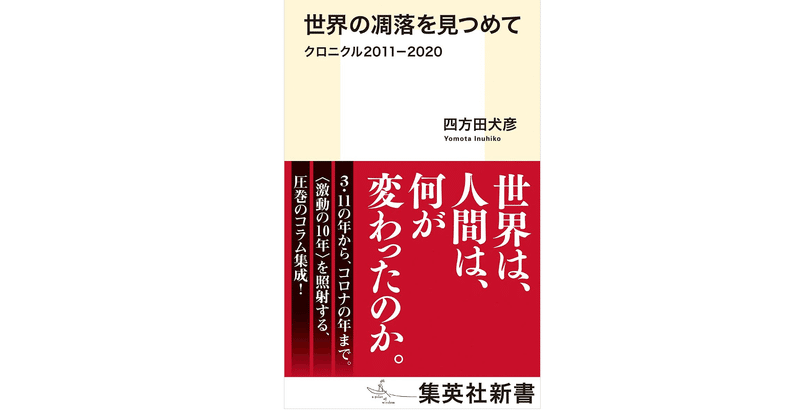
四方田犬彦 『世界の凋落を見つめて/クロニクル2011-2020』
☆mediopos-2378 2021.5.21
昨日『情報の歴史』の新版に
1996年から2020年までの
15年間が追加されたのをみた
今日は四方田犬彦による
2011年から2020年の
「世界の凋落を見つめ」た「クロニクル」である
『週刊金曜日』に連載されたものに
書き下ろしと加筆を行ったものが収められている
そういえばここ数年
四方田犬彦の著作をずいぶん読むようになった
世の中の振りかざす正義や道徳に抗うようにして
しかもベタな政治的な仕方ではなく
文化の多様な深みのなかで
世界を読み取ろうとしていることに
以前よりずっと親近感を感じながら
「クロニクル」を読みながら
この15年
そしてこの10年
じぶんは何を思い
何をしてきたのだろう
そしてこれから
いったい何を思い
何をしてゆくことになるのだろう
そしてなぜじぶんは
この時代に生まれて
いまこうして生きているんだろう
そんなことを考えている
たしかに「世界は凋落してる。
間違いなく凋落のさなかにある」
けれどもその凋落しているさなかの時代に
生まれていること
生まれなければならなかったこと
そのなかにこそおそらくじぶんの課題がある
それを声高に叫ぶ必要はない
だれかに承認してもらう必要はないからだ
むしろそれを求めれば求めるほどに
肝心の課題は損なわれてしまうことになる
必要なのは日々淡々と
「世の中の振りかざす正義や道徳に抗」いながら
世に迎合し取り込まれるのでもなく
世からどこかに隠遁するでもなく生きていくことだ
みずからの課題を自由な精神のもとに
魂の深みに刻み込みながら
■四方田犬彦
『世界の凋落を見つめて/クロニクル2011-2020』
(集英社新書 2021.5)
「世界は凋落してる。間違いなく凋落のさなかにある。
暴力と不寛容が跳梁し、動機も定かでない大量殺人が平然と生起する。人々は差別され監視される。耐えかねて逃亡を図ると、監禁され排除される。テロと疫病は場所を選ばない。地上の誰もが犠牲者となる可能性のもとにある。空間の安全性をめぐって、これまでのように「こことよそ」という分割はもはや成立しない。いたるところが「ここ」になってしまったのだ。
真実というものの輪郭が曖昧となってしまった。情報の出所が問われることなく、一瞬のうちに世界を駆けめぐっている。虚偽の言説と映像が大量に拡散され、メディアの信憑性を加速度的に格下げしていく。かつては信じられたものは、もうどこにも存在していないのだ。だがそれを嘆くノスタルジアの感情もまた巧みに商品化され、観光の対象としてたちどころに消費されてしまう。
人間は人間以下のものになろうとしている。」
「紙媒体が忌避され、社会全体が電子メディアによって取って代わられようとしている。誰もが口をそろえてそういっている。重要なのは情報であり、速度を伴った情報なのだという。
本当だろうか。加速されることで情報はますます起源が曖昧となり、その信憑性を確認することが困難になってしまう。声高々に叫ぶフェイクニュースが横行し、手作りの作業で獲得された真実が遅れて到来したときには、もう誰の注目も惹かなくなっている。今日、人は、ほとんど無限に流れ込んでくる情報の一つひとつを、丹念に検討することなどしない。ただ情報を所有していることで得られる安心感だけを求めているのだ。
人は自分の信じるままに自分が自由な発言をし、周囲に向かって情報を発している。だがそれは幻想であって、誰もが同じことを、同じ口調で語っているにすぎない。いや、より正確にいうならば、語っているのではなく、何か見えない力によって語らされているだけにすぎないのだ。この愚劣さの構造をファシズムという。ファシズムは語ることを禁じたことなど一度もなかった。ただひたすらに同じことを語るように、人に命じてきたのである。
誰もが同じことを喋っている。それが正義だからだ。右も左もない。保守もリベラルもない。そして正義はつねに人を饒舌にさせる。それが多数派だからだ。正義に逆らって口を開くことは、絶対にしてはならない。そのような発言を口にする者がいたとしたら、その口を塞ぎ社会的に抹殺するのが、道徳的な務めである。以上が正義の典型的な言説だ。
正義を語ることはたやすい。なぜならば正義という名のステレオタイプは無料だからであり、いかなる自己犠牲も払うことなく、自分が道徳的に高い立場にあるという意思表示ができるからだ。
わたしは本書のなかで、できるだけこうした正義に抗おうとしてきた。世界がまさに凋落のさなかにあるとき、誰もが同じことを口にするこの世界にあって、たったひとり、異言を口にしようと試みてきた。」
「本書は日本と世界をめぐる、わたしの観察日記である。今から長い歳月の後、わたしたちはこの10年を、どのような形で回想することになるだろうか。」
「つい先ごろ、わたしは65歳になった。ロラン・バルトより1年長生きをし、吉田健一の死んだ年齢に達してしまった。
わたしが若いころ、このふたりこそ老いたる賢者であると信じていた。ヨシケンは人生の悦びを語り、バルトはその悲しみを説いた。けれども彼らは本当に賢者だったのだろうか。わたしには彼らと同じ年になったことが、ひどく滑稽な感じがする。自分には賢者めいたところなど、まったくないからだ。わたしが心がけてきたのは、なんとか人に尊敬されずに生きていくことだった。日本では尊敬されてしまうと、自由に生きることができなくなってしまう。
しばらく前に、高校の同窓会の通知が来た。わたしは同窓会などに出たくもないし、興味もない。すると160人の同級生の近況を知らせるメイルが送られきた。160人といっても、自殺と病死を除くと150人くらいだ。ほとんどの者が近況報告の欄に、定年退職したことしか書いていない。そのうちの18人が野球チームをふたつ作り、週に1回、球場を借りて試合をしている。暇だから週に2回でもいいという声もあったらしい。あとは孫の相手と趣味の園芸。働いている者はもうわずかしかいない。何人かの開業医と日本共産党の国会議員。共産党と決別したらしい経済学者。それにわたしくらいのものだ。」
「それにしても65歳になるというのは奇妙な気分だ。長い間わたしは、電車のなかで背広を着て、ネクタイを締めている男たちが大人だと、無邪気に思っていた。ヌードとゴシップの週刊誌を読んでいるようなサラリーマンのことだ。けれども今では誰も週刊誌など読んでいない。猿が身づくろいをするように、神経質そうにスマホを奔っている。最近になってわたしは気が付いた。日本ではホワイトカラーの定年は60歳だから、わたしが電車のなかで見かけるサラリーマンは、みんな自分よりはるかに年下の男たちなのだ。彼らもまた、定年後に野球チームを結成するため生きているのだろうか。」
わたしは野球のことなど何も知らない。選手の名前も、球団の名前も、それどころかルールさえ知らない。わたしは元同級生たちのように野球をしたことはなかったし、これからもないだろう。わたしは彼らのように歌ったこともなかったし、彼らのように泣いたり笑ったりしたこともなかった。けれども滑稽なのは、わたしが彼らと同じように、そう、まったく同じように死んでいくということだ。なんという厳粛な事実! 死が馬鹿馬鹿しいのは、ひとえにこの平等性にかかっている。どんな死も、自殺も含めて、死は斉しく凡庸なのだ。
凡庸さとは、それを振り払う身振りによって、いっそうそれを特徴づけられるといった何ものかだ。きっとこの凡庸性とどう折り合いをつけていくかが、これからのわたしの人生の課題となるのだろうなあ。」
「エンガチョという遊技がある。汚れたものに触った人間は、それを誰か別の者に移さないかぎり、汚れから解放されることができない。犬のウンチを知らずに踏みつけてしまった子供は、「縁がチョン切れる」ために駆け回らなければならない。
日本人にとって世界は二通りでしかない。清らかであるか、汚れているかだ。汚れたものは内面ではなく、つねに外側から到来する。だから禊をすれば、元の清浄なる姿に戻ることができる。水に流せばいいだけなのだ。日本人には汚れを内面化し、歴史的に検討する契機が欠落している。汚れた者はただちに排除か隠蔽する。汚れをわがこととして引き受け、ともに生きようという発想はない。
戦前の日本では「アカ」が、戦後は「ホモ」が汚れだった。もっとも新しい汚れはコロナウイルスである。家族も同罪である。誰も西洋社会のように辛苦を分かち合おうとはしない。だから感染者は公にされないし、家族は秘密にしようとする。患者は恐怖の対象にはなっても、憐憫の対象にはならない。
コロナウイルスは新しい現象だろうか。わたしには日本社会がこれまで隠蔽してきたケガレの構造を、もう一度、白日のもとに曝け出しただけだという気がする。繰り返していうが、どこまでも汚れと清めなのだ。罪と罰ではない。そのかぎりにおいて、日本人はいつまでも歴史の教訓に到達しない。」
「最後に短い詩を掲げて、本書を閉じることにしよう。
岡崎京子がむかし、いった通りになるよ。
もうすぐぼくたちはみんな忘れていってしまうだろう。
1960年があったことも、1970年があったことも、
1991年や2011年があったことも、それから
2020年があったことも、みんな忘れていってしまうのだ。
戦争はたとえばこんな風に始める。
ぼくたちはひさしぶりにばったり出逢って
昔のようにビールを呑みにいって
誰がふと何かをいいたそうになるのだけれど
もういいよ、そのことはと、別の誰かがそっと目で合図して
それでもと通り、ぼくたちは呑み続ける。
仕方なかったんだ、あのときは。
でも何も変わってはいないじゃないか、って。
気にすることはないよ。もうみんな忘れちゃえばいいんだから、って。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
