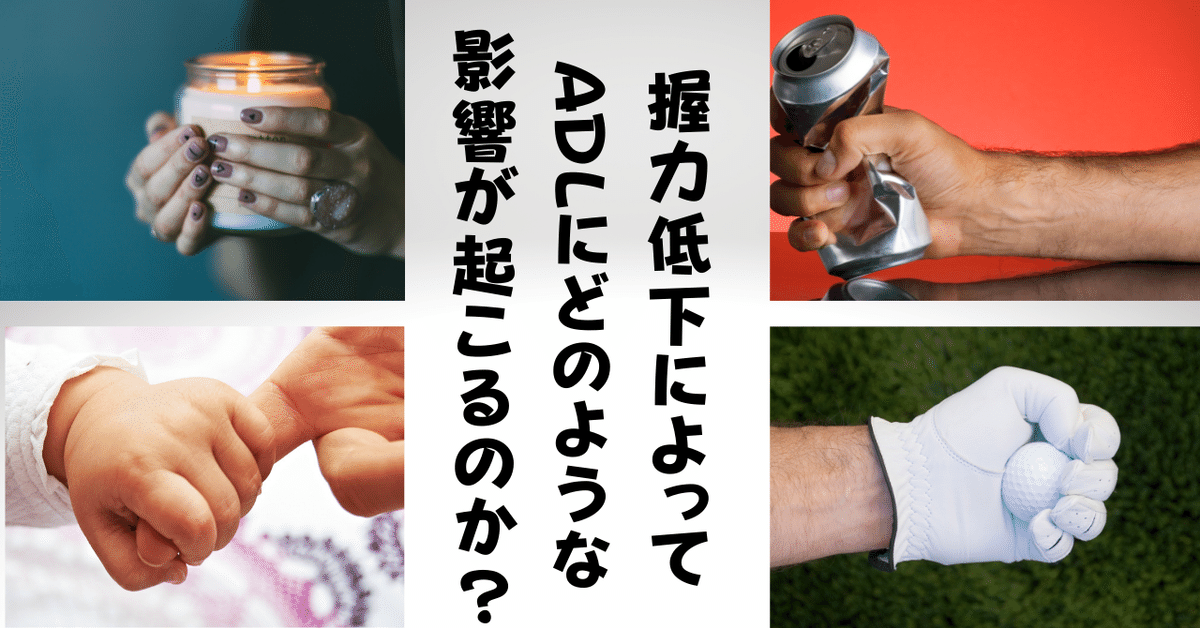
握力低下によってADLにどのような影響が起こるのか?
本日も「臨床BATON」にお越しいただきありがとうございます!
335日目を担当します、ミッキーです。よろしくお願いします。
BA5の影響が広がっていますね。1か月前には思いもしませんでした。
BA5とは 👇

皆様の勤務先は大丈夫ですか?
皆様と皆様のご家族、患者様・利用者様に影響が出ないことを祈っております。
◇はじめに
久しぶりにOTらしい投稿をしていきたいと思います💦
今回は握力低下によるADLへの影響について考えていきます。
高齢者では握力低下など筋力低下が将来その方のQOLに大きな影響を与えるというのは皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。
僕の勤務先でも要支援のデイケア利用者様に1か月ごとに握力等の評価を行っています(その他開眼片脚立位・TUG測定もあり)。
その時、僕は多くを考えずに
「前回と数値がそんなに変わってないですね、維持できていますよ。」とか
「今月は数値が上がりましたね!成果が出ていますね!」とか
言っていました。
体幹・下肢の筋力が落ちると寝返り・起き上がり・立ち上がり・立位保持といった基本動作に、歩行能力に影響が出てしまうことは理解がしやすいと思います。
しかしなぜ握力を測定するのか、握力が低下するとADL、IADLにどんな影響があるのかあまり理解できていませんでした。
そこで今回は
握力とは
握力測定はなぜ行うのか
なぜ握力が重要なのか、
握力低下によってADL(日常生活)にどんな影響があるのか
について考えていきます。
◇握力とは、年代別平均値について
まずは「握力」の定義についてお伝えしていきます。
握力(あくりょく)とは、主に物を握るときの手の力のことである。
現在では、主に以下の4つに分類される。
1.クラッシュ力(ものを握りつぶす力)
2.ピンチ力(物をつまむ力)
3.ホールド力(握ったものを保持する力)
4.ものを開く力
握力のうち1.のクラッシュ力は握力計を使って測ることができる。
2.のピンチ力を測定する、ピンチ力計も販売されている。
本格的に握力を鍛えるには、特定の部位の筋力を強化しようと思ったら逆方向の力も強くするというウエイトトレーニングの原則にのっとり、握る力同様に、4.の拮抗筋=ものを開く力を鍛えることが望ましい。ものを開く力というのは実際には役に立たない場合がほとんどではあるが、筋力のバランスをとる結果、怪我の防止にもつながるという利点がある。しかし、筋力のバランスを取ることは極めて難しく、大変なことである。
握力は,男女ともに青少年期以後も緩やかに向上を続け30歳代でピークレベルに達し, 他のテスト項目に比べピークに達する年代が遅い。

ただし今回の記事では握力についてクラッシュ力(ものを握りつぶす力)を表すものとしてお伝えしていきます。
ご了承ください。
◇なぜ握力が重要か

握力はサルコペニア(加齢に伴う筋力減少)やフレイル(虚弱)*詳細下記の評価基準にも採用されています。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
