
お産に安全以外のものを望む気持ちをどう表現するかの葛藤ーどうなるお産⑧番外編
さて、「どうなる?お産」をいつも読んでいただき、ありがとうございます。今回は同時に2本を公開します。なぜなら、ちょっと新聞紙面では伝えきれなかった、と思っている部分があるからです。今回はとても難しい回でした。
記事の中で、何度も何度も書き換えた箇所がありました。それは以下の部分です。
お産ができる施設が減る中で、望まない分娩誘発(陣痛促進剤の使用など)や予定帝王切開が、私の町でも増えていないか。(…中略…)
疑問をぶつけると、県の担当者は言った。
「あなたは出産に何を求めているの? 安全ではないのですか?」
実は、この質問に私は何パターンも答えを考えました。なぜここをそんなに書き換えたのか、長くなりますが、とても大切にしたいので、私の葛藤とともに、その過程を追ってみたいと思います。
始めて原稿にしたときに、私はこう書きました。
ある取材先で「あなたは出産に何を求めているの? 安全ではないのですか?」と聞かれたことが心に引っかかっている。
これまで、訴訟リスクを抱える産婦人科医が、母子安全に心を砕いて働く過酷な勤務実態を学んできた。なのに、申し訳ないのを承知で答えれば、お産に望むのは「安全第一。でもそれだけじゃない」。
私は妊娠した時、機械的に「お産」するのは嫌だと思った。出来るなら、自分の力で新しい命を生み出したいと願った。
県によると、2018年に助産所や自宅などで出産した人は46人、2019年は62人いた。昨年からはさらに、コロナ禍で病院での立ち会い出産ができない、家族の面会ができないなどの理由から分娩を扱う助産師への問い合わせが増えているという。検診を受診し、母体管理が順調であれば、病院以外の選択肢を選ぶ女性もいる。一方で、日本ではまだ1割に満たないが、合併症のリスクが指摘されていても「無痛分娩」を利用する人たちもいる。女性たちは「安全」だけで産む場所を選択しているわけではない。
最初に直したのは「機械的に」の部分でした。医療系メディアの編集をしている先輩に原稿を先に読んでもらった際に、
『現在お産にかかわっている医療者から見れば、どのお産も機械的に扱っているという意識はないと思う。「機械」という表現で、冷たい印象を与えてしまうので、「決められたルーチンに従った」や「医療者に任せるだけの」の方がいいかもしれない。』
とアドバイスを受けたことが理由です。私は、できる限り医療介入を望まない妊婦だったので、その心がここに透けてしまったと思い、先輩の指摘をありがたく思いました。そこで、まずは該当の個所を「私は妊娠した時、医療者に任せるだけの「お産」をするのは嫌だと思った。出来るなら、自分の力で新しい命を生み出したかった。」と書き換えました。
出稿後、担当編集者から以下のように戻ってきました。
県の担当者は言った。
「あなたは出産に何を求めているの? 安全ではないのですか?」
私の答えはこうだ。
「安全第一。でもそれだけじゃない」
妊娠した時、私は医療者にお任せの「分娩」は嫌だと思った。自分の力で新しい命を生み出す「お産」がしたかった。
県によると(略)
ここで私は「ウーン」と悩みました。なぜ悩んだのか。初稿と戻ってきた原稿を比べてみます。
「あなたは出産に何を求めているのか?」と聞かれた直後に初稿では
これまで、訴訟リスクを抱える産婦人科医が、母子安全に心を砕いて働く過酷な勤務実態を学んできた。なのに、申し訳ないのを承知で答えれば、と言い訳をしていた箇所がなくなり、私の答えはこうだ。「安全第一。でもそれだけじゃない」と強調されていたからです。
医療者に申し訳ないと思いながらも、心に引っかかかっている、と表現して「安全第一。でもそれだけじゃない」と控えめに出した答えを、医療者への言い訳(感謝の気持ちで)なしに堂々と伝えてしまっているところに違和感を持ってしまったのだとわかりました。
紙面は字数が限られています。デスクが意味を感じられない言い訳を省くのは当然です。私はなぜ、出産に求めるのは「安全だけじゃない」と強く答えることに違和感を持ち、医療者に言い訳をしながらも控えめにこの答えを出すのか、をもっと意味づけて伝えなければいけないと思いました。
以下に、紹介する記事では、漫画「コウノドリ」のモデルになった産科医が「正しい出産場所の選び方」を解説しています。
「イケてるお産」「安全か、アメニティか」…と言われてしまうと、なんだか、「安全第一、でもそれだけじゃない」と声を大にして伝えることが申し訳なく感じてしまいます。
実際、過去の記事で、産婦人科医の不足▽過酷な勤務実態▽一施設に集中する妊産婦▽高い訴訟リスクなどの現状を学んできました。そんな中で、「安全だけじゃいやだ」なんて、ただのわがままにも思えます。
そして、何より私が「安全だけじゃいやだ」と当然のように言うことを気を付けたいと思っているのは、決して母子安全に生まれてくることが世の中にとって当たり前ではないということを忘れてしまってはいけないと思っているからです。
国の調査(2019年)によると、日本全国で妊産婦29人、新生児755人が亡くなっています。世界(2017年)では、265万人の子が生後1カ月以内に亡くなり、妊娠中あるいは出産時に合併症により亡くなった女性は29万人以上にのぼりました。(ユニセフ)
母子安全は、現代でも決して当然ではない。日本の医療界が必死に築き上げてきた成果だということを忘れてはいけません。当たり前に母や兄妹が死んでいた過去を知らない世代が、安易に病院での出産や必要な医療介入を否定したり、「自然分娩は神聖で特別」と扱うことには気をつけたいと思っています。
だから、私は、出産に求めるものは「安全だけじゃない」と強く答えることに恐縮していました。
それでも、出産に求めるものが「安全だけじゃない」というのは本音です。そこで、以下のように伝えることにしました。
「あなたは出産に何を求めているの? 安全ではないのですか?」
私は答えに詰まった。
確かに国の調査(2019年)によると、全国で妊産婦29人、新生児755人が亡くなっている。母子がともに安全に産後を過ごせることが最善のケアだ。
それはわかっているのに、モヤモヤしてしまう。
県によると、助産所や自宅での出産は18年で46人、19年62人。最近はコロナ禍で、病院が立ち会い出産や面会を中止しているため、お産を扱う助産師への問い合わせが増えているという。母体管理が順調なら、病院以外を選ぶ妊婦もいる。
一方、日本では1割ほどだが、合併症のリスクがあっても「無痛分娩」を利用する人もいる。
女性は「安全」だけで産む場所を選んでいない。
終末期のビジョン「地域包括ケアシステム」には、かかりつけ医や病院、ケアマネージャーが個人に寄り添う「より良い死」を整えてくれる。
しかし周産期は、妊娠、出産、子育てそれぞれの支援に連続性がなく、県の示すビジョンもない。
私は「より良いお産(周産期)」も考えてくれたら良いのに、と思う。
デスクは、「前の方がよかった」と言っていました。夫も「なんか歯切れが悪かった」と言っていました。
字数の関係で、以下の箇所は削られました。
妊娠した時、私は医療者にお任せの「分娩」は嫌だと思った。自分の力で新しい命を生み出す「お産」がしたかった。
悩んだ結果の言い回しでしたが、ウーンやっぱり伝わりづらかったかなあ。
そして、なぜ、出産に求めるのは「安全」だけ、ではないのか。何を他に求めるのか。ここが一番大切なことです。安全以外を求めることは軽薄で不謹慎でしょうか。
でも、本音はごまかせません。私がお産に求めているものは「安全第一、でもそれだけではない」。
「そんなこといって、万が一のときには医療に頼るのでしょう? こんなに余裕なく働いている医療者に負担をかけるなんて軽薄すぎる。医療者に頼るなら最初から、医療者が仕事をしやすい環境を心掛けるべき。」
過酷な医療の現場を知れば、そんな批判もあるかもしれません。
でも実際、産むのは女性です。女性は産まないことも、選択できるのです。
女性が産まなくなったら、社会は存続しません。
多くの女性が「産みたい」と積極的に思える社会を構築することは、この社会を存続させていくために必要なことです。(念のため、自民党員がLGBTを道徳的に認めないなどと発言したこととは議論が違います。「産む」「産まない」は個人の自由であり、至極当然に誰を愛するかもまた自由です。そしてその価値観は誰かによって図られたりするものではないと思っています。ってなんでこんなに当たり前なことを書き加えなきゃいけないんだ。)
そのために、女性にとって「より良いお産」を考えることは軽薄なことではない、と私は思います。
それがある人にとっては「無痛分娩」かもしれないし、「自宅出産」かもしれない。
行政は「よりよい終末期」を整えるための「地域包括ケアシステム」を提唱しています。望めば、訪問看護や医療を自宅で受けながら在宅で死を迎えることも、緩和ケアを受けながら最期をホスピスで過ごすことも、先進医療を尽くして病院で亡くなることもできます。
同じように、「よりよい周産期」を過ごすためのビジョンも用意してほしいと思うのです。私が取材したときには、県が示す周産期のビジョンはありませんでした。病院の集約化は仕方ない、高齢化で診療所の閉鎖は仕方ない、と女性の選択肢が減っていくのを「仕方ない」で納得させ、「安全性」の一択を迫ることは個々の女性を尊重していないようにも映ります。
私は、「安全性」とは別の軸で「快適性」も求めたい。出産体験が、その後の産後うつ、育児困難感に関連するという研究もあります。
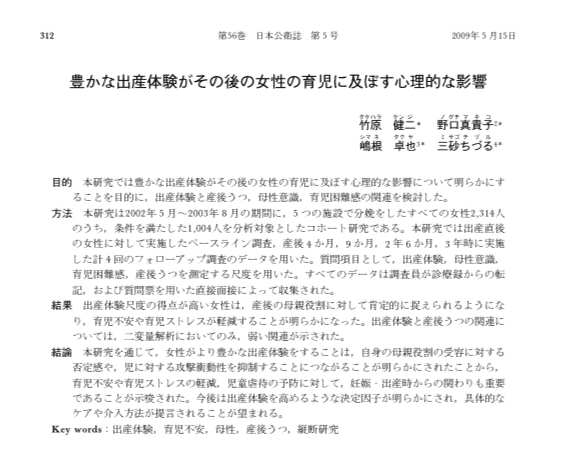
行政には、限られた医療資源の中で、「よりよいお産」を迎えるための連続性のあるケアや、多様性のある産み方を整える施策を、主体である女性と一緒に、考えてほしいと思っています。
投げ銭歓迎!「能美舎」の本もよろしくお願いいたします😇 ぜひ「丘峰喫茶店」にも遊びにいらしてください!
