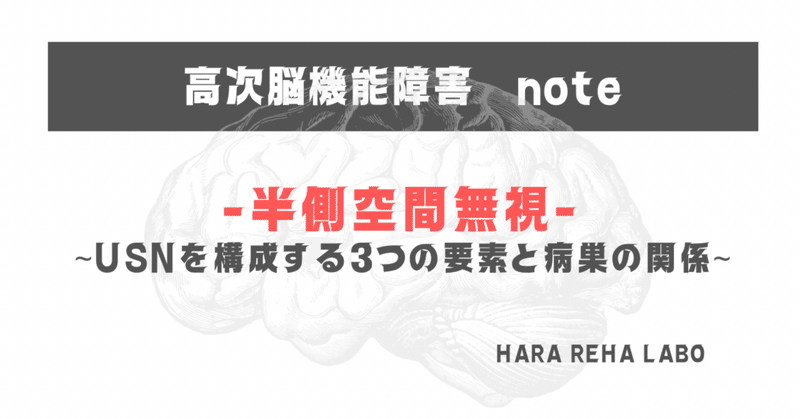
半側空間無視を構成する3つの要素と病巣の関係
お疲れ様です。はらリハです。
本日は…
「半側空間無視:半側空間無視を構成する3つの要素と病巣の関係」について解説します。
※ 引用、参考書籍
はじめに
半側空間無視は以下に定義されています。
「大脳半球病巣反対側に提示された刺激を、報告する、刺激に反応する、与えられた刺激を定位することの障害であり、感覚障害、運動障害では説明できないもの」と定義している
左片麻痺の方だと、右の脳に損傷を受けた結果、麻痺側から得られる情報(視覚/触覚等/聴覚)を受け取ることができないことです。
これらの症状が感覚障害、運動麻痺だけでは説明ができない場合に「半側空間無視」と専門的に表現します。
よく耳にするのは「左半側空間無視」であり、左側を無視する障害と臨床上でも捉える方が多い症状です。
ただ、それほど単純なものではなく、USNのメカニズムは様々な報告があり、方向性注意障害説/方向性運動低下説/表像地図障害説らが主であり、どれも混合して出現する可能性が高いとされています。
そこで、Verdonらが行った研究で、USNを3つに分類しているので、紹介します。
半側空間無視を構成する3つの要素と病巣との関係
タイプは以下、3つに分類しています。
A) 知覚性/視覚空間性要素の無視
B) 対象中心/物体中心要素の無視
C) 探索的/視覚運動性要素の無視

its functional components: a study using
voxel-based lesion-symptom mapping
Vincent Verdon,1,2 Sophie Schwartz,2,4 Karl-Olof Lovblad,3 Claude-Alain Hauert1,4 and Patrik Vuilleumier2,
これらの分類を「損傷領域/机上検査/症状」の3つで説明します。
A)知覚性無視
A) 知覚性無視
☑︎ 損傷領域:右下頭頂葉小葉(緑上回付近)の損傷
☑︎ 机上検査:線分二等分検査、絵画模写、文字読み検査で出現する
最も重症度が高く、左からの呼びかけや左半身への刺激などに対して全く反応できないタイプです。
反応が見られても、右側から与えられた刺激と判断したり、右側を向いたりなど、適切な反応を見せることができません。
また、左側への正確な追視や頭部、体幹の回旋を行うことができません。
B)対象・物体中心の無視
B)対象・物体中心の無視
☑︎ 損傷領域:右側頭葉(海馬傍回)の損傷
☑︎ 机上検査:Otaの探索課題、文章音読で出現する
病巣は右側頭葉の海馬傍回に中心を持ち、中側頭回に向かって白質内に伸びる病巣と関連したと報告しています。
この症状では、右側を向いていることが多いものの、左側の刺激へ注意を向けることができるタイプです。
A)とは異なり、ある程度、追視を行うことができ、身体への刺激や呼びかけに対しても左側から来たという認識ができることがあるが十分ではないです。
C)探索・運動性無視
C)探索・運動性無視
☑︎ 損傷領域:右下前頭回、背外側前頭皮質の損傷
☑︎ 机上検査:線分抹消試験、ベルテストで出現する
病巣は右下前頭回、より前方の背外側前頭皮質、中前頭後部と関連したと報告しています。
この症状では、左右両側へ注意を向けようとした際に、左側を無視するタイプです。
消去現象を半側空間無視に分類するならこのタイプです。
これは、左側への注意は左単体であれば可能であり、刺激への対応、追視もほぼ行うことができます。
これらの分類から、USNを呈した方に対してリハビリを行う上で「どのように無視をしているのか」「どこまでなら無視せずに処理できるのか」が重要になります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
