
【第1話】世界樹の迷宮Ⅱ マイギルド創作話【ギルド結成前編】
※本記事は、世界樹の迷宮ⅡHDリマスターをプレイしたときの体験をもとに脳内設定を膨らませて書いたものです。
※プレイ時に浮かんだ情景を一度アウトプットしたいと思って書き始めたのでほとんど自分用です
The dusk/深紅が墜ちる

Sahloinen・Ⅰ

ハイ・ラガードの冒険者ギルドを彷徨う影がひとつ、黒いオーラのようなモヤがかった輪郭のローブを纏い、力を感じる目つきと長い髪、その長さに勝るとも劣らないほどの銃身に禍々しい装飾の施された銃、外見からは男性とも女性とも区別のつかぬ「彼(か)」はいた。
この場所にいるということは加入できるギルドを探しているのだろうが、その目には鬼気迫るものがあった。
その目的は、世界樹のはるか上にたたずむという伝説を持つ城への到達、そして城の主を討つこと。その伝説はただ語られるだけの伝説にとどまるものではなく、彼は自身の五感に刻んだものを忘れることなどできなかった。
あのときはどれほどの時間落ち続けていたのだろう。それほどの高所から地へ叩きつけられても今こうして立っていられる。自分をこんな異形の性質に貶めた仇の居場所など、このハイ・ラガードまでどうやって堕ちてきたのかを思い返せば、判明するのは時間の問題だった。
「ガンナーか?いいだろう、名前を聞こうか」
「サーロイネンだ」
・・・明くる日、古跡ノ樹海1階から戻ったのはそのサーロイネンだけだった。
後日探索から帰った別の冒険者によると、4人の冒険者の死体と数多くの魔物の死体が同じ場所に横たわっていたという。人、魔物問わず、いずれにも強力な呪いの跡が見られたという。
それから、彼は死神と恐れられ、その通り名が引き入れてくれるギルドなどないことの証左となった。当のサーロイネンとしても、城の伝説を信じず野心のない者ばかりのギルドには最初からあてにしていないようではあったが。

それから幾月かが過ぎたが、いまだ弾が詰まったような足取りで冒険者ギルドの石床を踏みわたる彼の姿があった。城への執念が消えることなどあり得なかったが、1人で成し遂げられることではないというのは彼自身も理解していた。
皆意識して彼を避けていたので誰も知らないことではあったが寝食はどうしていたのだろう。その(あえてこう表現するが)生態について一部興味を持つ者もいたが、彼の通り名が示すリスクがあまりにも大きすぎる。
当のサーロイネンも流石に精神的に応えているようで、時折やつれた表情や疲れを見せることがあった。
〜♪
そんな折、声が聞こえてきた。
歌っているのだろうか、幻聴のようにすら聞こえる儚い声。
彷徨っていたこの数ヶ月では聴いたことのない声だった。
まずは城を信じている奴ならなんでもいい、と、運命に導かれるかのように、声のする方へ近づいていく。。

The storm/しずけさのあと
Myhinpää・Ⅰ

ミヒンパーは、遠く栄えた首都の出身だった。衛生兵である両親の支配に反発して単身この北国にやってきた。
いつの日か診療所に訪れた詩人とその音楽にえらく魅入られたらしい。このまま親が望むように衛生兵になったとしても、幼い頃から目に映してきた光景をただ繰り返すだけのように思えて、すべてが予想できると感じた途端につまらなく思えてしまったのだった。
歌という「個人にしか出せないスキル」を求めて、この道へ進もうと決めたという。
魔物との戦いの場においては、歌によって人の能力を引き上げたり、人の傷や精神を癒したりする歌い手がいると聞き及んでいる。彼は自らもその場に置き、自分の歌に宿っている可能性を開かせたいと考えていた。
この日はハイ・ラガードの冒険者ギルドで歌っていた。迷宮に挑む仲間を募るために自らの武芸などの得意技を披露する者も多くいるがそのうちの一つとして認識されていた。
・ ・ ・
Sahloinen・Ⅱ
突然、嵐の吹き荒ぶような歌声に変わった。冒険者ギルドの全員の視線が一点に集まる。さながら台風の目。ここが樹海なら、その歌声は聖騎士の挑発仕草の如く魔物の注意までも引き付けていたことだろう。
しかしあの身なりは何だ?パラディンというには軽装すぎ、ブシドーらしき刀を得物としている風でもない、歌を披露してはいるが、バードが持つような楽器の類も見当たらない。
ただ、この音からは確かな闘気と生命力を感じる。
こんなにも闘気が沸き立ったのは、ここよりも遥かに上の石床を踏み歩いていたとき以来だった。
サーロイネンはその場から離れることができなかった。
自分の中で別の何者かが蠢くのを感じた。来た、まただ・・・!
・ ・ ・
Myhinpää・Ⅱ
皆の注目を一気に集める快感。それがまだ長くは続かないのは課題だが、自分の歌の潜在能力を自覚するには十分だった。
視線が一つまた一つと外れていく中で一つ、突きつけられた銃口のようにすら思える、鋭く、情念をも感じ取れそうな「彼」はいた。
結局その日は深夜、人が捌けるまで歌い続けていたが、よほど気に入ったのか、最後の一人になるまでガンナーらしき彼は残っていた。
嬉しくなって、その1人のためだけに今日最後の曲を歌おうと息を吐いたとき、不意に殺気を感じ取り、吐きかけた以上の量を吸い込み手に持っていたものを構えた。
術式を用いた銃弾を弾いたのは、先ほどまで歌声を込めていた杖、というより巫剣。親元から反発して離れたミヒンパーではあったが、強制が嫌いというだけでそれまで身につけていた医術も無駄にはせず、ドクトルマグスとしてやっていくことにしている。
顔を上げる。さっきまで俺の歌を聴いていた(?)「彼」は、続けざまに見たこともない術式の弾丸を撃ち出して、自らも突進してきた。
状況整理よりもまずは呼吸を整え直し、身に染み付いたパフォーマンスのまま巫剣を振り回して、二丁の巨大な銃身をいなす。両方をいなして隙をつくったところで、巫剣の先に取り付けた珠を顔の前にあてがい叫ぶ:「俊足化」
・ ・ ・
Kakaristo・Ⅰ

「あれが、真の姿か」
東国風のブシドー然とした出で立ちの女性が呟く。目標の登場を待ち続けていた狙撃手のように、目を細める。
二丁の巨大な銃を持った、黒いローブを纏った見たこともない魔物と、一人誰かが戦っている。相当な速度で応戦しているようだが、呪術の類での強化によるものだろう。そう長くは続かなそうだ。彼の巫剣もついには銃身を防ぎきれず、銃口が向けられる。
仕方ない、加勢するとするか
彼女は腰を落とし、雪のように白い髪の間から獲物の動きを鋭く見極め、鯉口を切る構えをとる。抜刀したと思った次の瞬間にはすでに納刀されていて、二丁巨銃の魔物の背後に氷の刃が飛んできていた。
魔物は振り返り、もう一丁の銃でその刃を砕く。
Interval/逢魔が時
Myhinpää・Ⅲ
目を離した隙にミヒンパーは死角へと逃げのびた。得物の巫剣が別の冒険者の得物と触れ合う。
いかにもブシドーといった身なりの女性。
「さっきの抜刀氷雪はお前か?」
「きみ、皮硬化は使えるか?精霊の守りは?」
思いがけない言葉に一瞬戸惑ったが、言葉に詰まりながらも肯定する。
こちらの所持スキルを見抜いたこと、ブシドーにしては明らかに異質な雰囲気を漂わせているところから只者ではないと悟った。
「なら、これを」
差し出されたアムリタを流し込むとミヒンパーは再び前線に出向いた。
俺が耐久して時間を稼いでいる間に大技を喰らわせるつもりなのだろうが、先ほどの氷刃も対処されたので一体どうするつもりなのだろうか。
ただ、先刻俺の歌を確かに熱心に聴いていた「彼」から、今は目を離すことができなかった。
「解析できたぞ、さがれ!」
さっきの女の声が聞こえてきた。
言われるがまま、巫剣を下から回し床に叩きつけて反動で後ろに下がると、次の瞬間には俺と魔物の間の床に彼女の得物の刀が鞘ごと突き刺さっていた。
その鍔から魔物の両銃へ2本の紫電が走り、動きを鈍らせる。続いて2本の紫の糸は次第に角度を狭めていき、本体を一条の光で直撃した。
魔物は、その体の大きさからは拍子抜けする程度の控えめな音とともに崩れ落ちた。
白髪の女は刀を拾い振り返る。
「おい、そいつは、、まさか死んだりしてないよな??」
「魔物の心配などしている場合か。すぐに回復しろ。」
きついあたりに反抗して、さっきまで歌を聴いてくれていた(少なくとも自分にはそう見えた)一人のことを訴えかける。
「案ずるな。しばらくはあのまま倒れているだろうが、本当の意味であいつを斃すのは私たちには無理だ。」
次起き上がったら、古跡ノ樹海の入り口まで誘導してたたく。それが彼女の提示した作戦だった。あいつを正気に戻す方法はないのか問いかけたが、どうやら考えがあるらしい。
それまでに誘導できるだけの体力と、巫術の準備をするようにとのこと。影が小さくなっていく魔物を尻目に、準備のあいだ彼女の話に付き合わされた。
「ミヒンパー、きみは最近ハイ・ラガードにやってきたようだが、入国証は?・・・・・、持っていない、か。」
面倒な雰囲気がして片目を細めたが、彼女の次の一声は意外にも明るいものだった。
「なあ、わたしとギルドを組まないか」
このカカリストと名乗った女、聞けば、世界樹の伝承に尋常でない興味があるようで、攻撃一辺倒な能しかないので護衛役や回復役を探しているという。先ほどの落ち着いた対応を見ると、とても攻撃一辺倒とは思えず色々と勘繰れそうなポイントはあったが、迷宮の冒険を通して歌の道を極めたいという目的に対してはさして障害とはならなかった。
まだ慣れない彼女のテンポに半ば乗せられつつも承諾する。
「そうか、乗ってくれるか。」そう言って彼女は世界樹の謎や伝説の話を捲し立てる。
世界樹、聖杯、伝承、、、自身もそういったロマンのあるものには心躍る自覚があったが、彼女はそれ以上に思えた。心臓が血液だけでなく好奇心を身体中に送り出しているような、そんな人物にも思えた。
夜もだいぶ更け、そろそろ本当にさっきのリスナー(勝手にそう呼ぶことにした)を倒してしまったんじゃと不安の芽が出始めていた。
The dawn/火を灯す
Myhinpää・continued
「ーとまあ、こんなふうに、この伝承を真剣に追い求めている同士を募っているんだよ。例えば、アレみたいに。」
そう言って目線を流した先では、件のリスナーは消えるどころか、むしろオーラを増し立ち上がろうとしていた。心のどこかにわずかに火が灯った感覚を覚えた。
魔物は片方の銃を上空へ向けて、轟音を鳴らした。
カカリストはさっきまでの顔つきを変えた。「くるぞ。ミヒンパー!」
饒舌と冷静さ、熱中と視野の広さを併せ持つようなカカリストの言動に、ミヒンパーも完全にスイッチを切り替え、巫剣の珠を口もとにあてがう。

無数の銃弾が空から降ってきた。
轟音と張り合うかのように叫びをあげ、彼女に俊足化・鬼力化をかける。
彼女は目にもとまらぬ剣技で鉛の雨を捌いている。
というか彼女、刀をほとんど鞘に収めたまま空中を斬っていないか??
それでもまだ鉛の雨は止まず、じわじわと後退を余儀なくされる。
この猛撃では誘導の余裕など無かった。
隙を見て自自身にも強化を掛け、なんとか流れ弾を捌いているが、一撃一撃が、重い。巫術による強化なしでは、手足が痺れてろくに動けないだろう。
聞いたことがある。追い詰められたガンナーの発揮する銃撃術には時として敵を圧倒する物量攻撃があると。確か至高の魔弾と呼ばれていたー
魔物は両の銃を交互に撃ち尽くす。ミヒンパーの歌唱式の巫術にアドリブをねじ込むがごとく応酬が続く。
手練れの銃士一人が一度の戦いで出せる最大火力を幾度も続けて放ってきているようにすら思えた。
このままではもたない、そう思った矢先、目の前で鉛の雨を捌いていたカカリストの人影が傾いて小さくなった。しまった、ダメージを受けすぎたか。今のパートをまとめあげ、すぐに癒しをもたらす旋律への移行を、と息を吸った。
そのタイミングを待っていたかのように、彼女は一瞬口角を上げ射線から消えた。
癒しの巫術はそのまま目の前にいた魔物に直撃した。
1小節すぎたのち何かを理解したミヒンパーは、そのまま魔物に向かって歌い続けた。
魔物にとりついていた、もやがかった黒いローブのようなオーラはしだいに落ち着き小さくなっていった。
Not a crimson/紫立ちたる
Sahloinen・Ⅲ
ああ・・・また・・・なのか・・・?
蠢きが治ったあと最初に見るものは、いつも決まってくすんだ赤色だった。
・・・
しかし、今回は何かが違う。鉄のような匂いは伴っていない。
おそるおそる目を開く。今まで感じたことのない感覚が流れる。いや、むしろ、なくしたことのない感覚をなくしたという方が近いかもしれない。
自分の中で蠢いていたものの感覚は、おさまったというよりそのまま体外へ抜け出したという方が適切といえた。
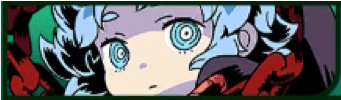
視線を上に移すと、朝焼けの色のような紫がかったローブを纏ったこどものうしろすがたが映った。見たことはないはずなのに、なぜかずっと昔から知っているかのような感覚があった。
その奥で、その子に背丈を合わせるよう屈み込んだ、紫の髪を後ろで結んだ男が、その子の顔を覗き込み、歯を見せてにっと笑う。
大型犬を可愛がるかのように、その子の頭をわしゃわしゃと掻き回し、歌を聴いてくれたことへのお礼を口にしていた。
「Harju…」その名前は勝手に口をついて出た。
その子はこちらに振り返る。純真であどけないこどもそのものの表情だが、その吸い込まれるような同心円状の瞳には底の見えない恐怖の予感すら覚えた。
裏の考えなどまるでないと思える調子でその子は口をひらいてこちらに問いかける。「ね、いい歌だったね?また一緒に聴こ?」
相対して感覚が確信に変わった。間違いない。この子は明らかに自分の中にいた…!
「お前も俺の歌を聴きたかったんだな。」
ミヒンパーと名乗ったその男は、2人へずっと歌を聴いてくれていたことへの感謝を述べた。
状況から、自分がこの男と戦い、解呪されたと推測したが、そんな戦いや呪術のことよりもまず歌のことを口にするこの男…
歌、か・・・
差し出された右手に、こちらも右手をのばしようやく立ち上がる。
常人には理解できない状況のはずだが全く動じないどころか、楽しんでさえいるようにも見える。もしかして彼なら…
繋いだ右手にさらに左手を重ね、この数ヶ月実ることのなかった言葉を紡ごうとしたとき、視界の左右からさらに2人の手が重なった。
・ ・ ・
Kakaristo・Ⅱ
そうかそうか!一緒に来てくれるか!世界樹の迷宮に!
サーロイネンへの対処で受けた傷は浅くはなかったが、それでも今は大いなる知識への扉が開かれたことに対する興奮の方が勝っていた。
人、魔物、呪い、歌、命、、、天空の城にたどり着くまででも好奇心が途切れることなど考えられない!
手を取っているミヒンパーとサーロイネンに、横からさらに手を重ね、奥にいたハリュー(確かそう聞こえた)の手も引き、4人で手を合わせる。

「おい、こいつらも迷宮探索に付き合わすつもりか?」所構わず歌う割にはちゃんと話し合う必要のあるやつだなと思ったが、説得の必要は無かった。サーロイネンの方から迷宮に連れて行って欲しいと要請があった。その特異な体質、私と同じように伝承を求めていること・・・聞きたいことは山ほどあるが、、これ以上は道中の楽しみにとっておくこととした。
ハリューはというと、こちらの体や周りの状況を見て気づいたように小さく口を開き、申し訳なさそうに少し俯いた表情を見せた。サーロイネンよりも魔物に近い存在に思えたが、コミュニケーションを取ることは可能なようだ。
ハリューの表情とミヒンパーの疑念を払拭するように伝承の話を始める。
ハリューの表情が明るくなり、それにつれてミヒンパーもやれやれといった感じで表情を戻した。サーロイネンは終始真剣な面持ちで聞いていた。
それからのことは興奮であまり詳細に覚えていなかったが、城の伝承の話題に花を咲かせていると夜が明けてきたので顔を出してきたギルド長にことの顛末を話し(もちろん魔物のことは伏せて)、ギルドを結成すると申し出た。
手続きのあまりのスムーズさにミヒンパーとサーロイネンは戸惑っているようだったが気にしてはいられなかった。
やはり冒険者ギルド内の惨状についても聞かれたが、サーロイネンと夜通し模擬戦をしていたと言っておいた。死神という通り名を持つようなやつだ。出まかせもなんとか受け入れられた。
かわりに今日このあとは後の片付けもすることになったが。ミヒンパーが。
>「俺かよ!」
宿の一室で"模擬戦"の傷を癒しつつ、5人目について考え筆を取っていた。
5人というのは、冒険者ギルドから勧められている迷宮探索パーティの人数で、力を合わせつつ指揮系統の混乱も極力抑えられるバランスの取れた人数らしい。
歌、か…おもしろい。私も迷宮に挑むのは久しぶりだし、5人目にはあいつを呼ぼう。ミヒンパーたちと合わせれば、お互いにとっていい刺激になるだろう。それに、あいつの歌が、また聴きたい。
彼と連絡をとるなんて一体いつ以来だろう。書き出しは、、、
・ ・ ・
つづく
*つづくよな?
References
次の話↓
プレイヤー目線でのプレイ記録↓
@sq_tale
— flavan (@DFyMgBb6awNae9k) December 22, 2023
マイギルドのポニテマグス、メディックの家系→反発してバードを目指す→ドクトルに落ち着く、という経緯なので、巫剣をマイクに見立てて歌いながら巫術を発動する設定。
※参考(from bayonetta3) pic.twitter.com/V7Qx4SPlIo
@sq_tale
— flavan (@DFyMgBb6awNae9k) March 10, 2024
雷の術式とかこんなんでもいいんでないという妄想(DMC5・ダブルチェック) pic.twitter.com/s1UORACj4J
@sq_tale
— flavan (@DFyMgBb6awNae9k) March 13, 2024
自分の頭の中の強斬の術式のイメージ大体これ pic.twitter.com/f4snMBvqW1
・余談
カカリストはもともとハイ・ラガードNPCの面々とそこそこ交流がある設定。ゲーム内でこの会話を見たときに結成時の様子が思い浮かんで書き始めました。解釈一致ってやつですね。

で
プレイした時の体験を元にとか言っておきながらまだ樹海入ってないですねこいつら…5人目もまだ登場させてないですね…
この調子・書き方で次回以降も書き続けるかは分からないものとする(保険)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
