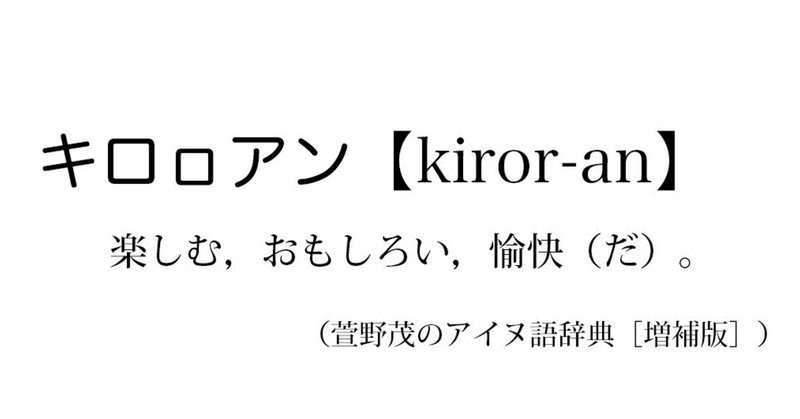
【備忘録】2018年11月16日 アイヌ文化公開講座キロロアン「メディアの中のアイヌ」講師:中川裕@アイヌ文化交流センター
覚書として置いておきます。照明を落とした状態でのメモ書きを元に執筆。聞き間違い、書き間違い、記憶違いがあるやもしれません。
案内メールに添えられた文は「アイヌ民族をとりまくメディアの動きはこれまでと大きく変わってきています。漫画「ゴールデンカムイ」などの登場によって、これまで関心を持っていなかった層もアイヌに目を向けるようになってきました。今回はアイヌ民族とその文化に関する正しい知識の普及のために、さまざまなメディアをどのように活用していくべきかなどをお話しいただきます」。
ただし厳密には「メディアをどのように活用していくべきか」といったテーマには踏み込まなかった。
1959年の映画「コタンの口笛」から、現在進行中のコミック「ゴールデンカムイ」まで、主だった映画とコミックを紹介しながら、常に関心の中心にあったのは「監修者」の存在。
アイヌ文化に精通した監修者がいるといないとでだいぶ隔たりのあることを、さまざまな作品を通じて検証する内容となった。
児童文学の映画化である「コタンの口笛」(1959年)は、巨匠・成瀬巳喜男の監督になる映画でありながら、いまだに一度もソフト化されていないという。ためにアイヌ文化を監修した者が誰であるのかわからない(今回の講義ではYouTube上にアップされた、伊福部昭の音楽紹介動画、もとい静画を、スクリーンに映して説明)。ただ、映画は舞台である千歳でロケをしっかり行なっているし、少年が川でサケを獲る場面ではマレㇰを使用したり、墓標に底の抜けた桶を通したりと、かなり正確な描写をしている。と同時に、墓標に花や白米が供えるといった和人の風習が混ざっているのが、アイヌ文化と和人文化の混淆を示していて、そこにリアリズムを感じさせる。
(アイヌ文化の伝承に務め、中川氏や片山龍峯氏の協力者として何冊も著作に参加した中本ムツ子氏が、主人公・畑中マサのモデルだという話を伺ったが、びっくり! 足の悪い教師・中西先生は実兄がモデルであり、酒に溺れて最後は倒木の下敷きになって亡くなる父親は実の父がモデルだと。本当なのでしょうか?)
武田泰淳の長編をその発表年に映画化した「森と湖のまつり」(1958年)では、アイヌ関係に多数の著作のある更科源蔵が監修しており、フチたちがウポポを歌う場面など描写に無理がない。ただ、元来は冬に行われるイオマンテを夏に行なっているのは撮影時の都合か。
「コタンの口笛」では森雅之、宝田明、山内賢、志村喬、「森と湖のまつり」では高倉健、三國連太郎、香川京子など、錚々たるトップスターがキャストを務めているが、アイヌに対するイメージは60年代70年代になると変化する。過激派と結びついて考えられるようになる(わたしは太田竜とか思い出しました)。
手塚治虫のコミック「シュマリ」(1974〜76年)は、そもそもの構想では主人公シュマリはアイヌと和人の混血だったのが、圧力を受けて出版社がビビり、設定を変えざるを得なくなった。ために主人公の性格が曖昧になり、作者も「失敗作」と断じてしまう出来に。アイヌはほとんど前景に出て来ず、ポン・ションと名乗る孤児のアイヌ少年が目立つ程度。赤ん坊はすべてpon sion(小さなウンチの腐ったもの)と呼ばれるから、そんな名前あるかとシュマリが難癖をつけるが、本当の名前をつける前に親がいなくなったことを示していて、手塚もそれを知っていたことになる。それでも、協力者や監修者を得られなかったことがこの作品の敗因に違いない。
(なお「シュマリ」には、榎本武揚が隠した埋蔵金の地図を背中に刺青にして逃げた者がいるというエピソードや、土方歳三が実は生きていたというエピソードがあるが、「ゴールデンカムイ」はそれに対するオマージュではないかと中川氏)
石塚啓の「ハルコロ」(1989〜91年)は、原作は本多勝一だが、監修の萱野茂の著作の影響が大きく、萱野茂の集大成といった観がある。舞台はコシャマイン戦争の前の時代で、アイヌしか出て来ず、恋の鞘当てが前面に押し出されるなど少女漫画的な印象も。
武井浩之「シャーマンキング」(1998〜2004年)は世界中のシャーマンがナンバーワンを争う少年漫画で、登場人物の一人としてアイヌのシャーマンが登場する。彼の使う技に「カムイランケオプケニ」というものがあり、「神から授けられた拳」と説明されるが、「こぶし」は「こぶし」でも「opkeni」は植物の「こぶし」。意味は「おならのする木」で、枝を折ると臭いらしい。つまり「神から授けられたおならの木」になってしまう。
けれど、これもきちんとした監修者がいたら避けられたこと。週刊誌漫画はスケジュールが慌ただしく、中川氏が関わっている野田サトル「ゴールデンカムイ」(2014年〜)にしてもチェックは不可能。掲載されたコミックを見て初めて内容を把握する状態。
ただ「ゴールデンカムイ」がアニメ化するにあたって、漫画で気になっていた箇所の修正を試みたと言う。
①コミックでは「おいしい」という意味で誤用されている「ヒンナヒンナ」は「どうもどうも」といったニュアンスの、物をいただいた時(食べ物に限らない)の感謝の表現。アニメではアシㇼパがお椀を何度か上げ下げして「ヒンナヒンナ」と唱えさせた。ただ、その腕の上げ方がアニメではやや高い。実際はもっと軽い上げ下げだとか。
②コミックで、カジカ(?記憶が曖昧)をもらったフチが首の後ろにそれを回すシーンで「サッサ」という擬音が添えられているが、それではなにが起こっているかわからない。中川氏は自分の経験をアニメに反映させた。取材の謝礼でアイヌのフチに三千円を渡したところ、そのフチが千円札を一枚ずつ右手でつまんで、左の肩から首の後ろにぐるりと回して、そこに宿っている憑神に見せたのだ。これは前回の中川氏の講演で、実際のビデオを視聴した。
③タタキを作る際は「チタタㇷ゚」「チタタㇷ゚」と声に出して唱えなくてはいけないとアシㇼパは言うが、実際にはそんなことはないというので、これはアニメでも修正できなかった箇所か。
④コミックでは、アシㇼパが鶴の舞を踊るが、アニメではそれを実際の動きと音声として表現しなければならない。中川氏は声優陣を連れて大久保のアイヌ料理店「ハルコロ」を訪店し、釧路出身の宇佐氏からそれを伝授してもらった。「指導」としてクレジットが入るべきところが、実際の放送では入っていなかった。監督は忘れたのか? ソフト化されたときは必ず入るようにすると中川氏。
⑤コミックで、狩ったヒグマを山から下ろしてくる場面で、男性と女性がそれぞれ異なる掛け声をあげるが、これもアニメでは声優に実際にやってもらう必要がある。男性の「フホホホーッ」と女性の「オノンノオノンノ」をビデオを見て練習してもらうが、やりつけていないとなかなか難しい。最後までできなかった人もいるとか。これは来週(11/19)の放映。スクリーンに当のビデオが映し出されるが、「オ〜ノンノ オ〜ノンノ」と節をつけて歌われる。初めて聞いた。
最後に中川大先生による本日のまとめ。
「コタンの口笛」「森と湖のまつり」でアイヌは「滅びゆく民族」としてマイナスなイメージで描かれていた。
「ハルコロ」は現代と切り離された時代のアイヌを描いていた。
「ゴールデンカムイ」はアイヌと和人が対等に協力し合い、「たくましくかっこいいアイヌ」を描いていると評価。
正確に一時間半の講義。充実した内容であり、無料で聞いて申し訳ないような気分でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
