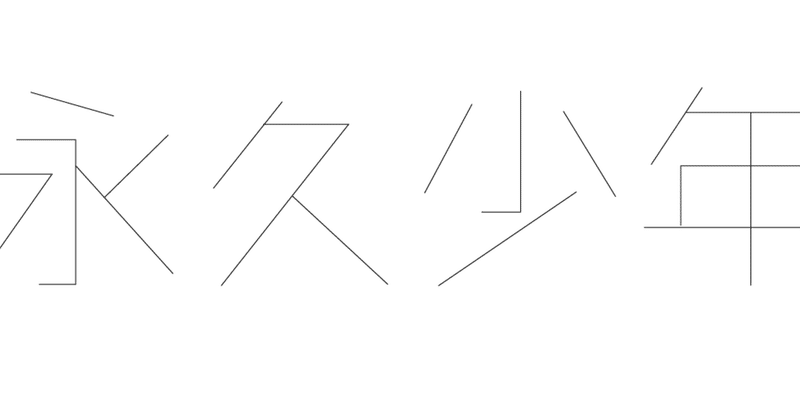
6.逆効果かも
翌日もハジメくんは猛烈に勧誘を続けた。これまでの成果に満足していなかったからだ。「年とらないんだよ」「死なないんだよ」「苦しくないんだよ」と言えば、希望者がわれもわれもと詰めかけてくるかと思っていたのに、永久少年(および永久少女)を申し出たのはほんのわずかにすぎなかった。
昨晩は、一人だけになった自宅でひたすら「セブンス・コンチネント」ごっこをしていた。「セブンス・コンチネント」は家じゅうのものを徹底的に破壊して、最後は家族三人が自死してしまう映画だったが、壊すことがあんまり楽しそうに描かれていなかったし、みんなが死ぬのもがっかりだった。だから、ハジメくんはアハハ! アハハ! 盛大に笑いながら、ガラス器陶器をたたき割り、布団の綿をぶちまけ、ケチャップ、マヨネーズ、タバスコを振りまいて、だれも死なない未来を思い描いたのだ。
「まだ様子を見てるんだろうか。自分の目で見たことが信じられないんだろうか。もうちょっと時間が必要なのかな。もうちょっと証拠が必要なのかな。これまではぼく一人だけががんばってた。でも、仲間はもう二十人も三十人もいる。それくらいのおでこはたたいたぞ。その全員で永久少年なこと永久少女なことをすれば、みんなも考え直してくれるはず。こりゃいいな! ぼくもぜひ! わたしも永久になっちゃお! って」
意気込んで学校に来てみれば、校門のわきには先生方がたむろっていた。ハジメくんが登校児童の間をすり抜けながら通りすぎると、「おい!」「ハジメだ!」「来ちゃったぞ!」と叫んで、泡食って追いかけてくる。先生方はたぶん、ハジメくんがどうせ遅刻してくるものと高をくくって、のんびり構えていたのだろう。その分を取り返そうとするかのように、鬼の形相で迫ってきた。その数、十人。
追いかけられたら逃げればいいし、逃げるのは楽しかったけれど、これではろくに勧誘している時間がない。永久少年ハジメくんの活動は三日目にして、大きな困難に直面したのだ。「とりあえずは逃げて逃げて逃げて様子を見るしかないな」ハジメくんは思った。「自称先生の人たちはそのうち、みんな疲れちゃうだろうし」
だから、ハジメくんは廊下を全力でダッシュし、階段をほとんど転げ落ち、窓を使って校内と校外を出入りし、体育館から用務員室までを繰り返し何度も周回し続けたのだ。
一度、放送室に立ち寄って、本日の営業形態について手短に告知した。「今日はものすごい追われてて、立ち止まってる暇がないんだ! とりあえず校内をぐるぐる走ってるから、見つけたら声かけて! 永久少年にしてくれとか永久少女にしてくれとか、できるだけ大声で言ってくれたら、そっち行くから! そのとき、おでこを突き出してくれたら、すぐにゴツン! やるからね! すぐに永久になれるからね!」
永久の持久力を持つハジメくんが耐久走で先生方に負けるわけはなかったが、スピードに関してはそうはいかない。危うく追いつかれそうになったことが何度もあり、そのたびに急ブレーキをかけたり、Uターンしたりしてやり過ごした。待ち伏せされて挟み撃ちにあうのも危険だったが、そのたびに手近の教室に飛びこんだり、窓から飛び降りたりして難を逃れた。追ってくる先生方は主に元気みなぎる若い先生ばかりだったが、疲労の蓄積は避けがたい。校内を五周するころになると、先生方の数は半分に減った。それでもなお食らいついてきた先生方も、校内を十周するころになると、歩くのがやっとという状態に陥った。滝のように汗を流し、嵐のように髪乱し、泥酔したみたいに千鳥足で歩いていた。
これではつまらないとばかりに、ハジメくんは水道の蛇口に手のひらを押し当てて、倒れた先生方に水ビームを食らわせたり、雑巾バケツに貯めた水を直接浴びせたりして励ましたが、元気を取り戻したのはほんの一瞬にすぎなかった。「この野郎!」「ふざけんな!」と叫んで再び猛烈に走りだすものの、百メートルと続かない。
「かわいそうに」ハジメくんは思わずひとりごちた。「ちょっと走っただけなのに、もう死にそうな顔してる。貧弱。軟弱。脆弱。虚弱。こんな人たちにぼくらの未来はまかせられないなあ」
「ハジメくん」その中で一人、うつ伏せになった状態で手をのばしてくる先生がいる。今年、大学を出たばかりの若いネムロ先生だった。「ぼくも永久にしてくれよ」
これにはハジメくんも驚かされた。大人を永久にするなんて、これまで夢にも思わなかったのだ。一緒に遊ぶことのできる存在のことが念頭にあって、それは当然ながら年の近い子供たちだった。それに、そもそも永久を申し出る大人はこれまで一人もいなかったではないか。
「なりたいの?」新たな可能性に目を見開かされる思いで、ハジメくんは尋ねた。なりたいというなら、ならせればいい。なりたい動機があるのだろう。思えば、この先生、いつも自信なさげだった。児童からも軽く見られて、陰では「ネムロくん」と呼ばれていた。一所懸命勉強して教師になったものの、居心地は悪かったのかもしれない。
「永久少女があったんだもの。永久青年がないともかぎらない。永久青年になりたいの?」
「永久青年にしてくれよ!」ネムロ先生の声はかすれていたが、その勢いは本物だった。
「きみはもう永久青年さ」
ゴツン!
「痛い」ネムロ先生は小さく抗議した。「もう少しお手柔らかにできないかな」
「ここは思いきりが肝心なんだよ。第一、遠慮する意味がないでしょ。空手で瓦を割るときみたいにバシッと行かなきゃ。動くなネムロ! エイ! ヤア! トウ!」
ゴツン! ゴツン! ゴツン!
「痛い痛い痛い! もうやめてくれよハジメくん!」
ネムロ先生は両腕で頭を抱えこんで、ダンゴムシのように丸まってしまった。
念のためにほかの先生でも試してみた。とりわけ死にそうな顔をした人の前に立って、「その苦しみから解放しよう。今すぐ楽にしてあげよう。永久青年になりたい。そう唱えなさい」と持ちかけた。
ゴツン! ゴツン! ゴツン!
「痛えよ!」「やめて!」「殺す気か!」
結果はすべて失敗だった。
「年齢制限があるのかな」ハジメくんは首をひねった。「十二歳以下を差別するPG12ってのが世の中にあるけど、その逆でナントカ12ってあるのかもしれない。逆だからGP12かな。本当に十二歳までかどうかは知らないけどさ」
討ち死にした先生方を尻目に、ハジメくんは先生の姿の消えた校内を練り歩いた。
ほとんどのクラスが自習になっていたが、真面目に自習している児童はごくわずかだった。仮にそういう意欲を持っていたとしても、周囲がこんなに騒がしくては無理だろう。委員長や生活指導係の児童、道義心いっぱいの児童、正義感あふれる児童が孤軍奮闘しても無理だった。
廊下の水飲み場やトイレでは蛇口という蛇口が全開になっていた。躍起になって止めてまわる児童もいたが、そのまたすぐ後ろから全開にして歩く児童がいた。洗い場にあふれた水は滝となって滑り落ち、廊下をじわじわ進行し、階段を一段一段下っていく。先生方がまた追っかけてきてくれないかなあとハジメくんは考えた。水をバシャバシャはじきながら、にぎやかに走り、時に転んで悪態をついたり、階段を滑り落ちたりしたら、さぞかし楽しかろうと思ったのだ。
ガシャン! ガシャン! どこかしらでガラスの割れる音が続いた。学校にはガラスがたくさんある。ガラスだらけだと言っていい。拳で割るのもいいし、蹴飛ばして割るのもいい。椅子をぶつけて、バットを振るって、割るのもよし。ガシャン! ガシャン! 永久の児童でないなら、このガラス片の中を歩くのはさぞかし大変だろうとハジメくんは同情した。抜き足差し足で歩かなくちゃいけないし、へたに転ぼうものなら血まみれなのだ。
「ハーイ」と片手を上げてかたわらを通りすぎたのは、四年生のヒトミさんだった。ハジメくんが思わず二度見をしてしまったのは、顔にいろんなものをくっつけていたからだ。耳たぶにはゼムクリップを三つも四つも通し、鼻には牛のようにカードリングを通している。両方の唇もそれぞれダブルクリップで挟んであった。「かっこいいな!」ハジメくんが叫ぶと、「でしょ」とヒトミさんはご満悦だった。「わたし、ピアスがしたかったんだ。ピアスがないからクリップで代用したんだけど、ピアスだったらうちにあったんだよ。ママのだけど。今はお家にいないから、勝手に借りちゃうつもり。借りパクしちゃうつもり。バイバイ!」
「行きまーす!」という号令とともに、窓の外をなにかが落下した。ゴトン! ガシャガシャ! すさまじい音響がとどろいて、ハジメくんが窓の下をのぞくと、地面には机やら椅子やらモップからカーテンやらの集積があった。何人かの男子がそこから一人の男子を引っ張りだす。片足が膝のところで逆方向に曲がっていて、どうやら折れているらしい。「なにしてんのーっ?」とハジメくんが尋ねると、「ハジメくん!」と足折れの男子が手を振ってきた。三年生のヒカルくんだった。「ぼく、飛行機を作ったんだよ! 空を飛ぶつもりだったんだ! 今回は失敗したけど、次はがんばる!」
「足折れてるけど」ハジメくんは指摘するが、ヒカルくんは笑い飛ばす。両脇から同級生に抱えられ、片足をブラブラさせながら、「空を飛ぶのに足はいらない! 両足なくなったって飛ぶんだぼくは」と熱く語った。
ぎゃああっ! いてええっ! 助けてえっ! ある教室からは耳をつんざくような悲鳴が聞こえて、大勢の児童が教室から転げ出てきた。ほかの児童は窓にかじりついて、教室内に見入っている。机が一つだけ残された教室の床では、左手を右手で握った男子児童が一人のたうちまわっていた。机の上にはカッターが一つと、どうやら小指らしい指が一本あるだけ。「どう?」ひとしきり暴れまわったあと、四年生のリュウジくんは同級生のほうに向きなおって問いかけた。「迫真の演技だったでしょ? 本当に痛そうに見えた?」
「なにしてんの?」ハジメくんが尋ねると、「ヤクザの真似だよ、ハジメくん!」とリュウジくんは答えて、根元から小指が切断された左手を掲げてみせた。「ヤクザが抗争する映画を見たんだ。指詰めのシーンがすごい迫力だった。ぼくもやってみたくてさ。痛いのはイヤだったから、永久少年があってよかったよ。もう一回やるから、ハジメくんも見ていきなよ。どの指がいい? 薬指? 右手の小指? 足の指って手もあるな。手もあるだって! 足なのに!」
一群の女子が逃げてきて、角を曲がると、そこには耳を持った男子児童が立っていた。五年生のマコトくんだった。「それなに?」ハジメくんが尋ねると、マコトくんは内気そうにほほ笑んで、自分の左の耳を指差した。そこに耳はなく、耳を切り取られたギザギザの跡があるだけだった。「それはヤクザの真似じゃないよね。耳なし芳一でもないか。片方だけだし」ハジメくんが首をかしげると、「盗聴する気だったんだ」とマコトくんは告白した。同じクラスのアイさんが大好きで、アイさんがお友達とどんなおしゃべりしているか、どんな笑い方をするか、どんなかわいいくしゃみをするか、ゲップとかおならとか聞けるだろうかと期待して、アイさんの机にこっそり自分の耳を忍ばせたらしい。「でも、なんの音も聞こえなかったんだ。見つかって、ギャーッ! 悲鳴あげたから、ゴメンゴメンそれぼくの、って出て行ったら、みんな逃げちゃった」
「早まったね」ハジメくんは指摘した。「そういう機能はないと思う。残念ながら。ハイテクじゃないんだよ」
「次は目玉を試そうとかって思ったんだけどね。残念だ。この耳、いる?」
「それにしてもすごい」ハジメくんは感嘆しきりだった。「みんな、ずいぶんいろんなことする。これも夢にも思わなかったことばかりだ。勉強になるなあ。だけど、どうだろう。これ見て永久少年、永久少女になりたいなんて思うんだろうか。うーん、かえって逆効果かも。困ったもんだ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
