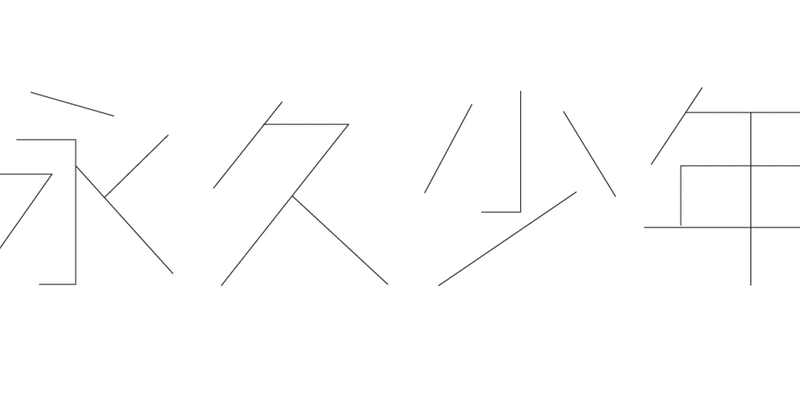
4.きみはもう永久少年さ
ハジメくんは猛烈に勧誘をはじめた。本当は焦る必要なんかないのだ。永久少年には永久の時間があるからだ。けれど、永久少年でない人はそうじゃない。生まれっぱなしの生き方しか知らないほとんどの人は、脇道にそれることも後戻りもできない、一方通行の窮屈な人生を強いられている。ゴールは死だ。それは高いビルから落ちるようなものだ。屋上から飛び降りようとする人が目の前にいれば、だれだって止めようとするだろう。だから、ハジメくんはそうしたのだ。
「永久少年になれば!」教室という教室に飛びこんで、ハジメくんは力説した。「もう腹が減らない。喉が乾かない。だから給食代も払わなくていい。大人になる必要はないんだ。成長なんてしなくていいんだ。成長、それは死ぬのと同じことなんだ」
「永久少年になれば!」教卓の上に仁王立ちして、ハジメくんは力説した。「夏でも暑くない。冬でも寒くない。怪我しても痛くない。夜でも眠くない。だって、そんなのいらないでしょ? いらないものはいらないだけだ。いらないものに振りまわされるのはもうやめよう。まとめて捨てちゃえ!」
「永久少年になれば!」席と席の間を駆けずって、ハジメくんは力説した。「オバケもこわくない。殺人鬼もこわくない。ひとりぼっちでも寂しくない。空っぽの部屋でも退屈じゃない。だって、永久少年は楽しいものって決まってるもの。じゃないと、永久少年になる意味がない」
いくら叱られても罵られても平気だった。それに負けじと声を張りあげればいいだけだ。追いかけられたら逃げればいい。追いかけっこはいつでも楽しいものだ。捕まったなら笑えばいい。右の頬をたたかれたら、左の頬も差し出して、ついでに尻も突き出すのだ。お目玉を食らうのは大歓迎だった。それによって、永久少年がどんなに盤石であるかが示せるからだ。
先生がぐったり疲れ果てたら、代わりに教壇に立ってあげる。雨ニモ負ケナイ云々の、永久少年の誉め歌を板書して、鑑賞を手引きするのだ。
「アラユルコトヲ勘定シナイ!」
「ナニモ見ナイ! ナニモ聞カナイ! ワカラナイ! 全部ワスレル!」
「日照リノトキハゲラゲラ笑イ! 寒サノ夏ハドタバタ走リ!」
お昼休みには放送室を占拠して、自分で自分に独占インタビューを敢行した。「巷で噂の永久少年ですが、それはいったいなんなのでしょうか、ハジメくん?」とインタビュアーのハジメくんが尋ねると、「教えてしんぜよう、ハジメくん!」とインタビュイーのハジメくんが答える。
「雨があがったら青空が広がるよね。道にはいっぱい水たまりができて、そこにも同じ青空がある。その両方を一緒に見ればわかるんだ。地面ってやつが実はペラペラの紙切れ一枚だってことが。水たまりは跳ねるでしょ? 跳ねたら宙に浮かぶでしょ? ペッラペラの地面を挟んで、頭の上の青空と足の下の青空の、ちょうど中間にぽっかり浮かぶ。それだよ。それが永久少年なんだ」
「でも、それって一瞬のことじゃないんですかあ?」
「一瞬だよ。だけど永久なんだ。その一瞬が永久なんだ」
締めくくりとばかりに、「永久になれば、なんでもできる!」と気合を入れ、スピーカを破らんばかりのボリュームで「エイッ! キューッ! ショーッ! ネンッ!」と連呼した。
反響は大きかった。先生方は総出で放送室に押し寄せて、内側からロックしたドアを借金取りのようにたたきまくり、教育者とは思えないほど口汚く罵りまくった。その間、ハジメくんはただただ笑い通しだった。アハハハハハハ! アハハハハハハ! アハハ! アハハ! アハハハハハハ! その模様は逐一、全教室に届けられ、先生方に代表される旧世代のぶざまさと、ハジメくんを先達とする新世代のめざましさをあますところなく示すことができた。新世代? いや、永久少年は世代を超えた存在ではないか。永久少年は超世代なのだ。
永久少年になりたいと申し出る者が出るのは時間の問題だった。
「ハジメくん」まずは同級生のイワオくんがやってきた。いつもでかい図体を持て余している小心者の男の子だった。「永久少年って、なんか自由で楽しそうだね」
「自由だとも。楽しいとも」ハジメくんは廊下の真ん中で逆立ち歩行しながら答える。
「永久少年になったら、なんでも自分の好きにしていいんだよね? 親の言うことを聞かなくていいし、勉強もしなくていいんだよね? 嫌いなものは食べなくていいし、掃除だってしなくていい。だよね?」
「だとも」
「ぼくも永久少年になれるかな」
「きみはもう永久少年さ」
ハジメくんは握りしめた拳をイワオくんのおでこにたたきつけた。ゴツン! と乾いた音がしたが、それは空っぽの壺をたたいたような、どこかマヌケな響きだった。
「本当だ! 全然痛くない!」イワオくんは顔を輝かせる。「ぼくは永久少年になったんだ! ありがとう、ハジメくん! ぼくは自由だ! うひゃっほう!」
「ハジメくん」次にやってきたのは隣のクラスのタツヤくんだった。いつも険しい顔をして宙をにらんでいる男の子だ。「永久少年になったら、もう痛みなんか感じないんだよね? どんなにぶたれたって蹴られたって平気なんだよね?」
「平気だとも」ハジメくんは廊下の壁とぶつかり稽古をしながら答える。
「喧嘩したら絶対勝つよね?」
「勝つとも」
「じゃあ、ぼくを永久少年にしてくれよ。近所に意地悪な六年生がいて、いつもぼくをいじめるんだ。会うたびに肩からぶつかって、拳固で殴る。通学中は後ろから蹴飛ばしてきて、ボケだのゴミだの死ねだの言う。ぼくは毎日泣いてるんだ。痛くて悔しくて泣いてるんだ。もうこんな人生イヤだ。ぼくはあいつに仕返ししたいんだ」
「きみはもう永久少年さ」
ハジメくんが拳をたたきつけると、ゴツン! とマヌケな音がした。
「全然平気だ! 痛くない!」タツヤくんは顔を輝かせる。「ありがとう、ハジメくん!
見てろ、あの野郎! コテンパンにしてやるからな!」
「ハジメくん」二年生のマコさんもやってきた。日本人形のような顔立ちをしたオカッパ頭の女の子だった。「わたしも永久少年になりたいんだけど」
ハジメくんは階段を上り下りしながら首をひねる。「なれないね。きみは女の子だから永久少女だ。そんなのあるかどうか知らないけどさ」
「じゃあ、それでいい。パパがね、マコは今が一番かわいいときだって言うの。大人にならなきゃいいのにって言って、悲しそうな顔するの。今はパパと仲良しでも、しばらくすると嫌いになっちゃうんだって。どっかにいるママと同じみたいに。だから、わたし、ずっとパパのいい子でいたいの」
「きみはもう永久少女さ」
ゴツン! とマヌケな音。
「ありがとう、ハジメくん! パパ、きっと喜ぶよ!」
「ハジメくん」六年生のカツヤくんもやってきた。ぶざまに腫れあがった顔で鼻血を流し、髪の毛が嵐のようにざんざらになった男の子だった。「卑怯なやつがいるんだよ。ぼくに力じゃかなわないからって、永久少年になりやがった。『仕返しだ!』って叫んで襲ってきて、もうひどい。しつこく何度も殴る蹴る。同じ場所を何度も攻める。逃げても逃げても追いかけてくる。鬼だ。悪魔だ」
ハジメくんはスキップしながら、カツヤくんの泥まみれ血みどろズタボロの姿を前から後ろから眺めまわす。「はりきったなあ!」
「苦し紛れに『今日はもうこの辺で勘弁してやる』って言ったら、『ありがとう』って言って帰ったけど、すぐに気づくよ。また襲ってくる。このままじゃ殺されちゃうよ。ぼくも永久少年になったら、あいつをやっつけられるかな?」
「それはやってみないとわからないね」
「やってみる。ぼくを永久少年にしてくれよ!」
「きみはもう永久少年さ」
ゴツン!
「見てろ、あの野郎! コテンパンのコテンパンにしてやるからな!」
ハジメくんは来る者は拒まずだった。拒む理由などなかったからだ。友達でなくても関係ない。これから友達になればいいだけだ。永久に生きるから年の差も関係なかった。大切なのは永久少年(および永久少女)になりたいという気持ちだった。ただ望みさえすれば、だれでも永久少年(もしくは永久少女)になれるのだ!
いったん永久の子供になったら、もうこわいものなしだった。永久の体を持っているから、なにを気にする必要もないからだ。恥も外聞も内申書も将来も関係ない。なんだってすることができる。永久の少年少女たちは、やりたいと思いつつもこれまでできなかったことを次々と実行に移していった。
三年生のヒデコさんは音楽の授業中にいきなり素っ頓狂な調子で歌いはじめた。音程がまるで合っていないし、なによりも声がでかすぎる。「やめなさい」「ちゃんと歌いなさい」「みんなと合わせない」と先生が叱っても、「だって、わたし、こっちのほうが楽しいんだもん」と主張して一向に従おうとしない。「ぼおくらあはあああ! みいいんなああ! いいきていいるううう!」とますます奇矯な声を張り上げて、クラスのみんなは生きた心地がしなかった。
五年生のフトシくんはもともと習字が大好きだったが、習字の時間のみならず、ほかの授業でも筆を使いはじめた。ノートからはみ出すくらい大胆に「5×4×6」「光合成」「応仁の乱」と筆書きをし、乾く間もなくページをめくり、ノートが足りなくなると、目の前にあるシャツや、机の上に書きはじめた。注意した人の顔にはすばやくバッテンをつけ、同級生が悲鳴をあげて退却すると、そこにできた広大なスペースにのびのびと「自由」「平等」「友愛」と書いた。
四年生のミツキくんは休み時間にいきなり机と椅子を倒しはじめ、同級生があっけにとられて見ている間に、縦にしたり横にしたりして積み上げはじめた。なにをしているのか尋ねると、「積み木だよ!」という返事だった。机に入っていた文房具も教科書も床に容赦なくばら撒かれ、ミツキくんによって踏みにじられた。散らかすな、わたしの机をいじるな、と抗議しても、「みんなもやればいいよ」と言って、取り合おうとしない。授業時間が始まってもやめないので、先生が「あいつを止めろ」「元に戻せ」と命じるが、だれも近寄ろうとしなかった。机と椅子の山はすでに天井近くまで達しており、ときおりガタン! ガシャガシャ! 派手な音を立てて崩れるのだ。ミツキくんも一緒になって崩れ落ちるが、そのたびになにごともなかったかのようにまた机と椅子を積みはじめる。
六年生のアンノさんは体操着に着替えている最中に考え直した。スカートを脱いだその手でシャツも靴下もパンツも脱いでしまった。同級生が驚いて、なにをしているのか、気が違ったのかと尋ねると、「全然恥ずかしくないのよ、これが」と平然としていた。それで体育の授業を受けるつもりかと尋ねると、体育の授業も受けるし、算数の授業も受けるし、このまま帰宅するし、明日はこのまま登校するとまで言う。とりあえずそのまま廊下に出て行った。隣の教室で着替えを済ませた男子がそこにはいたが、もう大混乱だった。女子たちはアンノさんを捕まえて無理やり服を着させたものの、隙あれば全裸になろうとするのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
