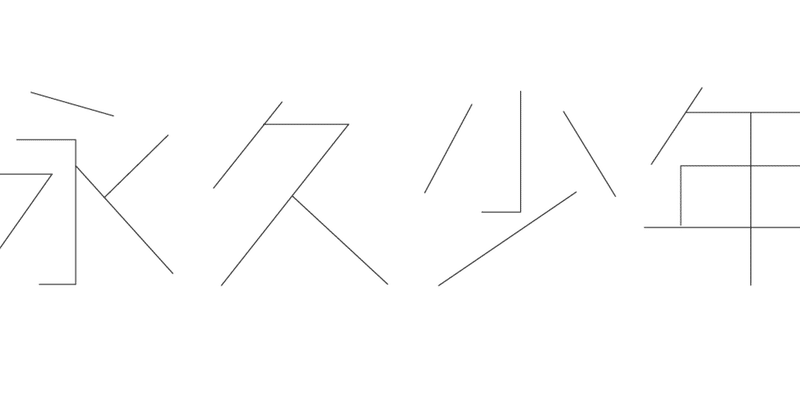
2.ソウイウモノニボクハナッタ
ばあん! 教室の前の扉を力いっぱい開け放つと、すべての視線が集まってきた。
「遅刻か、ケンジ」担当のヒノモト先生が苛立たしげにつぶやいた。「あれほど気をつけるよう言ってんのに、なんでおまえはわからないんだ。タイム・イズ・マネー。なにごとも時間を守ることからはじまるのであって」
ハジメくんは先生に目もくれないで自分の席に直行した。
「無視か! 言い訳のひとつもなしか? もしもーし、ケンジくん、聞こえますか?」
「ぼくのこと?」教壇を振り返って、ハジメくんは不思議そうに答える。 「ケンジなんて言うからわかんなかったよ。ぼくを呼ぶときはハジメって言わなきゃダメだよ、おじさん」
「だれがおじさんだ?」
「おじさんのことさ」
「先生だろ‼ おまえは児童で、わたしは先生。なんだ、そのおじさんってのは?」
「だって、ぼくは今日から永久少年だもの、もう児童じゃないから、おじさんも先生じゃなくて、おじさんなのさ」
先生にはよくわからないようだった。
「もういい。座れ。時間が惜しい。少年老いやすく、教科書を開いて。ノートを広げて、シャーペンを持って。とほほ! こんなこともいちいち言わにゃならんとはな!」
ハジメくんは教科書を広げたが、永久少年は勉強する必要がない。だから教科書を塗りつぶして時間をつぶすことにした。
「なにしてんの」隣の席のサチコさんがさっそく注意してきた。「それ、教科書だよ。いたずら書きしちゃダメなんだよ。そんなに力入れないの。消えなくなるよ。破れちゃうよ」
ハジメくんは耳を貸さない。通りすぎる風と同じだからだ。「馬の耳に念仏」ならぬ、「ハジメくんに注意」だった。シャープペンシルをボールペンに持ち替えると、サチコさんが息を飲んだ。ハジメくんの腕に思わず手をかけてきたが、もちろん、それで腕がロックされるわけではなかった。教科書の上を渦巻きがのたうち回るのを止めることができない。
「やめろ‼」と先生の怒号が響いた。ばん! 教卓に両手をたたきつけるという効果音つきだ。
「そこのケンジだかなんだかわからない人。そろそろ授業に参加してもらおうじゃないか。立ちなさい。朗読するんだ。先週配ったプリント。そいつだ。読みなさい。心をこめて読むんだぞ。それは罪深き傲慢な現代人が失った、気高い奉仕の精神を謳った、格調高い名文であって」
「読むのね?」
ハジメくんは朗読をはじめた。
雨ニモ負ケズ
風ニモ負ケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモ負ケヌ
丈夫ナ体ヲ持チ
「おっ‼」ハジメくんは驚嘆した。「なんだ、これはぼくのことじゃないか!」
「だれがおまえだ? 無駄口たたかないで本文だけ読む」
欲ハナク
決シテ怒ラズ
イツモ静カニ笑ッテイル
「うん、ぼくは欲張りじゃない。体ひとつあればいいんだし。怒らないってことはないけど、少ないな。静かに笑う。これは違うぞ。ぼくはうるさく笑いたいもの。そっちのほうが気持ちいいし、いかにも笑ってるんだなあって気分になるし。アハハハハハハ! アハハハハハハ!」
「笑うな! 感想は無用! 朗読を続けろ!」
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲ食ベ
「ダメだこりゃ! 全然なってない! 食いしんぼめ!」
「座れ! もういい! 頼まない!」
東ニ病気ノ子供アレバ
行ッテ永久少年ニナロウト言イ
西ニ疲レタ子供アレバ
行ッテ永久少年ニナロウト言イ
南ニ死ニソウナ子供アレバ
行ッテ永久少年ニナロウト言イ
北ニ喧嘩ヤ訴訟ガアレバ
行ッテ永久少年ニナッテ永久ニ続ケタマエト言イ
ミンナニカッコイイ永久少年ト呼バレ
大イニ褒メラレ
大イニ苦ニサレ
「ソウイウモノニボクハナッタ」
アハハ!
アハハ!
アハハハハハハ!
「黙れ黙れ黙れ黙れ!」
キンイチくんとジロウくんが心配して、休み時間に話しかけてきた。
「ケンジ、どした?」「ちょっと変だぞ。いつも変だけど」
ハジメくんは無言だった。
「あっ。ケンジじゃないのか」「ハジメって呼ばなきゃダメなんだっけ?」
「朝からずっと言ってることさ。ぼくのことなら心配ないよ。永久少年だもの。心配なのはきみたちのほうだ。そのままでいいの? 平気なの? いつ死んでもおかしくないのに。こうしてしゃべってるあいだにも、墓穴にむかってまっしぐらなんだ。ぼくにはきみらがもう死体にしか見えないよ。かわいそうに! だからどう? 永久少年にならない?」
キンイチくんとジロウくんは顔を見合わせた。「よくわかんないな」「考えとくよ」
体育の時間になったが、みんながジャージに着替えた中で、ハジメくんだけが私服のままだった。
「どうした、今日は見学か?」ヒノモト先生がさっそく難癖をつけてきた。「具合でも悪いか? 病気なのか? 休みたいんだったら構わないぞ。そのほうがまだ平和ってもんだ」
ハジメくんはクスクス笑う。「ぼくが病気になるわけないじゃないか。バカなこと言うなあ」
「ジャージを忘れたんだな、忘れん坊将軍? 正直に言いなさい」
「違うよ。なんで着替えなきゃいけないかわかんなかったからだよ」
「いいだろう。だったら、それでやれ。汚れて破れてしわくちゃになって、お母ちゃんに叱られても知らないからな」
この日はバスケットボールだった。まずは練習。二人一組になってパスの練習だったが、「場違いな格好をしてるやつなんかだれも相手にしないだろうよ」と先生が言うので、だれもハジメくんとペアを組もうとしない。
一人余ったカナオくんがしかたなくハジメくんに近寄ろうとすると、「ひっこんでろ」と言ってスグルくんがそれを差し止めた。チカラくんを呼び寄せて、ハジメくんにあてがった。
スグルくんは学級委員長で、クラスで起こることはすべて掌握したいたちだった。チカラくんは体格が良くて、力にものを言わせるたちだった。
チカラくんの繰り出す力強いパスを、ハジメくんはひとつも受け止めることができない。ボールは肩を強打し、膝を強打し、あさっての方角に飛んでいく。「だらしねえな」チカラくんはここぞとばかりにあざ笑う。「甘っちょろい考えだから、そうなるんだよ」
それでも、ハジメくんが顔面でまともにボールを食らってひっくり返ったときは、さすがにあわてた。「だいじょうぶか、おい」と言って駆け寄ったが、ハジメくんはもちろん平気の平左だったので、ひょっこり起き上がって「なんか用?」と答えただけだ。
次は二手にわかれてゲームだった。「みんなに合わそうとしないやつなんか、相手にすることないからな」と先生が言うので、だれもハジメくんにパスをまわそうとしない。たまたまこぼれてきたボールをハジメくんは拾ったが、ドリブルはおろかパスも出さず、だれもいない方角に投げた。ぽーん、ぽーん、とボールはむなしく弾んで転がっていく。みんなは白けてしまったが、ハジメくんは楽しかった。これでいい。楽しさは自分で見つけるものなのだ。
ボールを持っている人にむかってハジメくんは突進して、強烈なタックルを食らわせた。これはラグビーじゃないぞと一発退場を命じられると、その場に座りこんだ。コートの外に無理やり引きずり出されると、コートの中にボールを三個四個、次々と放った。文句をつけてきた同級生には、ボールをぶつけることで回答とした。頭にぶつけ、腹にぶつけ、尻にぶつけて、そのたびにケタケタ笑った。何人かは反撃とばかりにボールをぶつけ返してきたが、それに対して反反撃でボールをぶつけ返し返した。勝負ははじめからついていた。ハジメくんは痛みを感じないし、疲れることもないからだ。体育館じゅう駆けずりまわって、同級生全員に漏れなくボールをぶつけた。よく遊ぶ友達にも容赦なかったし、女の子だって関係なかった。「ぼくはもうぶつけられたぞ」とブウたれる人には、ご褒美とばかりにさらにぶつけた。「やめろ、このバカ!」「今すぐボールを離せ!」「いいかげんにしろ!」と終始怒鳴り続けだったヒノモト先生に対しては、いいかげんにするどころの話ではなかった。
知らせを受けて保健室から飛んできたルモイ先生は、体育館の惨状に呆れ返った。苦痛にのたうち、泣きじゃくる大勢の児童を前にして、戦場に乗りこんだナイチンゲールのような気分だった。袖もまくろうというものだ。
「もう大丈夫だからね。泣かなくていいのよ。わたしにまかせて。どこが痛むの? 教えてちょうだい。腰を打ったの? 足首をひねった? 膝を擦りむいた? たんこぶできた? 鼻血止まらない? 目がまわる? 消毒するわよ。添え木するわ。包帯巻いたげる。ぎゅっとしたげる」
「うん、ぼくは大丈夫だ。永久少年だもの。ほかをあたって」
ぷいと背をむけたハジメくんにサチコさんが詰め寄った。「どういうつもりよ、バカケンジ。それともバカハジメ? ひどすぎない? 自分がなにをやったかわかってんの? 友達を傷つけて平気なの? こんな人だなんて思わなかった。どんなにいいかげんでもわがままでも変わり者でも、友達思いの優しい人だと思ってたのに。裏切られた気分だよ。悲しいよ」
「うん、ぼくも悲しいな」ハジメくんは悲しそうに言う。本当は悲しくなかったが、真似っこくらいはできるのだ。「ちょっとはしゃいだだけなのに、だれ一人ついてこれない。まだまだこんなじゃないんだよ。ぼくはもっとスーパーに遊びたいのに、みんなは酸っぱいだけなんだ。かわいそうに! やっぱり永久にならないとダメなんだな」
サチコさんにはよくわからないようだった。「なに言ってんの?」
給食の時間になったが、もちろんハジメくんにとってはなんの意味もない時間だった。だから、トレーに並んだ調理品を再調理することにした。ポタージュ・スープに牛乳を注ぎこみ、手を突っこんで混ぜ合わせる。そこへプリンを加えた上で、ちぎったパンを散りばめ、さらにイチゴジャムとバターをトッピングして、全体を念入りにかきまわす。
「本当におまえはどうしちゃったんだ」ヒノモト先生は心底ウンザリしたように言う。「これまでも十分ひどかったが、ここまで底抜けじゃなかったはずだ。いったいどこまで抜けちゃってくれた? 地球の裏側か? ブラジルか? もしもーし! 頼むから食いもんで遊んでくれるな。そいつは粘土でもレゴでもない。口に入れるものなんだ」
「だって、ぼくは食べる必要ないんだもの。だったらあとは遊ぶしかないじゃないか」
「必要ないわけないじゃないか。仮のおまえのボンクラ頭が『必要ない』と判断したところで、体は必要としているはずだ。ちょっとくらい食欲がなくても食っとくもんだ。それで先生も気が休まる。頼むからさ」
「そんじゃ」とハジメくんは言って、再調理スープをごぶりごぶり飲みはじめた。周囲から悲鳴があがったので楽しくなって、サービスとばかりに今飲んだものを天井にむかって噴きあげた。
「掃除しろ掃除!」
ハジメくんはモップで床を一拭きしてから、濡れそぼったモジャモジャを先生の頭にひょっこり載せ、先生が怒り狂って捕まえにくると、窓からヒョイと飛び出して、そのまま学校をあとにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
