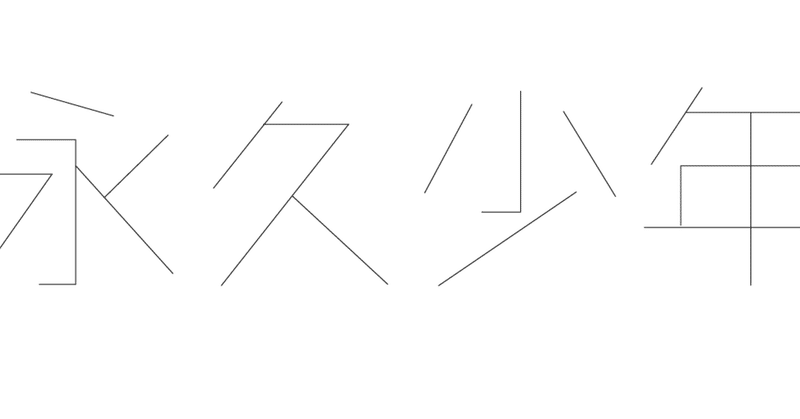
5.腐ったミカンの混ざったミカン箱
先生方は大弱りだった。児童が永久になった際の対処方法など指導要領のどこにも書いていなかったからだ。授業は事実上不可能になった。永久の児童が一人いただけで、クラスは腐ったミカンの混ざったミカン箱のように腐敗が蔓延してしまうのだ。まともに相手にするだけ無駄だった。永久の児童には先生の権威も大人の威厳も通じないのだから。かと言って無視すれば際限なくつけあがるだけ。いたずらに気力と体力を奪われて、クラスはおしとどめようのない無政府状態と化してしまう。
放課後の掃除および反省会のあと、児童が残らず退校しても一日はまだ終わったわけではなかった。明日からのことを考えなければならないのだ。校長先生、教頭先生、すべての教員は職員室に隣接した会議室に集結した。
「だが、その永久というやつ、それはいったいなんなんだ?」長テーブルの上に肩肘をつき、その手のひらに顎を乗せて、校長のトカチ先生が不機嫌に言う。「なにやら生意気ぶっこいた児童が好き勝手やらかしているという話だが」
「ちょっとタガがはずれてますね」議長をつとめる教頭のシラオイ先生はそう発言するものの、まだなにが起こっているのかよくわかっていないのだった。「後先見ないで突っ走って、いったいどこに向かってるやら。本人たちもわかってないんでしょうが」
「いやいや、こんなの、ただの悪ふざけですよ」担当のヒノモト先生はそう決めつけた。「あいつはそういうやつなんです。いきなり野生に返るとか言って四つ這いで登校してきたことがありましたし、だれかれとなくイタズラして、そのくせ逃げもしないんでなにかと思ったら、透明人間になったからだれにも見えないなんてぬかすんです。今回もその類ですよ。エーキューとかビーキューとかいうやつは。ただ、致命的に飽きっぽいやつですから、長くは続かないはずです。二日三日が限度でしょう。そう、三日我慢すればいいんです。そしたら正常に戻ります。本人の口から『永久ってなに?』とか言いだすはず。決まってます!」
「とは言え、あまりにも理解しがたい状況ですね」とシラオイ先生。「件の児童、ハジメくんですか、彼はまるで疲れ知らずじゃないですか。たたかれても蹴飛ばされてもへっちゃらじゃないですか。小学生の最重要イベントである給食を拒絶したそうじゃないですか。これをどう説明できるんです?」
「そのようなふりをしているだけでは?」そう発言したのは懐疑家のシコツ先生だった。「ぶたれても痛くないふりをして、そのくせ、みんなの見てないところでは、顔をしかめて『痛い痛い』うめいているのではないでしょうか? それに相手はしょせん子供ですので、先生方も本気で殴ってはいないでしょ? 同じように疲れてないふり、腹が減らないふりをしてたとわたしは思いますね。現実は物陰に隠れて噴き出る汗を拭い、教室の外に出た途端にチョコバーにでもかじりついているんでしょう。ほかの児童もそれを承知で、あえて合わせているのでは? ごっこ遊びと同じです。ちょっとおもしろそうだと思って、痛くないとか疲れないとか大げさに騒いで、この虚構に加担している。みんな、迷惑をこうむっていると? いやいや、それも含めてですよ。あえて迷惑顔をすることで、この虚構を補強している。これは純然たるイカサマです。わたしはそう信じますね」
「舐めてますな」熱血指導で知られるアバシリ先生は怒りを隠さない。「これはわれわれ大人に対する明白な挑戦です。ここは一発ガツンとやってしかるべきです。でないと、あいつらは悪くなっていくばかりだ。大人と世間を舐めきったシニカルなクズ人間になってしまう。やりますよ、わたしは。一切の手加減なしに特別強烈な一撃を見舞ってやる。真に愛ある鉄拳を食らえば、あいつらも目を覚ますでしょう。あまりのショックと痛みにびゃあびゃあびゃあびゃあ! 泣きだすはず。そしたら、わたしはがっしと抱きしめてやるつもりです。わかったわかった、痛いだろうつらいだろう寂しかったろう! あいつらはここぞとばかりにわたしにしがみついてくるのです。そこに真に人間的な共感が生まれる。自分が痛いだけじゃない、自分を殴った先生も同じように痛いんだとわかってくれる。あいつらの痛みとわたしの痛みがそこで完全に一体化し、そこに麗しい師弟関係が醸成されるのです。行くぞ! PTAが怖くて真の教育ができるもんか! 教育委員会もメディアもぶっとばせ!」
今にも会議室を飛び出さんばかりのアバシリ先生だったが、だれも止めようとはしなかった。すでに児童は学校に一人も残っていないのだから。「やってやる!」アバシリ先生は最後にダメ押しとばかりに一言放った。
「でも、永久ってのは本当ですよね」保健室のルモイ先生がどこかうれしそうに言う。「今日は午後になって何人も保健室に駆けこんできたんですよ。だけど、それは具合が悪いからじゃなくて、逆に具合がよすぎてなんです。これまで『体がだるい』だの、『頭が重い』『おなかが痛い』だの言っては、しょっちゅう保健室に逃げこんできた子が、『先生! 先生!』ってニコニコしながら飛びこんできて、ピョンピョン跳ねるは、ケタケタ笑うは、バンザイするはの大騒ぎ! 元気な体になったことを報告したくてたまらなかったのね。『ぼく、もう調子バッチリなんだ』『学校にだって喜んで来れちゃうよ』『先生はもうなんの心配もいらないよ』なんて言っちゃって。かわいいの! キョンくん、ショウちゃん、リュウくんとかが」
「元気であるというのは喜ばしいことです」シラオイ先生はちっとも喜ばしからぬ表情で言う。「しかし、ルモイさんはいったい、なにがおっしゃりたいんでしょう?」
「とっても元気なんですが、汗ひとつかいてないんですよ。息が荒くならないし、まばたきひとつしないんです。そりゃそうね。心臓が波打ってないんだもの。血が流れてないんだもの。わたしがどんなに途方に暮れてるかわかりますか?」
「困りましたね。今でも十分途方に暮れてるんですが」
「親はなんと言っているんだね?」不意に校長先生が発言した。「息子の不品行について、両親は当然知ってるんだろ? 今この状態をどういうふうに考えてるんだ? 家庭でどういう具合に指導していくつもりなんだ? 問いただしてくれないか?」
ヒノモト先生はハジメくんの自宅に電話をかけた。
「ぼくだよ!」しかし、電話口に出たのはハジメくんだった。「パパはどうした? ママはどうした? 電話を代われ」とヒノモト先生が言うと、「自称パパと自称ママか」とハジメくんは答える。「どこにもいないよ。帰ってきてないみたい。家出したのかも。昨日は自称ママが家出して、今日は自称パパが家出。明日はぼくが家出しようかな。どう思う、自称先生?」
「おまえはそのまま家にいろ。それで明日は学校に来い」
ヒノモト先生は自称ママ、いやいや、ママが避難しているという実姉の家の電話番号をなんとか聞き出した。電話口に出たのはママの姉で、妹が自身の息子について話のできる状態でないことを告げるばかりだった。
けれど、ここで有力な情報がもたらされた。ハジメくんの従兄である五年生ハルトくんの証言だった。
「あいつ、ずいぶん調子に乗ってるけど、もともとはぼくが考えたことなんです。あいつは永久の『え』の字も知らなかったんだもの。永久機関のことを教えてやったら、『え』って驚いて、そのとき初めて知ったくらいだ」
「ハジメの思いつきじゃないってことか?」
「永久機関には二種類あるんです。なにもエネルギーを受け取らないで、ずっと動き続けるやつと、受け取ったエネルギーと完全に等しい仕事をするやつ。あとのやつは1が1になるだけだからクソつまらない。本当におもしろいのは前のやつだ。だって、0が1になるんだもの。つまりなにも食べなくなって生きられるってこと」
「それはまさにハジメの主張だな」
「そこにあいつは飛びついたんだ。前から言っていたんですよ。大人ってちっとも楽しそうじゃない。大人になんかなりたくない。ずっとこのままでいたいって。もちろん、そんなの無理だって、ぼくは言いましたよ。食べ物食べて大きくなって老いて死ぬのが人間なんだ。でなければ怪我して死ぬか、病気になって死ぬか。どっちにしたって死ぬだけだ。『だったら、なにも食べなきゃいいのかな?』って聞いてくるから、それで永久機関のことを教えてやったんです。エネルギーがなくても動き続ける。永久に1であり続ける。それと同じように永久に子供でいればいい。永久少年になっちゃえって。だから、永久少年ってネーミングだって、ぼくの発明なんですよ。あいつ、お調子もんだから、すっかりその気になっちゃった。バカでしょう?」
ヒノモト先生はそのやり取りを先生方に伝えた。
「とすると、少なくともハジメくんは本気で信じちゃってるってことか」「思いこみの激しい児童なんでしょ? 自分で自分に暗示をかけた形でしょうか? 催眠と言ってもいいかもしれませんが」「それで実際にそうなったと?」「まさか。そんなことはありえない。生物学的にありえない。物理学的にありえない」「では、そういうふうに見えているだけですか? 幻想ですか?」「われわれもね。われわれも幻想を見てるんでしょう。いつしか暗示にかかってたんでしょう」「つまり集団催眠?」「集団幻想?」
「それが結論か?」校長が身を乗り出す。「教頭、これで対策が立てられるか?」
「そうですね。やることは一つ」シラオイ教頭は目の前に右の人差し指を一本立てた。「この一切が幻想だというのなら、幻想を振り払うことです。洗脳を解くのです。ハジメくんがやっていることがいかにあり得ないことなのか、永久少年というものがいかに科学的に間違っているのか、それを懇々と説いて聞かせましょう」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
