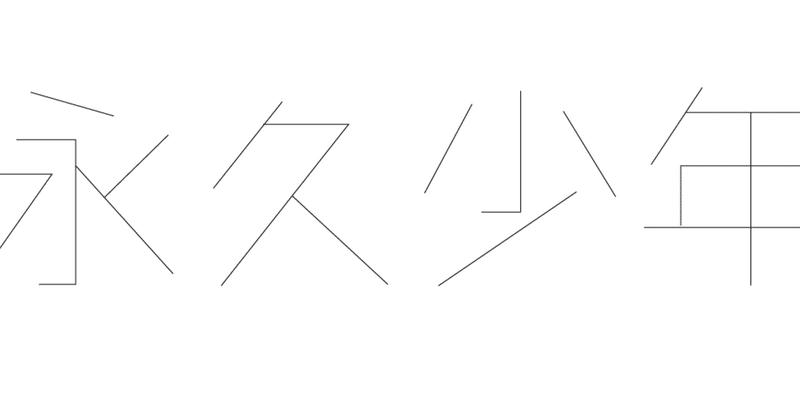
3.パパだったねえ
夜も遅くなったが、ハジメくんはもちろん元気だった。昨日は一晩じゅう突っ立っていたので、この日は部屋じゅう駆けずりまわった。机と本棚、箪笥、押入の中身を全部、床にぶちまけた上で、アルト笛をへし折り、地球儀を踏んづけ、零戦のプラモデルを床に墜落させた。ベッドをトランポリンにしてドッタンバッタン飛び跳ねたあとは、小太鼓のスティックを両手に持って、壁、柱、電気スタンド、椅子の背もたれ、目につくものをパキンパキンたたきまくった。
開けっ放しのドアからそのさまを目撃して、パパは愕然とした。神様! これはなんですか? しかし、神様からの返事はないようだ。
「ずいぶん張りきってるようじゃないか、ケンジ」ことさら何気ないふうを装ってパパは話しかける。「まるで地震でも来たみたいだな。汗かいたろう。どうだ、たまにはパパと一緒に風呂に入るか」
ハジメくんは無言だった。
「どうした、ケンジ? 疲れたか? ずっと暴れてたって聞くぞ。ママはこらえきれなくなって、お姉さんの家に避難中だよ。ははははは!」
「もう! 何回言ったらわかるんだろう。朝からもう百回もハジメだって言ってんのに。ぼくは今日から永久少年になったんだ。だから疲れないし、汗もかかないのさ。わかった、おじさん? 今度から気をつけて」
「おじさんってなんだ?」
「おじさんのことさ」
「ぼくはパパだぞ。おまえのパパだ‼︎ よりによって、おじさんなんてあんまりじゃないか。パパ、ちょっと傷ついたぞ」
ハジメくんは黙っていた。
「おまえ、ひょっとして怒ってるのか? パパがパパの役割を果たしてないとか? たしかにこの前の誕生日をすっぽかしたのは悪かった。どうしても断れない仕事が入ったんだ。休日にどこにも連れて行ってやらないのも悪いと思ってる。でも、パパは毎日疲れてるから、休日くらいゴロゴロしたいんだよ」
時刻は夜の十時をすぎていた。パパの息子はいつもなら寝床についているはずだった。
「だがな、パパがこんなにシャカリキになって働いてるのも、みんなおまえたちのためなんだ。おまえとママにはなにひとつ不自由させたくないし、将来に対する備えも必要だ。子供を一人前に育てるためには、それはそれは大層なお金が必要なんだ。そこんところをわかってほしい。ちょっとくらいすれ違いがあったとしても、パパはいつでもおまえのパパなんだ」
ハジメくんは首をかしげた。「あの人もママと呼べとかうるさかったけど、おじさんもそう? わかったよ。パパと呼ぶ。ただし、交換条件がひとつ。ぼくのこともちゃんとハジメって呼んでほしいな」
パパも首をかしげた。「なんか変な気がするが、まあいいだろう」
息子のためにパパはお湯をぬるめに調節したが、ハジメくんにとってはどうでもいいことだった。頭をシャンプーしてやろう、背中を流そうとしきりと持ちかけてくるが、それもどうでもいいことだ。あまりにしつこかったので、「ま、いっか」と思っただけだ。
パパには作戦があった。裸のつきあいを通じて息子と打ち解けることだ。ハジメくんがまだ幼稚園児だったころは、お風呂でしばしば楽しい時間をすごしたものだ。それを再現しようというわけだ。
ハジメくんの小さな背中を泡立たせながら、パパはうなじをくすぐった。パパの息子は昔から大のくすぐったがり屋で、ちょっと触れただけですぐにキャッキャッはしゃいだものだ。なのに、今はなんの反応もない。仏像みたいに平然としている。パパはムキになった。耳の裏、顎の下、脇の下と標的を変えて、強すぎず弱すぎず細心の注意を払って指先を動かし続けたが、やっぱりダメだ。「さっきからなにやってんのさ」ハジメくんはそう言っただけだ。
「それじゃ今度はおまえがやってくれるか。パパの髪をシャンプーして、背中を流してくれないか。パパの背中は大きくて大変だろうが、まあがんばれ。ははははは!」
ハジメくんはがんばったが、そのがんばりようはパパが期待したものとは違っていた。シャンプーで髪を泡立たせるのに爪を立てるのはやりすぎだった。垢すりタオルにボトル一本分のボディーシャンプーは必要ないし、人の背中をこするのに雑巾がけのような気合いは必要ない。泡は全身を覆うほどファンタスティックに膨れあがったものの、その内部では皮膚が悲鳴をあげていた。「痛い痛い痛い!」パパはたまらず叫んだが、本当に痛かったのは心だった。息子の思いやりに欠けた仕打ちが悲しくてならなかったのだ。
「もういい。お湯に浸かろうじゃないか」
ヒリヒリする肌をかばいながらパパは湯船にゆっくりと体を沈め、ハジメくんはなにもかばわないで湯船にざんぶと飛びこんだ。
「ママからね、聞いたんだ」パパはおもむろに話しはじめる。「今日一日起こったことを。朝ごはんを食べなかったとか、学校でトラブったとか、まあそんなことだ。おまけに、もう学校には行かないなんて言ってるみたいじゃないか。どうした。なにがあった、ケンジ?」
「ハジメ」とハジメくん。
「ああ、そうだったな。ハジメね。無理に話せとは言わないが、パパはいつでもおまえの味方だ。相談してくれればできるだけの力になる。学校のことに関して言えば、なるべく通ったほうがいいというのがパパの意見だ。学校はつまらないかもしれない。窮屈だったり厳しかったりするかもしれない。だけど、世間はもっと厳しいんだ。理不尽なことがごまんとあるし、不愉快な輩もわんさといる。そんな世間に耐えるための力をつける場所が学校なんだ。苦しいこと、つらいこと、わけわかんないことをひとつずつクリアしていくごとに、見えないポイントが加算される。そうやって蓄えたポイントが、いざ社会に飛び出したときに威力を発揮するわけだ。どうだ、そう考えれば気が楽にならないだろうか?」
ハジメくんはキョトンとしている。
「おまえはちょっと変わってるから、まわりから浮いてしまってるのかもしれない。だとしても悲観することはないぞ。心をオープンに開いていれば、自然と道は開けるものだ。おまえは今なにかの壁にぶち当たっているのかもしれない。話してくれないことにはそれがなにかはわからないがね。それでも確実に言えることがひとつある。つらいことは永遠には続かないということだ。そのうち心底打ちこめるものが見つかるだろう。無二の親友もできるだろうし、生涯の伴侶も見つかるだろう。おまえの人生はまだはじまったばかりなんだ。人生は大変長い。苦あれば楽あり。ちょっとくらいつまずいたって、立ち上がってまた歩けばいい。七転び八起き。三歩進んで二歩下がる。なにも焦ることはない。口笛でも吹きながら、のんびり歩いて行こうじゃないか」
どうだ、とばかりに渾身のスピーチを終えて、パパは息子の顔をうかがったが、そこにはなんの表情も浮かんでいなかった。「さっきからなに言ってんのさ」ハジメくんはそう言っただけだった。
「おまえのことを心配してるんだがね」
「なんで心配? ぼくは永久少年なんだよ。なんの心配もない」
「それじゃ、明日からはきちんとごはんを食べて、学校にも行くんだな?」
「学校にはもうちょっと行ってみるよ。みんな、まだよくわかんないみたいなんだ。もう一押ししなきゃダメみたい。一押しでダメなら、二押し三押し。だから学校は行くよ。ごはんなんかいらないけどさ」
「うん。食事のほうはパパもそんなに気にしてないんだ。腹が減ったら自然と食いたくなるもんだからね。飽食気味のこの現代、無理して食うよりよっぽどいい。もちろん、どこか具合が悪いんだったら、お医者さんに診てもらわないといけないけどね。病気だけは気をつけないと」
「じゃあ、それも問題ないね。ぼくは病気にならないもの」
「そうか」
相槌を打ちはしたものの、パパはまるでしっくりこなかった。ボタンをかけ違えてしまったような気分だった。息子との距離は縮まるどころか、逆に遠く離れてしまった。膝がくっつくほど近くにいるのに、二人の間には底知れぬ谷間が開いていた。
そうだ! そのとき、パパの中で閃くものがあった。「ケンジ。いや、ハジメか。あれやらないか。息止め競争。お湯に顔をくっつけて、先に顔を上げたほうが負けってやつ」
これは父子が昔、風呂場でよくやったゲームだった。パパは大人なので勝って当然だったが、息子に花を持たせる形で接戦を演じ、三度に一度はわざと負けてあげたものだ。それで息子に自信がつくなら結構なことだし、その成功体験をバネに将来は水泳選手として活躍しないとも限らないのだ。「親父がわざと負けてくれたことに気づいたのは、だいぶあとになってからでしたよ」と、大活躍を果たした息子はインタビューに答えもするだろう。晴れがましい表情で金メダルを掲げ、それを最愛のパパに捧げるのだ。感動の嵐! 随喜の涙! カメラのフラッシュ!
今回、パパはもうひとひねりを加えることにした。息子が耐えきれずに顔を上げた瞬間を見計らって、すかさず自分も顔を上げるのだ。そうすれば、二人で顔を見合わせて、仲良く笑うことができるだろう。あはははははは! 「引き分けか、残念!」「パパ、だらしないな!」
先に音を上げたのはパパだった。濡れそぼった顔にはそんなバカなという表情が浮かんでいた。ハジメくんの顔がまだお湯に浸かったままなのを見て、心臓が止まるくらい驚いた。
「ケンジ! いや、ハジメか。ああ、もうそんなことどうでもいい! わかった、降参だ。おまえの勝ちだ。もう顔を上げていいぞ。それにしてもすごい肺活量だな。本当に水泳選手になれるんじゃないか? いいからもうやめろ。やめろったら!」
ハジメくんはピクリともしなかった。不吉な予感が脳裏をよぎる。鳴り響くサイレン。救急車と担架。悲鳴と怒号。刑事の氷のような眼差しにカメラのフラッシュ! 明日の朝刊に踊る文字すらもう目に浮かぶようだった。「大旗町在住の会社員、ミヤザワケンイチ(三十五歳)、自宅浴室で悪ふざけの末に長男ケンジくん(九歳)を溺死させる! あわてて肩をつかんで持ち上げると、息子は白目をむいて、舌をだらんと垂らしていた。
うわうわうわあっ‼︎ パパは絶叫した。「なんてこった神様! ケンジ、ケンジイ!」
「ハジメだよ」
「あっ、ハジメか。うわうわあっ!」
パパが湯船にひっくり返って、盛大にしぶきを上げてジタバタ悶絶するさまを見て、ハジメくんはケタケタ笑いだした。ハジメくんが溺れ死ぬわけがない。これはちょっとした悪ふざけだったのだ。
「ああ、おもしろかった! おじさんのうろたえぶりったら!」そして、思い出したように付け加えた。「あっ、パパだったねえ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
