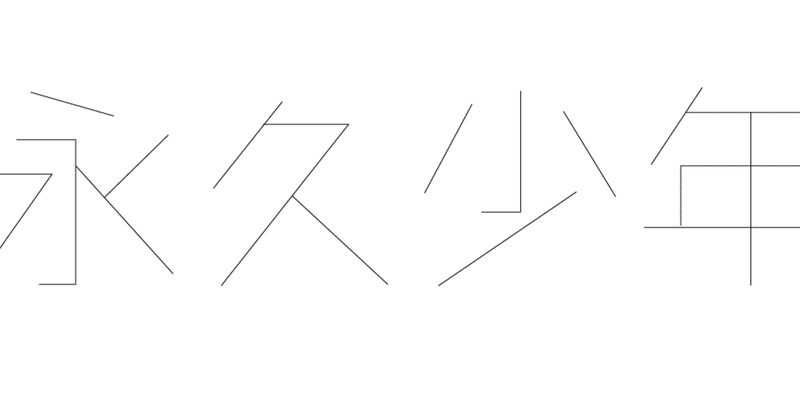
7.痛いだろ? 苦しいだろ?
脱洗脳班は着々と成果をあげていった。
最初はおとなしい児童から始めた。永久になったからといって、だれもが強烈に自己主張したり、迷惑行動を起こしているとはかぎらなかったのだ。
たとえば、二年生のマコさん。同級生が席を離れて勝手に歩きまわっているところを、一人席にすわってお絵描きをしていたので、担任のアカン先生は声をかけた。「マコちゃん、ちょっと来てくれるかな。先生、大事な話があるんだけど」
視聴覚室に窓はなく、打楽器演奏を思う存分できるように防音設備が万全だった。ポツンと椅子が一つだけ置いてあり、そこに座るように促されたので、マコさんはテストでも受けるような気分になった。歌でも歌わなくちゃいけないのかと。
「立ち入ったことを聞くけどさ、マコちゃん」アカン先生はマコさんの背後を行ったり来たりしながら語りかけた。「きのう、永久少女になったんだって? どんなふう? パパはなんて言ってた?」
「まだ内緒」マコさんは素直に答える。「おかしいなあ、マコちゃん、全然大きくならないなあ、どうしてかなあ? って首ひねったら教えてあげるの。ジャンジャジャーン! パパ、わたし、永久少女よって!」
「それまで隠すつもりなの?」
「普通にごはん食べるふりして、ウンチするふりして暮らせばいいの。ゆうべもずっと眠ったふりしてた。電気つければ疑われるから、ベッドに入ってずっと真っ暗な天井を見てたの。羊さんを八千五百十一匹まで数えたとこで、目覚ましのベルが鳴った。新記録。全然眠くならなかったよ」
「ずっと続けるのは難しいんじゃないかな」
「大丈夫。わたし、根性あるの。今日はノートに世界じゅうの動物を描いた。アルパカもトドもミーアキャットも描いた。シロクマがアザラシを食べるとこと、レミングがみんなで押し合いっこして海に落っこちるとこも描いた。見る?」
「そのうち気づかれるんじゃないかと思うけど」
「かもね。ジョンテはすぐに気づいたよ。うちのネコちゃん。わたしが近寄ってったら、『どなたさまですか?』って顔して、よそよそしいの。あれはちょっと悲しかったな。本当はそんなに悲しくないけど」
「でも、永久少女ってつまらないんじゃないかな。なにを食べてもおいしくないんだろ? パパと食事が楽しめないじゃないか」
「それがちょっと面倒かな。食べたくないのに無理して食べて、だれも止めないからどんどん食べたら、パパ、すごいびっくりしてた。トイレに行ったら、お腹がぽっこり膨らんでたから、本当にすごい食べたんだなあってわかったの。みんな、トイレに吐き出しちゃった」
「そんなことして悪いとは思わないの? せっかくのおいしいものをトイレに捨てたりして。それを聞いたら、パパは悲しむと思うな」
「そうなの?」
「パパはきみに普通の女の子でいてほしいって思うだけで、大きくならなきゃいいのにっていうのは、文字通りの意味じゃなくて、どれだけかわいいかってことを言いたかっただけなんだよ」
マコさんは動揺した。そんなこと思ってもみなかったのだ。
「きみのパパと電話がつながったよ」そのとき準備室のドアを開けて、副担任のエサシ先生が入ってきた。携帯電話をマコさんに差し出す。「きみが永久少女だってことはちゃんと説明しといたからね」
マコさんはおそるおそる電話に出て、「パパ?」とか細い声で呼びかけた。「そうだよ」「ずっとこのままなの」「そうしたかったの」とつぶやいたのち、「パパのためだったのに!」と叫んで携帯電話を床にたたきつけた。
次の瞬間、マコさんは全身をぶるぶる痙攣させたかと思うと、アアアア アッ! と喉が引きちぎらんばかりの悲鳴をあげて床に崩れ落ちた。
止まっていた時計が動きだしたのだ。大量の水を堰き止めていたダムが決壊したのだ。閉ざされた静かな個室から、喧騒渦巻くパーティー会場に放り出されたようなものだった。
固唾を飲んで待機していた先生方が準備室から飛び出してきた。真っ青な顔で立ちつくすアカン先生の足下で、マコさんは激しく嗚咽し身悶えしている。なにか邪悪な生き物が今にも腹を破って飛び出してきそうな雰囲気さえした。
「救急車を」マコさんをざっと診察して、ルモイ先生が言った。「命に別状はないと思いますが。何日か休養すれば回復するはずです」
パーポ! パーポ!
マコさんを送りだしたのち、先生方は顔を見合わせて、無言でおたがいに問いかけあった。これでよかったんだろうか? 間違ってなかったんだろうか? こうするしかなかったはず。だけど、あの顔。あの痙攣。ゾッとする。
「大成功でしたね」しかし、教頭のシラオイ先生はキッパリと断言した。「思った通り。永久少年ってやつは実にちょろい。適合不全の児童による都合のいい願望にすぎないんです。矛盾だらけ。嘘まみれ。突っこみどころは無数にある。突いて突いて突きまくるのです。タガがはずれていると、以前どなたかが言いましたっけ? いえ、彼らは永久というタガをまとっているんです。そのタガをはずしましょう。永久はずしをするのです」
教室と廊下を行き来して無制限デスマッチをしていたタツヤくんとカツヤくんは、止めに入ったアバシリ先生を早々に追い返したが、その後駆けつけてきた五人も六人もの先生によって取り押さえられた。
タツヤくんの説得には担任のオタル先生があたった。もともとおとなしい児童であり、喧嘩をしていたのだって、やむを得ない事情があったはずで、説得も一人で十分と踏んだのだ。「きみは以前からいじめられてると訴えてたけど、先生は本気にしなかった。カツヤくんは親分肌の児童で、同級生から慕われて先生方の受けもよかったから、単にきみをかわいがっているだけだと思ったの。でも、ようやくわかったわ。こんなことになったからには、よっぽどのことがあったのね」
オタル先生は改めて教え子の顔を見たが、いまだに信じられないような思いだった。タツヤくんはこんなに鼻がつぶれていなかったし、唇の端が大きく裂けて歯茎がのぞいてなどいなかった。こんなに髪が引きちぎられていなかったし、戦災孤児かと見紛うようなボロボロの服を着ていなかった。
「うん。これをやったのはカツヤだよ。でも、永久少年になれたから、きっちり仕返しできて満足だよ。むこうも永久少年になって条件は同じになっちゃったけど。今は顔を合わすたびに殴り殴られで、どっちも引かないもんだから、だれかが止めてくれるのを待つしかないんだ」
「まあ」オタル先生は首を振る。「先生、それ、よくないと思うなあ。喧嘩して、たとえ勝ったとしても、最終的に傷つくのは自分だよ。ハジメくんになにを吹きこまれたかは知らないけど、こんなことはありえないよ」
オタル先生はタツヤくんがこれまでどんなに真面目でおとなしくて平凡ないい子だったかを話して聞かせた。このままなんの問題も起こさず学業を終え、常識をわきまえた青年として成長し、優良な企業に就職して真面目に職務をこなし、結婚をして子供をもうけ、小さいながらも楽しいマイホームを持ち、周囲に尊重されて穏やかに年老い、やがて死んでいくという幸せな見通しについて語った。「それがきみの人生なの。きみはそうやって生きて死んでいくの。それは逃れようのないことなの。きみはその現実と向き合わなくちゃいけないの」
そして、あらかじめ用意していた資料を広げた。国語の時間の課題作文、夏休みの絵日記、図工の時間に描いた水彩画、遠足のときに撮った写真、コンクールに応募した読書感想文、つまりタツヤくんが小学校で送ったこの四年間の生きた証だった。
誕生日のケーキを取り巻いて笑っている家族を描いた水彩画はとてもつたなかったが、笑っている口は顔からはみ出さんばかりだった。友達と肩を組んで撮られた写真は、遠足の際、岩場で足をくじいて、友達に助けられてなんとか山の頂上までの登ったときの思い出だった。将来の夢をつづった作文ではフェリーの運転手になって、晴れの日も雨の日も東日流海峡を行ったり来たりしたいと希望していた。タツヤくんがどんな人生を歩んできたか、どんな性格の男の子であり、どんな未来を思い描いていたかがそれらに明瞭に示されていた。
「わかる? きみは本当に感受性豊かな、すてきな男の子だったのよ。それが今はどう?」オタル先生はそう言って、タツヤくんの目の前に鏡を立てた。「こんな男の子をどう思う?」
だれだこいつは? なんておぞましい姿! オエーッ!
永久という一枚岩にヒビが入るや、それは一気に全体に及ぶ。タツヤくんは転落した。ギャアアアアアアアッ! と叫んで床に崩れ落ちると、手足を激しくブルンブルン振りまわした。
パーポ! パーポ!
静かに話のできる児童もいれば、反抗する児童もいる。カツヤくんは手足をやたらと振りまわして、ことのほか凶暴だったので、ロープでぐるぐる巻きにして視聴覚室に運びこまなければならなかった。逃げられても困るので、そのまま椅子に縛りつけた。「やめろ! 離せ! ふざけんな! てめえら!」と騒がしいことこの上ないので、説得も三人四人でまわりを固めて同時に行わなければならなかった。
「いいかい、カツヤくん。きみは自分が永久だと思って、いい気になっているが、それは本当に本当なのか?」
「痛みを感じないだの、疲れないだの、腹が減らないだの、そんなことはみんな、きみの思いこみにすぎないんだ」
「つい数日前のことを思い出せ。朝起きれば腹ペコだった。おいしい朝食を腹いっぱい食べたはず。階段をのぼるときはハアハア息があがったはず。机の角に小指をぶつけたら、すぐには立てないほど痛かったはず」
「それが自然の姿なんだ。それが生きている証なんだ。きみが成長している証拠だ。ずっと子供のままなんかありえない。永久なんか不可能だ」
うるさい! 黙れ! 聞こえない!
「きみは妄想の虜になっているだけだ。つらい現実を受け入れたくなくて、心地よい夢に浸っている。だが夢はいずれ覚めるものだ。覚めるなら早いほうがいい。取り返しがつかなくなる前に、早くこっちがに戻ってこい」
「今きみは猛烈に腹をすかせている。あまりの疲労困憊で、口を開くこともままならない。体じゅういたるところの擦り傷、切り傷、打ち傷がヒリヒリ、ズキズキ、ジクジクと悲鳴をあげている。当然だ。何時間も何十時間も飲まず食わずで、片時たりと休む間もなく、なりふり構わずはしゃぎまくってたんだから」
「どうだ、痛いだろ? 苦しいだろ? いっそ死んだほうがマシだろ? どうだ、どうではないのかね? どうだ、そうではないのかね? どうだどうだどうなんだ?」
効果が現われるまで何時間でも続けるつもりだった。疲れたら交代して、同じことを繰り返した。先生方にとっては苦しいながらも充実したひとときだった。身動きできない児童にむかって、時間も授業態度もPTAも気にせず思う存分授業をすることができるのだから。
カツヤくんは最初のうちは馬耳東風と決めこんでいたが、単調に繰り返される先生方の言葉にうっかり耳を傾けたのが運の尽きだった。「そう言えば」とわが身を振り返ってしまったのだ。どうしてなにも食べなくて平気なんだろう? どうして体が傷だらけなのに痛くないんだろう? 永久、永久っていうけど、それはなに?
心の片隅にチラリとよぎったそんな疑念が永久という一枚岩にヒビを入れ、カツヤくんはガラガラと崩れ落ちた。アアアアアアアッ! 傷という傷から噴き出す血。目からは涙。口からは泡。
パーポ! パーポ!
救急車でタツヤくんを送り出してなお、先生方は青ざめたままだった。「よかったんだよな?」「これでよかったのよね?」「間違ったことしてないよな?」
「このままでいてもしょうがないですからね」ルモイ先生が慰める。「永久、永久、言ってますが、これが本当に永久に続くとは思えませんもの。だから、今のうちに落ちちゃったほうがいいんです」
とは言え、午後になってから連れてこられた児童には、先生方一同震えあがった。リュウジくんは右手の指を二本、左手の指を三本、右足の指を一本、左足の指を二本欠いていて、さも大層な事業を成し遂げたとでもいうような誇らしげな顔をしていたのだ。
「リュウジくん、よかったら、なんでこんなことをしちゃったのか教えてくれないかね?」シラオイ先生は問いかけた。
「これまで見た一番ドラマチックなシーンだったんだ」リュウジくんは欠損だらけの両手を目の前に掲げながら答えた。「わかる? 一本切り離されるたびに、それまで住んでた世界と切り離されちゃうんだ。ものすごいショックな出来事で、高い崖からドーン! って突き落とされるような感じなんだ」
「でも、それじゃ不便じゃないのかい?」
「すっげえ不便! なにもしっかり握れないし、みんな、こわがって近寄らないし」
「切り離した指はどうしたね?」
リュウジくんはプラスチック製の筆箱を差し出した。そこに切り離された指がきれいに並んでいた。うひゃあっ! 先生方はひっくり返り、指も床にばら撒かれた。アハハハハ! リュウジくんはさも愉快そうに笑う。
「ああごめん、下敷きにしちゃった」尻餅をついた先生があわてて尻をずらすと、下敷きになった左の中指がぴょんと跳ね上がった。ひゃああっ! アハハハ!
もう一回実演してみせるというリュウジくんを先生方は必死で止めた。それじゃ代わりにと、リュウジくんは切り離された指を中央でポッキリ折ったり、ナイフで切断してみせたりする。やめろやめろ! もういいリュウジくん!
椅子に縛りつけられたリュウジくんをどう処理していいか、先生方は困りきった。
切り離された指は切断面に骨、神経、血管が金太郎飴のように見えていて、生体の一部とは思えなかった。血がにじんでいるわけでもなく、湿っているわけでもなく、シリコーンかなにかで作った生体模型のようだった。
先生方の出した結論はこうだった。これらの指を所定の位置に置いて、切断部をテープできつく固定する。リュウジくんが脱永久化を果たした暁には、その切断の事実がリセットされ、まるで最初から切り離されてなどいなかったかのようにきれいに接合されるのではなかろうか。そうであってほしかった。それ以外の可能性など考えたくもなかった。
「だから、いいかい、リュウジくん、永久の体なんてものはありえないんだよ」
長時間にわたる説得の末に、リュウジくんはついに陥落した。椅子にロープで縛りつけられたまま床の上をのたうちまわり、指の切断面からはどす黒い血がにじみ出た。あああっ! あああっ! あああああっ! それはもう、ほんの数時間前に、あははははは! 笑っていた児童と同一人物とは思えなかった。さっきまで模型のようだった切断指も完全に疑いようもなく生身のものだった。先生方は震えあがった。どんな恐ろしい事態が進行していたのか改めて思い知らされたのだ。
「それにしても時間がかかりすぎますな」シラオイ先生はしかめ面で首を振る。「一人を永久はずしするのに優に一時間は要しますし、先の児童にいたっては三時間だ。ハジメくんはおでこをゴツンするだけで児童を永久化できるというのに。ここはやはり本丸を攻めるしかない。すべての元凶、悪の枢軸、ラスボスたるハジメくんを屈服させなくては話にならない。やつを地べたに引きずり下ろすのです。ハジメくんの捕獲に全力を傾けるのです。もうタマがないですって? 二十代三十代の若手が壊滅? ああ、それじゃ四十代五十代が行けばいい。教師生命すべてをかけて、あの教育の敵、学校の敵、社会の敵を捕まえるのです!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
