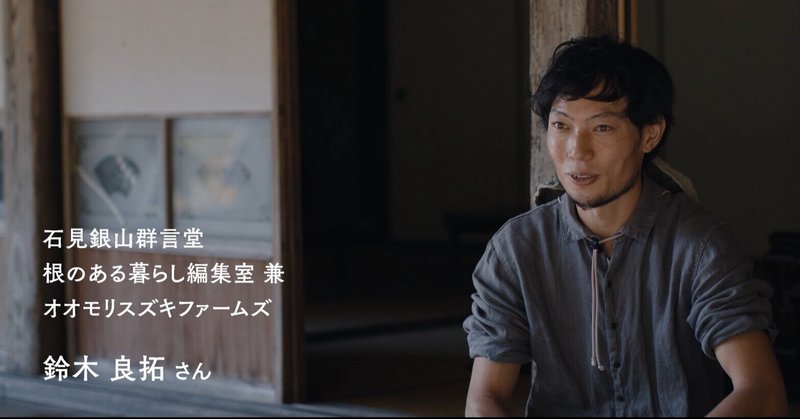2021年2月の記事一覧

糸と糸を結うように、つながって、はたらいて、はぐくんで。築90年以上の呉服店を利活用したシェアスペース『Coworking & Cafe yuinowa』
『仕事をする、くつろぐ、学ぶ、参加する』をテーマに、人と人が出会って結ばれ繋がるための拠点を目指すシェアスペース『yuinowa』。結城の街に集うさまざまな方々の “ハブ” として、数々の健やかなつながりを生み出しています。 築90年以上の呉服屋さんをリノベーションし利活用しているという『yuinowa』とは、はたしてどのようなスペースなのか。どんなポイントが人々を惹きつけているのか。ここでは、そんな『Coworking & Cafe yuinowa』の魅力にせまり