
VC10人くらいに聞いた、シード期のファイナンスのよくある勘違い
こんにちは。
インキュベイトファンドという独立系ベンチャーキャピタルに勤めている岩崎と申します。
Twitterでも創業期のスタートアップ向けに色々と発信しているので、よければフォローお願いします!
DMにて資金調達相談、事業壁打ちなどなどなんでもお気軽にどうぞ!
今回は、「シード・シリーズAのVC10人くらいに聞いたシード期のファイナンスのよくある勘違い」という記事です。
ご存じの通りファイナンス周りは落とし穴が多いです。
しかし、ファイナンス周りは世の中に情報がありふれすぎていて体系的に学びづらく、忙しい起業家さんには意外と知られていないことや「えっそうなんだ」と反応をされることも多いです。
という想いから、諸先輩方に話を聞いて落とし穴となる部分をピックアップして簡単にまとめました。
本当に協力してくださった皆様ありがとうございますm(__)m
きちんと体系的に学びたい方はこの記事を流し読みした後に、FoundXと磯崎哲也先生の2冊を読むことをお勧めします。
今回の記事に書いてあること多分全部網羅されてます。
勘違い①:スタートアップの資金調達は融資じゃなくて投資!
株を買う仕事であるベンチャーキャピタルの人間がいうのは変な話ですが、当然株は簡単には売ってはいけません。エンジェルやプレシードで少額の出資を受ける際に、「本当にこの1000万は必要なんだっけ?」「わざわざ株を発行する必要あるんだっけ?」と自問自答しましょう。
投資だけでなく融資も選択肢に入れましょう。
日本政策金融公庫の新創業融資制度は無担保無保証で融資を受けることができます。ある程度事業計画を書けば、運転資金で500万円程度の融資を受けることができ、返済期間や利率も非常に良心的です。
日本政策金融公庫のホームページを見ると、「難しくてよく分からないなあ」となってしまうかもしれませんが、そんな時は窓口に電話をしてみましょう。
友人の起業家がHPを読んでもよく分からず日本政策金融公庫の東京支店に電話をしたところ、
めちゃくちゃ親切に色々と教えてくれたらしいです。

勘違い②:バリュエーションは高ければ高い方がいいよね!
勿論【バリュエーションが高い=調達を沢山できる or 希薄化率が低くすむ】し、
「シードでバリュエーション〇億すごっ!」みたいな会話も時折耳にするのでバリュエーションが高ければ高い方がいいと思われがちです。
しかし、バリュエーションは次のラウンドの基準にもなるので、次の調達をする際にハードルが上がってしまいます。
というのも、シードVC側からしたら「シリーズA投資家より1年半も早くリスク取って頑張ってきたのに、なんで大して値段が変わらないんだ」というモヤモヤが出てしまいます。
勿論シリーズA調達時にはシードVCも既に同じ船に乗っているので、責任は確実に背負っているはずですが、もしそれでコンフリクトしてしまうと厄介です。
ですので、高すぎれば高すぎるほどいいというわけではなく、妥当な線を確認しましょう。
確認の方法としては、他の投資家との会話の機会を作れるとベストです。「自分は投資しないけど、これくらいのバリュエーションで投資する人がいても全然おかしくない」という感覚を持ち合わせている人間にバリュエーションの妥当さをチェックできると、高すぎるバリュエーションにならずに済むでしょう。(とはいえ、バリュエーションを下げる交渉をするのも変な話なので、「是非投資を受けたいが、自分はそのバリュエーションが高いと思う」という部分はシードVCと握っておきましょう。)

勘違い③ バリュエーションは〇億円がいいです!
別に間違いではないので揚げ足を取っているようですが、前提としてシード段階でバリュエーションを正確に決めることはできません。
考え方としては、
① 次のラウンド(シード調達ならシリーズA)までにどれくらい必要か(=調達額)
② 今対峙しているVCなら(※)、このラウンドでどれくらいの希薄化率までなら許していいか(=希薄化率)
③ じゃあバリュエーションはこれくらいがいいな!
があるべき姿です。
なので、バリュエーション額自体に固執するのは変な話で、「これくらい調達したくて、これくらいなら株を発行することができます」という表現になって然るべきです。
(※)全てのVCに対して希薄化率のレンジを同様に提示するのも少し違和感を感じます。VCによって支援内容やコミット量、得意な支援体制(ハンズオン・ハンズオフ)があるので、投資家のリファレンスチェックをしたうえで「こういうことをやってもらえるだろうから、このVCにはこれくらい発行してもいいかもな」というような考え方も一つありだと思います。
:勿論資本政策を引いたうえで希薄化率をがっちり決めることもありですし、そこまでVC周りに時間をかけるのもよくないと思うのであくまで1つの考え方です。

勘違い④:エンジェル・シードVCに株をじゃんじゃん発行しちゃおう!
どれだけ株を投資家に渡していいか(希薄化していいか)は、EXITまでのラウンドの回数、事業モデルの性質(資本集約型かそうでないか)、チャレンジするテーマ・産業の資本ニーズなど、非常に変数が多く考えることが難しいです。
しかし注意すべきこととしては、希薄化率の交渉の際に基本は投資家と利害がコンフリクトする(投資家はできるだけ多くのシェアを取りたい)ので、目の前のラウンドの投資家とのみ会話をしていると、不本意にシェアを取られてしまう可能性があります。
なので、常に1つ先のラウンドの投資家との会話の機会を作れるとベストです。少しまだ自社の投資ラウンドからは早いけど魅力的と考える投資家とは利害が一致する(前のラウンドでシェアを取られすぎたくない)ので、フェアな相談が可能となります。
勿論投資契約書の中身についてベラベラしゃべってしまうのはダメですが、「大体こんな感じでオファーをくれているVCがいるんだけどどう思う?」という粒度の相談はセーフだと思います。

勘違い⑤:凄い人に協力してもらうためにストックオプションをじゃんじゃん発行しよう!
原則フルコミットをしてくれる人にしか、生株は勿論ストックオプションも発行すべきではありません。
これは勿論、資本政策上株は慎重に発行するべきという観点からでもありますが、その後に雇うフルコミットの従業員のモチベーションにも関わってきます。
「なんであの週2くらいしか働かない偉そうな人が株持ってて、自分は持ってないんだ?」「上場したら自分にもインセンティブはいるけど、あの人の方が金持ちになるのか。」
こういった小さなモヤモヤを生まないためにも、フルコミットではない人には原則生株もストックオプションも発行するべきではありません。
今回お聞きしたシリーズAのVCの方も、「シード段階で弁護士・税理士に対してSOを発行していたら違和感を感じるので、当時の経営判断に対して色々と聞くと思う」と仰っていました。
とはいえ勿論原則で、「発行しては絶対にいけない!」というものではないことはありません。
また、もう1つ原則という話だと、一般的には【ストックオプションの発行は上場時に全部で10%程度】と言われています。シード段階のアドバイザーに10%とかを上げないようにしましょう。

勘違い⑥:沢山の投資家と事業会社に投資してもらった方が仲間増えていいよね!
勿論株主にとって会社の成長は利益なので、力のある投資家や事業会社が株主になることはメリットに繋がりそうですが、
がっつり入れてもらわないとVCや事業会社側のコミットメントが上がらず、支援メニューを受けられない可能性はあります。
株主候補のポートフォリオから投資先を調べて、投資先への対応や支援如何をチェックするべきです。
また、つらいラウンドの時に支えてもらうためにも、主軸となる株主は立てたほうがいいでしょう。

勘違い⑦:有名人をエンジェルに入れて宣伝!
あまりにエンタメ要素のある株主名簿はVCが嫌う傾向があります。
サッカー選手や芸人が入っていることでC向けサービスの認知が広まることは嘘ではないですが、リテンション率の向上につながる保証はなく、大規模なスケーリングという観点からみると影響がないケースが多いです。
エンジェルは起業経験者orスタートアップCXO経験者で、メンタリング・ブレストに付き合ってくれる人やメンタルを安定させてくれる方がベターです。

勘違い⑧:株の譲渡する覚悟は決まったから、税務とか法務とかよく分からないけど無償で譲渡する!
勘違い(?)です。(笑)
まず贈与税とは、以下のような定義となります。
「贈与税は個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。」(国税庁HPより)
細かい規定は勿論ありますが、原則として【価値の高いものを無償ないしは安い値で譲渡】してしまうと、「贈与」とみなされ贈与税が発生してしまう可能性があります。
例としては、
〇 初回ファイナンスでバリュエーションがついた時点で、創業者の株式を他の従業員などに無償譲渡をする(=1株〇万円×100株を無償で譲渡している)
〇 バリュエーションがついていない時点で創業者の株式を譲渡してすぐに、数億円規模のバリュエーションで調達をする(贈与税を払っていないならば、なぜ短期間でバリュエーションが一気に上がったのか?という議論になる)
税務・法務に関しては複雑な上に上場リスクにも関わってくる部分なので、気になったことは税理士・弁護士先生を頼りましょう。

勘違い⑨:VC・エンジェルはプロだから投資契約書は正しいはず!
訳の分からない条件で資金調達をしてしまうと、次以降のラウンドでVCが入れなくなってしまいます。
実例として諸先輩方に伺ったケースだと、
・ エンジェルに40%渡してしまう
・ 3年後に絶対に〇倍で返さなければならないという条件(=ただの借金)
・ バリュエーションが1000万
・ 配当を出すよう契約がある(謎)
などなどです。
世間に転がっている雛形と見比べて異なる所を丁寧にチェックし、違和感を感じる部分はきちんと聞いてみる、もしくは弁護士などきちんとした人にきちんとした形で頼るなどをしましょう。
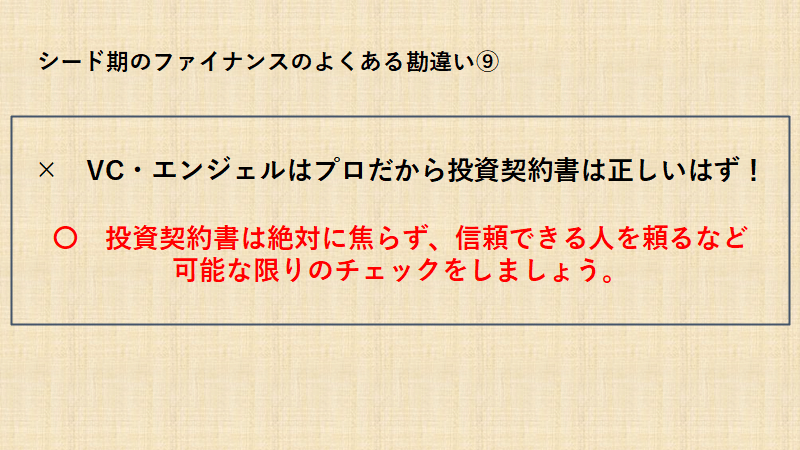
勘違い⑩:あるパートナー・アソシエイトの反応が微妙だったから、そのVCは全部諦める(泣)
ご存じの通り全員がピンとくるスタートアップというものはなく、ベテラン同士でも意見が食い違うことばかりだそうです。
また、ベンチャー投資の性質上、意思決定の仕方として投資の意思決定権を持っている人間が独立して意思決定をして投資をするケースが多いはずです。(弊社はそうです)
であるからして、「○○さんにリアクション悪かったから××社は全部だめだ!」ではなく、「あなたには刺さらなかったみたいですが、社内で刺さりそうな別の人っていますかね?」といったコミュニケーションをとることで可能性をつなげることは十分あり得ます。
1人の反応が悪かったからといって、会社全体を諦めるのは勿体ないです。

その他:細かい勘違い・ミスまとめ
その他頂いた細かい勘違い・ミスとして以下のようなものがあったためご紹介します。
✖ 創業者とは一緒に友人だから信頼しあっている!
△ 創業株主間契約は難しいしテンプレ通りでいいや!
〇 テンプレはあくまで参考で、きちんと創業株主間契約を結びましょう。
✖ 銀行から借りたいから、とりあえず三井住友銀行に突撃だ!
〇 まずは日本政策金融公庫などから借りましょう
✖ 調達をしたいからとりあえずVCに突撃だ!
⇒ 勿論VCには投資フェーズ(シード・シリーズA・…)がある上、シードVCでもかなり幅が広いです。この記事にシードVCの違いが書いてます。
あと、下の図によると、優先分配権は1倍参加型が統計的に見ても通例らしいです。(Coral先生の記事より)

最後に
「ファイナンス周りは即死の地雷だらけ」という表現を依然聞いたことがありますが、まさに取り返しのつかないミスを起こしかねません。
とはいえ、起業家の方々は忙しく全ての情報を入れて学びつくすというのは難しいケースもあるかと思うので、
迷ったり違和感を感じたりしたら気軽に専門家に相談をしましょう。
もし体系的に学びたい場合は、
FoundX、磯崎先生の2冊をきちんと読み込むのがいいでしょう。
私が今回の記事に書いたことがすべて書いてます。
何かお困りごとや記事が間違っている点がございましたら、お手数ですがTwitterまでDM頂けると幸いです。
ファイナンスで変にミスる起業家がいなくなりますように!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
