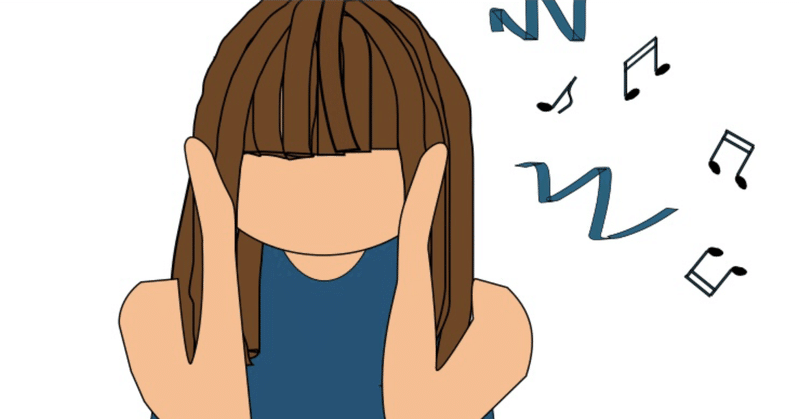
【小説】こどもの音
俺には悩みがあった。
向かいの一家が引っ越してきて半年、毎日のように夕方になると聞こえてくる子供たちの騒ぎ声だ。
何をしているのかはわからないが、表の道路に出てありったけのボリュームでキーと鳴き、ワーワーと叫びながら走り回っているらしい。
親は何をしているのか知らないが、それを注意する声は聞こえた試しがない。
そもそも親は家にいないのだろうかとすら思えるほど、その家から大人の気配を感じたことはなかった。
ある日、20時を回った頃もキャーキャーと騒ぎ立てているので流石に文句の一つでも言ってやろうかと思って、鉛のように重たい体を起こしてカーテンから表の道路を覗いた。
3歳かそこらの男の子がはしゃぎ周り、そこから数個上に見える男の子が相手をしていた。
あの奇声は幼い方だけが発していた。
兄の方は一緒になって楽しんでいるようには見えなかった。
まるで溢れ出る弟のパワーをどう扱えばいいのかわからないような目だった。
俺はカーテンを閉じてヘッドホンをした。
そこからしばらく日が流れて、気づけばその兄弟の遊び声が聞こえなくなった。
はてさて、彼らはどうしたのだろうか。
大人しくしろと親がようやく躾けたのか。
それかクレームが入ったのかもしれない。近くにいくらでも家はあるからな。親が知らない大人に怒られている姿というのは俺もガキの頃に見たが、まあショックなものだ。
俺はいつのまにか、夕方になると彼らのことを考えるようになった。
不思議なもので、あれだけうるさいと感じていた騒音も無くなると寂しいものだ。
俺の体が日に日に動かなくなっている。
不幸なものだ、若いうちに体が動かなくなるなんて。
親は嫌な顔せず看病してくれるが、本当は嫌だろうと俺にもわかる。
ああ、俺も外で目一杯に走り回って奇声を上げることができたらどんなに楽しいだろうか。
嫉妬の心をぶつけてしまって、彼らには悪いことをした。
今年ももう12月、同級生は高校最後の年末か。
いやに寒いと思ったら天窓から見える空は雪を降らしていた。
雪、もう触ることもないかもしれない。
外はどれだけ積もっただろう。
その時、キーと甲高い叫びが耳に届いた。
あ、あいつら元気にしてたんだ、そう思えた自分に安堵した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
