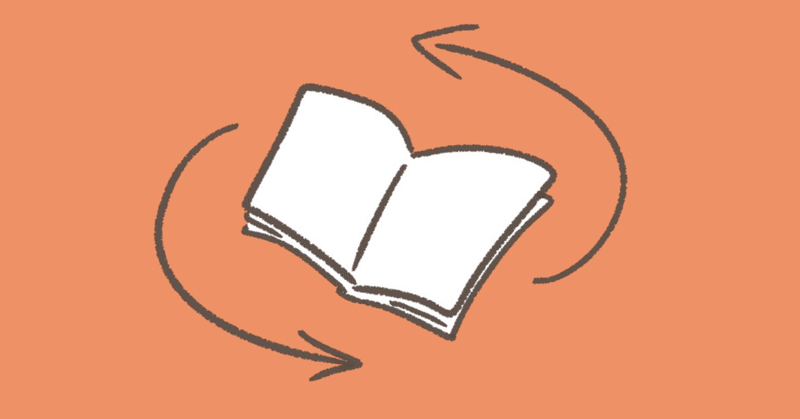
[取り急ぎ]一部ガラパゴス化する僕のリベラルフェミニズムと日本の表現規制の波〜日本の自由なBL表現の終わり〜
ロシアのウクライナ侵攻はただの侵略戦争であり、どちらかというと第二次世界大戦の延長という見方が強い。ここから学ぶ教訓など現状なさそうである。強いて言うなら、政府のシリア難民などとウクライナ難民の対応の差。国防意識、国連という組織の見直しくらいか。
ロシアが日本に侵略してきたとして、僕としては、日本の女性、子供、文化、領土を守るため戦うのみである。その先には、大勢の人の死のみがあり、そこからもまた、学ぶことはなさそうである。戦争は多くの人が死ぬ。意味など特にない…と個人的には思っている。単に戦争に対する興味が薄いだけかもしれない。少なくとも今回のような侵略戦争には。僕は個人としては国のためには戦うけど、どちらかというとリベラルで、人は死んでも思想は生き続ける。平和を願う思想…みたいなものが好きだから。
それより、人文科学が好きな僕としては月曜日のたわわを発端とした昨今の日本の表現規制の流れと、アメリカの過激リベラルに対抗する保守の表現規制の流れの方が興味深い。
歴史の教科書に載るとしたら前者だろうが、人文科学、思想、もっというと21世紀のオタク文化の教科書に載るとすれば後者であり、大きな転換点になり得ると感じる。
今現在、刻々と歴史が刻まれている。
ここまで興味を示しておいて何だが、僕は詳細な内容に詳しいわけではない。スタンスは傍観に近い。ただ、表現の自由を愛するものとして、手塚治、ディズニー…もっというと、西欧の童話を発端として、再解釈された系譜を受け継ぎ、21世紀に向けて鉄腕アトム、ガンダム、エヴァンゲリオン、鬼滅の刃とオタク文化、秋葉原の興隆、世界に羽ばたく日本のアニメ・漫画文化の歴史を追うものもして非常に興味深い出来事が起こりつつある。
昔から閉鎖的な環境が影響してか、日本の創作文化は奔放に、独自に発展してきた。西欧、その他国々を覗くと特に共産主義国の女性のBLに対する当たりが顕著だが、厳しい目が向けられてきた。
現在でもそうだが日本の同人誌の興隆を覗いても、女性のBL愛好の熱量は高く、ロリコン同人誌が誕生したのも、女性がBL2次創作を楽しむ姿を見たオタク男性が疎外感を感じたことに端を発する。
この女性のBL創作を守る意味においても、リベラリズム、またはフェミニズムの名において、僕は表現規制に反対してきた。BLを愛好し、表現規制に反対する女性は、グローバルスタンダードな表現規制派のフェミニストに、いないものとされている。
そのあたりの旗色も変わるかもしれない。
ついに男性側から、BL創作物の広告性、子供の目のつきやすいところに置きすぎている、過激である…という声が出始めている。
独自の発展を遂げてきた日本のアニメ・漫画文化であっても、西欧の我こそはグローバル・スタンダードである!という態度の表現規制からは逃れられなくなったのだろうか。
表現規制の流れは、オタク文化が若年層に浸透し、大手メディアや街中の広告として溢れ出したからこそ、引き起こされたのだろうか。
オタク男性としては今まで散々偏見の目を浴びせられ、マイノリティを背負って生きてきた先の、(オタク界隈でいう意味の)市民権を得た矢先の出来事であり、(これは邪推だが)表現規制を推進している人は、今までオタクという人々を毛嫌いし、我こそがマジョリティである…という態度を取り続けてきた人達のように…少なくともオタク男性の側からしたら感じられるように思う。
かつてマジョリティであった彼女らが、若年層へのアニメ文化浸透によって徐々にマイノリティと化し、その先に性被害を受ける女性という別のマイノリティを背負ったように振る舞っている…こういう見方がかつての(今も?)弱者オタク男性の間ではありそうである。
僕はオタク文化にも理解があり、リベラリストであり、フェミニストでもある。至ってどちらにも肩入れしないようにしたいが、何より人文科学、オタク文化がどこから来て、どこに行くのか…という流れそのものが好きである。
いつか社会学者の教授方、萌える都市アキハバラの著者森岡嘉一郎先生などが本にまとめてくれないだろうか。今回の件はどちらかというと、フェミニズムの分野かもしれないが。
日本ではオタク文化が取り沙汰されているが、アメリカでは過激左翼のLGBTの児童への過激表現を保守が表現規制をし守ろうという動きも興味深い。こちらの方のノートを参考に置かせていただく。こちらは有料記事だがこの方ツイッターでも分かりやすく発信してくださってる。
こちらに保守リベラルそれぞれから見た問題書籍を紹介していますが、保守派が目を光らせているのは主に「過激な性描写」と「トランスジェンダリズム」です。
— 🇺🇸Blah (@yousayblah) April 19, 2022
悪意ある偏った元スレッドにより多くの日本人が「保護者が教育内容に口を出す権利」と「表現の自由問題」を混同しているのが気になります。 https://t.co/stzezuM143
萌える都市アキハバラの感想記事です。
しかし僕としてはやはり、大正デモクラシー、平塚雷鳥らをはじめとする圧力からの解放、リベラリズムを源流とするフェミニズムが、表現規制、圧力をかける側、共産主義や国連やグローバルスタンダードを使った権威主義に転ぶのが納得がいかないところではある。フェミニズムの名前を変えてほしいところではある。家父長制の女性版…のような。良いネーミングはないだろうか。
今回の一連の流れは総じて、閉鎖的な環境で独自の進化を遂げた極東の島国と西欧のグローバルスタンダードをめぐる論争と言えるかもしれない。
今後どうなるにしても僕としては良く、この日々刻まれる歴史そのものが僕にとって美しく面白いものであるとこは間違いない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
