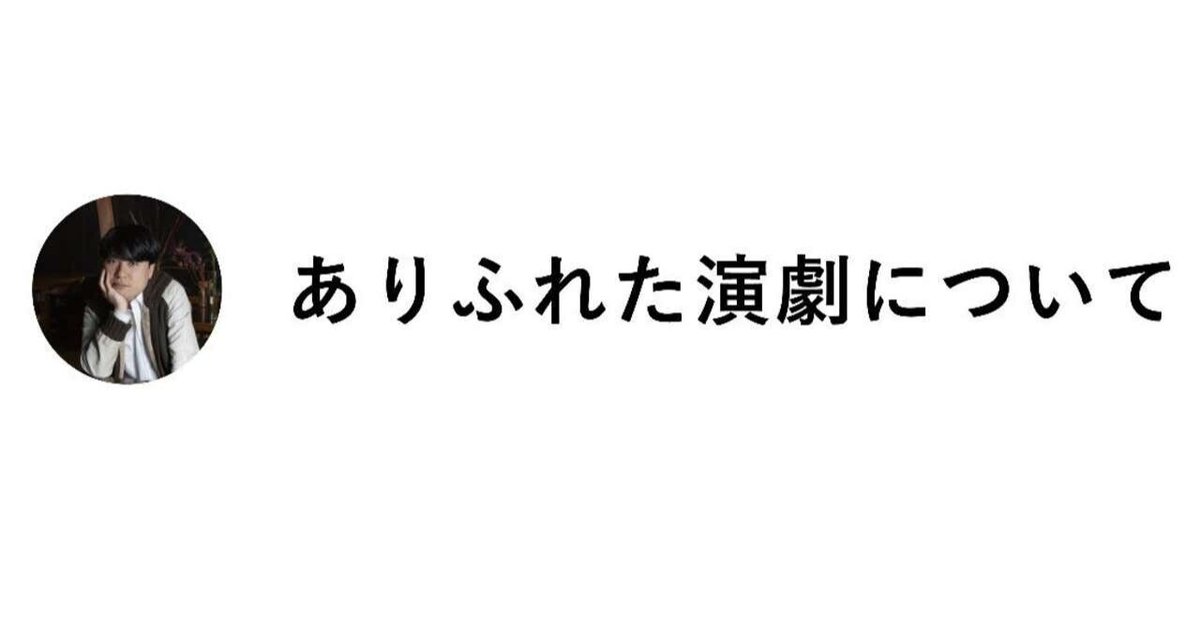
「ありふれた演劇について」17
前回は、鈴木忠志と大滝詠一という二人のアーティストについて、形式の「類型」とそれに対する「批判」という共通点を軸に書いた。そして改めて二人の仕事について思い返したとき、そこに強い「戦後」という歴史性を感じずにはいられなかった。
ここでいう「戦後」というのは、欧米と日本・アジアという強力な二項対立の存在する時代のことだ。鈴木忠志が日本人・アジア人としての身体について語るとき、それは決してただ素朴に民族性について語っているのではなく、いわば欧米をマジョリティとした「世界史」が想定されていることは明らかだ。大滝詠一がエルヴィス・プレスリーやフィル・スペクター、キャロル・キングといったアメリカンポップスに多大な影響を受けていることは言うまでもないが、同時代の他のフォロワーのようにただ盲目的にその真似をするのではなく、膨大な日本歌謡・芸能史に対する知識を基に、それがいかに欧米音楽を受容してきたかという流れの中に自らの音楽を定めている。
二人が類型を非常に重視し、パロディを繰り返す背景にはこの「戦後」という歴史性があったに違いない。新しい憲法ができ、アメリカの基地が作られ、様々な文化が流入してきた時代において、自分たちのあり方を批判的に検討するために類型を用いるということは自然に思われる。もちろん、この批判性には深い洞察と膨大な知識、卓越したセンスが求められることは言うまでもない。日本の「戦後」という時代の中で、この二人に匹敵するほどのパロディ作家はなかなか思いつかない。
というのも、この意味での「戦後」は長いようで実は短い。日本と欧米の対立構造は次第に薄れ、今やその感覚はすっかり過去のものとなっている。パロディは次第に軽薄になり、批判性を失っていく。もはやどのようなパロディなら可能だろうか?
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
