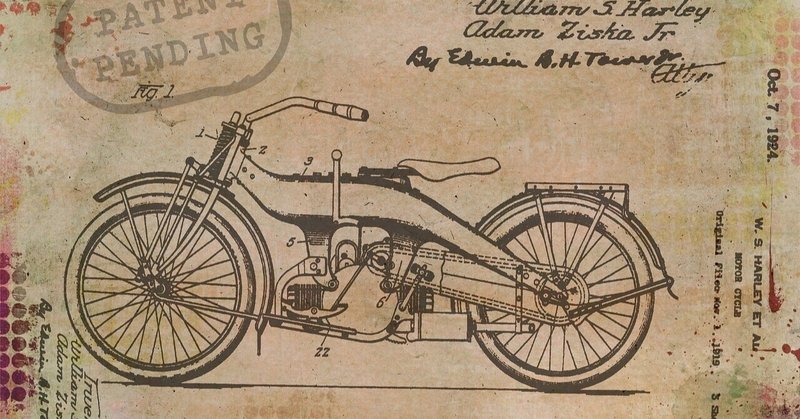
特許とはそもそも何なのか
弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
今回は、「特許とはそもそも何なのか」について説明します。
特許とは、発明を保護するものです。
発明とは、簡単に言うと技術的思想のうち高度なものです。
そして、高度とは何かですが、これは新規性と進歩性があることだと考えます。
新規性とは、過去に無い新たなものであるということです。
極端な例を言えば、テーブルの脚の長さが700mmと600mmは既に市販されている。しかし、800mmは過去に無く新たに作ったといえば、そのテーブルは新規性があります。
進歩性とは、その業界の標準的な知識を持った人(当業者といいます)が、容易に想到できないこととされています。
この進歩性が否定される例として、過去にあるものの単なる組み合わせがあります。
但し、その組み合わせに阻害要因があってそれを解決したとか、組み合わせることで顕著な効果があるとかがあれば進歩性が肯定されます。
例えば、鉛筆は既にありました、消しゴムも既にありました。
この場合、単に鉛筆と消しゴムとを組み合わせるだけでは、進歩性が否定される可能性が高くなります。
しかし、鉛筆と消しゴムとの接合部に薄い金属を巻いてかしめることで、消しゴムが外れたり折れないようなります。
すると、進歩性が肯定される可能性が高くなります。
特許には他にも要件がありますが、上記の新規性と進歩性とがあれば、殆どが特許査定となります。
余談ですが、これらの新規性と進歩性が、審査官に認められるように出願書類を書くのは、弁理士の腕の見せ所です。
そして、特許査定となって登録手続きをすれば、特許原簿に設定登録されて晴れて特許となります。
この特許となった状態で特許権が発生します。
すると、他人は許諾なしに特許に係る発明を実施することができなくなります。
これが特許による直接的な効果です。
間接的な効果は、私が別に投稿している「特許出願の効果 特許ありの企業の方が利益率が高い秘密」https://note.com/norio_sakaoka/n/nc4cc6ce8f01cをご覧ください。
ここで注意点を申します。
特許権の侵害は、「特許請求の範囲」に記載されている請求項のうち、他の請求項に従属していない独立項に記載されている構成要件を全て実施することで発生します。
この侵害か否かを見るには、請求項1が必ず独立項であるため、先ずは請求項1を確認します。(その後に、他の独立項を確認します。)
この請求項1に記載されている文言を全て実施すると侵害なのです。文言の全てです。
基本的には、請求項の文言の一部を除外又は変更することで侵害にはなりません。
ですので、請求項はシンプルな方が権利範囲は広いのです。請求項にたくさん書くと、権利範囲は狭くなってしまうのです。
この権利範囲がなるべく広くなるよう書類を書くのも、弁理士の腕の見せ所です。
さて、特許となった後は、権利を維持するために年金といわれる登録料を納付しなければなりません。
年金は、最初の第1年~第3年分は、設定登録のときにまとめて納付します。
そして、第4年分以降は、必要に応じて納付していきます。
この年金ですが、年を追う毎に高くなっていきます。
請求項数によって変動しますが一般的には、第1年~第3年が毎年数千円、第4年~第6年が毎年1万円、第7年~第9年が毎年2~3万円、第10年以降が毎年7~9万円くらいです。
これに、特許事務所の費用が1万円くらいかかってきます。
年金が段々と高くなるのは、権利を維持しているのはそれだけ利益が出ているのでしょ、だったらたくさん納付してね、嫌なら権利を放棄して特許の技術を万人に開放してね、という国の考えだと思います。
そして、特許権の存続期間は、原則として出願から20年ですので、いくら年金を納めていても当該期間をもって権利は消滅します。
いかがでしょうか。
特許について多少なりともご理解いただけたでしょうか。
坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
ホームページ http://www.sakaoka.jp/
Facebook https://www.facebook.com/sakaoka.norio
Twitter https://twitter.com/sakaoka
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
