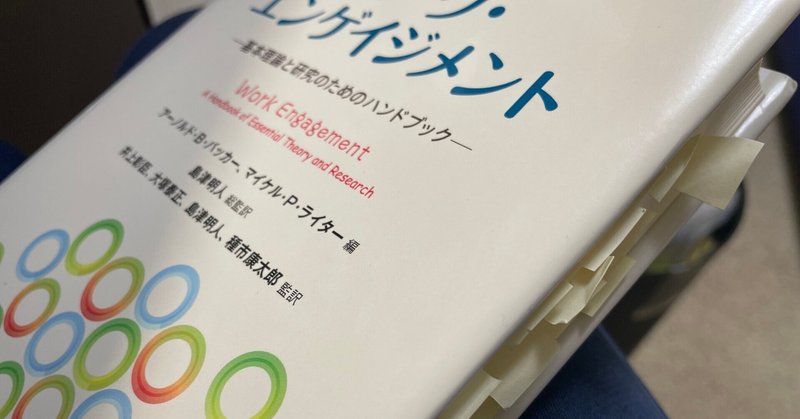
主体的に、役割外行動、スライヴィング?|2冊目『ワーク・エンゲイジメント』
アーノルド・B・バッカー、マイケル・P・ライター 編 島津明人 総監訳(2014, 星和書店)
もうずいぶんと昔になりますが、キャリアコンサルタントの養成講座でカウンセリングについて学びました。
アレン・E・アイビイ教授のマイクロ技法を示すピラミッドの下の方に基本的かかわり技法があり、その中に「感情の反映」という技法があります。
カウンセラーがクライアントの感情に気がつき、ピッタリの言葉を当てはめたとき、クライアントの感情に名前をつけることができたときにクライアントは納得感をもちスッキリする、そんな内容だったと思います。
前回、私は自己肯定、正当化を求めて「これでいいのだ。」というために経営学を学んでいると書きました。
仕事観、職業人生、もっといえば自分の生き方を肯定するための根拠を探すことが自分の学習意欲の根幹にあるようです。
そして、その根拠となるもの、自分が仕事感を語る上でピッタリとくる言葉を3つ、この本の中に見つけました。
質の高い「感情の反映」が行われたときは、きっとこんな気持ちなのだろうなと思いました。
その言葉とは以下の3つです。
スライヴィング
ジョブ・クラフティング
クロスオーバー
1.スライヴィング
スライヴィングとは「自分自身の成長に向かって進歩している、あるいは前進しているという感覚」と定義されていて、「学習する力」と「生命力」によって構成されています。
本のタイトルであるワーク・エンゲイジメントは「仕事に関連するウエルビーイングの状態」と定義されていて、その対極はバーンアウトです。
エンゲイジメントはスライヴィングとよく似ており、その構成要素は「活力」「熱意」「没頭」です。
活力はスライヴィングの構成要素の生命力と共通します。
しかし区別できるところもあります。
たとえばエンゲイジメントは仕事、パフォーマンスに焦点が当てられますが、スライヴィングはむしろ改善や従業員の成長、発達や進歩に焦点が向けられています。
そして予測するアウトカムにも違いがあります。
エンゲイジメントは「組織コミットメント」「離職意思・転職率の減少」「キャリア満足感」「バーンアウトや健康問題の減少」「配偶者のエンゲイジメント」「前向き行動」を成果として予測し、一方のスライヴィングでは「変化する環境への適応」「創造的・革新的行動」「組織市民行動(役割外行動)」「ジョブ・クラフティング」「行動レパートリーの開発」を成果として予測します。
2.ジョブ・クラフティング
ジョブ・クラフティングとは従業員が自分自身の仕事を主体的に形作るプロセス(Wrzesniewski & Dutton, 2001)でスライヴィングの成果としてあげられています。
ジョブ・クラフティングはエネルギーを創造し、学習機会を創出します。
物理的な変化と認知的な変化が起こり、「仕事の要求度」と「仕事の資源」および「個人の資源」のバランスを改善して、個人と仕事との適合をさせます。
3.クロスオーバー
クロスオーバーとは情動の伝播です。
従業員個人の情動は、ポジティブな場合もネガティブな場合も他者に伝播して、やがて組織風土として形成されます。
特にポジティブな情動はチーム全体に協力的な行動とより良いパフォーマンスをもたらします。
仕事にエンゲイジし、自分の楽観性やポジティブな態度、イニシアティブ行動を同僚に伝播する従業員は、仕事の要求度や仕事の資源とは無関係にポジティブなチームの風土を創造することができるといいます。

自分自身を振り返ってみて、ワーク・エンゲイジメントの状態にあると言われることには少し抵抗感があります。
それはおそらくそのアウトカムとして予測される「組織コミットメント」にあるかと思います。
組織コミットメントという言葉に、私は組織への依存のようなものを感じてしまいます。
現在、勤務する組織は素晴らしい組織であり、尊重していますし、好きですが、自分の世界をその組織だけにしたくはありません。
ところがスライヴィングしているかと言われたら、そう思われることは光栄に思います。
私は自分自身の成長を常に願っていますし、自分の成長のためには組織の成長も必要だと思っています。
組織が成長をしなくなることがあれば、それはおそらく自分の転機になると思います。
ワーク・エンゲイジメントのアウトカムとして組織コミットメントが予測されているために心理的抵抗があったように、スライヴィングのアウトカムとしてジョブ・クラフティングが予測されていることには、逆に、心理的な大賛成があります。
認知的な変化、つまり「気の持ちよう」によって、今ある仕事上の資源や個人の資源をポジティブに捉えて活用し、やがてそれは物理的な変化にもつながります。
思えば私はいつもそのような仕事の仕方をしてきたと思います。
仕事上の環境は、自分の学習や成長の上でいつも最適な環境であったと思っています。
そして極め付け、大いに共感して、「これだ!」と思ったのがクロスオーバーです。
いつも自分は楽しそうに仕事をしているので(実際に楽しいのですが)、嫌な仕事を避けてやりたいことだけやっていると思われがちですが、そうではなくて、面倒で嫌な仕事をいかに楽しくしようかとしているだけです。
そして、率先して仕事を楽しくしようとしているのは、ポジティブな情動をチームに伝播させて、前向きでチャレンジングで、そして毎日楽しいと思えるチームの雰囲気、組織風土を形成したいためなのです。
これは私の価値観なので人に押し付けてはダメだと思いますが、私は自分の行動によって誰かがよろこんでくれることが大好きです。
そのため、頼られたり頼まれたりすることをうれしく思います。
社会に出てきてからずっと営業畑を歩いてきた私にとっては、仕事を与えられるということは売り上げにつながるうれしいできごとです。
だから今でも頼まれるとうれしい気持ちになるのでしょう。
しかし、ずっとスタッフ部門の仕事をしてきている人にとっては仕事を与えられるということは負担が増えることに過ぎないのかも知れません。
本当なら、誰かがよろこんでくれることをうれしく思い、それを何よりも優先する組織風土を作りたいのですが、それはいずれ自分が会社を起業したときのために取っておきます。
参考書籍
アレン・E・アイビイ , 1985『マイクロカウンセリング』 (福原真知子他訳)川島書店
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
