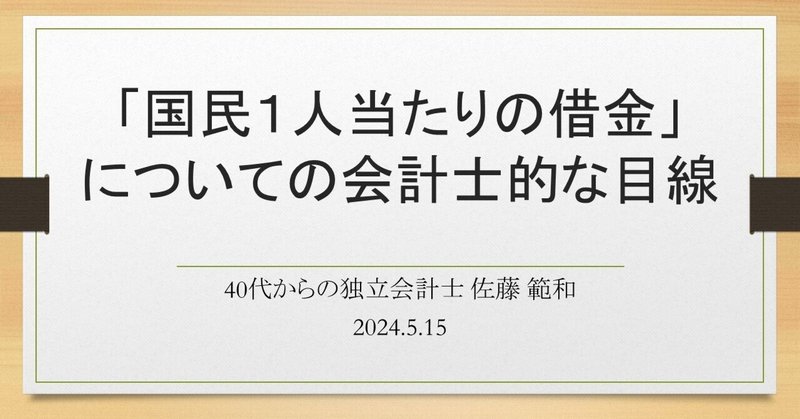
「国民1人当たりの借金」についての会計士的な目線
「国の国債発行額が○○兆円を超え過去最大規模に。国民1人当たりの借金は○○万円の計算 国民負担に懸念」
といった報道がたびたびTVや新聞でなされます。
このニュースを見るたびに「またか」と思ってしまうのですが、「国民1人当たり借金」と題してしまうところが誤り、というのに最近少しずつ気づかれている方が増えているように思います。
今日はこのあたりを会計士的な目線で少し書いてみたいと思います。
連結会計を国の財政にあてはめてみる
国債発行の仕組みについては、詳しい解説をされているかたはおおぜいいらっしゃるので、ここで改めて深堀することは割愛しますが、要は国債は誰が発行して誰が引き受けているのか、ということを考えると「国民1人当たり借金」という発想なんか出てくるわけがありません。
国債は、当たり前ですが政府が発行します。財政上の資金需要に応じて国債を発行し、資金調達を実行し、国が財政支出をするわけです。
ではその国債を引き受けるのは?これは日本の中央銀行である日本銀行が実質的な引受人となります(財政法第5条の規制があるため、実際は一度民間銀行が引き受けたものを日銀が買い取る、ということですが)。
これを簡単ですが図に表すと下記のようになります。

よく見てみてください。政府と日銀間で資金移動は発生していますが、「日本」を連結単位としてみた場合、全体としては何も借金は発生していません。
仮に仕訳に起こしてみると、下記の通りとなります(便宜的に100円国債を発行したとの前提)。
【政府個別仕訳】
・(借)Cash 100/(貸)国債(負債) 100
【日銀個別仕訳】
・(借)国債(資産) 100/(貸)Cash 100
【日本連結仕訳】
・(借)国債(負債) 100/(貸)国債(資産) 100
日本が財政悪化していると言いたいからなのか「過去最悪の国債発行水準」という言い方をされたりもします。
しかし、日本国内で国債による資金調達が行われている限りにおいては、日本全体として財政破綻しようもないわけで、このことをわかっているのかいないのか、国もマスコミもこのことを全くと言っていいほど触れていません。なぜなのでしょうね。
「国民1人当たり借金」という表現を使うことで、国の財政がそれだけひっ迫している、プライマリーバランスの実現に向けて、国民1人1人が協力して改善するしかない、よって増税する、というシナリオを描きたいのだろうな、という私の感覚です。
もちろん、市場にお金が流れすぎるとインフレを助長する、いたずらに自国通貨を発行すると国際的に信用ならない通貨とみなされてしまう、という点もあるので、借金が増えないからいいじゃないか、という考えは短絡的すぎます。
日本公認会計士協会への疑問
色々説明を端折ったため、突っ込みどころはあると思いますが、初歩の初歩としてはこのようにご理解いただければいいのではないでしょうか。
そして、この仕組みを理解した際に私が疑問に思ったのは、日本公認会計士協会(JICPA)が、なぜこの国債発行の仕組みに関して会計的な観点から発信を行っていないのか、という点です。
さきほど説明した通り、連結会計の考え方に立てば、現在の国やマスコミの情報発信は是正されるべきです。
にもかかわらず、私の知る限り、そのような観点からのJICPAの情報発信はどこにもなされていません。
もちろん国家運営の話なので、会計だけでは説明できない点もあると推測していますが、まったく何も触れないのはどうなのだろう、と思ってしまうわけです。
公認会計士法第44条第1項第15号では、JICPAの会則に「会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定」を記載しなければならない旨が定められています。
「国民経済の健全な発展に寄与」することが公認会計士の使命であるならば(同法第1条)、まずは国民にこういった観点からの情報発信活動も積極的に行うところから始めるべきなのではないでしょうか。
~編集後記~
・ペン字
・5/19から3泊4日で台湾へ旅行に行くので、お土産リストを検討

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
