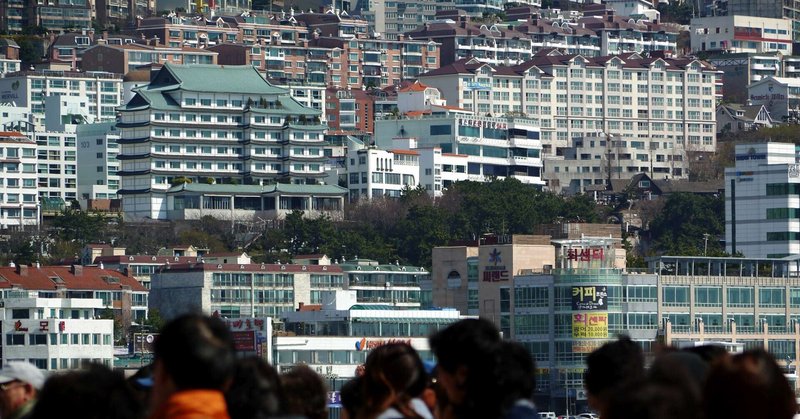
「自分がわからないときは聞けばいい」は無理があるのかも知れない
【ぐぐってもわからん。聞いてもわからん】
専門家という人がいる。ぼくもとりあえずは専門家の一人だが、結局、多くの時間を割いて勉強したことは確かだ。実際に触ってみて、実際にやってみると、かなり座学で学んだことと違うものもある。要するに「やってみなければわからないことがある」ってことだね。そういう専門的な仕事をいろいろしてきてわかるのは「自分でわからないことは誰かに聞けばわかる」というのは多くの場合「幻想」だ、ということだ。
【「簡単に。。。」が無理なことがけっこうあって】
「簡単に概略を言ってくれればいいから」と聞く人は言うのだが、聞く人がどのくらいの知識を持っているか?ということは、説明するほうが最初から考慮に入れなければならない。場合によっては、話すほうが「この人は話してもわからない基礎知識しかない」とか「この人の持っている基礎知識は間違ってる」なんていうときがあって、そんなときは、その基礎知識から話さなければならない。そのための時間はたいていはない。これを簡略化すると、全く違うことが伝わってしまうから、場合によっては「失言」とも取られかねないことがあるから、専門家は「簡単に語る」ことを、しなかったりする。「わかりたかったら、勉強して、私の話がわかるようにしなさい」ということだね。親切な専門家の場合でも「まずこの本を読んで、わからないところを質問に来てくれれば、そこから話ができるかもしれない」と言うばかりだ。
【複雑なことを複雑なままに】
特に最近は物事に複雑なものがとても増えた。専門家の言い方としては「専門というものが先鋭化してきた」ってことだね。分類はできても、その分類そのものがどういう基準で作られて、どういうふうに実際の場合に当てはめられるのか?とか、なかなか簡略化できないものがある。「複雑なもの」と「複雑なもの」がぶつかりあい、お互いに全く違う分野のものだったりした場合は最悪だ。それを聞いている第三者だって、わからなかったりするから、仲裁のしようもなく、落とし所を探すことさえできない。この「紛争が起きたときの仲裁役」は、このぶつかる2つの分野での専門家でなければならない。ってそんな人いないよ。普通。ってことになる。
【人生でどのくらいの時間を費してきたか】
結局、人は生まれてきたその時には、そんなに違う人はいない。皆同じだと言っていい。しかもそこから最後に至るまでの人の一生の長さは限られている。具体的な時間で。その中で何時間をある一つのことをしてきているか。それでその人の専門が決まる。Aさんが長い時間費やして来たものに、Bさんはかなわないが、そのBさんもまた違うことに多くの時間を費やしているから、もちろん別の専門分野のことではAさんはBさんにかなわない。専門というのはそういうものだ。
例えば、クルマのエンジンを作る専門家は、毎日そのことだけしている。クルマの内装の専門家は毎日そのことだけしている。一方でクルマの運転だけしている専門家がいる。クルマの運転の専門家はクルマのエンジンを作れない。クルマのエンジンの専門家だからといって、クルマの免許を持っているとは限らない。
【専門家に聞けるのは「結論」だけ、だが】
ネットの広まったこの社会では、専門家のカゲが薄くなった、と言われる。「そんなことはググればわかる」「そんなことはWipikedia見ればわかる」。しかしそこで得られる知見(知識や見識)は専門家が一般の人にもわかりやすく、結論だけが書いてある。そして専門家ではない人はそれだけで十分なことも多い。知識のベースのない専門家ではない人にわかるように完全に説明するのは不可能だから、どうしても「結論だけ」「略して」書いてある。そこには、かんたんにするためにウソが混じったり、微妙なことは書いていなかったりする。あるいは「ある場合のことだけ」が書いてあるから、ちょっと状況や前提が変わると、書いてある知識では役に立たない、ということもある。専門家ではない人にはそれが「専門家なのにウソをついた」と、思われることもある。
【いま、目の前に】
このコロナ禍では「人は会って物事を決めてみんなで動く」という「(社会に生きる人として当たり前と考えている)前提」を崩して、そこから話を始めないといけないことも出てきた。数千年の人の歴史で世界がこのような災厄に見舞われたのは、数回しかない。「人間として当たり前と思ってきた前提が崩れた」のかも知れない。そう思うと、これまでは「平和な時代」が長く続いたのだ。だから、どんなに人生経験を経た人生の先輩でも戸惑うのも当たり前だ。しかし、その前提を崩して物事を考えていくことがなければ人類滅亡さえありえる、という結論さえ出てくる可能性がある。
【専門家がわかるのは「自分の専門ではわからないことがある」ということ】
いろいろと詳しく「ウソではないか」と問いただしてみたら、結論は「そのことはその人の専門のように見えて、実は他の専門の話だった」ということもある。だから、近い場所にいる専門家どうしは、お互いに連絡はできるようにしてある。学会などというものはその一つだ。そして大規模な「危機」になったとき、専門家どうしの連携が始まる。そのときまで、専門家でない人には「専門」が見えない、という「専門」もある。
【感染症一つでさえ】
このコロナ禍で、多くの「専門家」がマスコミなどに登場している。こういうことでも「感染症の社会における拡大と縮小についての専門家」もいるし、「感染症の感染メカニズムの専門家」もいる。これらは別な専門であることほとんどだ。さらに「感染してウィルスが体内に入ったときに何が起きるか?」だけでも、結論を得るのに複数の違う専門が必要だったりする。だから、今回のコロナのような大きな危機になると、複数の専門を持つ違う専門家どうしが集まって対策を練る。人の社会の仕組みが、こういう危機に対して立ち向かうその姿が少しは見えるようになる。そして、新たにわかることがある。それが「まだ考えられてもいないこの専門の学問が必要だが、それはまだ無い。だからこのことについては、今は誰もわかっている人はいない」ということだったりする。
【「簡単」「概略」にはウソが入るの?】
結局「簡単にする」とか「概略で」というのは、必ず端折るので「ウソ」が混じる。「たとえ話」も適切である場合はあまりないので「特殊な場合だけど、こんなことだと思って聞いてください」ということにならざるを得ない。それが専門家の「正直」なんだ、と思ったほうがいい、ってことになる。自分は、それでも普通以上の数の専門を持つことはできたけど、その知識なども、ボッとしていると、世の中のほうがどんどん変わっていくから、常に知識などのアップデートしておかなければならなくて、そういう「知のメンテナンス」に使う労力と気力や時間やお金はバカにならない。実社会とは、いま、そういう社会なんだろうな、と思うことが最近、多くなった。
【何でもわかったつもりになるのは危険だよ】
いま、インターネットができたことによって「知」「専門」について「わかったつもりになる」人が増えている。一方で現代ほど専門というものが先鋭化し、それぞれが孤立化しようとしている時代もない。それが生半可な知識であることや、結論が出ていないことであることは、専門家が一番良く知っている。正直な専門家であればあるほど「わかっていない」と正直に言う。専門家とは「わかっている」だけに「わかっていないことがわかる」人でもある、ということだね。
このパンデミックのさなか。そんなことを考えている。
【何かの専門家になる、ということ】
「何かの専門家になる」ということは「わからないこと」を知ることができる立場になる、ということだ。誰も知らないことがいっぱいの「知の海」に漕ぎ出す船を得る、ということだ。
ぜひ、あなたも「何かの専門家」になってほしい。
、と、私は思うのだが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
