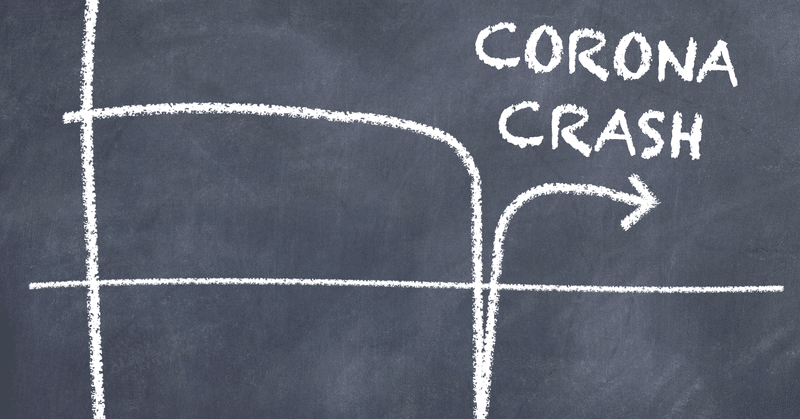
「負の原油価格」後のエネルギー地政学
歴史的な「負の原油価格」という現象の発生から2日が経った。歴史的といっても、WTIが上場したのが1983年だから、その歴史はたかだか37年。1859年に現代的な石油産業が始まったとすれば160年。あるいは油脂の貨幣取引の歴史からすれば数千年来の出来事といえるかも知れない。
「負の価格」はどんな時にあり得るか
負の価格、つまりお金を払ってでも引き取って欲しいものとして、例えば廃棄物がある。今回も負の価格になった石油を廃棄物になぞらえた人がいた。しかし、廃棄物はそれ自体に価値はないが、今回石油自体の商品としての価値がなくなったわけではない。
本来価値があるはずのものに負の価格がつくというのは、確かに一見奇妙に思えるが、例がないわけではない。例えば、ドイツの電力卸売市場では2008年よりネガティブプライスが導入されている。電力のネガティブプライスが発生する場合にはいくつかのシチュエーションがあるが、共通しているのは、需要に対し供給が過剰な状態で、発電設備の特性上、供給を一時的に止めるよりはお金を払ってでも消費してもらった方が発電事業者にとって得であるという瞬間である。最近もコロナで電力需要が落ちるなか、太陽光や風力の出力が上がることで、英国などで電力のネガティブプライスが発生している。
この様な事態は、一般に電力は貯蔵するコストが高く、在庫キャパシティがない(基本的に在庫という概念がない)ことに由来している(ただし、今後は蓄電池など蓄電技術の低コスト化・大容量化などによって変わるかもしれない)。
原油価格はどうなるか
今回の石油の場合も同様である。あまりにも急な原油需要の減少によって、供給削減が追いつかず、ローカルな在庫キャパシティが足りなくなる恐れがあったという背景があった(参考:前回の投稿)。
よりテクニカルな説明としては、現物取引を伴う期限つき契約である原油先物取引の特性と、その主な市場参加者が現物取引を行わないUSO(USオイルファンド)などの原油先物に投資するETF(上場投資信託)であるという状況が重なり、極端な値動きが実現してしまったといえる(参考:日経新聞記事)。
この構図は今も変わっていないので、市場関係者は、需要の回復や供給の十分な削減がなされなければ、5月上旬にも米国の原油在庫キャパシティはオーバーフローし、次の「6月もの」の期限が切れる5月19日に再び今回と同じ様なことが起きる可能性があると警戒している。
そもそも「負の原油価格」というのは、心理的なインパクトあるものの、それ自体は持続不可能なので、発生したとしても社会に対し実質的な意味はない。ただ、需要の回復も供給の削減も簡単には起こらないので、「負の原油価格」にならずとも、原油需要の大幅減と原油超低価格という事態はしばらくの間続くと考えるしかない。
さて、今後どうなるか
さて、多くの人が知りたいのは、これからどうなるのか。原油需要の大幅減の影響は、石油産業のみならず、金融システム、国際政治、再生可能エネルギー開発、温暖化政策など、さまざまな分野に広がっている。そして、さらに気になるのが、「アフターコロナ」の社会がどうなっているのかということだろう。それを述べることは時期尚早ということもあるが、非常に広範な話なので、これから少しずつ書いていきたいと思う。
今回は、石油産業〜国際政治に関わるところで、まず起きるだろうと思われることについて触れる。
産油国のインパクトの違い
原油の需要3割減、超低価格という事態に対し、協調減産をするなどして、人為的な供給削減が十分に行わなければ、高コストなところから順に市場から排除されていくことになる。
下の図は、BPのチーフエコノミストSpencer Dale氏が2015年に行った講演で使われたもので、かなり簡略化されたものではあるが、原油を低コスト順に並べて積み上げた「原油コストカーブ」のイメージである。仮に、中東産油国が減産することなく、原油需要の3割減を市場メカニズムだけで生産削減しようとすると、「米国シェール」より右側にある生産が理屈の上ではすべて吹っ飛んだ上で、ようやく50ドル/バレルが均衡価格ということになる。

原油コストカーブのイメージ
Dale氏2015年講演資料図に筆者加筆
もしそうなってしまえば、一部地域の石油産業が崩壊してしまう。一見すると、中東産油国からすれば、ライバル国を排除できることになるかも知れないが、ここまでの規模になると、将来需要が回復した時に再び供給をすることができず、安定した石油需給が保てなくなってしまう。これが現在石油産業が最も恐れていることであり、中東産油国にとっても大きなリスクである。
また、米国からすれば、エネルギー安全保障の観点から、自国のシェールオイル産業だけでなく、カナダ、メキシコ、英国といった同盟国の石油産業を守るためにも、指を加えてみているわけにはいかない。
したがって、中東産油国と米国の間でお互いにそうならないように、(駆け引きを含みつつ)協調減産のための話し合いが行われていると考えられる。(話を簡略化するためロシアなど他の重要国のポジションを省いている)
また、産油国も一枚岩ではない。下の図は、IMFの推定による2020年度の産油国の国家財政を成り立たせるために必要な原油価格である。国によってかなり差が大きいことがわかる。特にイランは厳しそうである。また、現在のドバイ原油価格を30ドル/バレルとしても、表の全ての国が基準価格に達していない。

財政収支がゼロになる原油価格水準(IMFデータより筆者作成)
また、産油国といってもその石油産業への依存度は様々である。例えばロシアは原油価格下落でさぞかし苦しんでいるだろうと一般に思われている。確かに安泰ではないが、同時にルーブル安でもあり、ドル決済される輸出分についてはある程度相殺されている。また、ロシアの石油産業の大きさは製造業よりも小さい上、石油輸出額の対GDP比は約21%で、ノルウェーの約32%より小さい。
妄想的地政学見通し
大筋で言えば、欧米の石油関連企業(特に新規開発がなくなるので掘削サービス関連)で大量のレイオフや経営破たんが発生する。失われた人材は簡単には戻ってこないが、相対的に余力のあるサウジなどの中東産油国の事業会社に転職し、技術移転が起きるだろう。破たんした企業を中東の国家ファンドが買収するということもあるかもしれない。
いずれにしろ、シェール革命でアメリカに傾きかけていた石油業界のパワーバランスは、再び中東に戻るトレンドにある。ただし、欧米石油会社の破たんの責任が中東産油国にある(意図的である、または未必の故意)と解釈される場合、同盟国である米国とサウジの関係が変化する可能性がある。既に一部議員が、サウジアラビアが着実に減産を行わなければ米軍を撤退するという脅しをかけているという。
しかし、先に述べたように中東諸国も一枚岩ではまったくない。既に政治的な理由で国交断絶している所もあるが、特に近年のサウジアラビアは単独主義的な行動が多く、OPECの足並みがますます揃わなくなっている。
これは妄想でしかないが、利害関係を含む大きな社会変化があった後のリバランシングの中で、新たな争いが生まれるということはありうることなので、十分な警戒が必要だ。正直、影響範囲が広すぎてなかなかフォローしきれていない。もう一歩踏み込んだ分析はまた次回以降で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
