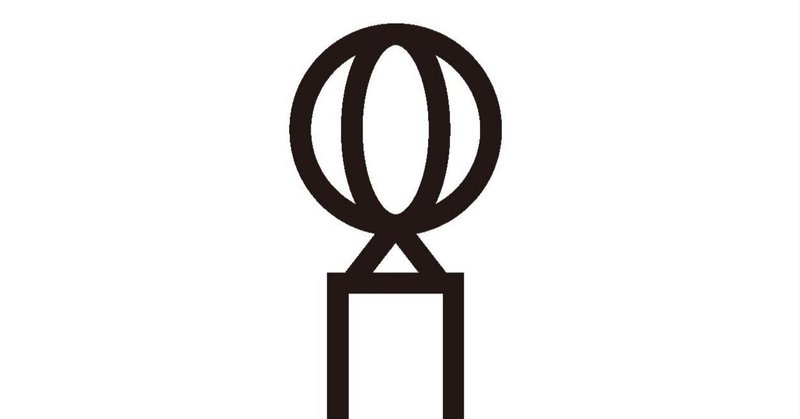
アドバルーン
「パパバイバイ」
自転車のハンドルに取り付けたチャイルドシートから娘が私の方を振り返った。
「うん?もうお家帰る?」
娘の言うバイバイは帰りたいという意味であることが多い。しかし娘はブンブンとかぶりを振り、陽が傾き始めアンバー成分が増加の傾向を見せ始めた空に繋ぎ止められた、銀色のアドバルーンを指差した。やれやれ今度はあのアドバルーンを目指せということらしい。私は電動アシスト付き自転車のペダルを踏んだ。
自転車に乗って娘の行きたい方へどこまでも走ってゆく。まだうまく会話の出来ない娘と父親とのこれがほぼ唯一のコミニケーションだ。「あっち」、「こっち」、毎日朝から弁当をもって、娘の指示に従って一日中自転車を走らせるのが、育児休暇中の私の勤めということになっている。いくら電動アシスト付きとはいえ、これはこれで結構くたびれる。
「デンワ」
娘は首から下げた銀色の丸いバックからオモチャのスマホとりだし、神妙な顔をしてその表面を指でなぜてから、どこかの誰かと不思議な言葉で話を始めた。彼女はその”デンワ”でちゃんとメールも送れるし、写真もとることができるのだ。たまに自撮りをすることもある。
娘がいったい何処へ行きたいのか?それは私にはまったく予測不能なのであったが、意外なことに娘の指示は割と的確であった。娘の言う通りに自転車を走らせてゆくと、結構な確率でそれなりの場所にたどり着くのである。それは古い井戸の跡であったり、街の中にひょっこりと現れるビューポイントであったり、いったいいつからその場所に立っているのだろうかと改めて考えると、思わず手を合わせてしまいたくなるような古いおおきな木であったり、私が普段つい見過ごしていたような場所であることが多かった。そしてそういう場所に辿り着くと、娘は満足げに彼女の”デンワ”で写真を撮るのだった。
銀色のアドバルーンに下がった垂れ幕には「地球環境に配慮した生活を」という標語が染め抜かれていた。おそらく公共広告の類だろうが、このあたりでは最も広い、中心に野球場くらいの大きさの池のある『森の公園』から上げられているようであった。それにしてもアドバルーンを見るのも随分久しぶりのような気がする。それにこんなに大きなものだったろうか。それはまるで、人類に環境問題を訴えるために地球に降りてきた月が、公園の池に錨をおろして一休みしている、といったような感じだった。もちろん本物の月はちゃんといつものサイズで上空に浮かんでいる。
公園の入口付近は、工事中なのか制服を着たガードマンによって封鎖されていて、白い防護服姿の人がなにか作業をしているのが見えた。
「中には入れないみたいだよ」私は娘にそう言い聞かせたが娘は大きくかぶりを振って公園の中を指差した。
「どうかしましたか」そこへ黒いスーツにサングラスをかけた二人組の男が近寄ってきた。私はなにか不味いことになるのではないかとすぐにその場を離れようとしたのだが、自転車のペダルはロックでもかかったかのようにピクリともしなかった。
「いえ、なんでもないんです」二人組は私がそういうのを無視して娘の前に立つと、娘の”デンワ”とそっくりな端末のようなものを取り出し娘と話を始めた。と同時に電動アシスト付きの自転車が勝手に公園の中へとゆっくりと走り始めたのだった。
「あなたはここで降りて下さい」
白い防護服のマスクから男とも女ともつかない声がした。公園の入口からやや奧まったところに設置されたテントの脇で、私が促されるままに電動アシスト付き自転車から降りると、自転車は娘を乗せたままそのまま移動を続けた。
「娘をどうする気だ」私が娘をチャイルドシートから引き離そうとすると、数名の白い防護服に取り押さえられてしまった。離れてゆく自転車のチャイルドシートから”デンワ”で誰かと話をす娘がチラッと私の方を見て手を振った。
「彼女はあなたの本当の娘ではありません」白い防護服の一人が言った。「あなたは彼女のアシストをするように仮の記憶を植え付けられていたのです」娘を乗せた自転車はアドバルーンを繋いだロープを伝いそのまま垂れ幕を気球に向かって登り始めた。「彼女は地球の環境問題を解決するための調査に派遣された異星の科学者なのです」娘を載せた自転車が登ってゆくと垂れ幕の文字が消え、新たに手書きの文字が浮かびあがってきた。「もはや地球の環境破壊を食い止めるには、彼女たちの高度な科学の協力なくしては、」
パパバイバイ。覚えたばかりのような拙い筆跡で書かれた文字が垂れ幕に浮かび上がると、アドバルーンは上昇を開始した。夕日が反射した銀色の風船が小さくなりやがて見えなくなると、私の記憶も消えてしまった。(了)210621
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
