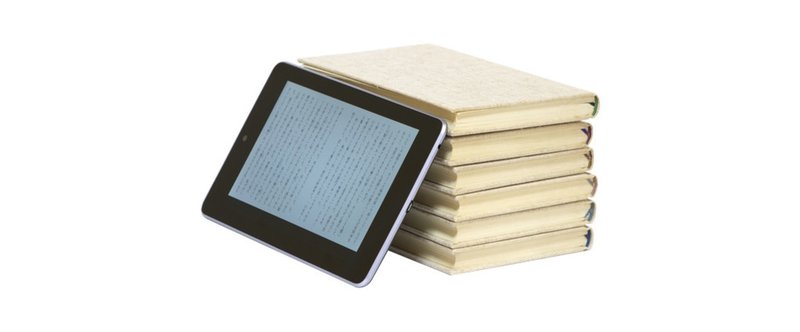
怠惰な思考をしていると言われてもしかたがない姿勢の改憲論者たち──古関彰一『平和憲法の深層』
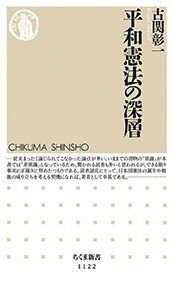
日本国憲法の成立の背景に新たな視点をもたらしたとても刺激的な一冊です。
古関さんはまず「第九条」がどのような意味を持っていたか、こう記しています。
「平成を迎えるなかで、昭和天皇に関する記録や東京裁判の研究が進む。「戦争の放棄」を定めた九条は、昭和天皇の戦争責任を免罪するためであり、それはマッカーサーの意図でつくられたことが解明できた。同時に日本国憲法に「戦争の放棄」を謳う九条があることで、沖縄に基地をつくることになったことが明らかになった」
「しかし、憲法九条の成立過程を調べた限りは、マッカーサーもGHQ案も「平和」という言葉にはまったくかかわっていない。では、いつ、どこで、誰によって、憲法九条に「平和」という言葉が挿入されたのであろうか」
第九条にはもともと「戦争の放棄」しかありませんでした。GHQ案は「平和条項ではなく、マッカーサー三原則とともに「戦争放棄」条項あるいは「対外的に国家としての主権行使の中核である戦争ができない、あるいは他国に対して戦争を行わない、ひと言でいえば「主権制限」条項「戦争違法化」条項として存在していた」のです。
そこにあったものは「マッカーサーの政治戦略的意図」でしかありません。
では「平和条項」はいつ加えられたのでしょうか。それは第九十帝国議会の議事録に現れていました。そこでの片山哲議員の発言、また本会議に設置された「帝国憲法改正案特別委員会」(委員長は芦田均)でその道筋が作られたことを古関さんは突き止めていきます。この時の芦田委員長の平和への情熱がそれを生んだのです。この芦田さんの委員会の修正提案と九条の意義を記録した議事録は一読の価値があります。ここには新たな国家、すなわち平和国家を建設しようという強い願いがあったのです。ここでの古関さんの議事録の取り扱い方は私たちが身につけなければならないことだと思います。言論の府である国会のアイデンティティが議事録だと思うからです。
古関さんは芦田委員長のこの発言を明示すると同時に、のちになされた「芦田修正」との落差をも公平に指摘しています。この「芦田修正」についての経緯に触れた部分は自衛戦力合憲論とも関連しており必読の箇所ではないかと思います。
戦後憲法を成立させたものに、明治以来の自由民権運動の研究者がいたことも重要な指摘だと思います。明治憲法の改正にどちらかというと否定的だった政府の憲法問題調査委員会案ではGHQの許諾を得ることはできませんでした。GHQ案の背景には民間の鈴木安蔵さんを中心とした憲法研究会の存在があったのです。旧態依然たる政府案に対して、植木枝盛以来の自由民権運動の研究者だった鈴木さんたちの憲法研究会案は、とりわけ人権意識については政府案の一頭地を抜くものでした。
「鈴木らの憲法研究会案は、その内容は言うまでもなく、極めて早い段階で起草し、GHQ案の国民主権条項や人権条項へ影響を与え、さらにはGHQ案にはなかった生存権を研究会員で社会党所属の衆議院議員である森戸辰男を通じて修正させることに成功するなど、注目すべき改正案であったことはまちがいない」
とその存在を大きく評価しています。
明治憲法の修正でしかなかった政府案に対してGHQが出してきたものは憲法研究会案に基づくものだったのです。
現行憲法を単なる「押しつけ憲法」といういいかたで片付けてはいけません。そこには間違いなく日本人の叡智があったというべきなのではないでしょうか。
段階的改憲などという声も出てきている安部政権の改憲路線ですが、このようにして現行憲法に込められた人権というものはどのようになっていくのでしょうか。
古関さんは二〇一二年発表の自民党の憲法改正にふれたくだりでこう記しています。
「明治憲法に勝るとは劣らぬ人権制限憲法だということが解るのである。(略)一項で人権保障を規定しつつ、二項では、「公益及び公の秩序」という「魔物」によって、人権制限、いや事実上の否定に等しい条項を加えている」
ここには明らかな後退が見られると言うのです。
この本は〝押しつけ〟と簡単に言ってはならない現行憲法成立過程の再検討であり、また敗戦を終戦と言い換えた原因、8月終戦革命説等にも再検討を加えた読み応えのあるものです。
「いまや平和は国家に対して戦争を止めさせるという、いわば人権の自由権のみならず、恐怖と欠乏の禁止という、より広い生存権の視点を国家に求める時代になっているということである」
と始まる末尾近くの文章から
「貧富の差は急速度にすすみ、かつては先進国と途上国の差が問題になったが、いまやそれに止まらず、先進国内の貧富の差は、途上国内での差を上回る程になっているという。新自由主義の帰結である」
へ、さらに新たな安全保障についても
「国家安全保障の時代が過ぎ去りつつあり、それに代わる人間の安全保障や社会保障の」時代へと移りつつあるのである」
と記されている個所には、現在の私たちが考えなければならないことが数多く含まれていると思います。
改憲、改憲という言葉にあふれて決して改憲ありきという〝空気〟に縛られてはならないと思います。
何が必要とされているかということだけでなく、なにを私たちは目指すべきかをとことん考えなければならないと思います。少なくとも現行憲法の前文に込められた理念、
「この前文に意味における国民的な生存権は、国際社会における日本国民のいわば基本権として確認されている」(丸山真男さん)
ということを一顧だにすることなく、自民党案では前文は削除されています。それも……、
「前文は、我が国の歴史・伝統・文化を踏まえた文章であるべきですが、現行憲法の前文には、そうした点が現れていません」
という理由で……。
古関さんの言うように「自民党にとって、普遍的な価値や理想よりも日本的な情緒的表現や現実の方が大切なようである」としか思えません。それは、同時にまた怠惰な思考をしていると言われてもしかたがない姿勢のようにも思えるのです。
書誌:
書 名 平和憲法の深層
著 者 古関彰一
出版社 筑摩書房
初 版 2015年4月10日
レビュアー近況:サッカー女子W杯、UEFAユーロ2016予選、コパアメリカ、そして明日からW杯アジア二次予選と、(欧州の)オフシーズンなのにナショナルマッチ目白押しで、中継観戦、正に寝る間がありません。
[初出]講談社BOOK倶楽部|BOOK CAFE「ふくほん(福本)」2015.06.15
http://cafe.bookclub.kodansha.co.jp/fukuhon/?p=3636
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
