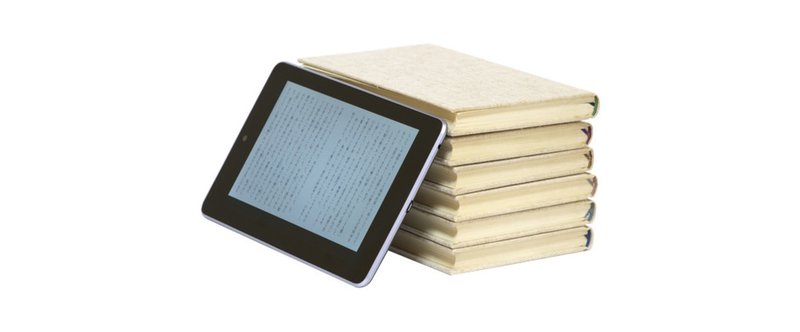
自己保身・自己肥大に走る行政権力へのチェックをし続ける必要があるのです──周防正行『それでもボクは会議で闘う』

周防さんたいへんごくろうさまでした、そして普段私たちが目にすることのない委員会、審議会というものの内実を明らかにしてくれてありがとうございます、というのがまず頭に浮かびました。この本は法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」(メンバーはhttp://www.moj.go.jp/content/000122717.pdfでわかります)に参加した周防監督の苦闘の日々を綴ったものです。周防さんが委員に選ばれた理由は映画『それでもボクはやってない』を作ったことによるようです。
この審議会は本来は、誤判・冤罪を起こすことのない「司法制度改革」を達成すべく発足したはずでした。委員には強引な検察捜査で自白を強要された経験を持つ村木厚子さんも加わっていました。
ところが話された(議論されたとはとてもいいがたいものです)ものは、本来の目的とは大きくかけ離れたものだったのです。
「もともとは検察の不祥事が原因で開かれた会議であったはずなのに、その不祥事に対する批判も反省も忘れている人たちを相手に、改革の必要性を訴える日々は、虚しさに満ちたものだった。言葉を重ねても、手応えなく素通りしていったり、強く跳ね返されるばかりで、およそ意見を闘わせたという実感はない。それでも最後まで諦めずに言葉尽くした。そうするよりほかなかった」
以前取り上げた『虚構の法治国家』にもありましたが〝有罪率99.957パーセント、拘留決定率99.9パーセント〟という実績(!)にあぐらをかいた「他国の法にならう必要はない」などという夜郎自大的な発言をする警察・検察官僚たち……。そもそもこの審議会のメンバーの選出時代が「ある法曹関係者から「絶望的なメンバーですね」」と言われるようなものだったのです。周防さん(もちろん村木さんや幾人かのメンバーもですが)はその壁に向かってほとんど絶望的な闘い(論議)を挑みます。
けれど帰ってくる言葉といえば、
「会議を通じて思っていたが、正確で不足なく過剰に丁寧に喋るお役人言葉というのはじつにわかりにくい。このわかりにくさについて、お役人は当然気がついていると思うのだが、きっと誰も抗うことはできないのだろう。そして、このわかりにくさを逆に利点として活かしているような気もしないではない」
という周防さんの言葉どおり、各委員の発言のわかりにくさとその底にある強引さはこの本の各所に、各ページごとにといいたいくらいあふれています。
この「お役人言葉」は官僚だけではありません。とりまとめをはかろうとする学者の人びとにも見受けられるものです。いえ、むしろ学者の発言のほうがひどいものです。村木さんを目の前にしながら平然と「人質司法という実態があるのか疑問」(椎橋隆幸教授)と言う人をはじめとして、自己の学説にこだわるだけの教授、本来の司法改革(取調べの可視化、証拠の全面開示、人質司法)を骨抜きにして落としどころに導こうとしているようにしか思えない井上正仁教授の発言など、〝曲学阿世の徒〟としか思えません。
誰におもねっているのか、もちろん警察・検察という行政権力です。(検察庁は行政権を持つ行政に帰属する官庁ですし、捜査を中心とする司法警察活動は、司法と名がつくものの、行政活動です)
彼らは彼らでこれを好機とばかりに捜査権限の拡大をもくろみます。それが通信傍受(盗聴)や刑事免責制度(司法取引)の導入です。警察・検察の捜査・取調べ過程の不透明さを問題にしたことから始まったはずの審議会はわずかな成果を残したものの、周防さんたちが望んだものとは大きくかけ離れたものでした、残念ながら……。
「ことほどさように、この会議は、刑事司法制度のあるべき姿、その「理念」を共有し、誤判・えん罪を起こすことのない「司法制度改革」を達成しようとするものだった、とはいえない。しかしながら、まったく意味のない会議ではなかった。理念に違いはあっても、すくなくとも裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件では、取調べの全課程が録音・録画されることになったのである。公判前整理手続に付される事件だけではあるが、検察官手持ち証拠のリスト開示も行われることになるだろう。新しい制度が始まることで、取調べのやり方が自体が変わる。証拠開示も変わる。その変化がやがて、「取調べ」「証拠開示」のあり方、そして「刑事司法制度」全体に影響を及ぼし、改革していくと信じている」
周防さんはほんのわずかな一歩であっても「道具が変わることで、考え方が変わることもある」と未来への希望を捨てることはありません。それを実現するのは私たちの課題です。
そしてそれがこの貴重な記録を残してくれた周防さんへの私たちの回答なのです。
「自らの非を決して認めようとしない、あまりに日本的な「お上」のあり方」を認めることなく、自己保身・自己肥大に走る行政権力へのチェックをし続ける必要があると思います。
なんども席を立って辞任しようとした周防さんが耐えて委員を続け残してくれたこの記録は、審議会というものが持つ落とし穴を私たちに教えてくれてもいると思います。どこが「新時代」なのだというため息とともに……。
書誌:
書 名 それでもボクは会議で闘う
著 者 周防正行
出版社 岩波書店
初 版 2015年4月8日
レビュアー近況:なでしこジャパンW杯準決勝、勝利監督インタビュー越し、ピッチ中央でオウンゴールをしてしまったイングランドのバセット選手を囲むチーム全選手・スタッフの輪が出来た絵にグッときました。
[初出]講談社BOOK倶楽部|BOOK CAFE「ふくほん(福本)」2015.07.02
http://cafe.bookclub.kodansha.co.jp/fukuhon/?p=3691
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
