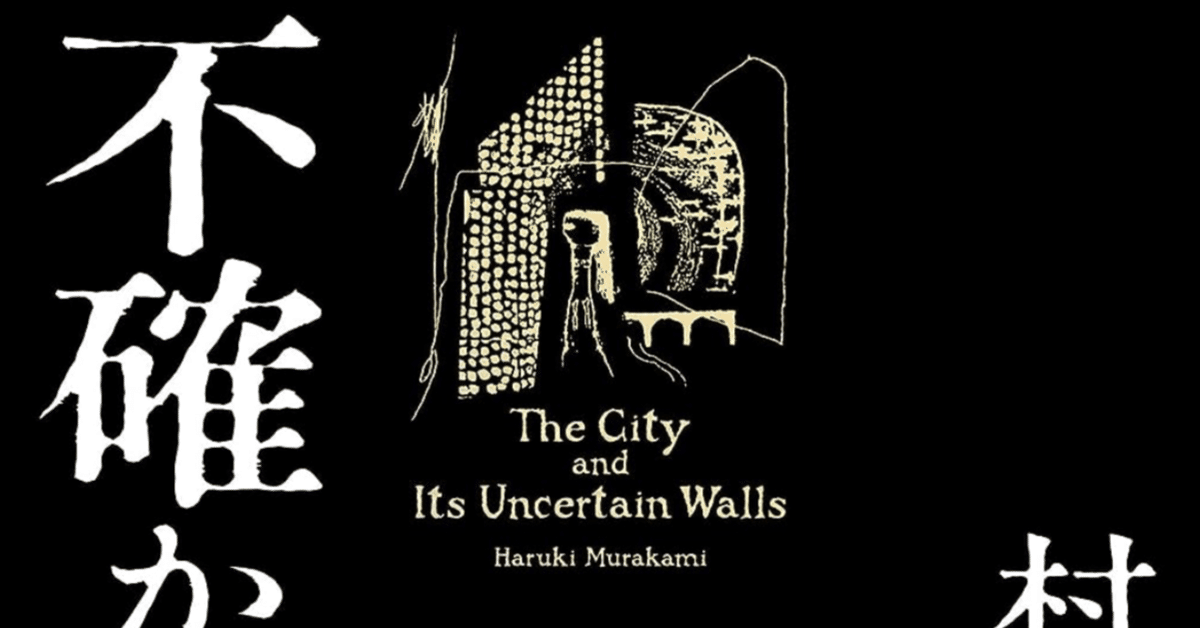
『街とその不確かな壁』(村上春樹)を読んで
ここのところ、心揺さぶるような本や映画に出会えていない気がする。満を持して読んだ村上春樹の最新作『街とその不確かな壁』も深い世界に連れて行ってはくれなかった。
駅前のカフェでは、左側の席で「どうしても3ヶ月で恋人と別れてしまう30代女性」が、久しぶりに会った長年の友人に、「同僚である15才年上の男性との最近はじまった恋愛」について語っていた。天才肌で、家には物が多くて、デートは月に一回らしい。新しい恋人にウキウキが隠せない話ぶりだが、それとは裏腹に、事実からは不穏な雰囲気が漂う。
右側の席では、ラグビーの試合帰りのような風貌な男性と、フルートのコンサート帰りのような空気感の女性2名の計3名が、哲学について語っていた。ギリシャ哲学からレヴィ=ストロースの構造哲学までその幅は広く、男性が質問し、女性たちが教えるような知の交換を行なっていた。
首を振ってみると現実は意外と面白くその振り幅は大きい。
知らない世界が広いことに気が付く。
『街とその不確かな壁』には、なぜだか、深い思想の世界よりはそういう現実の気付きを与えられるような気がした。
内容に戻る。
あとがきでその理由は明かされるのだが、物語は『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』と似ている。それどころか『ねじまき鳥クロニクル』とも似ているし『海辺のカフカ』とも似ている。
似ているがゆえに、完成度の高いそれらの作品と比較して酷評が目立つのが本書だ。
(実際にぼくも『ねじまき鳥クロニクル』では自分の人生が歪められたと感じたが、本書に関してはサラッとしていた)
それでも他の村上春樹作品との違いが際立つ点が一つあった。
それは、主人公の立場だ。
『海辺のカフカ』には、「田村カフカ」に対して「ナカタサトル」がおり、
『ねじまき鳥クロニクル』には、「岡田亨」に対して「間宮中尉」がいる。
『街とその不確かな壁』での「僕」は、「イエロー・サブマリンの少年」にとっての「ナカタサトル」であり「間宮中尉」ではないかと感じた。
世界観は時代を超えて継承されていく。
それぞれの時代にはそれぞれの戦いがあり、現在の戦いは先達の語られない人生の上に成り立っている。過去の作品では、導く人や通り過ぎられる人だけだった人の物語が、ここでは描かれているような気がした。
それは一見、救いのようにも考えられた。
だけどもしそう読むのだとしたら、実際にそこにあるのは、地獄のようなひたすらな自意識との向き合いだった。
整理がつかないので、つづく。





最後まで読んでくださいましてありがとうございます! 一度きりの人生をともに楽しみましょう!
