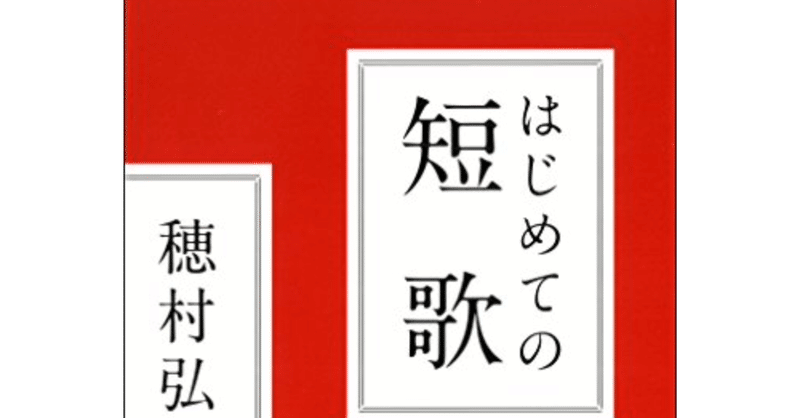
対談の名手、穂村弘さん(歌人)からいろいろ教わる
※「ほぼ日の學校 Advent Calendar 2021」4日目です。
あこがれが、ぼくの対談の作法。
穂村弘 (歌人)
"歌人として、作家として知られる穂村さんは、対談の名手
でもあります。つらくてしかたがなかった十代のころに
「あこがれ」の人のまねをすることで抜け出したという穂
村さん。やがて身につけた「あこがれるという作法」とは?"
タイトルが雑で申し訳ない。思った以上にいろいろ聞けたんです。
私が、この穂村さんの授業を聞こうと思ったのには二つの理由があります。
一つは、私が仕事でインタビューすることがあるためです。
ちょっとした記事を書くために、1時間。長ければ、一時間半。
あるいは、一時間のインタビューの後、もう一回、一時間程度。
相手は、話しやすい同僚のこともあれば、会社のお客様だったり、偉い先生や経営者ということもあります。
対談の名手の話が聞けるとあっては、そのコツを聞かないわけにはいかない!
(でも、実は、穂村さんの対談って読んだことなく、、とりあえず、今回の話でも紹介されていた対談本を購入)
もう一つの理由は、穂村さんが歌人であるということ。
私は、短歌を少しやっています。もう三年くらいになりますが、薄く続けてます。短歌のことを知る上で、こちらの本は大事にしていて、たまーーーーに、読み返しています。
動いている穂村さんを見るのは、今回が初めてです。
「対談」について
インタビューの参考にしようと思って聴いた穂村さんの話ですが、基本、穂村さんが行う対談というスタイルは、好きな相手、憧れの相手がセッティングされるので、プロのインタビュアーがやるインタビューとは種類が違うとのことでした。
例えば、興味がない芸能人や、スポーツ選手と話すわけではない。
確かに、私が仕事をするようなインタビューとは大きく異なります。実際に、インタビューの相手が、憧れの存在だったことはありません。
でも、私が行う普段のインタビューでも、相手に対して、どこか尊敬できるところを探して、この人はここがすごいなぁという気持ちを持って臨みます。そうしないと、相手のことを深掘りできない。単純にプロフィールをなぞって、穴埋めをするような質問だけに終始して、記事になるわけではありません。それがアイドル的な人であれば、それだけで価値がある記事になるかもしれませんが。
穂村さんの対談は、基本、ファン目線からスタートします。
でも、ただのファンに留まらない。しっかり、言語化するところに、その特徴があるようです。
「僕はその人の核にある才能とか
美質をピックアップして
言語化してフィードバックする
という能力はあると思う」
単純に、褒める、という言葉も使われていましたが、相手が喜ぶテクニックとしても、いいですよね。それを他の人にない目線で切り取れるのは、また別の問題だと思いますが。
穂村さんも、何かを生み出す人として、創作の秘密、その作品がなぜ、どうやってできるのか、それを知りたい、と考えているそうです。それを専門的な目線でなく、きっとファンとしての目線だから、記事の読み手にも、共感するポイントが見つかるんだろうと思います。
もちろん、相手のファンであるところからスタートするので、ちょっとした仕草や、行動がおもしろく、大先生の見慣れない部分にも出会えるんでしょう。
ただ困ったこともあるようです笑
一番困るのはさっきも言ったけど
自分のリスペクトが強すぎて
それが邪魔になる
尻尾を振っている犬みたいに
なっちゃうとね 相手も困る
憧れの人と話すって、それだけで緊張もしますしね。
話の中では、ちょいちょい、過去のいろんな方との対談について、語られます。
冒頭、友人で精神科医の春日武彦さんとの対談の話では、なるほど、そこに興味を持つのね、と思いましたし、
ぜひ、聴いてほしいのですが、楳図かずお先生の表現の根底部分に触れての部分も気になります。横尾忠則さんのエピソードもおもしろい。
憧れの人と出会った時、自分は、どういう振る舞いをするだろうかと想像しながら、聴いてみるのもいいかもしれません。
確かに穂村さんの憧れの人達と
されてる対談はファン的な要素が
すごく強い感じになってて
可愛らしい感じになってるんですが
でもそこにふと
的を得た一言というか
相手の本質をつくようなものが
入ってくると
おぉ!と思うんですよね
的を得た一言、これは、短歌を詠む人の視点じゃないかな、と思います。
「短歌」のこと
短歌のことについて、説明してくださった部分があります。
僕の言い方で言うと
それは生(生きる)の一回性と
交換不可能性
一回しか生きないと
当たり前のことですけどね
リハーサルがないってことと
さっきも言ったように
他の命とは交換できない
自分が死ぬ時自分が死ぬ
他の人が死んでも自分は死なない
自分が死んでも他の人は死なない
ということの
圧倒的な実感が描かれている
でも短歌でやることは逆で
月食って言葉がない時代の
月食を書くとか
足がつるっていう言葉で
規定される以前の
足がつるを書くとか
そっちなんだよね
より根源的な体験の方に
もう一度解体する
他人の短歌を読んでいると、えっ、そこ?! っていう点に注目されていることがよくあります。確かに同じことに違和感を感じたことはあるけど、なるほど、言われてみれば… そう感じないことはない、見えないことはない、という場面によく出会います。
きっと感じる違和感には、すでに誰かがつけた名前があって、初めての体験でも、あぁそうかこれは「足がつる」ってことなんだ、この現象を月食っていうんだ。仕組みはこうなんだ、と聞いて理解することがあります。それこそ、ググることが当たり前になった今、違和感はあっという間に去っていきます。
しかし、歌人は、最初の違和感、驚きを逃さず捕まえて、言葉にします。
例えば、インタビューの記事一つにしても、そこが聞けたら、その一点を言語化できれば、もうそれだけで成立してしまうことはあるでしょう。短歌をやっている身として、何とか、小さな、あっという間に過ぎ去る違和感をとらえられるようになりたいな、と思いました。
穂村さんのお話を聞いて
12月は、アドベントカレンダーを書くついでに、たくさんの方の授業をまとめて見ています。
話の調子がゆっくり過ぎて、もっと早く、要点だけしゃべって!
という気持ちにもなりましたが、今のような話し方になった要因を最後のほうで話してくださいます。
悩みつつ、それを少し変わった形ではありますけど行動に移して、ずっと続けてこられた穂村さんのお話。楽しく、そして、参考になりました。
いつか…
そんな言い方じゃ、きっとなれないでしょうけど、いつか歌人になれるなら、その時にお会いしたい。
いい歌を詠むため、歌の肥やしにいたします。 「スキ」「フォロー」「サポート」時のお礼メッセージでも一部、歌を詠んでいます。
